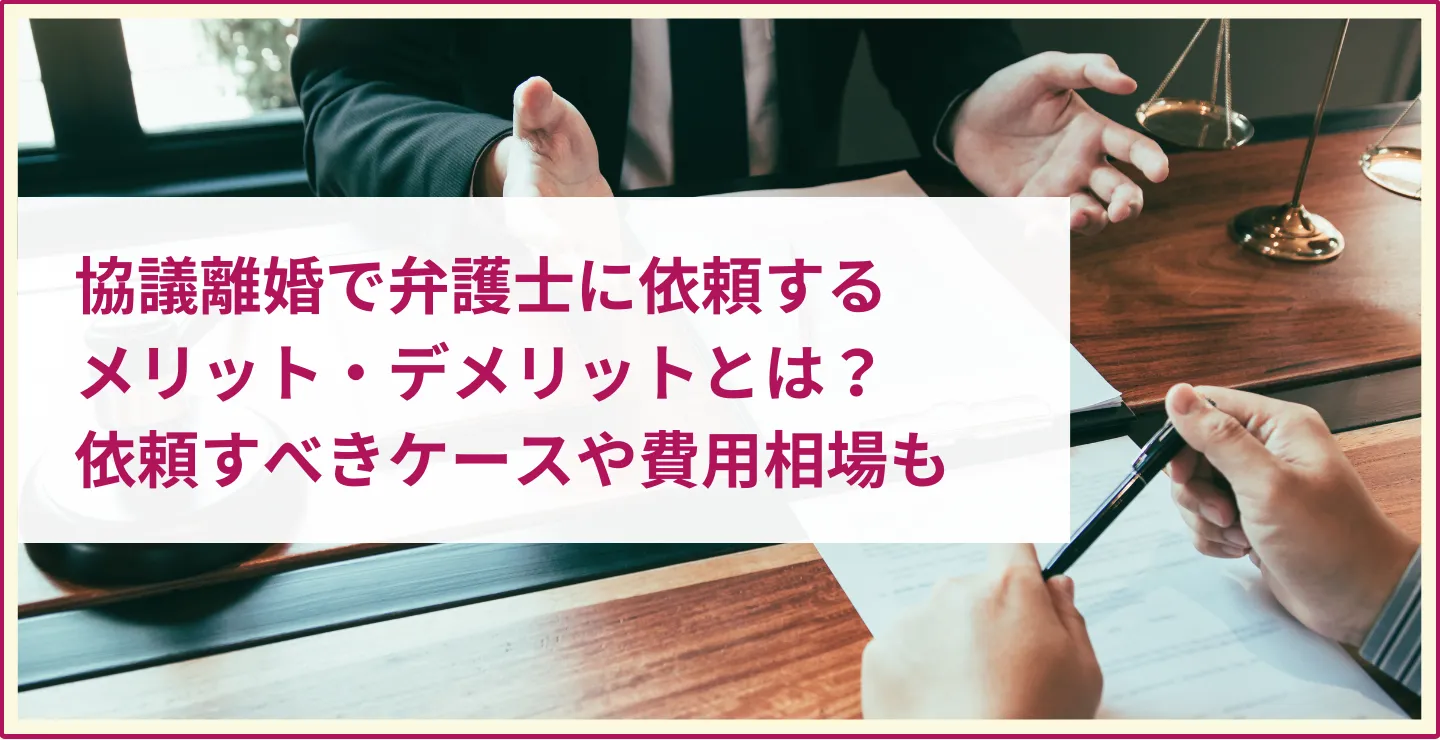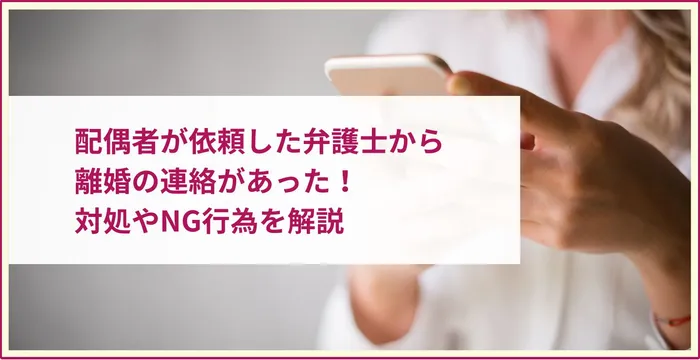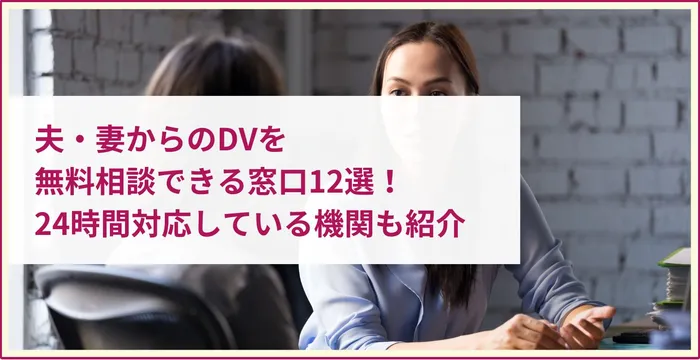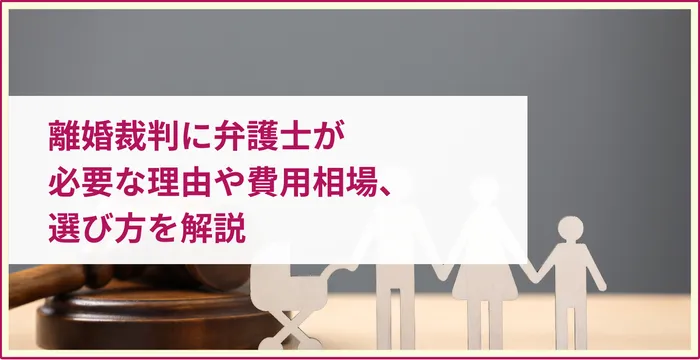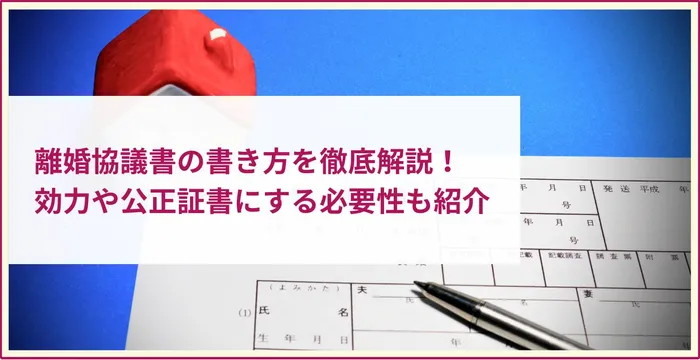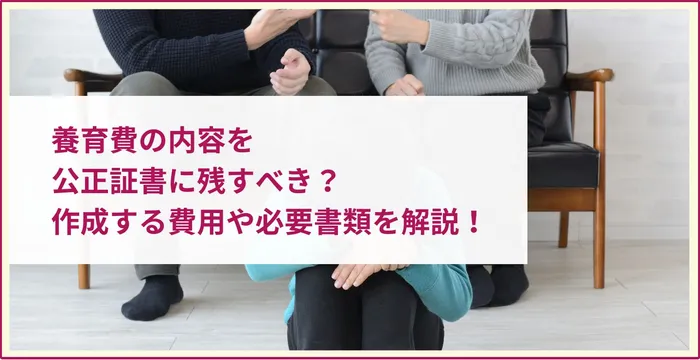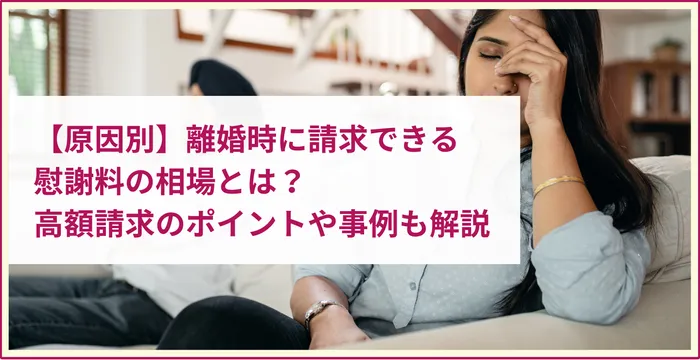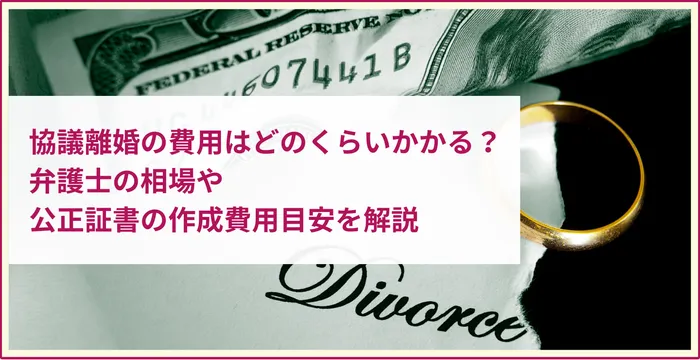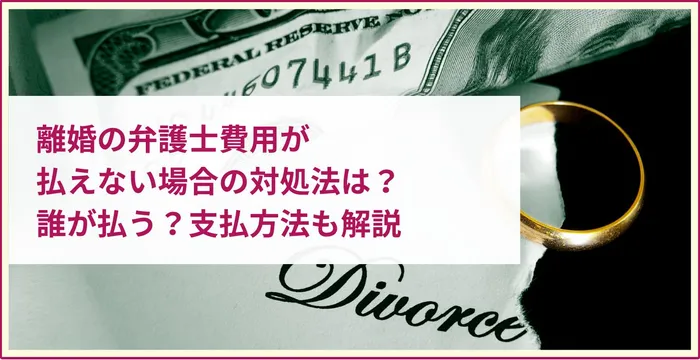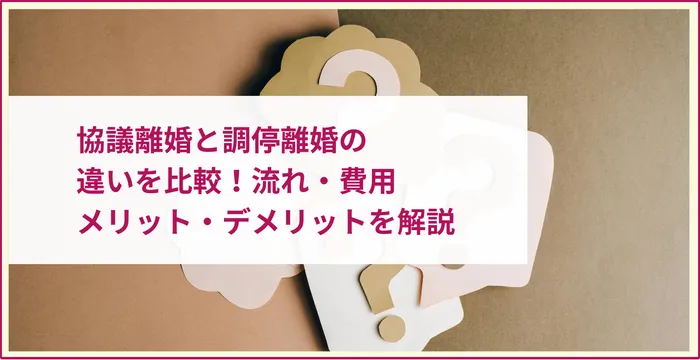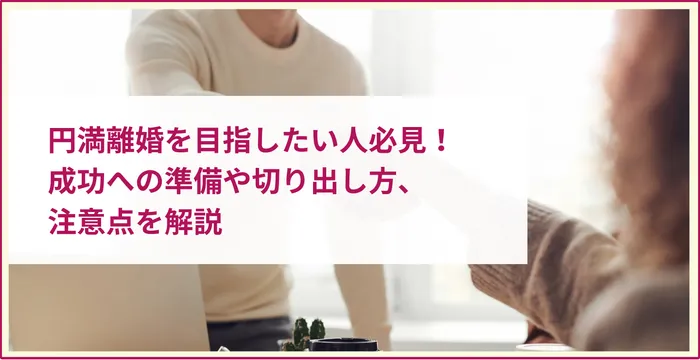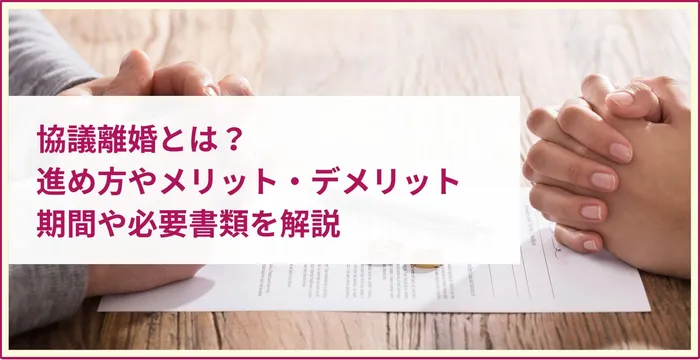協議離婚を弁護士に依頼すべきケース
協議離婚を弁護士に依頼すべきケースは以下のとおりです。
- 相手の弁護士から連絡があった
- 財産分与・慰謝料・養育費などで意見が対立し離婚条件がまとまらない
- DVやモラハラを受けており相手と会いたくない
- 相手が離婚に反対しており話し合いに応じない
- 相手の主張が何度も変わり話し合いが進まない
それぞれのケースについて詳しく解説します。
相手の弁護士から連絡があった
相手の弁護士から連絡があった場合は、こちらも弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼せず協議離婚に臨むと、法的知識や交渉力に差があるため、交渉が難しくなる恐れがあるからです。
たとえ相手に非があったとしても、法的根拠を主張できなければ、慰謝料や養育費などの希望条件が通りにくいです。
弁護士に代理交渉を依頼すれば、法的に適切な主張ができるだけでなく、離婚条件の整理や書類作成などの実務面も任せられるため、相手と対等に話し合いができます。
相手の弁護士から内容証明郵便などで通知が届いた場合は、正式な法的対応が始まっているサインです。できるだけ早く弁護士に相談しましょう。
財産分与・慰謝料・養育費などで意見が対立し離婚条件がまとまらない
協議離婚の話し合いでお互いが離婚条件を譲らず、話し合いが進まなくなったときは弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
たとえば夫婦双方が親権を持ちたいと考えている場合や、相手が慰謝料や養育費について納得していない場合は、話し合いが平行線になりやすいです。
協議離婚では離婚するかどうかだけでなく、具体的な条件についても話し合う必要があります。主な取り決め項目は以下のとおりです。
| 項目 |
取り決め内容 |
| 親権 |
配偶者のうちどちらが親権を持つのか |
| 養育費 |
子どもの教育に必要な養育費の金額・支払い期間 |
| 面会交流 |
別居する子どもと面会する回数や頻度、方法 |
| 慰謝料 |
相手方の非が原因で離婚する際の慰謝料の金額 |
| 財産分与 |
夫婦が共同で築いた財産の分配比率・内容 |
| 年金分割 |
婚姻期間中の厚生年金の分割方法 |
| 婚姻費用 |
別居する際の生活費となる婚姻費用の金額・支払い期間 |
とくに親権については、離婚の際に必ず決めなければならない項目です。ほかの内容については、必ずしも離婚と同時に決める必要はありません。ただし後回しにすると時効を迎えてしまったり、離婚後だと話し合いに応じてくれなかったりといったトラブルに発展する可能性があります。
離婚条件で揉めそうな場合は、あらかじめ弁護士に相談しておきましょう。
弁護士に早めに相談しておけば、相手方とのトラブルや交渉の長期化を防げるケースもあります。
DVやモラハラを受けており相手と会いたくない
DVやモラハラなどを受けている場合、弁護士に相談せず協議離婚を進めると状況が悪化する恐れがあります。離婚を持ちかけたことで配偶者が逆上し、さらに暴力や嫌がらせなどの危害を受ける可能性があるためです。
またDVやモラハラをする配偶者は、離婚に応じないケースも多く、話し合いが進まない可能性も高いでしょう。
配偶者からDVやモラハラを受けている場合は、すみやかに弁護士に相談し、相手と直接顔をあわせずに離婚手続きを進めることをおすすめします。弁護士に依頼すれば、代理人として相手とのやり取りを代行してもらえるため、安全に離婚協議を進められます。
あわせて、以下のような公的機関にも相談しておくとよいでしょう。
- 配偶者暴力相談支援センター
- 婦人相談所
- DV相談プラス
- 女性の人権ホットライン
公的機関では、一時保護や支援措置に関する説明を受けられるほか、必要に応じて保護命令などの手続きについても案内してもらえます。
相手が離婚に反対しており話し合いに応じない
相手が離婚に反対しており、話し合いに応じない場合は、弁護士に依頼すると解決に近づく可能性があります。
弁護士から相手方に直接連絡をしてもらうことにより、離婚の意思が真剣であることや、事の重大さを伝えられるからです。
また、相手が離婚を頑なに拒否し続ける場合は、協議離婚では合意できず、離婚調停や離婚裁判に発展する可能性があります。
調停や裁判になると、証拠の提出や主張の整理など、専門的な対応が求められます。弁護士に依頼せずに手続きを進めるのは難しいため、協議離婚の段階から相談しておくとよいでしょう。
こちらの言い分を聞いてもらえず頑なに離婚を拒否される場合は、一度弁護士に相談してみてください。
相手の主張が何度も変わり話し合いが進まない
相手の主張が何度も変わり、話し合いが進まない場合は弁護士に介入してもらったほうがよいでしょう。
話し合いのたびに相手の主張が変わると、それまでの内容が白紙になってしまい、交渉が一向に進みません。
たとえば前回は離婚に前向きだったのに、次の話し合いでは離婚を拒否するなど、態度が一変するケースもあります。毎回意見を変えられると、そのたびに話し合いを一からやり直すことになるため、精神的な負担も大きくなりがちです。
弁護士に依頼すれば、法的根拠に基づいて交渉を進めてもらえるため、相手の主張に振り回されることが少なくなります。
話し合いが長引けば、感情的な対立も深まりやすくなります。早期解決を図るためにも、相手の主張が何度も変わるときは弁護士に相談しましょう。
協議離婚を弁護士に依頼するメリット
協議離婚は、夫婦間での話し合いによって進める離婚手続きです。しかし話し合いが思うように進まないケースや、条件面での対立がある場合は、弁護士に依頼したほうがスムーズかつ有利に進められる可能性があります。
弁護士に依頼することで得られる主なメリットは、以下のとおりです。
- 法的知識を活かし交渉を代理してくれるため有利な離婚条件を獲得しやすい
- 離婚協議書などの書類作成を代行してもらえるため負担が軽減される
- 慰謝料や養育費などの条件を考えてもらえるため適正額を算出・請求できる
- 代理人になってもらえるため相手と対面せずに話を進められる
それぞれのメリットについて詳しく解説します。
法的知識を活かし交渉を代理してくれるため有利な離婚条件を獲得しやすい
離婚条件について、親権や養育費のことなどで譲れない部分がある方も多いでしょう。
離婚分野に精通した弁護士に依頼すれば、離婚の話し合いを有利に進められるため、希望する条件が通りやすくなります。
弁護士は家庭裁判所の判断基準や過去の判例、養育費算定表などをもとに、法的な観点に基づいて交渉を進めつつ、可能な限り依頼者の利益になるように行動してくれるためです。
また、相手から不利な離婚条件を突きつけられている場合でも、法的観点から適切な水準に基づいて反論し、納得できる内容に修正できる可能性もあります。
とくに相手が弁護士をつけている場合は、対等な立場で交渉するために弁護士のサポートが重要になります。
離婚条件の希望がある場合、弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。
離婚協議書などの書類作成を代行してもらえるため負担が軽減される
弁護士に協議離婚を依頼すれば、離婚協議書など重要な書類の作成を代行してもらえます。
離婚協議書は、夫婦間で話し合って決めた離婚条件を確認するための契約書です。
離婚協議書には法的効力が発生しますが、内容が不足していたり誤っていたりすると、効力がなくなる恐れがあります。
書式や記載内容に不備があると、書類として無効になるリスクがあるため、自力での作成には注意が必要です。弁護士であれば、離婚協議書の作成にも精通しているため、正確かつ法的に有効な書類を作成することが可能です。
また、離婚協議書を公正証書として残す場合にも、弁護士への相談を検討しましょう。
なぜなら、相手と交渉中で離婚協議書の内容が決まっていない場合や、住宅ローン・不動産・自動車・株式などの複雑な条件がある場合は、法的なチェックや整理が必要になるためです。 弁護士に依頼すれば、公正証書にする際に必要な書類の準備や、公証役場とのやり取りもすべて代行してもらえるため、手続きの手間やミスを減らせます。 また、将来的にトラブルにならないよう、法的に有効かつ明確な内容で協議書を作成してもらえるのもメリットです。
公正証書は、公証役場で作成する公文書です。離婚協議書を公正証書として残せば、相手が慰謝料や養育費の支払いを滞納した際に裁判をせず強制執行できます(※強制執行には「執行認諾文言」の記載が必要です)。
離婚が成立してから「養育費を払ってもらえない」「連絡が取れない」といった事態に陥っても、公正証書があれば金銭回収の手段として役に立ちます。
慰謝料や養育費などの条件を考えてもらえるため適正額を算出・請求できる
弁護士に協議離婚を依頼すれば、慰謝料や養育費などについて、法的な根拠に基づき適正な水準を提案してもらえます。
養育費はお互いの収入をもとに、最高裁が公表している「養育費算定表」を参考にして算出するのが一般的です。しかし法的な知識がないと、正しい金額の目安がわからず、相手方と揉める原因になりやすいです。
弁護士に依頼すれば、お互いの給与明細や源泉徴収票などをもとに、適正額を算出してもらえます。
慰謝料も、離婚原因や婚姻期間、年収などから金額が算定されます。慰謝料が認められるのは、不貞行為(浮気)やDVなど相手に明確な責任があり、それを立証できた場合です。
法的な観点から条件を見直してもらえるため、相手方が提示してきた不利な条件に気づき、納得できる離婚条件に整えられるでしょう。
代理人になってもらえるため相手と対面せずに話を進められる
弁護士に代理交渉を依頼した場合、弁護士が代理人の役割を担って話し合いを進めるため、相手方と対面せずに済みます。
弁護士が代理人になると、相手とのやり取りはすべて弁護士を通じて行われます。たとえば、離婚条件に関する通知書や交渉内容の書面も弁護士が作成・送付してくれるため、感情的な対立を避けながら話し合いを行うことが可能です。
協議離婚で揉めているときは、相手方との話し合いにストレスを感じる方も多くいます。
弁護士に依頼すれば相手方との話し合いをすべて任せられるため、自分自身は仕事や家事、育児に専念できます。
とくにDVやモラハラなど、配偶者から攻撃を受けていた場合、弁護士に依頼するメリットは大きいです。
相手と対面せずに協議離婚を進めたい方は、弁護士への依頼を検討しましょう。
協議離婚を弁護士に依頼するデメリットは費用がかかること
協議離婚を弁護士に依頼するうえでもっとも大きなデメリットは、費用が発生する点です。
協議離婚の弁護士費用の相場は20〜60万円ほどと、決して安い金額ではありません。
相手方と揉めておらず、話し合いだけで離婚が成立しそうな場合は、弁護士に依頼せずに解決したほうがよいでしょう。
弁護士費用の内訳と相場は、以下のとおりです。
| 項目 |
費用相場 |
内容 |
| 相談料 |
0円~1万円(1時間あたり)
※無料相談の事務所もあり |
弁護士に相談する際に発生する費用。相談終了後に支払うのが一般的。 |
| 着手金 |
0円~30万円
※着手金無料の弁護士事務所もあり |
弁護士に離婚問題の解決を依頼する際に発生する費用。依頼時に支払いが発生する。 |
| 報酬金 |
離婚成立:20万~30万円
慰謝料請求:経済的利益の10~20%
財産分与:経済的利益の10~20%
親権の獲得:10万~20万円
養育費の獲得:合意金額の2~5年分の10~20%
|
離婚成立および、慰謝料請求や財産分与などの要望がかなった際に発生する費用。離婚問題の解決後に支払いが発生する。 |
| 日当 |
3~5万円(1日あたり) |
弁護士が事務所外で活動した際に発生する費用(相手方の居住地で交渉にあたるなど)。
離婚問題の解決後に支払うのが一般的。 |
| 実費 |
都度変動 |
弁護士の交通費や切手代、書類の取り寄せなどで発生する費用。離婚問題の解決後にほかの費用とまとめて支払うのが一般的。 |
弁護士に依頼すれば、相手との交渉を代行してもらえるほか、専門知識に基づいたアドバイスや解決策が受けられます。
一方で、費用も発生するため、自分の状況や予算とのバランスをみながら、弁護士への依頼が必要かどうか検討しましょう。
弁護士費用について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
協議離婚で弁護士を付けている人の割合は?弁護士無しでも大丈夫?
協議離婚は、夫婦の話し合いによって進める離婚手続きです。ただし、すべての夫婦が弁護士を介さずに進めているわけではありません。では、実際にどれくらいの方が協議離婚で弁護士を利用しているのでしょうか。
当社が実施したアンケートでは、協議離婚を選んだ方のうち約30%が「弁護士をつけた」と回答しています。 令和3年に法務省が公表した調査でも、弁護士を利用した人は約3割という結果がでており、当社アンケートと同様の傾向がみられます。
夫婦双方が離婚に合意しており、話し合いが順調に進むなら、弁護士に依頼しなくても問題ありません。
しかし離婚条件で意見が対立している場合や、話し合いがうまく進まないと感じている場合には、弁護士のサポートを受けたほうが円滑に手続きを進められる可能性が高くなります。
弁護士が必要かどうかはケースバイケースですが、離婚条件に迷いや不安がある場合は、弁護士への相談を検討してみてください。
※法務省:協議離婚に関する実態についての調査研究業務報告書の公表について
弁護士が協議離婚に介入して解決した事例
弁護士が協議離婚に介入して解決した事例は以下のとおりです。
- 専業主婦でも親権を獲得できたケース
- 夫の不倫に対する慰謝料を勝ち取ったケース
- 財産分与で公平な結果を得たケース
それぞれの事例について、詳しく紹介します。
【事例1】専業主婦でも親権を獲得できたケース
専業主婦は収入面で不利と感じてしまいがちですが、親権の判断において最も重視されるのは「これまでどれだけ子どもと関わってきたか」です。ここでは、専業主婦のAさんが親権を獲得した事例を紹介します。
どういう問題を抱えていたのか
Aさん(30代女性)は、結婚してからずっと専業主婦として家庭を支えてきました。しかし、夫との関係が悪化し、ついに離婚を決意。夫婦には5歳の子どもがいましたが、夫は「自分の方が収入があるから、子どもを育てるのにふさわしい」と主張し、親権を手放すつもりはありませんでした。
Aさんは、これまで子どもの世話をしてきたのは自分なのに、経済的な理由だけで親権を取られてしまうのではないかと大きな不安を抱えていました。
弁護士に依頼してどう解決したのか
Aさんは弁護士に相談することにしました。弁護士は「親権の判断には、どちらが子どもの生活に深く関わってきたかが重要」と説明し、Aさんの育児実績を裏付ける証拠をそろえる方針を立てました。
具体的には、育児日記や保育園の連絡帳、病院の診察履歴などを整理しました。また夫が仕事で多忙だったため、育児にほとんど関与していなかった事実も確認できました。
さらに、Aさんは離婚後の生活に備えてパート勤務を始めており、子どもと生活できる環境を整えていました。弁護士は「収入だけで判断すべきではなく、子どもの安定した生活が最優先」と主張。粘り強い交渉の末、夫も最終的に親権を譲ることに同意しました。
争点と結果
このケースでは、親権と養育費が主な争点となりました。
結果として、Aさんが親権を獲得し、夫から毎月6万円の養育費を受け取ることで合意しました。
【事例2】夫の不倫に対する慰謝料を勝ち取ったケース
不倫が原因で離婚を決意しても「証拠がなければ慰謝料は取れない」とあきらめてしまう方も少なくありません。ここでは、夫の不倫に悩んでいたBさんが、弁護士のサポートを受けて慰謝料と財産分与を勝ち取った事例を紹介します。
どういう問題を抱えていたのか
Bさん(40代女性)は、夫の様子が次第におかしくなっていることに気づいていました。夜遅くまで帰宅せず、休日も家を空けることが増えたため不審に思っていたところ、共通の知人から「夫が女性と一緒にいた」と聞き、夫の不倫を確信します。
しかし、夫を問い詰めても「証拠がないだろう」と取り合わず「離婚はしてもいいが、慰謝料は払わない」と強気な態度を取り続けました。Bさんはこのままでは泣き寝入りになるのではと悩み、弁護士に相談することを決意しました。
弁護士に依頼してどう解決したのか
弁護士は、不倫の慰謝料請求には証拠が必要であることを説明し、探偵を使って証拠を集めることを提案しました。
その結果、夫と不倫相手がラブホテルに出入りする写真が撮影され、夫のスマートフォンからLINEのやり取りも確認できたため、不倫の事実が明確になりました。
これらの証拠をもとに弁護士が交渉を開始しました。当初は強気だった夫も、裁判になると不利になることを理解し、態度をやわらげます。最終的に夫は200万円、不倫相手の女性も100万円の慰謝料を支払うことで合意しました。
また、夫婦の共有財産である貯金や不動産についても弁護士が丁寧に整理し、折半する形で財産分与が成立。精神的にも経済的にも納得のいく離婚となりました。
争点と結果
このケースでは、不倫の慰謝料と財産分与が主な争点となりました。
結果として、Bさんは夫から200万円、不倫相手から100万円の慰謝料を受け取り、夫婦共有の財産もおおむね半分ずつ分け合う形で合意に至りました。
【事例3】財産分与で公平な結果を得たケース
離婚の際、とくに揉めやすいのが「財産分与」です。相手から過剰な要求をされても、法的な知識がなければ適切に対処するのは難しいものです。
ここでは、退職金や不動産の分け方で揉めたCさんが、弁護士のサポートを受けて公平な財産分与を実現した事例を紹介します。
どういう問題を抱えていたのか
Cさん(50代男性)は、30年近く連れ添った妻と離婚することになりました。夫婦関係は冷えきっており、離婚自体にはお互い合意していましたが、財産分与の話になると妻が「自宅はすべて私のものにすべき」「退職金もすべてもらうべき」と主張し、協議が難航してしまいます。
Cさんとしては、これまで家庭を支えるために働き続けてきたことから「財産は公平に分けたい」と考えていましたが、どう話を進めればいいのかわからず、弁護士に相談しました。
弁護士に依頼してどう解決したのか
弁護士はまず「結婚後に築いた財産は、基本的に夫婦で2分の1ずつ分けるのが原則」と説明し、妻の要求が過剰であることを法的な観点から整理しました。
さらに、自宅の購入資金や住宅ローンの支払いについてもCさん側が多く負担していた事実を資料から明らかにし、正確な財産の把握を進めました。
退職金についても「婚姻期間中に積み立てられた分のみが財産分与の対象となる」と説明し、全額を分けあう必要はないことを明確にし、妻側に理解を求めました。
弁護士が冷静かつ根拠に基づいた交渉を重ねた結果、最終的に自宅は売却し、売却代金を半分ずつ分けることで合意。さらに、退職金のうち500万円を妻に支払う形で話がまとまりました。
争点と結果
このケースでは、自宅などの不動産と退職金の分け方が主な争点となりました。
結果として、自宅は売却して売却代金を折半し、Cさんの退職金から500万円を妻に支払うことで、双方が納得できる形で財産分与が成立しました。
協議離婚における弁護士費用を抑える方法
弁護士費用は高額なため依頼を躊躇する方も多いのですが、以下の方法を活用すれば、費用面を抑えられます。
- 無料の法律相談を利用する
- 法テラスの民事法律扶助を利用して弁護士費用を立て替えてもらう
それぞれの方法について詳しく解説するので、費用面が気になる方は参考にしてください。
無料の法律相談を利用する
弁護士費用をできるだけ抑えたい方は、まず「無料の法律相談」を活用するのがおすすめです。今回実施した東京都で弁護士を利用した人向けアンケートでは、協議離婚で弁護士に依頼する前に無料相談を利用した人が約8割にのぼり、そのうち約8割(78.3%)が「利用してよかった」と回答しています。
無料相談を利用したきっかけとしては「無料ならとりあえず相談してみようと思った」「困っていてすぐに話を聞いてほしかった」といった声がみられました。費用面の不安や、弁護士に相談すること自体への心理的ハードルを感じていた方もいたようです。
相談先としては、弁護士事務所(30.8%)のほか、法テラス(23.1%)、弁護士会の相談センター(15.4%)、自治体の相談窓口(12.8%)などがあり「初回相談は30分〜1時間まで無料」としている弁護士事務所もあります。
実際に利用した人からは「費用の目安がわかって安心した」「自分の状況に合ったアドバイスがもらえた」などの満足の声が多く寄せられました。一方で「相談時間が短かった」「担当者と相性が合わなかった」といった不満もありましたが、全体としては満足度の高い結果といえるでしょう。
費用を抑えるだけでなく、弁護士との相性や対応の丁寧さを見極める場としても、無料相談は有効です。
- 弁護士の人柄や事務所の雰囲気がわかり、説明もわかりやすく安心できました。
- 法的なアドバイスに加えて、費用や手続きについても丁寧に説明してもらえ、不安が解消されました。
- 専門的なアドバイスを無料で受けられたことで、金銭面の不安もなく前に進むことができました。
法テラスの民事法律扶助を利用して弁護士費用を立て替えてもらう
法テラスでは、経済的に余裕がない方を対象に、弁護士費用などを立て替える「民事法律扶助制度」を利用できる場合があります。協議離婚を進めるうえで弁護士に依頼したいものの、費用面が心配という方は、まずこの制度の利用を検討してみましょう。
民事法律扶助を受けるためには、所得や資産などの経済条件を満たしていることに加えて「勝訴の見込みがないとはいえないこと」や「本人の意思での申請であること」など、いくつかの利用条件があります。
主な利用条件は以下のとおりです。
| 利用条件 |
内容 |
| 経済的条件 |
収入や資産が法テラスの基準以下であること(家族構成・住居費等により変動) |
| 勝訴の見込み |
「全く勝ち目がない」と判断されないこと(=ある程度の法的根拠があること) |
| 法律問題であること |
民事・家事・行政などの法的手続きに関する問題であること(道徳的・宗教的な相談などは対象外) |
| 本人の意思での申請 |
相談・申請が本人の意思に基づいて行われること(第三者の代理や強制によるものは不可) |
民事法律扶助を利用すれば、経済的負担を抑えつつ、法律の専門家による支援を受けられます。利用を希望する場合は、まず法テラスや弁護士に相談して、自分が条件を満たしているかどうかを確認してみましょう。
96%が「離婚問題を弁護士に依頼してよかった」と回答
自社アンケートによると、弁護士に離婚問題の対応を依頼した人のうち、96%が「依頼してよかった」と回答しています(※協議のみならず調停や裁判で弁護士利用した方も含む)
アンケートでは「期待通りの結果が得られた」という理由が最も多くあげられています。ほかにも「説明が的確だった」「弁護士が親身に対応してくれた」「費用が明確だった」など、対応力の高さが安心感にもつながったようです。
実際に利用した人からは「感情的になりやすい場面でも冷静な助言をもらえて落ち着いて対応できた」「複雑な手続きを任せられたことで時間にも心にも余裕が持てた」といった声が寄せられています。
自分ではどうにもならないと感じていた場面でも、専門知識のある弁護士に支えてもらうことで前に進めたという声が多くみられました。丁寧な対応と的確な判断が、利用者の満足度につながっていることがうかがえます。
実際に弁護士へ依頼した人たちからは、次のような声が寄せられました。アンケートで印象的だった体験談をいくつか紹介します。
弁護士の先生がとても親身に相談に乗ってくれ、分かりやすく説明してくれたので、納得できる結果につながりました。
ストレスの多い手続きをすべて任せられたおかげで、時間も気持ちも余裕を持って進めることができました。
息子が2人いるため親権のことで不安でしたが、先生の尽力で円満に話し合いが進み、本当に助かりました。
みんなは離婚に強い弁護士をどう選んでる?
協議離婚で弁護士に依頼すると決めたものの、どのような基準で弁護士を選べばよいか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、協議離婚の経験者を対象に「弁護士事務所を選んだ理由」についてアンケートを実施しました。
なかでも、とくに多くの方が重視していたのが、次の3つです。
- 家から近い弁護士事務所を選んだ
- 実績や経験が豊富な弁護士を選んだ
- 説明が具体的で分かりやすい弁護士を選んだ
ここでは、実際のアンケート結果をもとに、離婚に強い弁護士の選び方について詳しく解説します。
家から近い弁護士事務所を選んだ
アンケートでは「自宅から近い場所にあること」を理由に弁護士事務所を選んだ方が一定数いました。離婚問題は1回の相談で終わることは少なく、何度か足を運ぶ必要があるため、移動の負担が少ない立地を重視する傾向があります。
現在ではオンライン相談に対応している弁護士も増えていますが「直接会って話したい」「顔を見ながら説明を受けたい」と考える方も少なくありません。実際に「何度か通うことを考えて近くの事務所を選んだ」「話してみて印象がよかったので依頼を決めた」といった声も寄せられました。
実績や経験が豊富な弁護士を選んだ
アンケートで最も多かった理由は「実績や経験が豊富だったから」という回答でした。離婚問題は慰謝料や財産分与、親権、養育費など、取り決めるべきことが多いため、法律知識だけでなく実務経験も重要です。
たとえば「DVや不倫のトラブルがある」「親権を確保したい」「相手と条件面で折り合わない」など、複雑な事情を抱えている場合は、離婚分野に特化した実績のある弁護士に相談するのが望ましいといえます。
アンケートでは「ホームページで解決事例をみて信頼できそうだった」「自分と似たケースを取り扱っていた」という声も寄せられました。事務所の得意分野や過去の実績を確認しておくことが、弁護士を選ぶ際の重要なポイントといえます。
説明が具体的で分かりやすい弁護士を選んだ
離婚に関する手続きでは、法律用語や制度の説明を受ける機会が多くあります。そのため「説明が具体的でわかりやすかった」「今後の流れや手順を丁寧に教えてくれた」などの理由で弁護士を選んだ方もいました。
信頼できる弁護士は、専門用語をかみ砕いて説明し、見通しやリスクについても明確に伝えてくれます。「無料相談の段階で信頼できると感じた」「話しやすさが決め手になった」という声もありました。
初回相談では、説明の丁寧さや質問への対応力など、コミュニケーションのしやすさを意識して確認するとよいでしょう。弁護士との相性や信頼感は、協議離婚をスムーズに進めるうえで重要な要素となります。
まとめ
協議離婚は夫婦の話し合いで進められる手続きです。しかし状況によっては弁護士に依頼すると、よりスムーズかつ有利に進められる場合があります。とくに相手の弁護士から連絡を受けている場合や、交渉が思うように進まないと感じている場合は、弁護士に依頼することを検討すべきでしょう。
弁護士に依頼すれば、書類作成や慰謝料・養育費の算定、代理人としての交渉など、専門的な部分を任せられるため、精神的な負担の軽減にもつながります。DVやモラハラなど、深刻な問題を抱えている場合には、弁護士が間に入ると安全に離婚を進められる可能性も高くなるでしょう。
ただし、弁護士に依頼すれば費用がかかるうえ、必ずしも希望どおりの結果が得られるとは限らないことも事前に理解しておく必要があります。費用や相性の不安がある場合は、無料相談を活用するなど、納得できるかたちで進めることが大切です。
離婚は今後の生活に大きく影響する節目です。協議離婚の話し合いに不安を覚えている方は、ぜひ弁護士への依頼を検討してみてください。
協議離婚を弁護士に依頼する際によくある質問
協議離婚の弁護士費用は自己負担ですか?
協議離婚を弁護士に依頼する際の費用は、基本的に自己負担となります。相手に弁護士費用を支払わせたり、国から助成金をもらったりすることはできません(※ただし収入などの条件を満たせば、法テラスの民事法律扶助制度を利用できる場合もあります)。
たとえばDVや不倫など、相手に非がある場合の離婚だとしても、原則として自分自身で支払う必要があります。
弁護士に依頼して離婚手続きを進めるかどうかは、依頼者本人の意思によるものだからです。
離婚裁判まで進めば慰謝料に弁護士費用の一部を上乗せできるケースもありますが、協議離婚では相手方に弁護士費用の請求はできません。
弁護士に離婚届の証人を依頼することはできますか?
弁護士に離婚届の証人を依頼できるかどうかは、事務所や弁護士の考え方によって異なります。
離婚届には18歳以上の証人2名の署名が必要ですが、証人を頼める人が身近にいない場合は、弁護士に依頼して引き受けてもらえるケースもあります。
ただし、離婚届の証人になることは基本的に弁護業務には含まれていないため、断られる可能性もあります。
そのため、弁護士に離婚届の証人になってもらいたい場合は、依頼先の弁護士に相談して確認しておきましょう。
弁護士に離婚届の証人を依頼することはできますか?
弁護士に離婚届の証人を依頼できるかどうかは、事務所や弁護士の考え方によって異なります。
離婚届には18歳以上の証人2名の署名が必要ですが、証人を頼める人が身近にいない場合は、弁護士に依頼して引き受けてもらえるケースもあります。
ただし、離婚届の証人になることは基本的に弁護業務には含まれていないため、断られる可能性もあります。
そのため、弁護士に離婚届の証人になってもらいたい場合は、依頼先の弁護士に相談して確認しておきましょう。