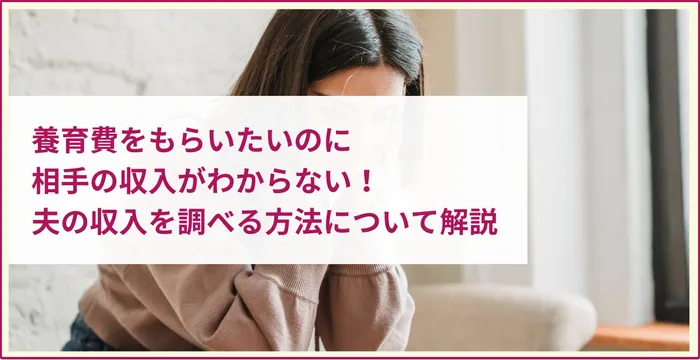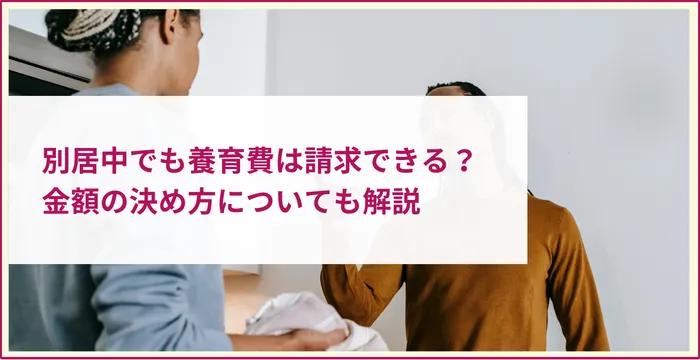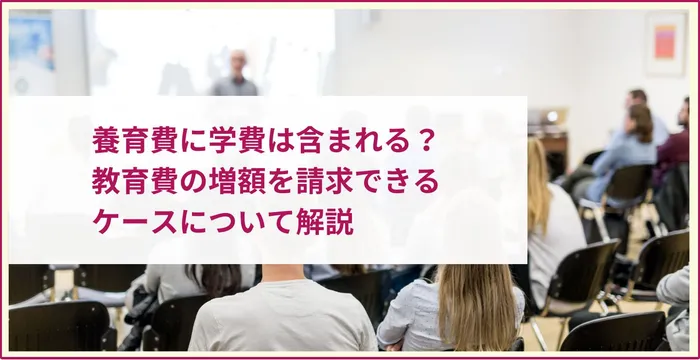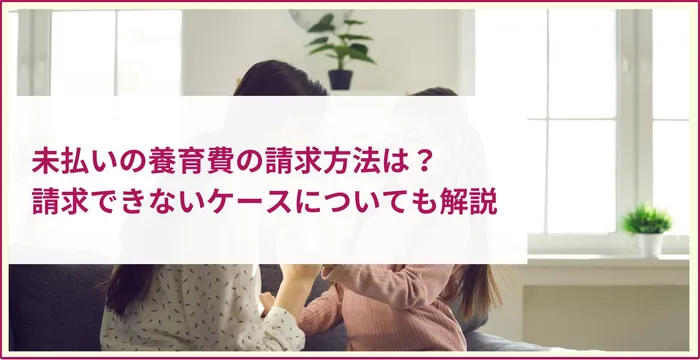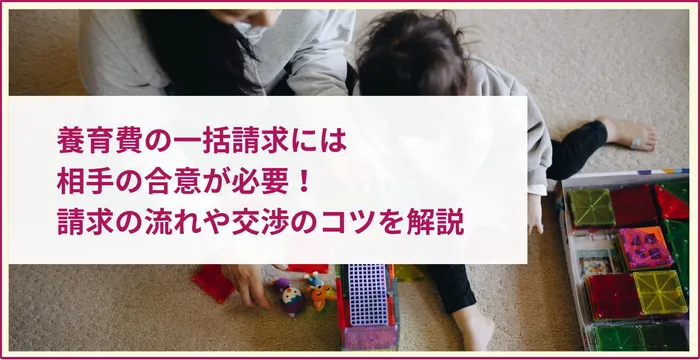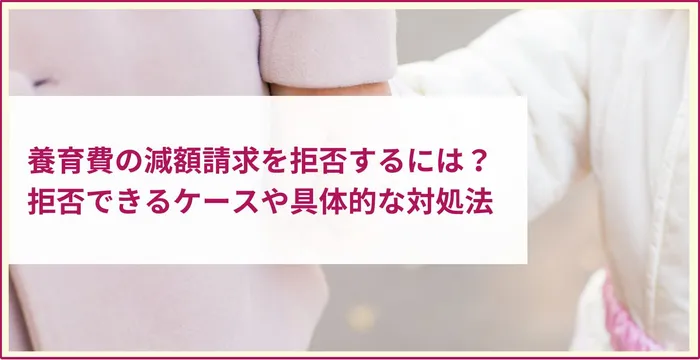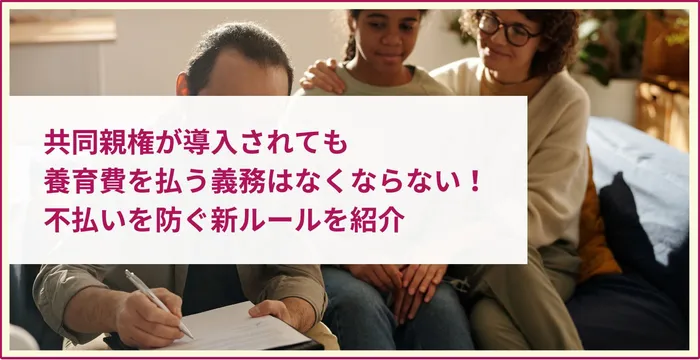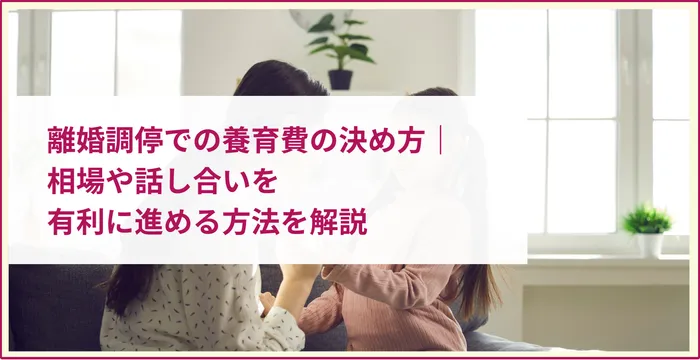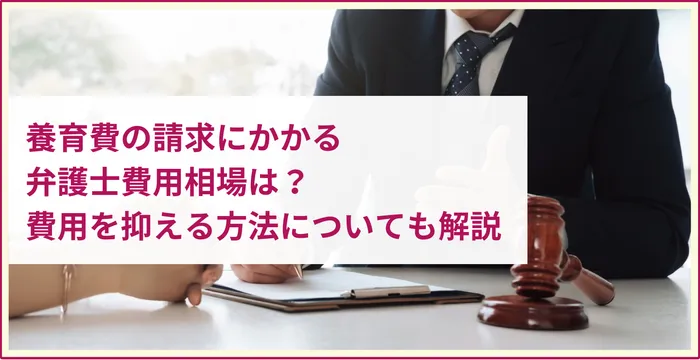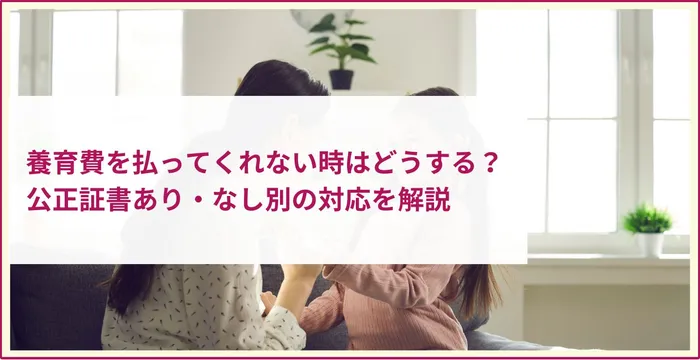養育費を請求したいものの、相手方の収入が分からず困っていませんか?実は収入を調べる方法は、同居中と調停・審判手続中で異なっているのです。本記事では養育費義務者の収入の調査方法や、養育費の算定方法について解説していきます。
養育費一覧
カテゴリーから離婚コラムを探す
未成熟の子どもがいる夫婦が別居した場合、子どもと一緒に暮らして養育している親は、子どもと離れて暮らす相手に対して養育費を請求できます。本記事では、別居中に養育費を請求できるケースや別居中の養育費の決め方、注意点について解説します。
養育費には公立学校を前提とした学費が含まれるのが一般的であり、私立や大学の費用は考慮されていません。そのため養育費を増額するためには、相手と交渉して合意を得る必要があります。本記事では、養育費を増額請求できるケースなどについて解説します。
何度請求しても支払いがない場合は、調停や審判の手続きを経て強制執行で相手の財産を差し押さえ、未払い分の養育費を回収できます。本記事では、養育費が未払いになった場合の回収方法や時効について解説していきます。
元配偶者の合意さえ得られれば養育費の一括請求は可能です。ただし、相手に養育費を全額支払えるだけの経済能力や資産があることが前提となります。本記事では、養育費の一括請求をする方法や、一括請求のメリット・デメリットなどを解説します。
養育費は子どもの生活や教育に必要な費用であるため、相手の一方的な都合で減額請求された際には拒否できる可能性があります。ただし、事故や病気、再婚などやむを得ない事情がある場合は、減額請求の拒否が難しくなるでしょう。
2026年5月までに開始する共同親権制度下でも、養育費の支払義務や金額などに影響はありません。むしろ、養育費がより確実に支払われる制度も開始します。新たな法制度で適切な対応ができるよう、弁護士への相談をおすすめします。
離婚調停における養育費は、養育費算定表をもとに決められます。ただし、子どもの進学状況や健康状態などで変わることもあります。本記事では、事例をもとに養育費の相場や離婚調停で話し合いを有利に進めるためのポイントについて解説します。
養育費に関する弁護士費用の相場は、結果にかかわらず必ず必要な着手金は30万円程度、養育費を獲得または減額できた際の報酬金は30万円と5年分の16%程度です。仮に獲得した養育費が月額5万円の場合、着手金と報酬金の合計額は108万円となります。
相手が養育費を払ってくれず、話し合いで解決できない場合は公正証書の有無によって対応方法が変わります。公正証書がある場合は、履行勧告や履行命令を経て強制執行が可能です。公正証書がない場合は、養育費背教調停の申し立てが必要です。