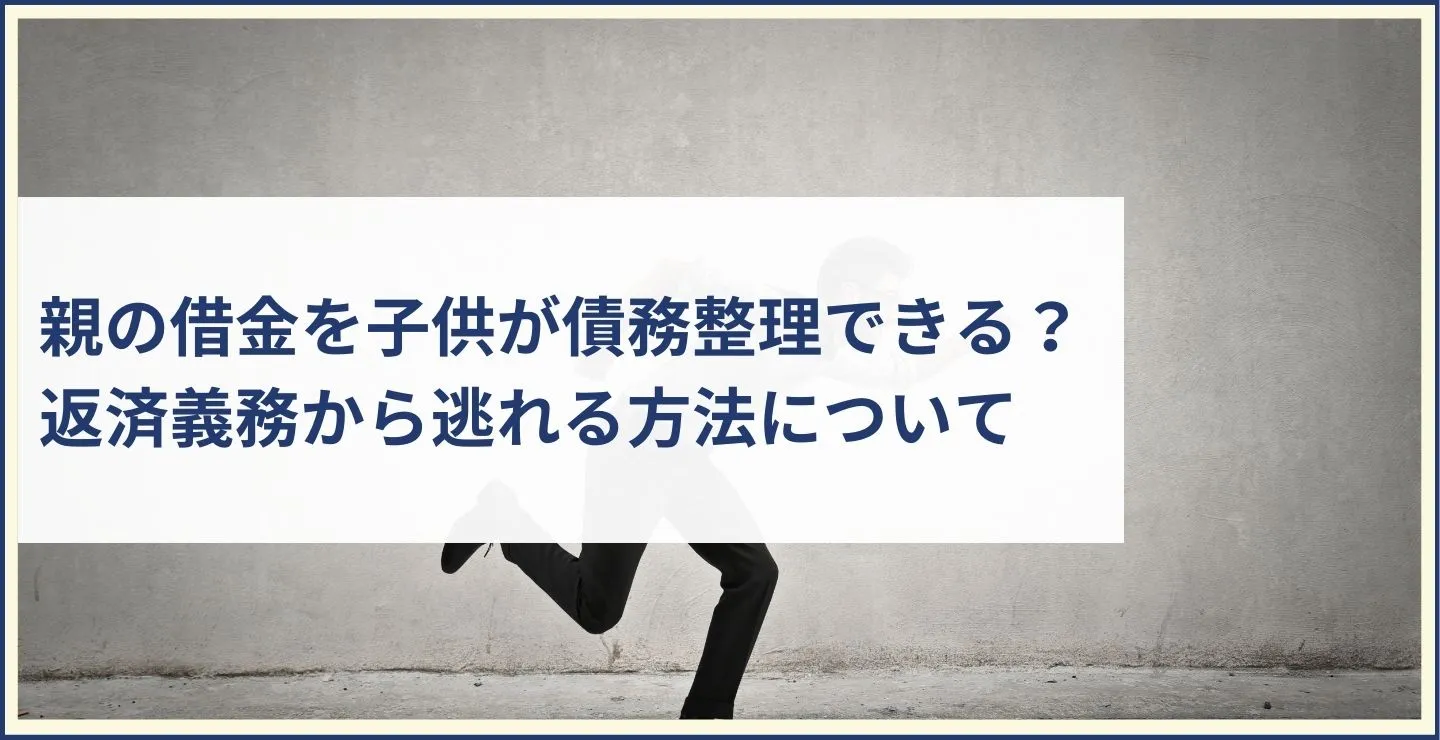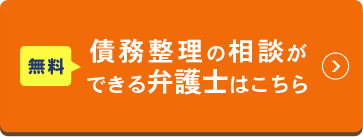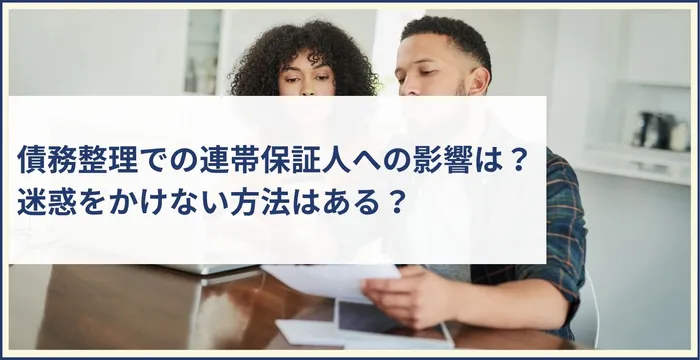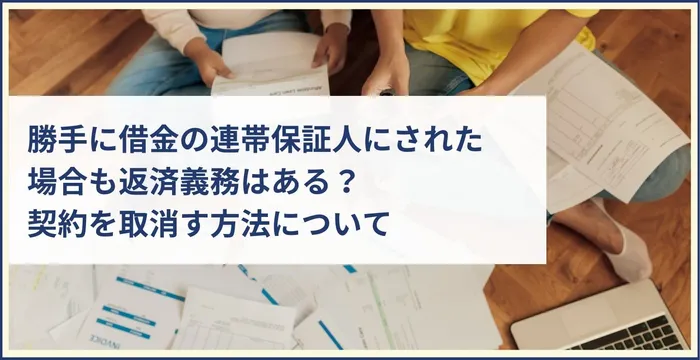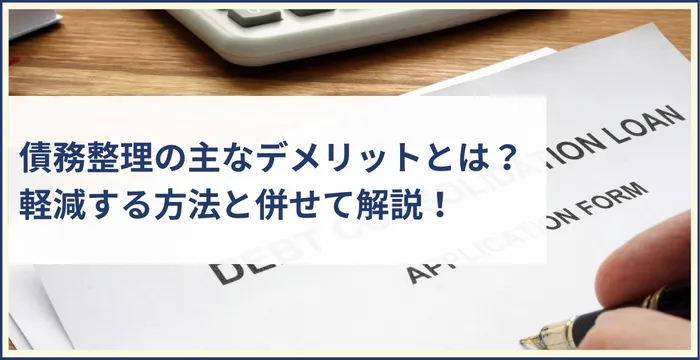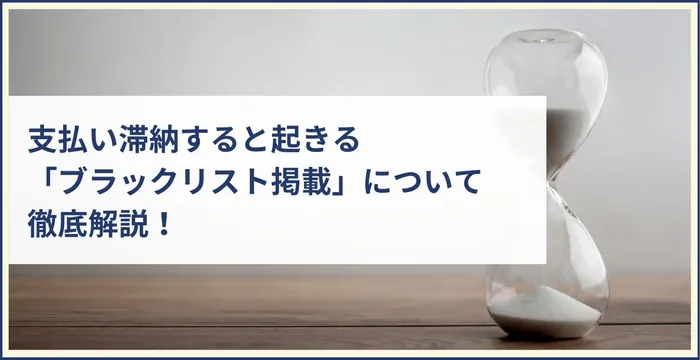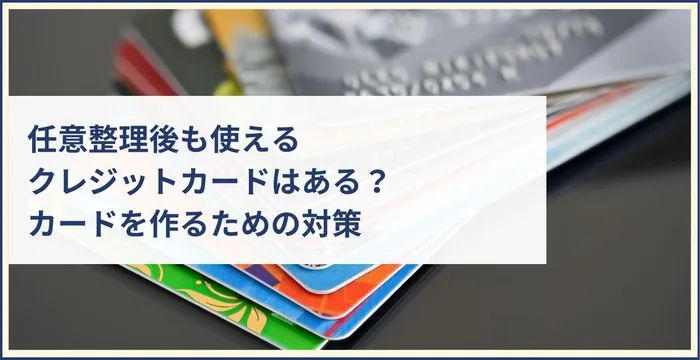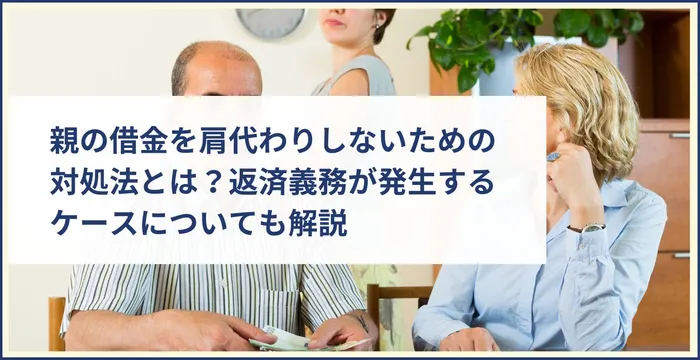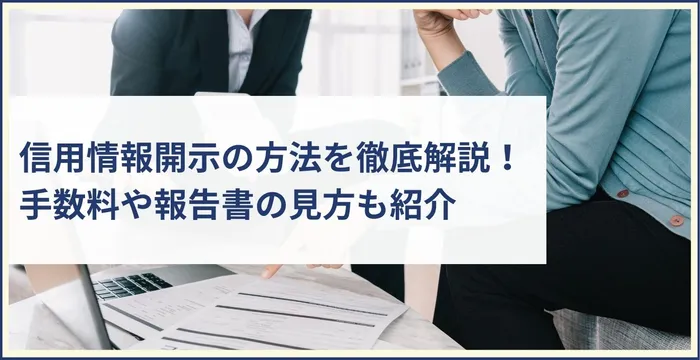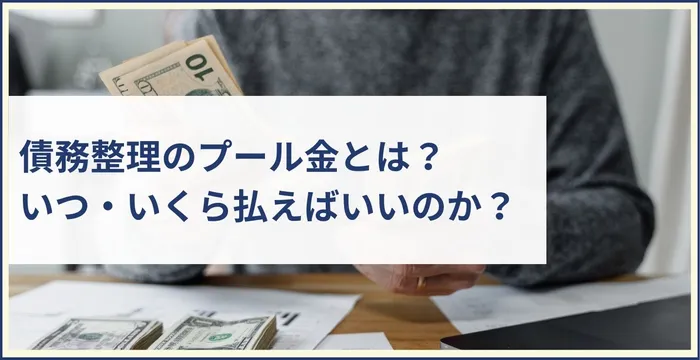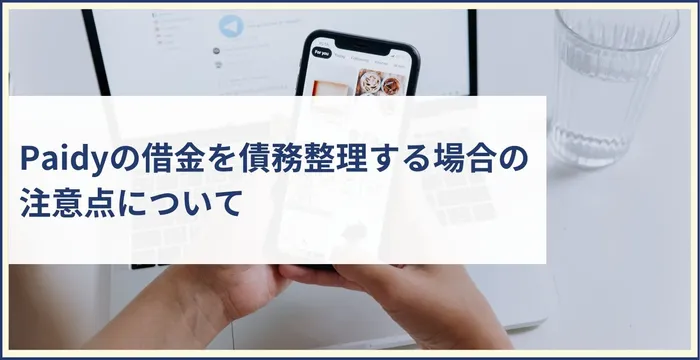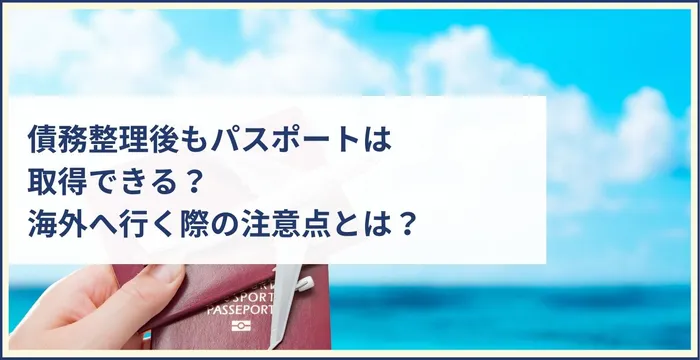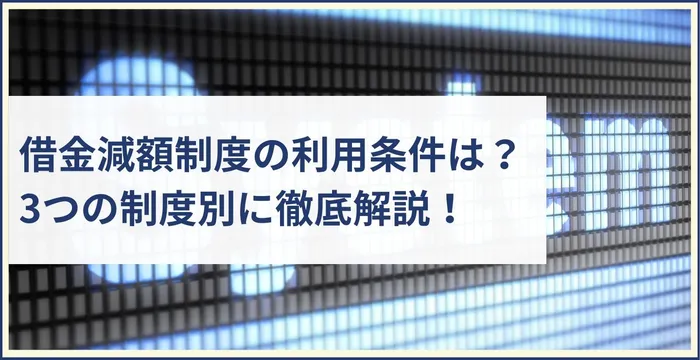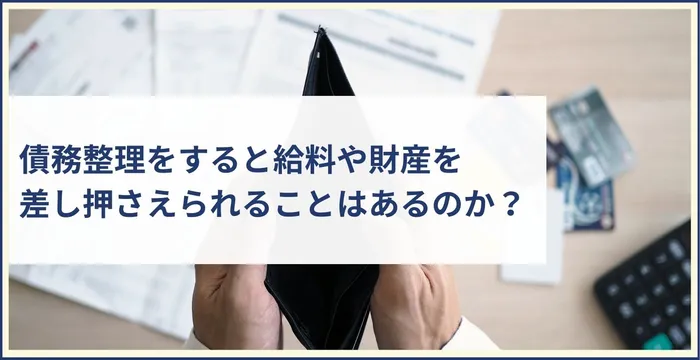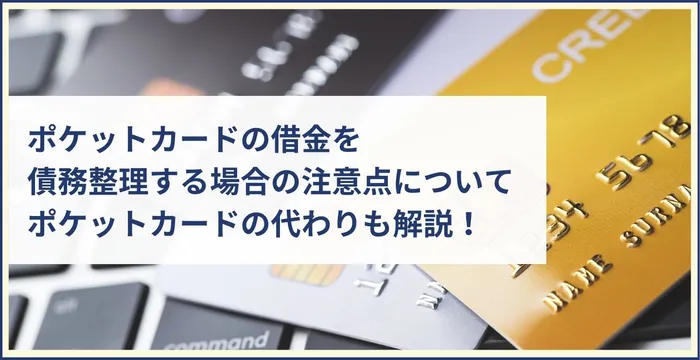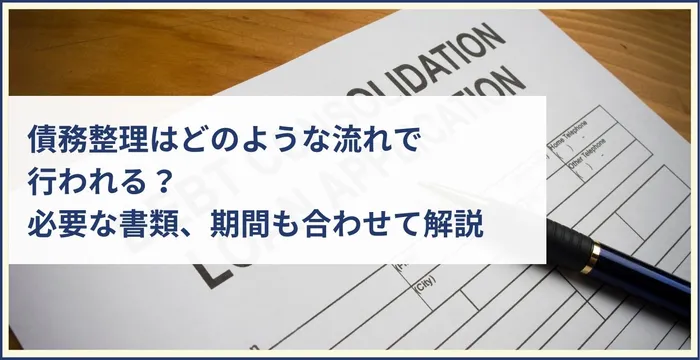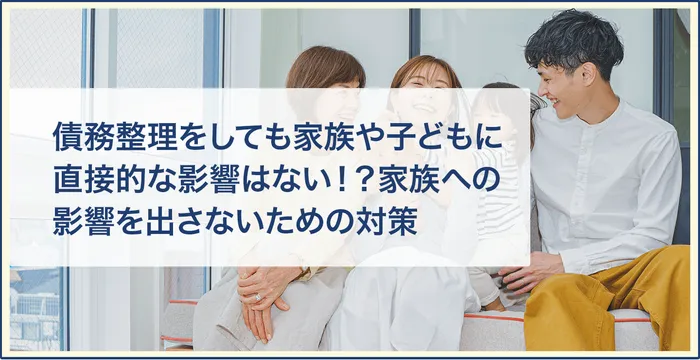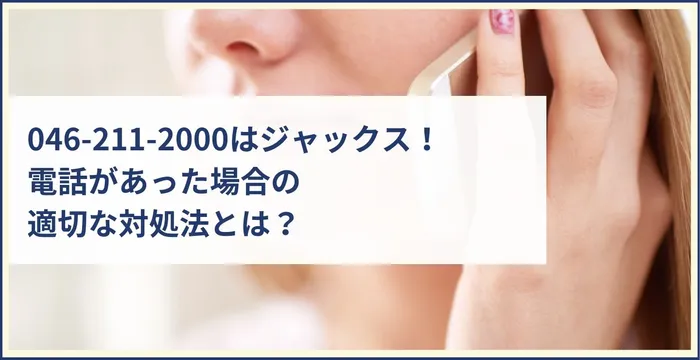親の借金を子供が債務整理することは原則不可能
結論からいうと、親の借金を子供が代わりに債務整理することは不可能です。債務整理の手続きは、基本的に借金をした債務者しか行えません。
そもそも借金とは、債務者と貸金業者の間で交わした契約に基づくものです。そのため、第三者が勝手に契約内容を変更することは認められていません。
しかし、親の借金が発覚した際、子供が少しでも返済を楽にしてあげたいと考えることは自然なことです。
その場合、親が自ら手続きを進められるように債務整理の仕組みを説明したり、弁護士を紹介したりするなどのサポートするのは問題ありません。
また、例外として親が認知症や精神疾患、後遺障害などの理由で判断能力を失っている場合には、裁判所から選任された成年後見人が債務整理の手続きを進められます。
親が債務整理をする際に子どもがサポートすることは問題ない
前述のとおり、親が債務整理をする際に、子供が親のサポートをすること自体は問題ありません。債務整理の依頼は債務者本人しか行えませんが、親に債務整理を行うことを勧めたり、債務整理の手続きにかかる費用を負担してあげたりすることなら可能です。
親の借金問題をそのまま放置すると、利息や遅延損害金で借金がますます膨らんでしまい、将来的には親が抱えた多額の借金を子供が肩代わりすることにもなりかねません。そのため、親が借金を抱えていて返済がどうしても難しい場合は、親が存命中に債務整理を行ってもらい、早めに借金問題の解決を図ることが得策だといえます。
しかし、債務整理は手続きが複雑で精神的にも大きな負担がかかります。そのため、子供は債務整理を行う親に精神的に寄り添いながら、手続きがスムーズに進むように優しくサポートしてあげることが大切です。
親の借金であっても返済義務がないなら応じる必要はない
親の借金であっても、借金の返済義務がなければ子供は返済に応じる必要はありません。借金の返済義務を負うのは、原則として借金した債務者本人のみです。
親の借金の保証人・連帯保証人になっている場合や死亡した親の借金を相続した場合など、後述する一部のケースでは子供が返済義務を負う可能性がありますが、そうでなれば子供が返済義務を負うことはありません。
これは、親と生計を同一にしている場合でも、別々に暮らしている場合でも同様です。
自分に返済義務が生じていれば親の借金を債務整理できる
原則として子供は親の借金を肩代わりする必要はありませんが、例外的に親の借金の返済義務が子供に生じるケースも存在します。
- 死亡した親の借金を相続した場合
- 親の借金の保証人・連帯保証人になっている場合
- 親が子供名義で借金をしていた場合
親の借金を子供が代わりに債務整理することは原則として不可能ですが、親の借金の返済義務が子供に生じている場合は子供も債務整理を行うことが可能です。親の借金を肩代わりするのが難しい場合は、債務整理を行って借金の負担を軽減することも検討してみましょう。
ここからは、親の借金の返済義務が子供に生じるケースを1つずつ解説していきます。
死亡した親の借金を相続した場合
親が死亡して相続が発生すると、子供は死亡した親の財産を相続する権利が得られます。遺産相続は、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産をすべて引き継ぐ「単純承認」という方法で行われるケースが多いです。
親が借金を抱えたまま死亡し、何も手続きをせずそのまま相続が行われることになった場合は、親の借金の返済義務も引き継がれることになります。
親の借金を相続したくない場合は、「相続放棄」を行ってすべての財産を放棄するか、「限定承認」を行ってプラスの財産と親の借金を相殺しましょう。
親の借金の保証人・連帯保証人になっている場合
子供が親の借金の保証人・連帯保証人になっている場合は、子供にも親の借金の返済義務が生じます。保証人や連帯保証人とは、お金を借りた主債務者が借金を返済できなくなった場合に、主債務者の代わりに借金の返済義務を負わされる人物のことです。
保証人や連帯保証人は、主債務者が返済できなくなった場合に返済義務を負う点は共通していますが、以下の3点に違いがあります。
| 項目 |
保証人 |
連帯保証人 |
| 債権者から借金返済を請求された場合 |
主債務者に返済能力がある場合は「先に主債務者に請求してください」と主張して、債権者からの請求を拒否できる |
主債務者に返済能力があっても、債権者からの請求は拒否できない |
| 債権者から強制執行をかけられた場合 |
主債務者に資力がある場合は「先に主債務者の財産を差し押さえてください」と主張して、強制執行を拒否できる |
主債務者に資力があっても、強制執行は拒否できない |
| 保証人が複数いる場合 |
保証人の人数で割った金額のみ返済義務が生じる |
人数にかかわらず、1人ひとりに借金全額の返済義務が生じる |
主債務者である親が借金を完済しない限り、親の借金を肩代わりしなければならないリスクが常に生じるため、親の借金が発覚した場合は自分が保証人・連帯保証人になっていないか確認しましょう。
勝手に連帯保証人にされた借金であれば返済義務はない
保証契約は、保証人・連帯保証人となる本人と債権者との間で交わされる契約です。そのため、親が代わりに子供を保証人・連帯保証人とする保証契約を交わす場合は、事前に子供の許可を得て代理権を取得しておく必要があります。
代理権とは、本人に代わって法律行為を行う権限のことで、子どもが未成年の場合は親権者が自動的に子どもの代理権を持つことになっています。もし、勝手に親の借金の保証人・連帯保証人にされていた場合は、無権代理行為にあたるとして保証契約の効力は子供に及ばないため、親が借金を返済できなくなっても子供は借金を肩代わりする必要はありません。
ただし、子供が親の借金の保証人・連帯保証人であることを認めたり、債権者からの請求に応じて返済したりした場合は、本来無効であるはずの契約が最初から有効であったとみなされてしまいます。
子供が保証人・連帯保証人としての責任を負うことになるので注意が必要です。
親が子供名義で借金をしていた場合
親が子供名義で借金をしていた場合も、借金の返済義務は親ではなく子どもが負います。たとえば、親の支払い能力が乏しく、親名義では借金ができない場合に、子供が親に自分の名義を貸して借金したとします。
この場合、子供は名義を貸しただけで実質的な借主は親であるといえるため、借金の返済義務は親にあると思われるかもしれません。しかし、成人した子供が同意の上で自分の名義を親に貸して借金した場合、法的には名義人である子供に借金の返済義務があります。
実際には親が返済するケースが多いですが、あくまで借金の返済義務は名義人にあるため、親が借金を返済できなくなった場合は子供が借金を返済しなければなりません。
知らないうちに自分の名義で親が抱えた借金であれば返済義務がない
親が子供名義で借金をしていても、子供が知らないうちに親が勝手に子供名義で借金をしていた場合は、子供に借金の返済義務はありません。成人した子供が親に対して借金の代理権を与え、それに基づいて親が子供名義で借金をしていた場合は、名義人である子供が返済義務を負います。
しかし、子供が代理権を与えていないにもかかわらず、親が勝手に子供名義で借金をしていた場合は無権代理行為にあたるため、名義人である子供には返済義務が生じません。ただし、子供が債権者からの請求に応じてしまったり、契約内容が有効であることを認めたりすると、本来無効であるはずの契約が最初から有効であったとみなされてしまいます。
すると、子供に借金の返済義務が生じてしまうので注意が必要です。
親の借金を債務整理するならデメリットを十分に把握しておくべき
債務整理を行えば合法的に借金を減額・免除できますが、債務整理には以下のようなデメリットもあります。
- いわゆるブラックリスト入りの状態になる
- 契約しているクレジットカードやローンが解約されるのが一般的
- 保証人を立てている借金を債務整理するとその人に返済義務が生じる
債務整理にも種類があり、それぞれ異なるデメリットもありますが、上記のデメリットは任意整理・個人再生・自己破産のいずれの手続きでも必ず生じます。親の借金を債務整理する際は、これらのデメリットをよく理解した上で本当に手続きを行うべきか十分に検討することが大切です。
ここからは、債務整理のデメリットについて1つずつ解説していきます。
いわゆるブラックリスト入りの状態になる
借金を債務整理すると、いわゆるブラックリスト入りの状態になります。ブラックリスト入りの状態とは、信用情報機関が管理している信用情報に、借金の滞納や債務整理を行った履歴が登録された状態のことです。
ブラックリスト入りの状態だと返済能力がないと判断されるため、クレジットカードやローンなど以下の審査に通りづらくなります。
- クレジットカード
- 新たな借り入れやローン
- 携帯電話・スマホ端末の割賦契約
- 保証会社を通した賃貸物件の契約
ブラックリスト期間は債務整理の手続きの種類や信用情報機関によって異なりますが、手続きが完了してから最長5~7年は履歴が残ります。
契約しているクレジットカードやローンが解約されるのが一般的
債務整理を行うと、契約しているクレジットカードやローンは原則として強制解約となります。解約のタイミングは、弁護士がカード会社へ受任通知を送った時点からで、即日利用停止となるケースもあります。
また、クレジットカード会社は、キャッシングとショッピングを分けて扱うことはほぼないため、一部の機能だけを継続することはできないと考えられます。そのため、債務整理の対象にした借金がキャッシング枠のみであっても、同じカードのショッピング枠も使用不可となります。
さらに、クレジットカードに付随する家族カードやETCカードも利用不可となるため、親と同じカードを使っている家族がいる場合は、事前に説明しておくことが大切です。
保証人を立てている借金を債務整理するとその人に返済義務が生じる
債務整理を行うと主債務者の借金は減額・免除されますが、保証人・連帯保証人の債務は減額・免除されません。そのため、保証人・連帯保証人は債務整理前にあった借金全額を返済する義務を負います。
保証人・連帯保証人も経済的に苦しく借金を肩代わりするのが難しい場合は、主債務者だけでなく保証人・連帯保証人も債務整理を検討することになるでしょう。このように、保証人・連帯保証人を立てている借金を債務整理すると、保証人・連帯保証人に多大な迷惑をかけることになります。
そのため、債務整理を行う場合は保証人・連帯保証人への影響も十分に理解しておく必要があります。
親の借金を子供が肩代わりしないための対処法
親の借金を子供が肩代わりしたくない場合は、以下の方法で返済義務を回避できます。
- 親の存命中に債務整理をしてもらう
- 親の死後に相続放棄・限定承認をおこなう
ここからは、それぞれの対処法について1つずつ詳しく解説していきます。
親の存命中に債務整理をしてもらう
親に返済能力があれば親自身に借金を返済してもらうのがベストですが、親に返済能力がなく自力で借金を返済するのが難しい場合もあるでしょう。そういった状況での借金問題の解決手段として、親自身に債務整理を行ってもらう方法があります。
債務整理とは、債権者との交渉や裁判所への申し立てにより、借金を減額または返済義務を免除してもらう制度です。債務整理には以下の3つの方法があります。
| 任意整理 |
返済条件を見直してもらうために債権者と交渉をする手続き。将来利息や遅延損害金のカットに応じてもらえるのが一般的。 |
| 個人再生 |
裁判所へ申立てて借金を1/5~1/10程度減額してもらい、残りの借金を原則3~5年かけて返済する方法 |
| 自己破産 |
裁判所へ申立てを行い、借金全額(非免責債権を除く)の返済義務を免除してもらう方法 |
親自身が債務整理を行って借金の負担を軽減すれば、相続で親の借金を肩代わりせずに済む可能性があります。とはいえ、親に債務整理を勧めても、本人にその気がなければ手続きを進められないため、以下のような債務整理のメリットを伝えてあげて、親を説得するとよいでしょう。
- 債務整理をすれば借金が減額・免除される
- 過払金が発生していればお金が返ってくる
- 親だけでなく家族全体の生活が楽になる
- 弁護士に依頼した時点で即座に取立てが止まる
- 依頼した弁護士にほとんどの手続きを任せられる
ただし、子供が保証人や連帯保証人となっている親の借金を債務整理した場合は、子供が債権者から一括請求を受けることになるので注意が必要です。
債務整理による減額効果が及ぶのは主債務者である親の借金のみで、保証人や連帯保証人の債務は一切減額・免除されないため、子供は親の自己負担分を差し引いた残りの借金を肩代わりしなければなりません。
親の死後に相続放棄・限定承認をおこなう
親がすでに死亡している場合は、相続放棄や限定承認を行うことで親の借金の返済義務から回避できます。
| 相続放棄 |
プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法 |
| 限定承認 |
相続したプラスの財産を限度として、マイナスの財産も引き継ぐ方法 |
相続放棄を選択した場合は、プラスの財産が引き継げなくなる代わりに、マイナスの財産も一切引き継がれないため、親の借金を返済する必要はありません。プラスの財産がほとんどなく、多額の借金しか残らない場合は相続放棄を検討してみましょう。
限定承認を選択した場合は、プラスの財産の範囲内で親の借金の返済義務を引き継ぐことになりますが、相続したプラスの財産以上の借金を肩代わりする必要はありません。相続したプラスの財産で親の借金を返済した後、プラスの財産が残った場合はその財産を相続できます。
借金を返済しきれなくても、超過分の借金の返済義務を相続せずに済むため、子供が自腹を切ってまで親の借金を肩代わりする事態は避けられるのがメリットです。そのため、プラスの財産と親の借金がどれくらいあるのか不明な場合や、プラスの財産が親の借金額を上回る場合は、限定承認を検討してみましょう。
なお、相続放棄と限定承認の手続きは相続発生を知った日から3ヶ月以内でないと行えないため、親の借金の返済義務を負いたくない場合は早めに手続きを済ませておきましょう。
親に借金があるかを調査する方法
親が銀行や消費者金融、クレジットカード会社などから借金をしていた場合は、信用情報機関に親の信用情報の開示請求を行うことで借金を調査できます。信用情報機関は以下の3社あり、それぞれ管理している金融機関の信用情報が異なるため、親が借金をしていたと思われる金融機関に対応した信用情報機関に問い合わせてみましょう。
| 信用情報機関 |
対応する金融機関 |
| CIC |
アイフル・アコム・プロミス・SMBCモビット・みずほ銀行・楽天銀行など |
| JICC |
アイフル・アコム・プロミス・SMBCモビットなど |
| KSC |
みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・楽天銀行・オリックス銀行など |
ただし、個人間融資や勤務先からの借入などは信用登録機関に登録されないため、存命中の親に直接確認するか、既に亡くなっている場合は債権者を探さなければなりません。
また、既に親が亡くなっている場合か存命中の親から許可を得た場合でない限り、子供であっても親の信用情報を勝手に開示することはできないため注意しましょう。
債務整理を検討するほど親に借金があるなら弁護士・司法書士に相談するべき
債務整理を検討するほど親が多額の借金を抱えている場合は、早めに弁護士や司法書士に相談するのが得策です。弁護士や司法書士に相談すれば、下記のような親の借金や債務整理に関する不安や疑問点について、法律の専門知識や経験に基づく的確なアドバイスが受けられます。
- 子供に親の借金の返済義務があるのか
- 債務整理をすべきかどうか
- どの方法で債務整理をすべきかどうか
また、弁護士は代理人として債務整理の手続きを進められるほか、依頼すれば下記のようにさまざまなメリットがあります。
- 債権者からの取り立てがストップする
- 債務整理の手続きにかかる手間やストレスを大幅に軽減できる
- 有利な条件で債務整理を進めやすい
親が債務整理の手続きに前向きではない場合でも、専門家を介して説得すれば債務整理に応じてくれるケースも多いため、まずは弁護士や司法書士に相談してみましょう。
まとめ
借金の名義人・保証人・連帯保証人になっている場合、または親の死後に借金を相続した場合でない限り、基本的に親の借金を子供が返済する必要はありません。
しかし、親が生きている限り、親の借金を子供が債務整理することはできないので、親本人に債務整理をおこなってもらうか、親の死後に相続した借金を債務整理しましょう。
とはいえ、自分で債務整理をおこなう場合、5〜10年はクレジットカード・各種ローンなどを利用できなくなるため、なるべく親に債務整理をおこなってもらうことをおすすめします。
自力で親を説得できない場合でも、弁護士を介してメリットを伝えれば、親が債務整理に納得してくれるケースも多いので、まずは弁護士に相談してみるとよいでしょう。
親の借金に関するよくある質問
親の借金でも、子供に返済義務はありますか?
死亡した親の借金を相続した場合、親が子供名義で借金をしていた場合、借金の保証人・連帯保証人だった場合を除いて、親の借金を返済する義務は子供にありません。
親の借金を子供が債務整理することは可能ですか?
債務整理は債務者本人しかおこなえないため、親の死後でない限り、子供が親の借金を債務整理することはできません。
どうすれば親の借金を子供が返済せずに済みますか?
存命中の親に債務整理をしてもらい借金を減額するか、親の死後に相続放棄または限定承認という手続きをおこないましょう。
どうすれば親に債務整理をおこなってもらえますか?
「債務整理をすれば借金が減額・免除される」といったメリットを伝えたり、弁護士と協力して親を説得するとよいでしょう。
どうすれば親の借金を調査できますか?
親が借金をしていたと思われる金融機関に対応している信用情報機関へ問い合わせて、信用情報の開示請求をおこないましょう。
亡くなった親の借金は相続放棄をしてしまうと自分が返済しなければなりませんか?
亡くなった親の借金を相続放棄した場合は、親の借金を返済する必要はありません。相続放棄をすれば、預貯金や不動産などのプラスの財産が相続できなくなる代わりに、借金などのマイナスの財産も一切引き継がれなくなります。
絶縁した親の借金は子供が返済するのでしょうか?
親と絶縁していても法律上の親子関係は解消されないため、絶縁した親の遺産を相続した場合は親の借金の返済義務も負うことになります。また、絶縁した親の借金の保証人・連帯保証人になっている場合は、親と絶縁した後も保証人・連帯保証人であることに変わりないため、親が借金を返済できなくなった場合は子供に返済義務が生じます。
親の借金を子供が返済するべきかがわかりません。どこに相談すればいいでしょうか?
親の借金を子供が返済するべきかがわからない場合は、法律の専門家である弁護士や司法書士に相談しましょう。弁護士や司法書士に相談すれば、子供に親の借金の返済義務があるかどうか、親に債務整理を勧めるべきかどうか適切なアドバイスがもらえます。
親の借金を相続放棄した場合は誰が返済するのでしょうか?
親の借金を相続放棄した場合、自分以外に親の遺産を相続した人がいれば、その相続人が主債務者として親の借金を返済する義務を負います。相続人全員が相続放棄を選択し、親の遺産を相続する人が誰もいない場合は、保証人や連帯保証人が親の借金を肩代わりすることになります。なお、保証人や連帯保証人としての責任は相続放棄をしても必ず引き継がれるため、子供が親の借金の保証人や連帯保証人になっている場合は相続放棄をしても返済義務が残ります。
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-