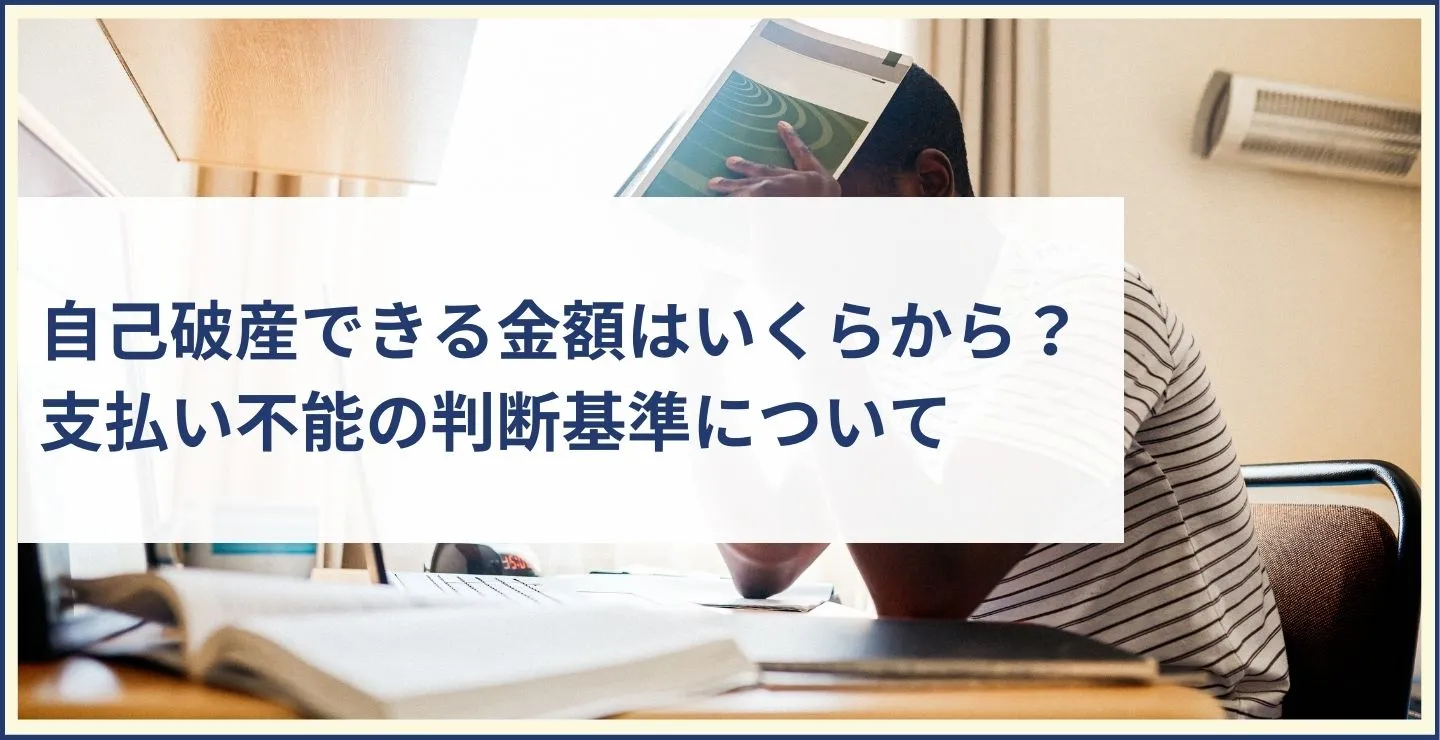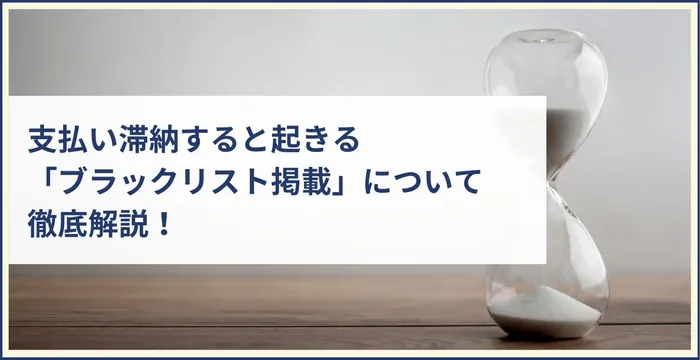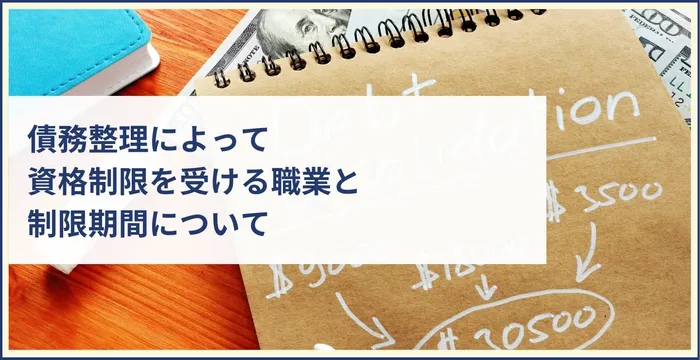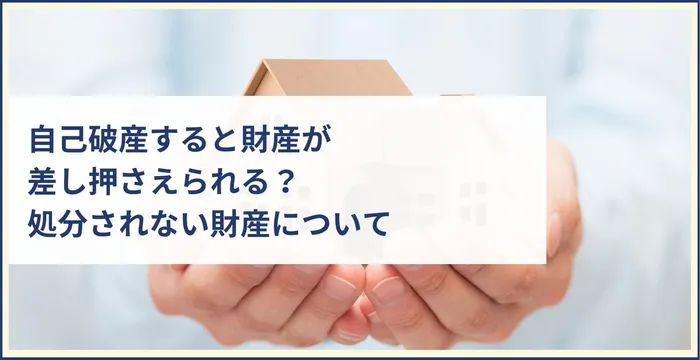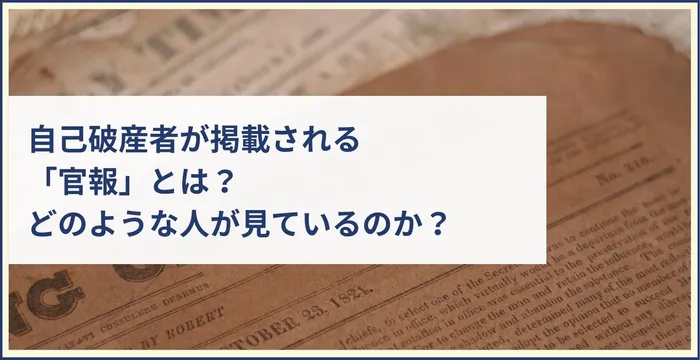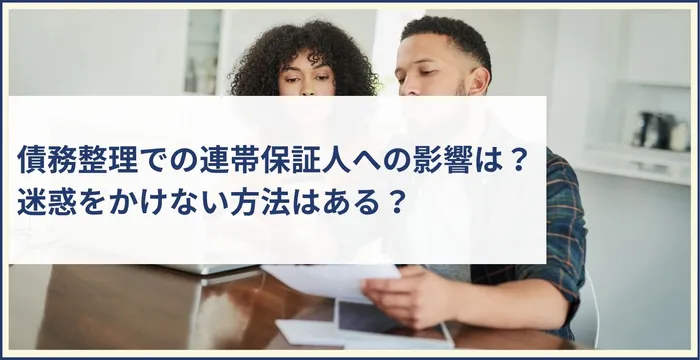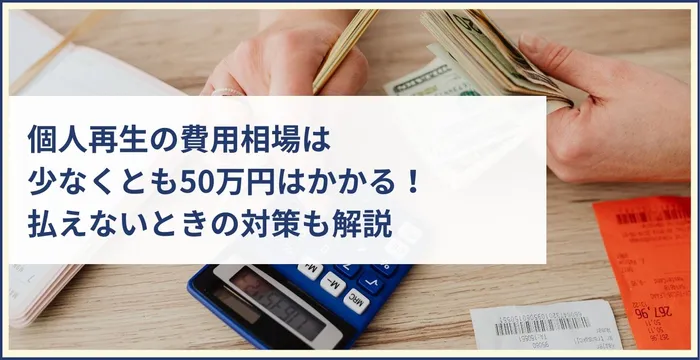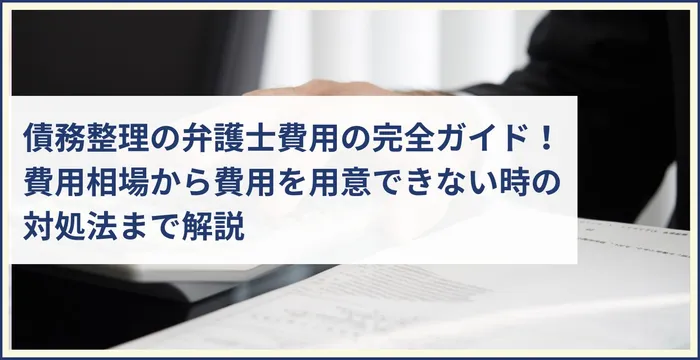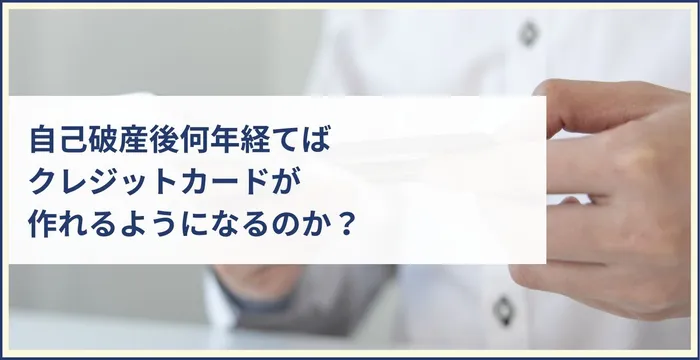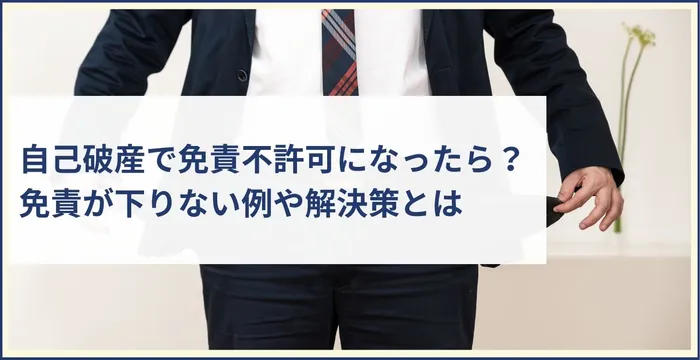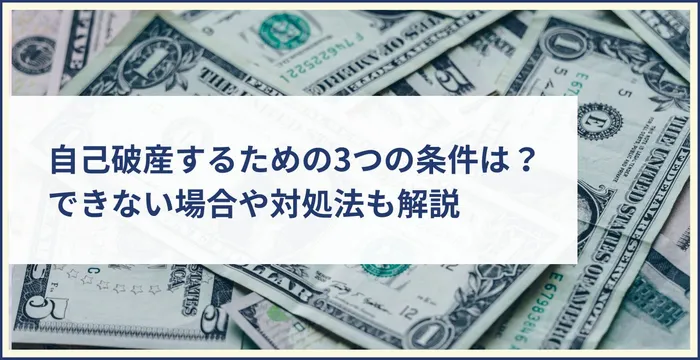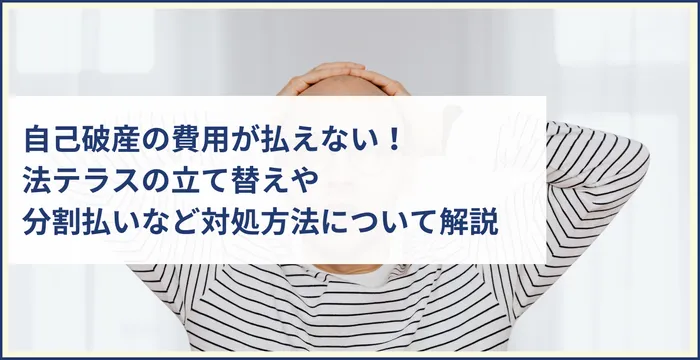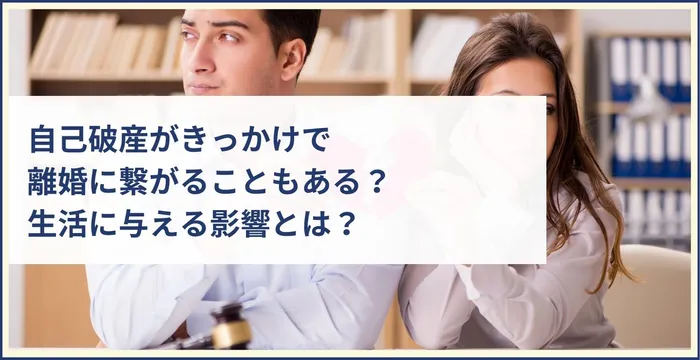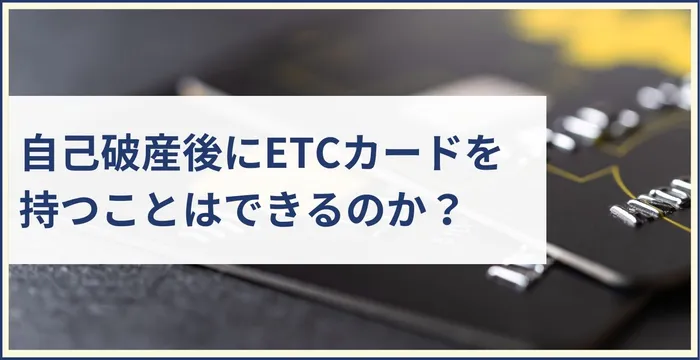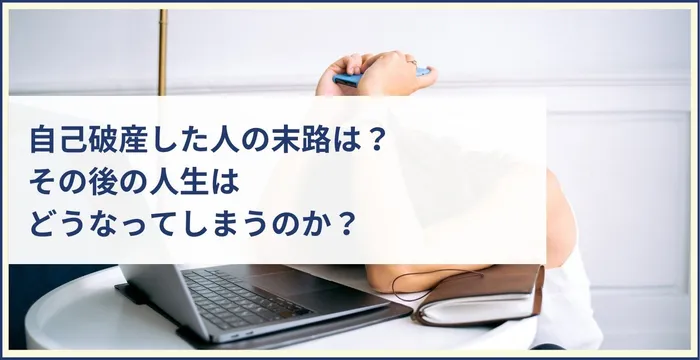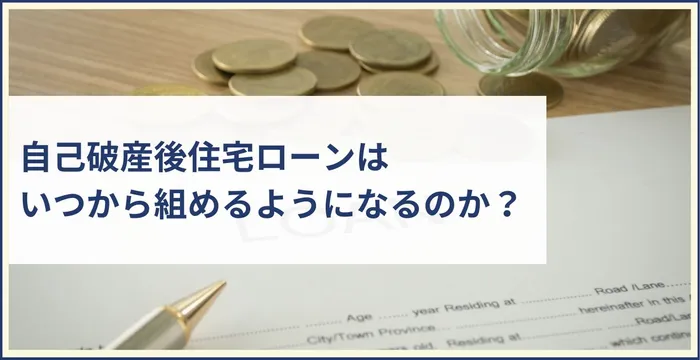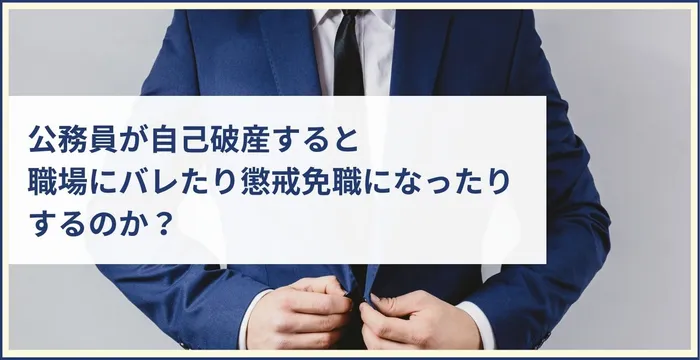自己破産の条件に金額は定められていない
自己破産というと、「何百万もの多額の借金を抱えている人しかできない」というイメージをお持ちの人も多いかもしれませんが、実は自己破産の条件に借金額は定められていません。
破産法15条では、自己破産できる基本的な条件を下記のように定めています。
破産法十五条
債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
引用元 破産法 | e-Gov 法令検索
支払不能についてはこちらで詳しく解説していますが、上記の通り自己破産できる借金額については法律で定められていません。そのため、返済不能な状況であれば、法律上は借金の金額にかかわらず自己破産が可能です。
自己破産の金額は少なくとも30万円以上を目安にしておく
自己破産が可能な金額は法律で定められていませんが、実際は少なくとも30万円以上が目安になります。なぜなら、自己破産をするには少なくとも30万円程度、一般的には50万円以上の費用がかかるからです。
これよりも借金額が少ないと、自己破産をしても費用負担がほとんど変わらない、または自己破産の費用の方が大きくなって費用倒れになる可能性があります。そのため、借金が30万円よりも多いかどうかで、自己破産をするべきかどうかを考えるのも1つの基準となります。
なお、自己破産の手続きは、財産の有無や債務の内容によって「同時廃止事件」「少額管財事件」「管財事件」のいずれかに分類されます。
あくまでも目安ですが、それぞれの事件にかかる費用相場は下記の通りです。
| 項目 |
同時廃止事件 |
管財事件 |
少額管財事件 |
| 概要 |
債務者に財産がほとんどない場合に選ばれる簡易な手続き |
破産者に一定以上の財産がある場合や、免責不許可事由がある場合などに適用される手続き |
通常の管財事件よりも手続きを簡略化し、費用負担も抑えられるようにした手続き |
| 裁判所費用 |
約1万~3万円 |
50万円以上 |
約20万円 |
| 弁護士費用 |
約30万~50万円 |
約50万~80万円 |
約50万円〜60万円 |
管財事件や少額管財事件では、破産者の財産を管理・処分する「破産管財人」が選任されるため、裁判費用が高くなります。破産管財人とは、裁判所が選任する弁護士などの専門家で、破産者が持つ財産の調査や処分を行い、必要に応じて財産を売却して債権者への配当を行います。
破産手続きの公正性を保つために重要な役割を果たしており、その報酬や調査費用が「引継予納金」として破産者に課されるのです。そのため、管財・少額管財事件では20万円〜50万円以上の費用がかかるのが一般的です。
一方で、同時廃止事件は管財人がつかない分、手続きも簡略なほか、費用も抑えられる傾向です。ただし、同時廃止が選ばれるのは財産がほとんどなく、免責不許可事由もないシンプルなケースに限られます。
免責不許可事由とは、下記のような自己破産をしても免責が認められない可能性のある行為や状況を指します。詳しくはこちらで解説しています。
自己破産の手続きには裁判所費用に加えて弁護士費用もかかるため、総額で30万円を超えるのが一般的です。そのため、自己破産を検討する際は、借金が30万円を超えているかどうかを1つの判断基準とし、費用倒れにならないかどうかを慎重に見極めましょう。
ワンポイント解説
自己破産をしたくても一括で費用を用意できない場合は、「法テラス(日本司法支援センター)」の民事法律扶助制度の利用を検討してみてください。。
民事法律扶助制度では、下記条件を満たす場合に弁護士費用や裁判所費用を立て替える支援が受けられます。
・収入・資産が一定基準以下であること
・勝訴の見込みがないとはいえない
・民事法律扶助の趣旨に適すること
・民事・家事・行政に関する法律問題であること
立て替え分は、援助開始決定後から月々5,000円〜10,000円程度ずつ分割で返済することになります。援助終了後は、原則3年以内に立替分を完済しますが、無利息なので無理なく返済しやすいです。必要であれば、法テラスの利用も視野に入れるとよいでしょう。
自己破産を検討する際には借金額や平均月収の統計データも参考にする
自己破産を検討する際は、実際に自己破産した人の借金額や平均月収の統計データも参考にしてみるといいでしょう。自己破産した人の借金額のボリュームゾーンや平均月収を把握しておけば、自己破産をするかどうか迷った際の1つの目安となります。
ここからは、日本弁護士連合会が実施した「[2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」に基づく破産者の借金額や平均月収をご紹介します。
自己破産をした人の借金額:100万円〜300万円がボリュームゾーン
日本弁護士連合会が実施した「[2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」によると、自己破産した人の借金額の分布は下記の通りです。
| 破産者の借金額帯 |
割合 |
| 100万円未満 |
8.39% |
| 100~200万円未満 |
13.87% |
| 200~300万円未満 |
14.52% |
| 300~400万円未満 |
11.13% |
| 400~500万円未満 |
7.42% |
| 500~600万円未満 |
5.56% |
| 600~700万円未満 |
4.76% |
| 700~1,000万円未満 |
8.71% |
| 1,000~2,000万円未満 |
11.05% |
| 2,000~3,000万円未満 |
5.65% |
| 3,000~4,000万円未満 |
2.50% |
| 4,000~5,000万円未満 |
1.05% |
| 5,000万~1億円未満 |
1.77% |
| 1億円以上 |
2.90% |
自己破産をした人の借金額でもっとも多かったのが「200〜300万円未満(14.52%)」、次いで「100〜200万円未満(13.87%)」と、100~300万円で自己破産をしている人が多いという結果となっています。
ただし、これは「100~300万円の借金がなければ自己破産を検討すべきではない」という意味ではありません。たとえば、100万円未満で自己破産した人に関しては約8%と、700~1,000万円未満で自己破産した人と同程度の割合という結果でした。
つまり、自己破産を検討すべきかどうかは、借金の金額そのものよりも「自分の収入や生活状況から見て、継続的な返済ができるかどうか」が重要な判断基準となります。
「これくらいの金額なら自己破産はできないのでは?」と自己判断するのではなく、今後の返済見通しが立たない場合は早めに専門家へ相談し、選択肢のひとつとして検討することが大切です。
自己破産をした人の平均月収:約14万円
「[2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」によると、自己破産した人の平均月収は約14万円で、月収帯別の割合は下記の通りでした。
| 破産者の月収帯 |
割合 |
| 0~5万円 |
13.23% |
| 5~10万円 |
15.89% |
| 10~15万円 |
23.06% |
| 15~20万円 |
20.56% |
| 20~25万円 |
13.79% |
| 25~30万円 |
6.53% |
| 30万円以上 |
4.11% |
破産者の月収帯でもっとも割合が高かったのは「10~15万円(23.06%)」、次いで「15~20万円(20.56%)」でした。ただし、こちらも「平均月収が14万円未満でなければ自己破産を検討すべきではない」という意味ではありません。
月収がそれほど低くなくても、状況次第では自己破産が認められる可能性があります。実際に「20~25万円」や「30万円以上」の月収がある人でも、自己破産を選択している人は一定の割合でいます。
そのため、自己破産を検討する際は、月収や借金の総額に加えて、毎月の支出や将来の収支見通しなどを含めて総合的に判断することが重要です。必要に応じて弁護士などの専門家に相談し、自分にとって最善の方法を見つけましょう。
自己破産をするには条件を満たす必要がある
自己破産は借金額にかかわらず利用できる解決手段ですが、手続きを行うためには以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 借金の返済が不能状態であること
- 借金が非免責債権ではないこと
- 免責不許可事由に該当しないこと
これらの条件を満たしていなければ自己破産は認められないため、借金額だけで自己破産できるかどうか判断できません。ここからは、それぞれの条件について1つずつ詳しく解説していきます。
借金の返済が不能状態であること
自己破産をするには、支払不能な状態であることが条件になります。支払不能とは、破産法で下記のように定義づけています。
破産法第二条
11 この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいう。
引用元 破産法 | e-Gov 法令検索
つまり、支払不能な状態とは収入や資産が不足していることで、すでに支払い期日が到来している債務を一般的・継続的に弁済するのが不可能な状態を指します。
支払不能な状態であるかどうかは、裁判所が借金額や収入、資産、生活状況、家族構成などを総合的に考慮したうえで判断します。以下のように、返済できない理由が一時的なものである場合や、客観的に見て返済が可能だと判断される場合は支払不能な状態とはいえず、自己破産が認められない可能性があります。
- 一時的な病気やケガによる休職中だが、復職の予定が明確にある
- ボーナスや臨時収入の見込みがある
- フリーランスや自営業者で、一時的に売上が落ち込んでいるが、今後の契約や回復の見込みがある
- 育休中や産休中で一時的に収入が減っているが、復帰予定がある
そのため、借金額が多くても返済能力があると判断されれば、破産手続きが認められないこともあるのです。
借金が非免責債権ではないこと
自己破産をするには、借金が「非免責債権」ではないことも条件になります。非免責債権とは、自己破産をしても免責の効力が及ばず、支払い義務が免除されない債権のことです。破産法253条では、以下の債権を非免責債権として定めています。
借金の中に非免責債権にかかる債務があっても自己破産は可能です。しかし、支払い義務が免除されるのは借金やローンなどの非免責債権ではない債務のみで、税金・社会保険料の滞納分や養育費の支払い義務などの非免責債権にかかる債務は免除されません。
借金が非免責債権にかかる債務しかなければ自己破産をしても借金は一切免除されないため、自己破産をする意味がありません。
免責不許可事由に該当しないこと
自己破産をするには、借金の理由や債務者の行為などが免責不許可事由に該当していないことも条件になります。免責不許可事由とは、裁判所から免責許可が得られない原因となる行為や状況のことで、破産法第252条で規定されています。
具体的には、以下のような行為や状況が免責不許可事由に該当します。
- 財産を第三者に贈与したり、不当に安く売却したりした
- 特定の債権者にだけ返済した
- 支払能力があると嘘をついて新たに借入をした
- 収入に見合わない浪費やギャンブルで多額の借金を抱えた
- 破産手続きにおける帳簿や書類を隠したり、改ざんしたりした
- 裁判所の調査で説明を拒否したり、虚偽の説明をしたりした
- 過去7年以内に自己破産をした
ただし、免責不許可事由に該当しているからといって、絶対に免責許可が下りないというわけではありません。破産者が誠意を持って手続きに対応している場合や、更正しようと努力している姿勢が見られる場合は、裁判所の裁量で免責が認められる可能性もあります。
金額にかかわらず自己破産を検討するべきケース
債務整理の手続きには、自己破産以外に個人再生や任意整理があります。どの手続きを選ぶかどうかは、債務者の借金額や収入、保有財産、仕事、家族構成などを総合的に考慮して検討することになりますが、以下のケースにあてはまる場合は自己破産を検討すべきだといえます。
- あまりにも借金が多く、自力では返済が困難である
- 収入がないために返済ができない
- 生活保護を受けている、または受給を検討している
ここからは、それぞれのケースについて1つずつ詳しく解説していきます。
あまりにも借金が多く、自力では返済が困難である
下記の様に、あまりにも借金が多く自力での返済が困難である場合は自己破産を検討した方がよい可能性があります。
- 借金額が収入の3分の1を超えている
- 毎月の返済額に占める利息の割合が大きい
借金が年収の3分の1を超えている状態は、返済能力を超えた借入になっている可能性が高く、自己破産を含む債務整理を検討すべき段階といえます。
これは、貸金業法で定められている「総量規制」というルールに関係しています。総量規制とは、消費者金融やカードローンなどの貸金業者が、原則として年収の3分の1を超える金額を個人に貸してはならないとする制度です。
「借りすぎによる多重債務を防ぐ」ことを目的としたルールであり、借金額が年収の3分の1を超えている状態は、法律上でも返済困難になりやすいリスクの高い状態と判断されています。
具体例として、下記のAさんのケースを見ていきましょう。
| 項目 |
Aさんの状況 |
| 借金額 |
500万円 |
| 利息額 |
213万6,958円 |
| 年利 |
15% |
| 返済期間 |
5年間 |
| 手取り月収 |
20万円(正社員) |
| 毎月の返済金額 |
11万8,949円(うち利息は最大6万2,500円) |
| 生活状況 |
賃貸物件で一人暮らし |
参照:ご返済金額シミュレーション(結果)【公式サイト】カードローン・キャッシングならアコム
Aさんの場合、手取りの月収が20万円なので年収は240万円です。借金額は500万円なので、総量規制である80万円をはるかに超えた状態であることがわかります。
また、借金を完済するためには、実際に借りた金額に加えて利息額もかかります。利息は返済期間や借金額が増えるほど高くなる傾向にあるため、毎月の負担を減らそうと返済期間を長く設定していても、実際には借金額を超える金額を返済しなければなりません。
特に、毎月の返済額のうち元金が利息額を下回ってしまう場合は、返済を続けても元金がなかなか減らず完済が見込めません。Aさんの場合も、12万円弱程度の返済額のうち、利息は最大6万2,500円と元金を上回るほか、利息だけで総額200万円以上支払わなければなりません。
また、Aさんは正社員で安定した収入はあるものの、手取り月収が20万円しかありません。一人暮らしで食費や家賃、水道光熱費などの最低限の生活費だけでも10万円以上はかかるため、毎月12万円弱程度の返済資金を確保するのは困難です。
これらを踏まえると、期日が到来した借金を継続的に弁済できないのは明らかであり、このまま返済を続けても元金が減らず完済の見込みが立たないため、支払不能な状態だと判断されて自己破産が認められる可能性があります。
収入がないために返済ができない
定職に就いておらず、収入がないために借金の返済ができない場合も、自己破産を検討すべきケースの1つです。個人再生や任意整理では、手続き後も借金が残るため、計画通りに返済していけるだけの安定した収入が求められます。
現在収入がなく、今後も安定した収入が得られる見込みがなければ個人再生や任意整理は認められない可能性が高いため、借金が帳消しになる自己破産が有力な選択肢になります。具体例として、以下のBさんのケースを見ていきましょう。
| 項目 |
Bさんの状況 |
| 借金額 |
100万円 |
| 利息額 |
24万7,934円 |
| 年利 |
15% |
| 返済期間 |
3年間 |
| 手取り月収 |
0円(病気で無職) |
| 毎月の返済金額 |
3万4,665円 |
| 生活状況 |
実家で両親と3人暮らし |
参照:ご返済金額シミュレーション(結果)【公式サイト】カードローン・キャッシングならアコム
Bさんは病気で長年定職に就いておらず、収入や自分名義の高額な財産がないため、借金の返済を継続するのが不可能です。病気も数ヶ月以内に治る見込みがなく、今後安定した収入を得られる予定もありません。
借金が比較的少額である場合、定職に就いていて安定した収入を得られている人であれば返済を継続することはさほど難しくないため、自己破産が認められる可能性は低いでしょう。
しかし、Bさんのように無職で収入も財産もない人の場合は、借金が比較的少額であっても支払不能な状態だと判断されて自己破産が認められる可能性があります。
生活保護を受けている、または受給を検討している
すでに生活保護を受けている人や受給を検討している人も、金額にかかわらず自己破産を検討すべきだといえます。前述の通り、任意整理や個人再生では、手続き後も借金を分割で返済していかなければなりません。
しかし、生活保護費は最低限の生活を維持するために支給されるものなので、生活保護費を借金の返済に充てることは認められていません。生活保護費を借金の返済に充てたことがバレると、不正受給として支給を打ち切られたり、返還を求められたりする場合もあります。
したがって、生活保護受給者や受給を検討している人が債務整理をする際は、必然的に借金の返済義務が免除される自己破産を選択することになります。具体例として、借金額50万円で現在生活保護を受給しているCさんのケースを見ていきましょう。
|
Cさんの状況 |
| 借金額 |
50万円 |
| 利息額 |
12万3,963円 |
| 年利 |
15% |
| 返済期間 |
3年間 |
| 毎月の生活保護費 |
13万円 |
| 毎月の返済金額 |
1万7,332円 |
| 生活状況 |
賃貸物件で一人暮らし |
参照:ご返済金額シミュレーション(結果)【公式サイト】カードローン・キャッシングならアコム
Cさんは生活保護費のみで生活している状況で、高額な財産も一切持っていないため、自力で返済することができない状態です。今後も定職に就くのが難しく、生活保護から抜け出せる見込みは今のところありません。
生活保護費での返済が禁止されている以上、期日までに到来した借金を返済できないのは客観的に見て明らかです。そのため、生活保護を受給している場合は借金額が100万円以下であっても支払不能と判断される可能性が高いといえるでしょう。
自己破産を検討する際にはデメリットも十分に把握しておくべき
自己破産を検討する際は、今後の生活に影響するデメリットについても十分に把握しておくことで、「本当に自己破産が自分にとって最適な選択かどうか」を冷静に判断できるようになります。
他の債務整理手続きと比較するうえでも、デメリットの把握は非常に重要です。自己破産のデメリットとしては、主に以下の5つが挙げられます。
- 最長7年間はいわゆるブラックリスト入りになる
- 自己破産の手続き後まで一部の資格が制限される
- 自身の名義の財産を手放す必要がある
- 自己破産をした事実が官報に掲載される
- 連帯保証人に返済義務が生じる
ここからは、それぞれのデメリットについて1つずつ詳しく解説していきます。
最長7年間はいわゆるブラックリスト入りになる
自己破産をすると、最長7年間はいわゆるブラックリスト入りの状態になります。ブラックリスト入りとは、支払いの滞納や債務整理によって、信用情報機関に自己破産をしたという履歴が登録された状態のことをいいます。
信用情報機関には、個人の金融取引が記録されています。この記録は、金融機関が取引の申し込みを受けた際に、申込者の審査を行うために使用されるのが一般的です。審査の際に、信用情報に自己破産をはじめとした「債務整理の記録」が残っていると、返済に不安があると判断される可能性があります。
そのため、信用情報機関に照会がかけられる以下の審査に通りにくくなるのです。
- クレジットカードの発行
- 借り入れやローンの契約
- 信販系の家賃保証会社を介した賃貸契約
- スマホ・携帯電話端末の割賦契約
- 保証人・連帯保証人
ほとんどの金融機関や貸金業者は信用情報機関に加盟しているため、ブラックリスト入りの間はクレジットカードやローンなどの審査に通りづらくなります。自己破産の場合のブラックリストの登録期間は手続きが終了してから最長7年ですが、これは信用情報機関によって異なります。
| 信用情報機関 |
加盟会社 |
登録期間の目安 |
| CIC |
消費者金融、クレジットカード会社 |
破産手続開始決定日から最長5年 |
| JICC |
消費者金融、クレジットカード会社 |
免責確定日から最長5年 |
| KSC |
銀行、信用金庫、信用組合、農協など |
破産手続開始決定日から最長7年 |
借入先によって加盟している信用情報機関が異なりますが、それぞれで保有している信用情報はCRINというネットワークを介して3社間で共有されています。
つまり、クレジットカード会社の債務を自己破産した場合、CICやJICCでは所定日から最長5年で記録が消えますが、KSCではさらに2年間残り続ける事態が発生する可能性もあるのです。
そのため、借入先にかかわらず自己破産した場合は破産手続開始決定日から最長7年間はブラックリスト入りすると考えておくのが無難でしょう。
自己破産の手続き後まで一部の資格が制限される
自己破産をすると、一部の職業や資格に制限がかかります。自己破産で制限の対象となる職業・資格は以下の通りです。
| ジャンル |
職業制限を受ける職業・資格 |
| 士業系 |
弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取引士、中小企業診断士、通関士など |
| 公職系 |
人事院の人事官、教育委員会の教育委員、公正取引委員、公証人、固定資産評価員など |
| 団体企業の役員 |
日本銀行、信用金庫、商工会議所、金融商品取引業、労働派遣業などの役員 |
| 会社法上の役員 |
取締役、執行役員、監査役など |
| その他 |
警備業者の責任者や警備員、貸金業者の登録者、生命・損害保険募集人、証券外務員、旅行業務取扱の登録者や管理者、質屋を営む者など |
上記の職業に従事している人は、破産手続開始が決定してから復権するまで一時的に仕事ができなくなります。制限の理由は、これらの職業や資格が社会的信用を基盤として成り立っているためです。
自己破産が本人の責任によるとは限らない場合でも、破産という事実そのものにマイナスな印象があるため、業界全体の信用を守る観点から一定期間の就業制限が設けられているのです。
そのため、自己破産の手続き中は勤務先に相談して制限対象外の業務に従事したり、一時的に休職したりなどの対応が必要になります。会社役員や団体企業の役員は、破産手続開始決定後に一旦退任となりますが、会社役員は手続き中でも株主総会で再任されれば役員に留まることができます。
なお、自己破産のみを理由とした解雇は労働基準法で認められていないため、基本的に解雇されることはありません。ただし、人事院の人事官や教育委員会の委員、公正取引委員会の委員といった一部の公務員は、法令によって例外的に退職させられることになります。
国家公務員法 第五条
③ 次の各号のいずれかに該当する者は、人事官となることができない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
引用元 国家公務員法 | e-Gov 法令検索
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第四条
3 次の各号のいずれかに該当する者は、教育長又は委員となることができない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
引用元 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 | e-Gov 法令検索
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第三十一条
委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一 破産手続開始の決定を受けた場合
引用元 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号) | 公正取引委員会
自己破産の手続きが終了した後は資格制限が解除されるため、以前と同じように働けるようになります。
自身の名義の財産を手放す必要がある
自己破産では借金が帳消しになる代わりに、自分名義の財産のうち原則20万円以上の価値がある財産は手放す必要があります。現金や預貯金、不動産、車などの換価価値が20万円を超える財産はすべて処分の対象です。
処分の対象となる財産は破産財団に組み入れられ、換価されたうえで債権者への配当に回されます。
ただし、「自由財産」や、法律で差し押さえが禁止されている「差し押さえ禁止財産」に該当する以下の財産は処分の対象外となります。
そのため、自己破産後も手元に残しておくことが可能です。
| 自由財産 |
差し押さえ禁止財産 |
・99万円以下の現金
・自己破産後に取得した財産
・差し押さえ禁止財産
・自由財産の拡張が認められた財産
・破産財団から放棄された財産
|
・衣類や家具家電
・生活に必要な一ヶ月分の食料や燃料
・業務や学業に欠かせない器具や道具
・仏像や位牌、礼拝・祭祀に欠かせないもの
・実印や生活、仕事で必要な印鑑 など
|
破産財団から放棄された財産とは、破産手続において破産管財人が「処分・換価しても費用倒れになる」と判断して、手続の対象から除外された財産のことを指します。また、日常生活で使用する家具家電などは差し押さえ禁止財産に該当するため原則処分されることはありません。
処分した結果生活が成り立たなくなると判断されれば、自由財産の拡張として、車や自宅などの財産も残すことが認められる可能性があります。
このように、自己破産後はすべての財産が失われるわけではなく、生活に必要な最低限の財産は保護される仕組みになっています。そのため、自身がどの財産を保持できるのかを事前に確認したうえで自己破産すべきなのか判断することが重要です。
自己破産をした事実が官報に掲載される
自己破産をすると、その事実が官報に掲載されます。官報とは国が発行する新聞のようなもので、法令の公布や各省庁の人事情報、破産や失踪宣言などの裁判所公告などが掲載されています。
自己破産の場合は、破産手続開始決定時と免責許可決定時の2回、破産者の氏名や住所などが掲載されます。官報は一般に公開されているものなので、官報から自己破産をした事実がバレる可能性はゼロではありません。
しかし、官報をチェックしているのは、信用情報機関や金融機関、警備会社、役所の税担当者など一部の人に限られています。そのため、一般人で頻繁に官報をチェックしている人はほとんどいません。
官報は誰でも見られるものではありますが、そこから自己破産の事実が周囲に知られてしまうのは極めて珍しいケースなので、官報に掲載されたからといって過度に心配する必要はないでしょう。
連帯保証人に返済義務が生じる
連帯保証人は、お金を借りた主債務者と連帯して借金全額を返済する義務を負っています。そのため、主債務者が借金を返済できなくなった場合は、連帯保証人が残りの借金を返済していかなければなりません。
自己破産による免責の効力が及ぶのは破産者本人の債務のみで、連帯保証人が負っている保証債務には効力は及びません。主債務者が自己破産した場合は連帯保証人が残りの借金を返済する義務を負うことになります。
連帯保証人を立てている借金を抱えている場合は、自己破産によって連帯保証人に多大な迷惑をかけてしまいます。そのため、連帯保証人への影響も考慮して慎重に検討した方がいいでしょう。
自己破産以外にも個人再生や任意整理で借金問題を解決できる可能性もある
債務整理には、自己破産のほかにも個人再生や任意整理があります。
| 個人再生 |
最低弁済額を100万円として、借金総額を1/5~1/10程度に減額し、原則3年で返済していく手続き |
| 任意整理 |
返済条件を見直してもらうために、裁判所を通さずに債権者に交渉をする手続き |
自己破産は借金を帳消しにできるのが最大のメリットですが、下記のようにデメリットも多くあります。
- 原則20万円以上の価値がある財産が処分される
- 一定の職業の資格制限
- 所定日から最長7年間はブラックリスト入りする
- 官報に掲載される
- 連帯保証人にも返済義務が及ぶ
- 手続き中は旅行や引越しに制限がある
状況によっては、わざわざ自己破産をしなくても個人再生や任意整理を行うことでデメリットを抑えつつ、借金問題を解決できる可能性があります。そのため、借金額や収入、財産、家族構成などを考慮し、どの手続きが適しているかどうか総合的に判断することが大切です。
では、個人再生と任意整理の特徴をそれぞれ詳しく見ていきましょう。
個人再生:100万円を限度として借金自体を1/5〜1/10程度に減額する手続き
個人再生とは、最低弁済額を100万円として、借金総額を1/5~1/10程度に減額する手続きです。減額後の借金は、原則3年かけて毎月分割で返済していくことになります。
自己破産と同様に裁判所を介して行う手続きなので官報への掲載はありますが、住宅や車などの財産の処分が原則として不要で、職業の資格制限や引越し・旅行の制限もありません。
例外としてローンが残っている財産は処分されてしまう可能性がありますが、持ち家の場合は「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用することで、住宅ローンの返済を続ける代わりに処分を回避できます。
個人再生による借金の減額幅は、借金総額に応じて異なります。
| 借金総額 |
最低弁済額 |
| 100万円以下 |
全額(減額なし) |
| 100万円超500万円以下 |
100万円 |
| 500万円超1,500万円以下 |
借金総額の1/5 |
| 1,500万円超3,000万円以下 |
300万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 |
借金総額の1/10 |
最低弁済額とは、個人再生後も債務者に対して支払わなければならない、最低限の金額のことをいいます。たとえば1,000万円の借金を抱えている場合、最低弁済額は借金総額の1/5になるため、借金は最大で200万円まで減額されます。
個人再生後は、最低弁済額の200万円を3年以内に分割返済するのが原則です。なお、個人再生では手続き後も最低で100万円の返済義務が残るほか、50~90万円程度の費用がかかります。
借金額が比較的少ない人は費用倒れになってしまう可能性もあるため、任意整理を検討した方がいい場合もあります。また、安定した収入がない人や生活保護受給者、借金総額が5,000万円を超える人は個人再生が利用できません。
そのため、自力での返済が難しい場合は自己破産を検討する必要があるでしょう。
任意整理:返済条件を見直してもらうために債権者に交渉をする手続き
任意整理とは、返済条件を見直してもらうために、債権者と直接交渉する手続きです。あくまでも任意による債権者との交渉であるため、必ず返済条件の見直しに応じてもらえるとは限りません。
しかし、和解に応じてくれた場合は利息や遅延損害金をカットしたうえで、借金を3~5年で完済できるように調整してもらえるのが一般的です。裁判所を通さない手続きなので、個人再生や自己破産と比較すると手続きが比較的容易で、費用も5〜15万円と安く抑えられます。
また、任意整理では手続きの対象となる債務を自由に選べるため、ローンが残っている財産の処分や連帯保証人への影響を回避できるのもメリットの1つです。
一方、任意整理でカットできるのは利息や遅延損害金のみであるケースが多く、元金のカットには応じてくれないのが一般的なため、借金の大幅な減額には期待できません。
多額の借金を抱えている人や収入が不安定・無収入の人は任意整理では対応できないケースもあるため、借金額が比較的少なく安定した収入のある人に向いている手続きです。
まとめ
自己破産が可能な条件に借金額は定められていません。客観的に見て支払不能な状態であると判断されれば、借金額にかかわらず自己破産を利用できます。自己破産を申し立てて免責許可が下りれば借金が帳消しになり、借金の返済生活から解放されます。
ただし、自己破産を利用できるからといって、自己破産がその債務者にとって適切な方法であるとは限りません。借金額が比較的少額だと自己破産の費用の方が大きくなったり、自己破産に至った経緯次第では免責不許可事由に該当して免責が認められなかったりする可能性があります。
自己破産のメリットだけに飛びつくのではなく、自己破産のデメリットや個人再生・任意整理の特徴も考慮し、どの手続きが最適なのかしっかりと検討することが大切です。ただ、自分に適した手続きを個人で判断するのは難しいため、借金問題でお悩みの人はまず弁護士に相談してみましょう。
自己破産についてよくある質問
自己破産とはなんですか?
自己破産とは、財産を手放す代わりに借金を全額免除する手続きです。弁護士に自己破産を依頼することで、支払督促を止めることもできます。
自己破産ができないケースはありますか?
申告内容を偽ったり、特定の債権者にだけ便宜を図って債務を弁済すると、借金が免除されないことがあります。
自己破産以外に、借金問題を解決する方法はありますか?
債権者と交渉して利子の減額をおこなう「任意整理」や、家など一部の財産を残しつつ借金を1/5~1/10まで減らす「個人再生」があります。
自己破産を相談できる弁護士を知りたいです。
当サイトで、自己破産の実績が豊富で借金問題に強い弁護士を紹介しています。どの弁護士も親身になって相談にのってもらえるので、ぜひ参考にしてください。→
【相談無料】厳選された「自己破産の相談ができるおすすめ弁護士」はこちら
自己破産できない収入はいくらですか?
明確に「この収入以上なら自己破産できない」という基準はありません。支払不能かどうかは、借金額と収入のバランス、生活費、扶養状況などを総合的に見て判断されます。
たとえ月収が高くても支出や家族扶養の負担が大きければ自己破産が認められる可能性もあります。
自己破産の平均金額はいくらですか?
日本弁護士連合会の「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」によると、自己破産をした人の借金額で最も多かったのは「200万円〜300万円未満(14.52%)」です。
次いで「100万円〜200万円未満(13.87%)」が続いており、100〜300万円の借金で自己破産している人が全体の約3割を占めており最も多い結果でした。
自己破産はしたもん勝ちって本当ですか?
「自己破産=借金が帳消し=得をする」というイメージから「したもん勝ち」と言われることがありますが、実際には財産の処分・職業制限・信用情報への影響など、相応のデメリットがあります。
また、連帯保証人に迷惑がかかるなど第三者への影響もあるため、「簡単に借金が消せるお得な制度」ではありません。