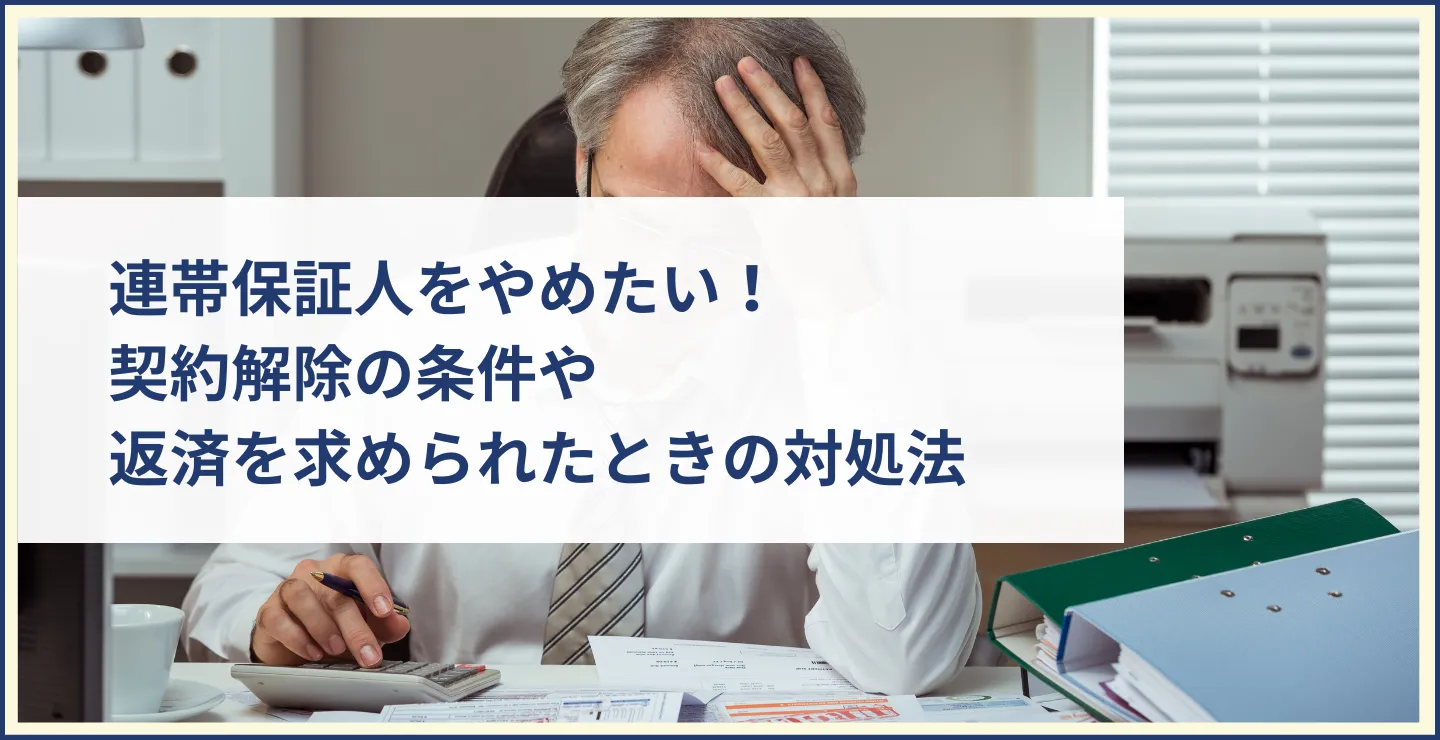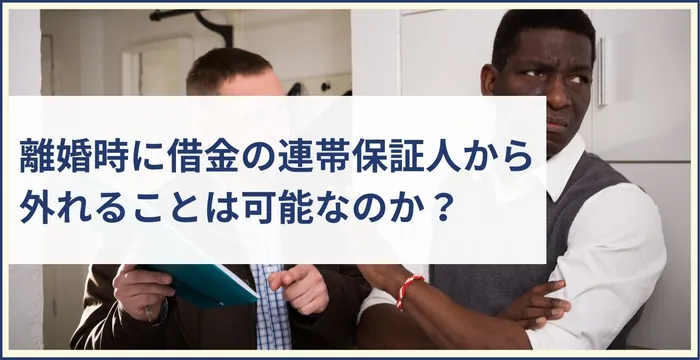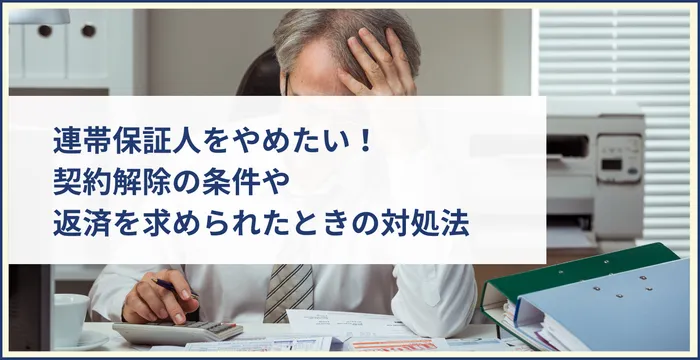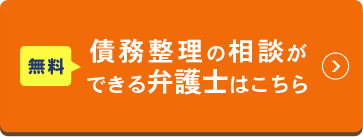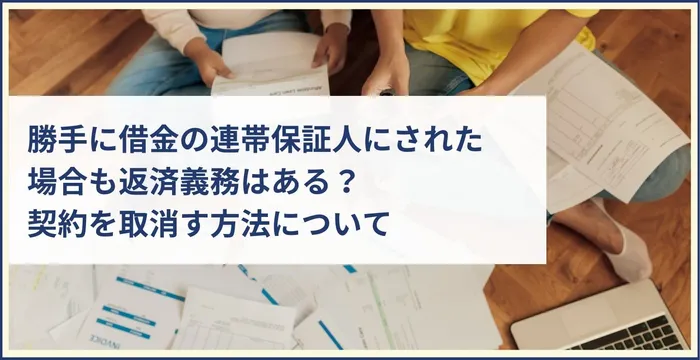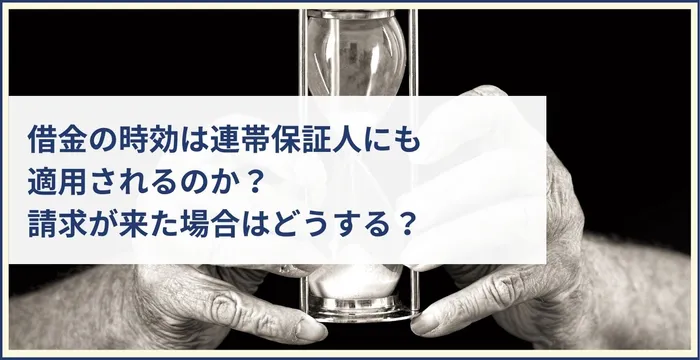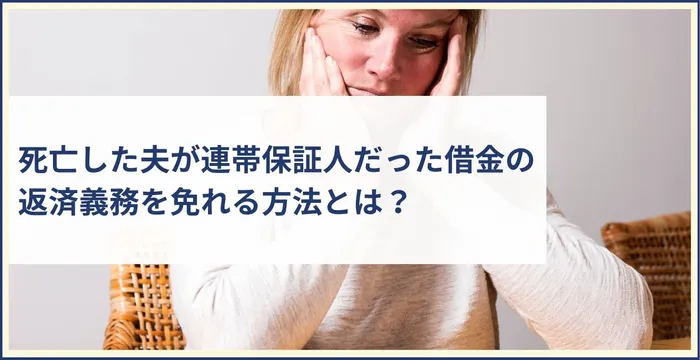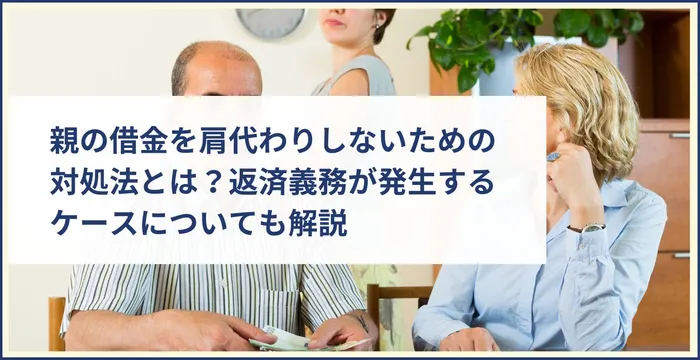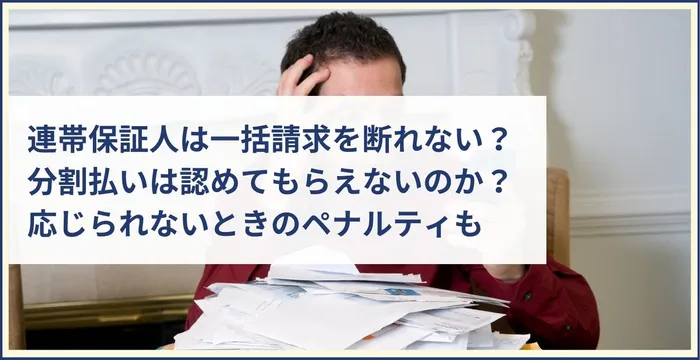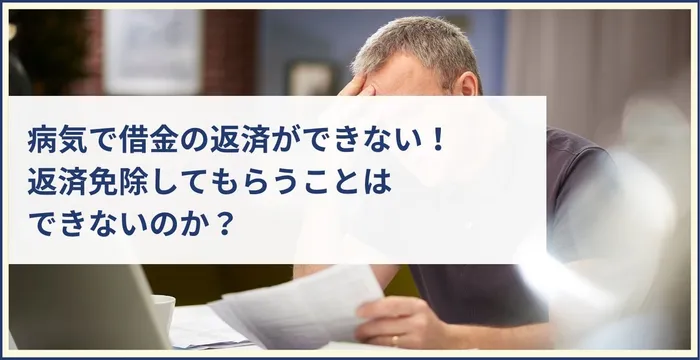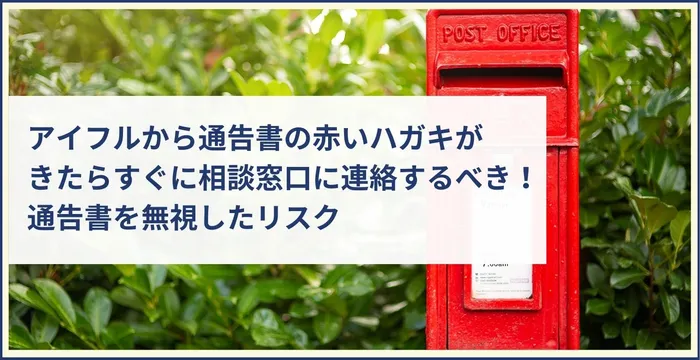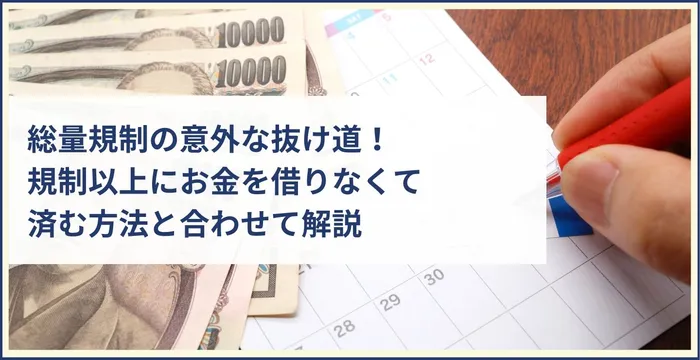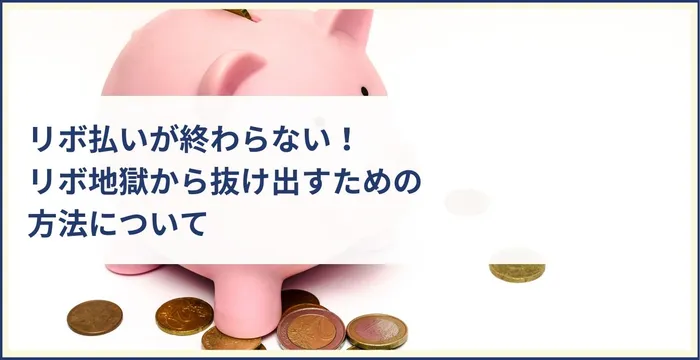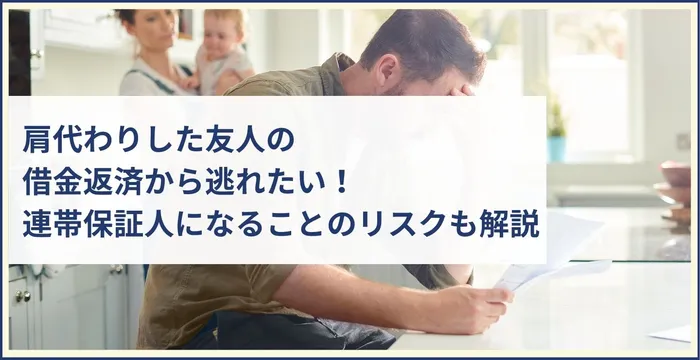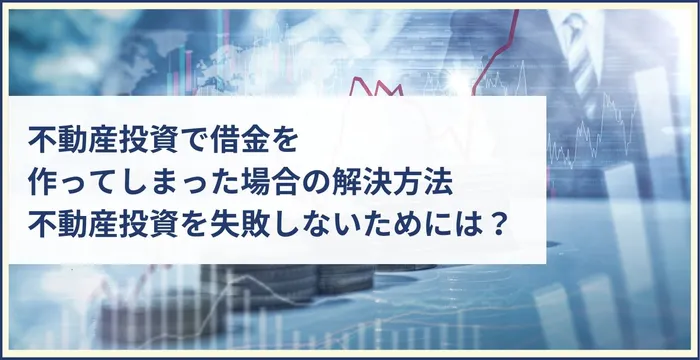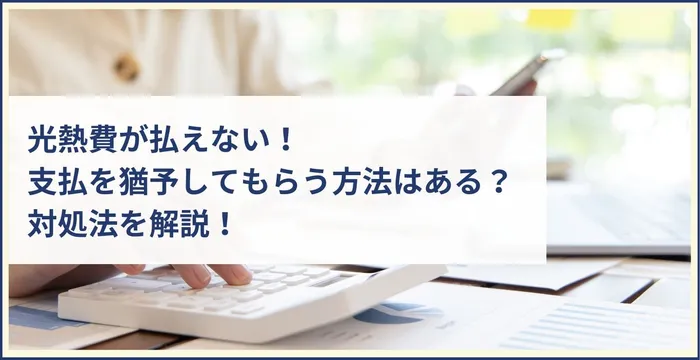家族や友人に頼まれて借金の連帯保証人になったものの、リスクを考慮して「やっぱり連帯保証人をやめたい」と考える人は多いでしょう。
結論から述べると、自分の意思だけで連帯保証人を一方的にやめることはできません。しかし、以下のようなケースであれば連帯保証人の契約を解除できる可能性があります。
- 自分以外の連帯保証人を立てる
- 債務の残債が少ない
- 契約自体が無効となる可能性がある
- 契約の時効を主張できる
- 相続の場合は相続放棄が可能
上記の条件を満たしていれば、債権者との交渉次第で連帯保証人をやめられる場合があります。相続の場合のみ、相続放棄をすることで債権者の許可を得ずとも確実に連帯保証人の債務から逃れることが可能です。
なお、すでに主債務者が返済不能な状態に陥っている場合は、連帯保証人が支払いをしなければなりません。
一括や分割での返済が可能なのであれば、支払いが完了したあとに主債務者に対して財産の返還を求めましょう。もしも返済が厳しいようであれば、弁護士や司法書士に相談のうえ、債務整理を検討する必要があります。
当サイトでは、借金問題の解決に力を入れる弁護士や司法書士を紹介しています。連帯保証人の契約が本当に有効かどうかも含め、一度無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。
>>【相談無料】連帯保証人として背負った借金を解消する
この記事でわかること
- 連帯保証人は一方的にやめられない
- 連帯保証人をやめるには、債権者と契約者の同意が必要
- 交渉次第で連帯保証人をやめられるケースもある
- 連帯保証人をやめられず、返済に困ったら債務整理を検討
- 弁護士や司法書士に相談すれば状況に応じた手続きを代理してくれる
連帯保証人を一方的にやめることはできない
前提として、連帯保証人の立場を一方的にやめることはできません。
債権者にとって連帯保証人は、契約者本人から借金が回収できなくなったときの保険のような存在といえます。
連帯保証人は「連帯保証契約書」で正式な契約を結んでおり、主債務者が債務を履行できなくなったとき、代わりに債務を履行する義務があります。そのため、連帯保証人をやめる際にも債権者や契約者本人の同意が必要です。
なお、連帯保証人と保証人は似ているようで権利の内容が異なります。
定義上は、保証人も連帯保証人と同じく契約者本人の支払いが困難になった場合に肩代わりをする存在です。しかし保証人には以下のとおり、3つの権利があります。
| 保証人の権利 |
概要 |
| 催告の抗弁権 |
まず主債務者に請求するよう債権者に主張できる権利 |
| 検索の抗弁権 |
まず主債務者の財産を調べて回収するよう債権者に主張できる権利 |
| 分別の利益 |
保証人が複数いる場合に、自分の負担分だけ責任を負うと主張できる権利 |
「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」は、契約者本人に督促をしたり財産を差し押さえたりなど、優先的に請求をするよう主張できる権利です。「分別の利益」は、保証人が複数いる場合に借金を人数で割った分を返済すれば、債務を履行したことになる権利です。
これに対し、連帯保証人は債権者からの請求を拒否することはできません。もしも契約者本人に支払い能力があるとしても、連帯保証人は債権者からの請求に応じる必要があるため、責任の重い立場といえます。
連帯保証人の契約を解除できるケース
原則として連帯保証人をやめることはできませんが、以下のようなケースであれば契約を解除できる可能性があります。
- 自分以外の連帯保証人を立てる
- 債務の残債が少ない
- 契約自体が無効となる可能性がある
- 契約の時効を主張できる
- 相続の場合は相続放棄が可能
上記を理由に債権者と交渉し、連帯保証人の契約解除について同意が得られれば、連帯保証人をやめられます。なお、相続放棄の場合は債権者との交渉は必要ありません。
次の項目から、それぞれのケースについて具体的にみていきましょう。
自分以外の連帯保証人を立てる
自分以外の連帯保証人を立てて、それを契約者や債権者が認めれば連帯保証人をやめられるケースもあります。
ただし、新たな連帯保証人になってくれる人を見つけるのは中々難しいでしょう。連帯保証人は責任が重いため、自分から「なりたい」という人はまずいません。すでに連帯保証人に請求が来ている状態ならなおさらでしょう。
とはいえ、状況をごまかして連帯保証人を依頼するのは、トラブルの元です。現在の返済状況を伝えたうえで連帯保証人になってくれる人を探しましょう。
債務の残債が少ない
ほとんど債務が残っていなければ、連帯保証人をやめられることもあります。この場合は債権者との交渉が必要です。
債権者は最後まで確実に債務を回収するために保険をかけておくのが一般的であるため、連帯保証人を外しても問題ないと判断するか否かは交渉次第になります。契約者本人に支払い能力が見込まれるなら、交渉の余地はあるでしょう。
しかし契約者本人の状況的に返済が期待できないとなれば、完済まで連帯保証人をやめられないということも十分にあり得ます。
また、債権者と直接交渉しても取り合ってもらえない可能性も高いため、弁護士に交渉を代行してもらうことをおすすめします。
契約自体が無効となる可能性がある
契約自体が無効な場合は、そもそも取引自体に効力がないため、連帯保証人をやめられます。
たとえば以下のような場合は無効な契約に該当します。
- 公序良俗に反する契約
- 虚偽の内容を含む契約
- 本来の説明と違う内容の契約
上記のような場合は、契約自体が無効なので契約者本人はもちろん、連帯保証人にも支払い義務が発生しません。
むしろ、民法上では無効な契約による行為は原則として原状復帰することが定められています。そのため、支払った分のお金を取り戻せるかもしれません。
ただし、連帯保証人が個人でお金を請求しても債権者は取り合ってくれないでしょう。債権者に対する請求をする場合は、弁護士や司法書士に相談して方針を決めることをおすすめします。
契約の時効を主張できる
契約の時効が主張できれば、連帯保証人をやめられることもあります。借金をはじめとする契約には、時効があります。
たとえば銀行から借り入れをした場合、返済しないまま返済期限から5年が経つと契約は時効にかかり、時効の援用をすることでそれ以降の返済義務をなくすことが可能です。
一般的に時効が成立するまでの期間は5年〜10年程度ですが、年数は契約者の状況などによって異なります。
ただし、債権者は時効を迎えるまでに内容証明郵便を送ったり裁判手続きを進めたり、何かしらの対策を取るものです。
また、時効を主張しても素直に受け入れる債権者は多くはなく、裁判で争う姿勢を見せてくることも多々あります。そのため、時効を主張する際は弁護士や司法書士に代理人を依頼して対応してもらいましょう。
相続の場合は相続放棄が可能
連帯保証人の立場を相続した場合、「相続放棄」という手続きを取れば返済義務を負わずに済む可能性があります。
たとえば親が誰かの連帯保証人になっており、親が亡くなったことで相続人である子供に連帯保証人としての立場が移った場合などです。
相続放棄は、相続できることを知ってから3ヶ月以内に手続きをすることが原則です。また一度相続を承認した場合は、相続放棄することはできません。
なお、相続放棄をすると借金だけでなく、現金や不動産など他の財産についても相続権を失うことになります。そのため、相続放棄をするのかどうかは慎重に検討しましょう。
もしも借金よりもプラスの財産の金額が上回る場合、相続したうえで借金を返済した方が手元に残る財産が多くなる可能性があるためです。
相続放棄をすべきかどうかの判断がつかない場合は、弁護士や司法書士に相談してみてください。
連帯保証人として支払いを求められたときの対処法
主債務者が返済を滞納しており、債権者から連帯保証人として支払いを求められたときは、原則として応じなければなりません。
債権者から支払いの請求を受けたときは、以下の対処法が考えられます。
- 分割払いにしてもらえるかを交渉する
- 全額支払ってから求償権を行使する
- 債務整理を検討する
それぞれの対処法について、詳しく解説します。
分割払いにしてもらえるかを交渉する
一括で返済をするのは厳しいものの、分割なら対応できそうな場合、債権者に分割払いにしてもらえるかを交渉する方法がおすすめです。
連帯保証人には基本的に一括で請求されるケースが一般的ですが、交渉次第では分割払いを認めてもらえる可能性があります。
債権者と交渉する際には「毎月○万円ずつ、12回で完済」のように、具体的な返済スケジュールを提示しましょう。返済スケジュールを立てることにより、債権者に対して支払う意思があることをアピールできます。
また、交渉の際は弁護士や司法書士に同席してもらうか、代行してもらうという方法もあります。専門家が介入することで、債権者との話し合いがスムーズに進みやすくなるでしょう。
分割払いが認めてもらえれば、生活に大きな影響を与えることなく借金を返済することが可能です。
全額支払ってから求償権を行使する
一括返済ができそうな場合は、いったん全額を支払ってから「求償権」を行使するという方法があります。
求償権とは、主債務者に対して支払った金額の返還を請求する権利のことです。連帯保証人が代わりに借金を返済した場合、時効を迎えていない限りはいつでも求償権を行使できます。
ただし、求償権を行使しても、主債務者が支払いを拒否する可能性があります。その場合は裁判を起こして支払いを求めることになりますが、裁判費用や弁護士費用などが相手から回収する金額を上回ってしまうケースも少なくありません。
また、主債務者の経済状況的に返済が困難な場合も多いです。仮に主債務者が自己破産をすると求償権も免除されてしまうため、裁判を起こしてまで求償権を行使するメリットは少ないといえます。
求償権を行使すべきかどうかは、弁護士や司法書士などに現在の状況を相談のうえで決めましょう。
債務整理を検討する
連帯保証人をやめられる見込みがなく、このままでは返済も難しいという状況であれば債務整理を検討してみてください。債務整理とは、借金の減額または免除をする法的な手続きのことです。
債務整理をすると信用情報に事故情報が記録され、5年〜10年間はローンやクレジットカードの審査に通りにくくなります。デメリットは大きいものの、契約者に支払い能力がなかったり連絡が取れなかったりするケースでは、債務整理をするのが有効です。
債務整理には以下3つの種類があります。
| 債務整理の種類 |
概要 |
| 任意整理 |
・利息をカットしたり返済期間3~5年まで延長したりする手続き
・債務整理する対象を任意で選択できる |
| 個人再生 |
・債務の返済額を少なくして原則3年以内に返済する手続き
・債務整理の対象は選択できず、すべての債務が対象 |
| 自己破産 |
・すべての債務が免除される手続き
・債務整理の対象は選択できず、すべての債務が対象 |
なかでも、最も手軽な手続きが任意整理です。任意整理は手続きの対象を任意に選べるため、連帯保証人になっている契約の債務だけを減額できます。
一方、個人再生や自己破産は債務整理の対象を選べません。連帯保証人になっている契約以外にも借り入れやローンがある場合、これらもすべて債務整理の対象となります。
ただし、個人再生なら借金を最大10分の1に、自己破産なら借金を免除できるのが特徴です。自身の経済状況や、その他の債務状況に応じてどの債務整理を選ぶのかを考えましょう。
なお、債務整理をする際には借金問題の経験が豊富な弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。借金問題に精通している弁護士・司法書士は債権者との交渉にも慣れており、債務者にとって有利な条件で話をまとめてもらえる可能性が高いです。
連帯保証人をやめたいときに弁護士・司法書士に相談するメリット
連帯保証人をやめたい場合や、債権者と契約内容について交渉したいときは、弁護士や司法書士に相談しましょう。
弁護士・司法書士に相談すれば、個人の状況に応じて最適な対処法を教えてもらえます。また、債権者との交渉を代行してもらえるため、個人で交渉をするよりも有利に進められます。
次の項目から、連帯保証人をやめたいときに弁護士・司法書士に相談するメリットを具体的に解説します。
状況に合った対処法を教えてくれる
弁護士や司法書士に相談すれば、状況を考慮してどのように動くのがベストか教えてくれます。
まずは現在の状況を踏まえ、連帯保証人をやめられそうかどうかを客観的に判断してもらえます。やめられそうな場合は債権者との交渉を代行してもらい、連帯保証人をやめるための手続きを進めていく形になるでしょう。
反対に、連帯保証人をやめることが厳しい場合、借金を返済するか債務整理をするか、具体的な方向性を決めていくことになります。借金問題に精通している弁護士・司法書士であれば、そのまま債務整理を依頼することも可能です。
このように、弁護士・司法書士に相談すれば具体的な対処法を教えてもらえるので、「どうすれば良いのかわからない」という状況から脱却できます。
連帯保証人をやめることができず、身動きが取れなくなっている場合は弁護士・司法書士に相談してみましょう。
債権者と交渉の余地ができる可能性がある
連帯保証人本人でなく、弁護士や司法書士が債権者と交渉すれば話が前向きに進展する可能性もあります。
弁護士や司法書士は交渉の専門家であるため、連帯保証人にとって最もメリットが大きくなるよう、有利に交渉を進めてもらえます。
たとえば支払いが滞ってしまい、すでに債権者から裁判を起こす旨を告げられていても、弁護士や司法書士が入れば任意の交渉で和解できる可能性があります。当事者同士の話し合いで解決しないように思えることも、弁護士や司法書士が間に入るとスムーズに解決できることがあります。
任意整理をする場合も、連帯保証人本人が交渉するより弁護士や司法書士が間に入った方が効果的でしょう。足元を見られることなく、きちんと減額してもらえる可能性が高くなります。弁護士や司法書士は第三者という立場で高い交渉力を持つため、連帯保証人の強い味方です。
債権者と有利に交渉するためにも、ぜひ弁護士や司法書士への相談を検討してみてください。
まとめ
連帯保証人を一方的にやめることはできませんが、状況によっては交渉次第でやめられるケースもあります。
もしも連帯保証人から外れることができず、支払いも難しいと感じたら弁護士や司法書士に相談しましょう。
連帯保証人でも、借金を減額または免除する債務整理の手続きが可能です。また、相続財産に連帯保証人の債務が含まれる場合は、相続放棄で連帯保証人をやめられる可能性もあります。
弁護士や司法書士に事情を相談すれば、どの手続きが最善か教えてもらえます。債務整理や相続放棄などの代理人を依頼すれば、自分で手続きするよりもスムーズに交渉が進むでしょう。
借金問題については無料相談できる事務所も多いため、ぜひ弁護士や司法書士への相談を検討してみてください。
連帯保証人に関するよくある質問
借金の連帯保証人になることのリスクは何ですか?
連帯保証人になることの最も大きなリスクは、主債務者が支払不能となったときに返済義務が回ってくることです。主債務者が債務整理をした場合も、返済義務が回ってきます。
主債務者が亡くなった場合はどうなりますか?
主債務者が亡くなった場合、基本的には相続人が借金を引き継ぎます。しかし、連帯保証人の返済義務が消えるわけではないため、相続人が相続放棄をしたり返済を滞納したりした場合は、連帯保証人が返済をしなければなりません。