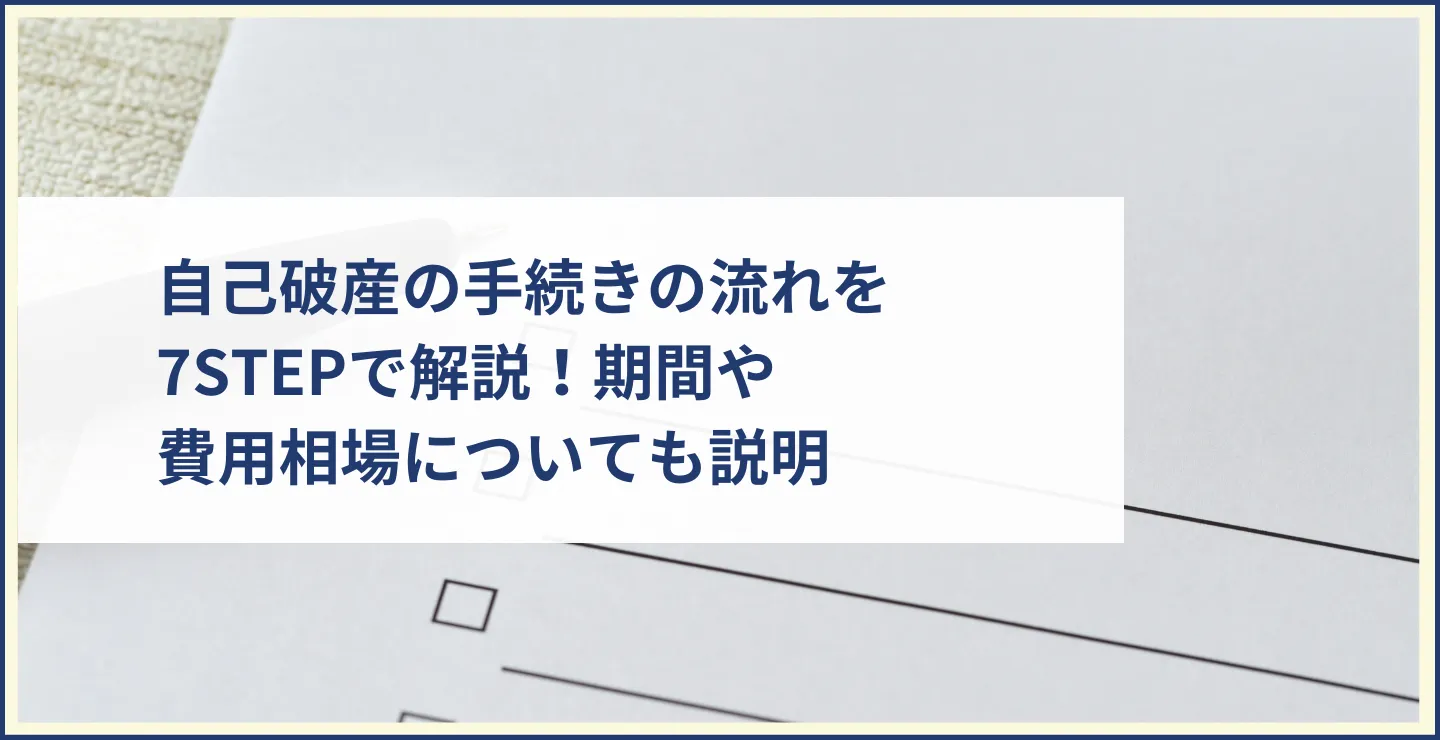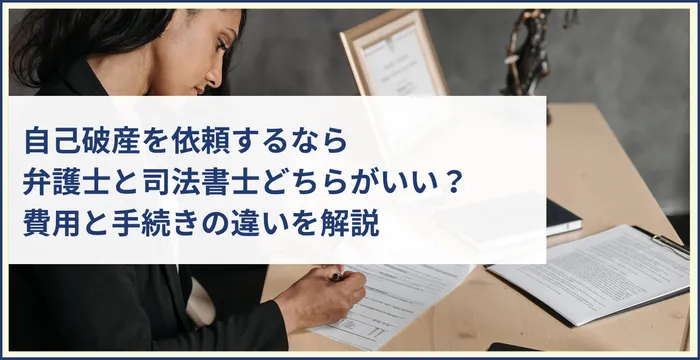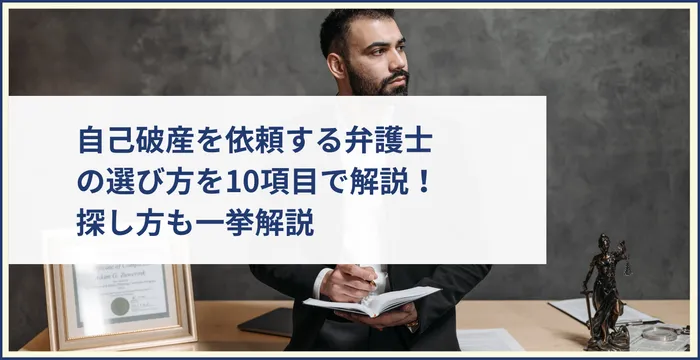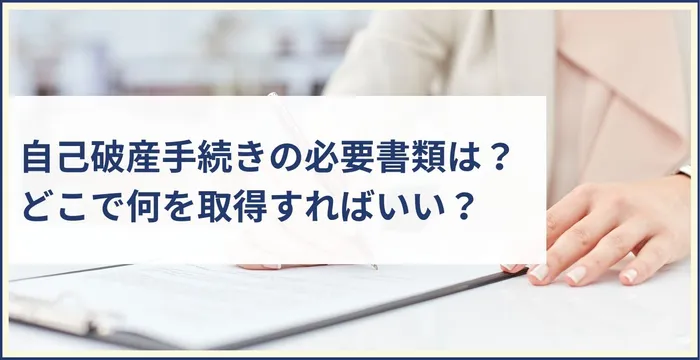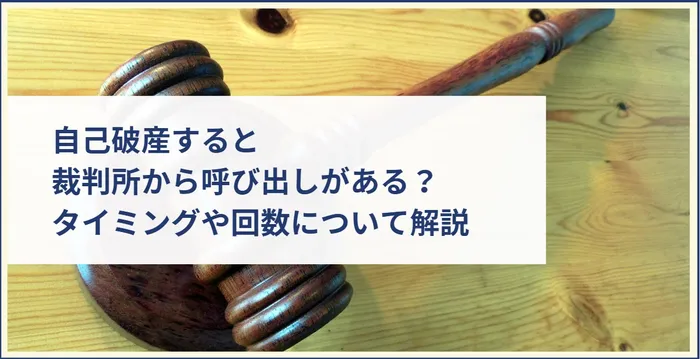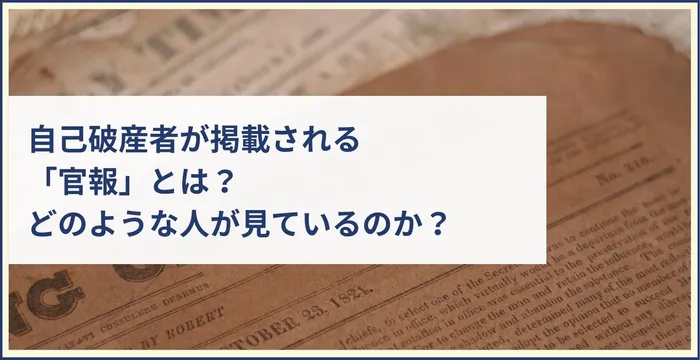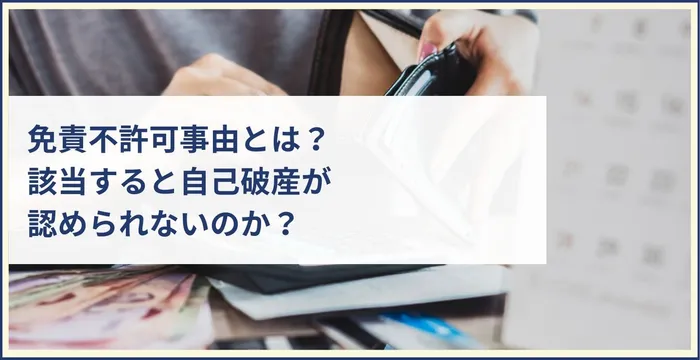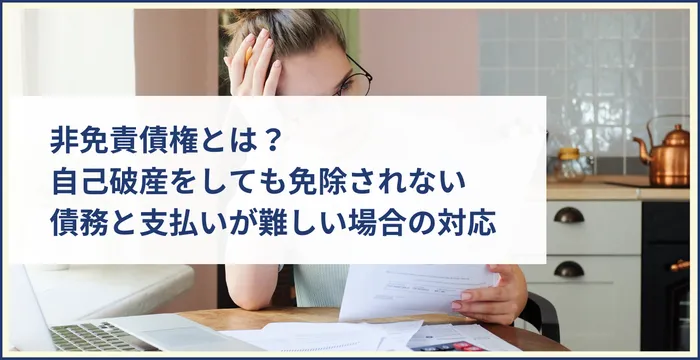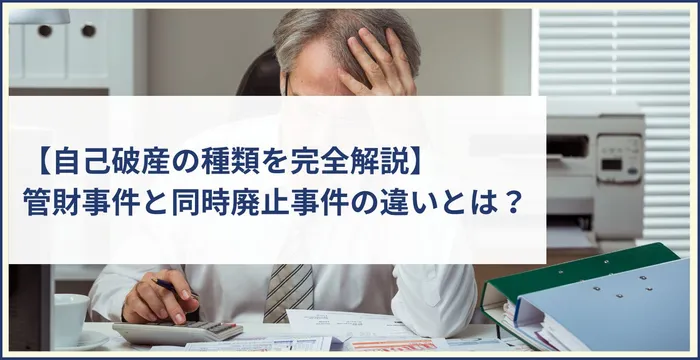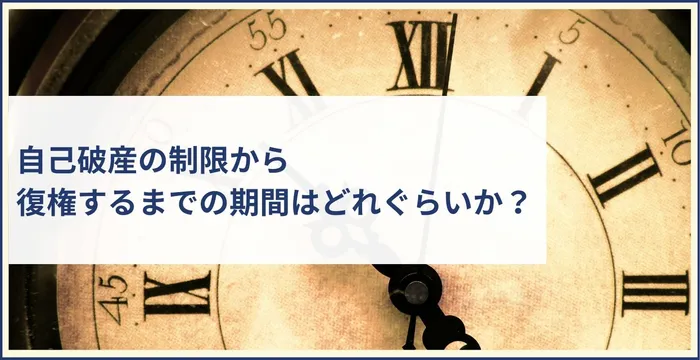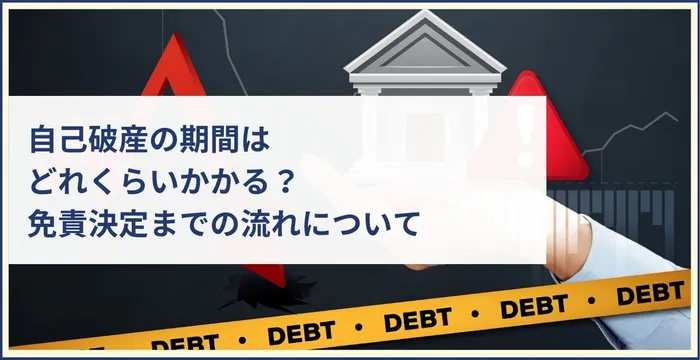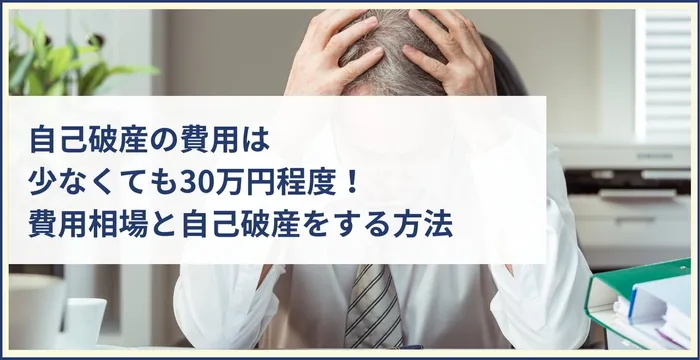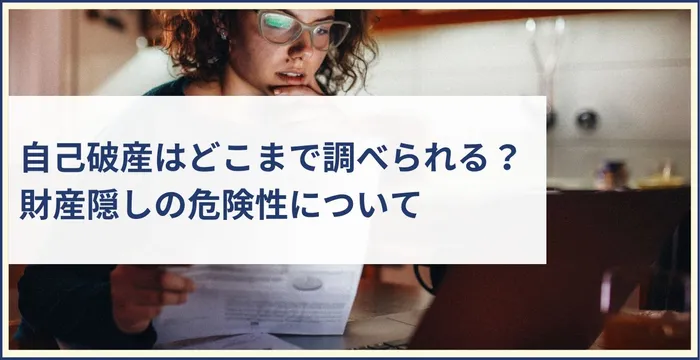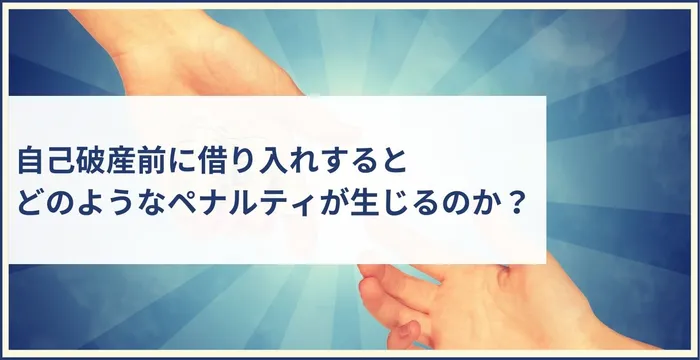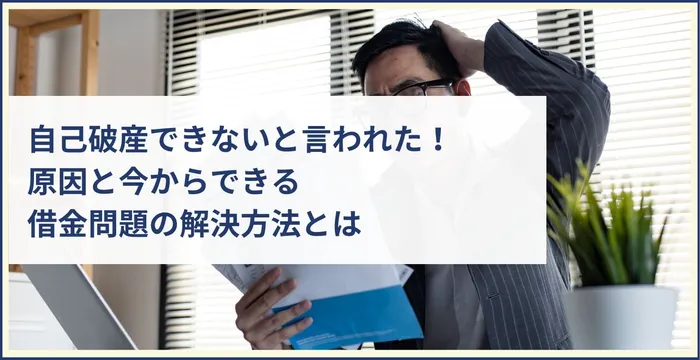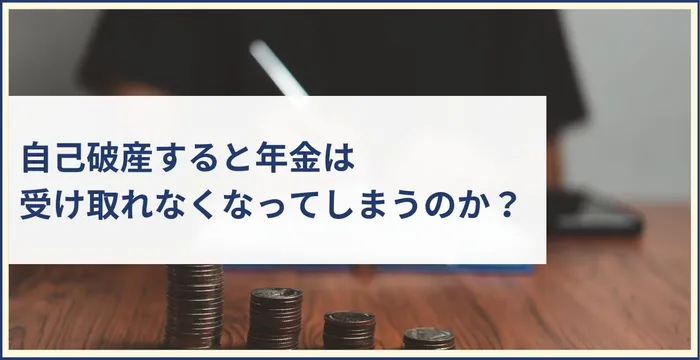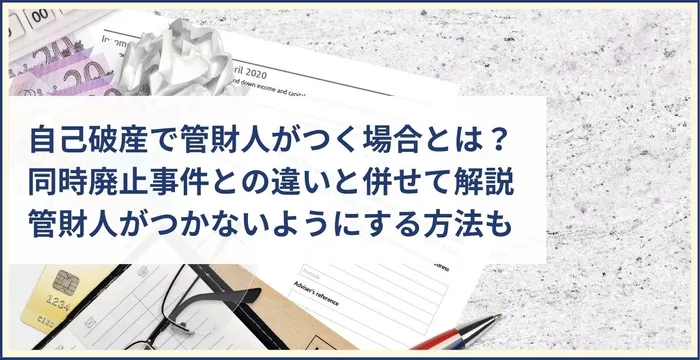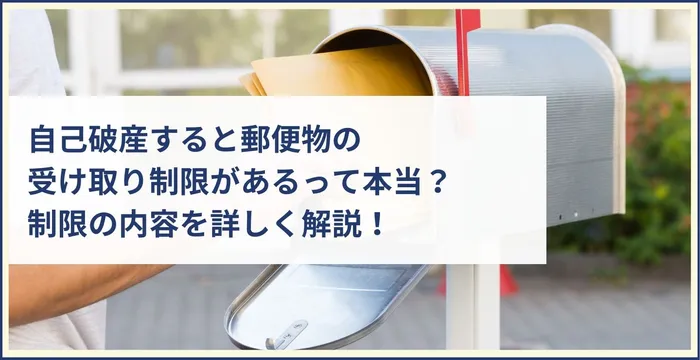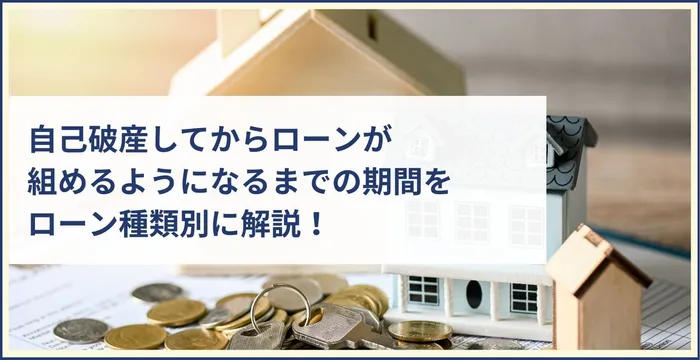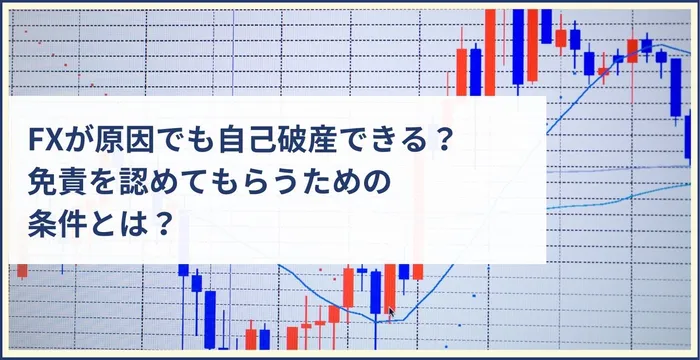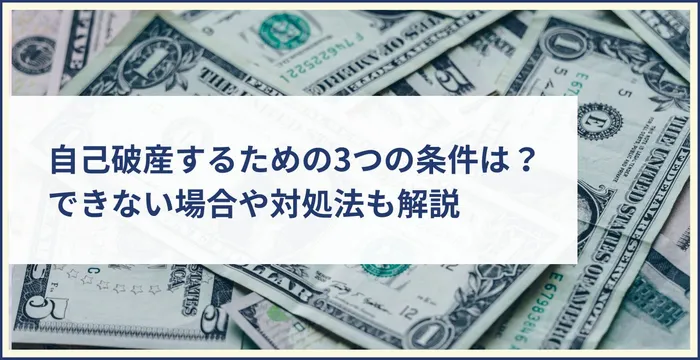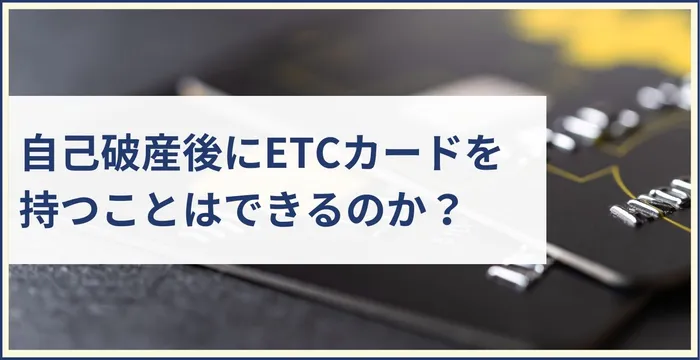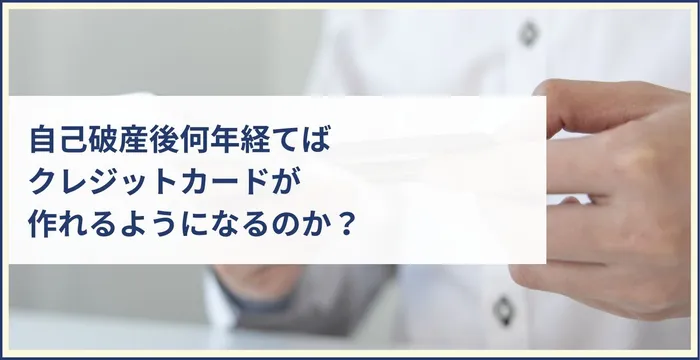自己破産の手続きの流れ
自己破産の手続きは、以下の流れで行われます。
| 1. |
弁護士に相談・依頼をする |
| 2. |
受任通知を債権者に送付する |
| 3. |
申立書類を作成する |
| 4. |
裁判所に自己破産を申立てる |
| 5. |
裁判所で破産審尋(はさんしんじん)を受ける |
| 6. |
【同時廃止の場合】
1.同時廃止決定が出される
2.免責審尋を受ける
3.免責の許可・不許可が決定される
4.免責許可決定が確定される |
| 7. |
【管財事件の場合】
1.破産管財人との面談・財産調
2.債権者集会が開かれる
3.債権者への配当
4.破産手続の終結・廃止
5.免責審尋を受ける
6.免責許可が決定される |
順番に解説します。
1.弁護士に相談・依頼をする
まずは、自己破産を得意とする弁護士に相談・依頼しましょう。電話やメール、問い合わせフォームなどで連絡をとり、相談日を予約します。多くの事務所が無料相談を実施しているため、無料相談を活用するのがおすすめです。
弁護士との相談は対面で行われるのが一般的ですが、オンラインでの面談に対応している事務所もあります。
相談の際は、弁護士に以下の情報を伝える必要があります。事前にまとめておくとよいでしょう。
- 現時点での借金残高
- 収入と支出
- 毎月の返済額
- 債権者の数
弁護士は面談を通して「本当に自己破産が最適かどうか」を判断し、弁護士自身が最適と考える法的手続きを提案してくれます。
債務整理には、自己破産以外にも任意整理や個人再生といった方法があり、どの方法を選択すべきかは相談者の債務状況や「何を希望するか」によって異なるためです。
| 自己破産 |
裁判所に申し立て、許可を得ることで借金をゼロにする方法。財産を処分される可能性がある。借金を返済できる見込みがまったくないケースや高額な財産を所有していない場合に適している。 |
| 任意整理 |
債権者と交渉したうえで、将来発生する利息をカットしてもらう方法。元金自体は減らないため「利息さえなければ返済できる」というケースに適している。 |
| 個人再生 |
裁判所に申し立て、借金を5分の1〜10分の1程度に減額してもらう方法。利息のカットだけでは返済が難しいが、元金自体を減額してもらえば返済が可能なケース、持ち家を残したい場合に適している。 |
弁護士への依頼や債務整理方法が決まれば正式に委任契約を結び、この時点で着手金が発生します。
本来、着手金を支払ってから業務がスタートしますが、費用に関しては弁護士費用だけでも30〜80万円程度かかるのが一般的であり、多くの事務所が分割払いや後払いなどに対応しています。支払いが難しければ相談しましょう。
なお、債務整理手続きは司法書士にも依頼できます。しかし、自己破産をするなら弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
司法書士に依頼したほうが費用を安く済ませられる傾向にありますが、自己破産の手続きで司法書士にできることは書類の作成までであり、裁判所での手続きや裁判官とのやりとりは弁護士でないと代理できないためです。
自己破産の手続きを弁護士・司法書士のどちらに依頼すればよいか迷うときは、以下の記事を参考にしてください。
2.受任通知を債権者に送付する
弁護士に自己破産の手続きを依頼したあと、弁護士は各債権者に対して「受任通知」を送付します。タイミングは事務所によって異なり、遅ければ7営業日程度かかる場合もありますが、ほとんどの事務所が即日〜翌日に発送してくれます。
【受任通知とは】
債務整理の依頼を受けた弁護士・司法書士が、今後は専門家が介入することを各債権者に知らせる通知。取り立てや請求が止まる効果がある。
受任通知で取り立てや請求が止まる理由は、受任通知を受け取った債権者は、原則債務者に対して直接取り立てができなくなる旨が賃金業法第21条第1項第9号で定められているためです。
賃金業法に違反すると「2年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科せられるため、受任通知を受け取ってからも取り立てをやめない債権者はほとんどいないでしょう。
もし受任通知送付後も取り立てが止まらないときは、違法のおそれやうまく受任通知が届いていない可能性があるため、依頼した弁護士に相談しましょう。
取り立てや請求が止まれば「債権者から電話や郵便物が来る」というプレッシャーから解放され、返済の必要もなくなります。また、弁護士費用を分割で支払う場合は、取り立てが止まっている間に支払えるためそれほど大きな負担を感じずに済むでしょう。
3.申立書類を作成する
受任通知発送後、裁判所への申し立てに必要な書類を作成します。申立書や陳述書、財産目録など、入力が必要なものに関しては弁護士が作成してくれますが、中には依頼人本人が収集すべき書類もあるため、丸投げというわけにはいきません。
自己破産の申し立てに必要な書類は以下のとおりです。
| 作成する必要があるもの |
・破産申立書
・陳述書(報告書)
・家計簿(既存のものがあれば添付する)
・債務者一覧表
・滞納公租公課一覧表
・財産目録
・債権者あて名ラベル原稿
・添付書類一覧表 |
| 住居に関する書類 |
【自分・親族の持ち家】
不動産登記事項証明書(1ヶ月以内)
【賃貸】
賃貸借契約書
【公営住宅】
住宅使用許可書 |
| 職業・収入に関する資料 |
【勤めている場合】
・直近2ヶ月分の給料明細書
・直近1年分の源泉徴収票
・商業登記事項証明書(会社役員の場合)
【自営業の場合】
・個人事業者用報告書(指定用紙あり)
・直近2ヶ月分の税務申告書控え・決算書
・事業者用資産目録
【無職の場合】
・直近1年分の所得・課税証明書
・医師の診断書(働けない場合)
・受給証明書(年金受給者)
・生活保護受給証明書(生活保護受給者)
【退職し過去2年以内に退職金を受給した場合】
・退職金支給明細書
・退職金の使途報告書
※同居人の分も必要 |
| 身分に関する書類 |
世帯全員の住民票(3ヶ月以内・本籍続柄入り) |
| 資産に関する書類 |
【所有財産がある場合】
・不動産登記事項証明書
・固定資産評価証明書
・車検証
・保険証券・解約返戻金試算書
・記帳済みの預金通帳
・財産価値があるものを購入した際の領収書(貴金属・毛皮など)
【所有財産がない場合】
課税台帳に記載がない旨の証明書 |
参照:破産申立てに必要な費用と書類など|盛岡地方裁判所第2民事部
多くの書類を集める必要があるため、準備には時間がかかります。そのため、弁護士に依頼してすぐに申し立てられるものではない点に注意が必要です。
自分で準備すべき書類については、依頼した弁護士から指示があるはずです。わからなければその都度弁護士に聞き、できるだけ早く集めましょう。
自己破産手続きの必要書類については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ合わせてチェックしてください。
4.裁判所に自己破産を申立てる
書類が整ったら自己破産を申し立てます。申立先は、住所地を管轄する地方裁判所またはその支部です。
自分で手続きするなら申立人本人が裁判所まで出向かなければなりませんが、弁護士に依頼した場合は弁護士が申し立てや裁判所費用の支払いを代理で行ってくれるため、申立人本人が動く必要はありません。
5.裁判所で破産審尋(はさんしんじん)を受ける
申立てから最短即日〜1ヶ月程度で破産審尋が行われます。
【破産審尋(はさんしんじん)とは】
裁判所が申立人に対して自己破産に至った経緯や事情、免責不許可事由の有無を確認し、破産手続きを開始してもよいか判断するための手続き。裁判官・弁護士・申立人の3者で行われるが、弁護士が出席すれば申立人は出席しなくてもよい場合もある。また、多くの裁判所は破産審尋自体を行わない。
破産審尋では、以下のことを聞かれます。
- 破産申立書や陳述書(報告書)といった提出書類の内容に間違いはないか
- 借金の経緯や事情
- 収入や財産、返済能力など
- 債権者一覧表から漏れている債権者はいないか など
もっとも安心なのは弁護士に対応を任せることですが、自分も出席するのであれば、事前によく弁護士と打ち合わせておくことをおすすめします。
6.【同時廃止の場合】破産手続開始決定以降の流れ
裁判所から支払い不能と判断されると、破産手続きに進みます。そのあとの流れは、「同時廃止事件」「管財事件」のうちどちらになるかによって異なります。
同時廃止事件とは、申立人に処分できる財産がほとんどないケースで適用される破産手続きです。破産手続開始決定後は以下の流れで進みます。
- 同時廃止決定が出される
- 免責審尋を受ける
- 免責の許可・不許可が決定される
- 免責許可決定が確定される
- 免責決定確定証明書を取得する
順番に解説します。
1.同時廃止決定が出される
同時廃止事件の場合、破産手続開始決定と同時に同時廃止決定が出されます。タイミングとしては、破産審尋から1週間程度です。
破産手続開始決定が出ると、申立人の住所や氏名、破産手続きを開始した旨が国の機関紙である「官報」に掲載されます。
また、申立人が免責されることについて異議のある債権者がいないか確認するため、1〜2ヶ月程度の「意見申述期間」が設けられます。
債権者の意見は免責許可・不許可の判断材料になりますが、債権者から反対意見が出るケースはほとんどなく、反対意見が出ない場合、意見申述期間のあと数日程度で免責許可が出るのが通常です。
なお、管財事件は引き上げた財産を現金化し、債権者に分配する必要がある分時間がかかりますが、同時廃止事件になる案件は処分できる財産がないため、管財事件よりも短期間で終了するのが一般的です。
官報をどのような人が見ているかは、以下の記事を参考にしてください。
2.免責審尋を受ける
破産手続開始決定から1〜2ヶ月後に、免責審尋が行われます。申立人は原則出席しなければならないとされていますが、裁判所によっては免責不許可事由がある場合にのみ実施するところもあります。
同時廃止事件は基本的に免責不許可事由がないと考えられるため、免責審尋が行われないケースも少なくないでしょう。
なお、免責不許可事由とはたとえば以下のような行為をいい、該当すると免責が認められない可能性があります。
- 特定の債権者にだけ返済をした
- 浪費やギャンブルが原因で借金をした
- 帳簿を隠ぺいした
- 破産手続きを遅らせるためにクレジットカードを現金化したりヤミ金から借金をしたりした
- はじめから自己破産をするつもりで借金をした
免責不許可事由については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
3.免責の許可・不許可が決定される
免責審尋終了後、1週間程度で免責の許可または不許可が決定し、その旨が官報に公告されます。
許可するかどうかは、以下のことから判断されます。
- 返済不能に陥っているか
- 免責不許可事由にあたらないか
- 免責審尋の内容
免責が許可されると借金は免除されますが、不許可になった場合は借金が丸々残ります。
そのためとれる対応としては、不許可を決定した地方裁判所に対して2週間以内に不服を申し立てるか、任意整理や個人再生といったほかの債務整理方法を検討するかのどちらかでしょう。
とはいえ、免責が不許可になるケースは非常にまれです。免責不許可事由にあたる場合でも、裁判官の判断によって免責が許可される「裁量免責」が可能であるためです。
依頼を受けた弁護士が、免責が許可される見込みがあるか判断して手続きを進めることも理由として挙げられるでしょう。
実際、日本弁護士連合会が公表している「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」では、申し立てられた破産手続きのうち、96%以上が免責許可になっているとのデータもあります。
4.免責許可決定が確定される
免責許可の決定は、1ヶ月程度で確定します。流れとしては、免責の決定から2週間程度で官報公告、さらに2週間で免責確定です。ここでようやく借金の返済義務がなくなり、破産手続きは終了します。
ただし、意図的に財産を隠したり嘘の証言をしたりすると、せっかく認められた免責が取消しになるおそれがあるため注意しましょう。
なお、免責不許可が決定したあと、2週間以内に異議申し立てをせず免責不許可が確定すると決定は覆せません。また、免責が許可された場合でも、以下の「非免責債権」は支払っていく必要があります。
- 税金や罰金
- 国民健康保険料
- 年金
- 養育費や婚姻費用
- 給与や預り金
- 債権者名簿にわざと記載しなかった債権
非免責債権については、以下の記事を参考にしてください。
5.免責決定確定証明書を取得する
免責の確定から1ヶ月程度経ったら、裁判所に「免責決定確定証明書」を請求しましょう。免責が確定しても、裁判所から通知が来るわけではないためです。
免責許可が決定した際に通知書は発行されますが、その段階ではまだ免責を受けていないため、免責決定確定証明書のほうが適しているケースもあるでしょう。
請求先や手数料などは以下のとおりです。
| 請求先 |
免責許可裁判所の窓口・郵送 |
| 手数料 |
150円の収入印紙 |
| 必要なもの |
・免責許可決定確定証明申請書
・身分証明書(運転免許証・健康保険証など)
・認印
・返信用封筒(郵送の場合)
・84円切手(郵送の場合) |
免責決定確定証明書は、免責が確定したことを第三者に証明したい場合に使用できます。たとえば生活保護を受給するときや、自己破産後に債権者から取り立てられた場合などです。
使用しない可能性もありますが、念のために取得しておくとよいでしょう。
7.【管財事件の場合】破産手続の開始決定以降の流れ
管財事件の場合は、同時廃止事件とは異なり「破産管財人」が選任されます。
破産管財人とは、申立人の財産を現金化して各債権者に分配したり、免責を認めても問題ないか調査したりする人のことです。裁判所の管轄内で活動する弁護士が選ばれることが一般的で、裁判所が選任します。
また、同時廃止事件と同様に、この時点で官報にも掲載されます。
破産手続開始決定のあとの流れは以下のとおりです。
- 破産管財人との面談・財産調査
- 債権者集会が開かれる
- 債権者への配当
- 破産手続の終結・廃止
- 免責審尋を受ける
- 免責許可が決定される
順番に解説します。
なお、管財事件と同時廃止事件の違いについては、以下の記事を参考にしてください。
1.破産管財人との面談・財産調査
管財事件では、破産手続きが始まり破産管財人が選任されると、破産管財人によって面談や財産調査が開始されます。
なお、管財事件には、通常の管財事件と少額管財事件の2つのパターンがあります。
| 通常の管財事件 |
99万円を超える財産があるケースで適用される手続き。破産管財人が選任され、手続きも複雑になるため、その分同時廃止事件よりも裁判所費用が高額になる可能性が高い。 |
| 少額管財事件 |
通常の管財事件よりも手続きが簡略化されているため、その分裁判所費用を抑えられる。財産が少ない場合や免責不許可事由に該当しないケースで適用される。弁護士からの申立てが必要。 |
面談は、申立人と代理人弁護士が破産管財人の事務所を訪れ、3者で行われるのが一般的です。
主に、以下のことについて聞かれます。
- 破産管財人が申立書類を確認した際に感じた疑問・確認が必要と判断したこと
- 借金をした理由や返済できなくなった事情
- 自己破産に至った経緯
- 事業の内容や事業で使用している財産の有無(事業を営んでいる場合)
また、以下の資料や情報をもとに調査が行われます。
- 申立書類
- 預金通帳・取引明細書
- 金融機関や賃金業者への情報照会
面談では、聞かれたことに対して正直に答えれば問題ありませんが、返答に困ったら弁護士がフォローしてくれるためそれほど心配する必要はありません。
もし不安なら、事前にどのようなことを聞かれるか、どのように返答すればよいかを弁護士に聞いておくとよいでしょう。
財産調査が終わると、持ち家や車などの20万円以上の価値のある財産が現金化され、破産管財人によって債権者に分配されます。
2.債権者集会が開かれる
財産が債権者に分配されたあとは、「債権者集会」が裁判所の一室で開催されます。
債権者集会とは、債権者に対して自己破産に至った経緯や財産状況、債権者が行う必要のある手続きなどを説明し、意見をもらうための集会です。
以下の流れで行われます。
- 依頼している弁護士とともに会場に入る
- 破産管財人が債権者に破産者の財産状況を説明する
- 破産手続きを終了することについて質疑応答が行われる(分配できる財産がない場合)
- 財産の配当方法を破産管財人が報告し、質疑応答が行われる
- 免責を認めてもよいか判断される
自己破産をすると、申立人は借金から解放されますが、その裏で債権者は大きな不利益を被る可能性があります。そのため債権者が意見を主張できるよう、このような場が設けられています。
ただ、実際に出席する債権者は多くありません。債権者には債権者集会への出席義務がなく、個人であればまだしも、消費者金融やクレジットカード会社、金融機関などが数十万円、数百万円のためにわざわざ個人の債権者集会に出席するのは現実的とはいえないためです。
債権者集会は1回で終わることもありますが、債権者集会までに財産を現金化できていなければ後日再び開催されます。
なお、申立人は破産者として債権者集会に出席する必要があります。たとえ代理人として弁護士に依頼していても、欠席はできません。欠席してしまうと免責が許可されなくなるおそれがあるため、必ず出席するようにしましょう。
3.債権者への配当
債権者集会が終わると、債権者に対して配当が行われます。債権者集会と配当にかかる期間の目安は以下のとおりです。
- 通常の管財事件:3ヶ月〜半年程度
- 少額管財事件:1〜3ヶ月程度
処分できる財産が残っている限り配当は続きますが、配当できる財産がなくなれば破産手続は廃止されます。
なお、配当を行うのは債権者です。そのため申立人が直接配当を行うことはありませんが、破産管財人に情報を提供したり手伝ったりなど、協力しなければなりません。
4.破産手続の終結・廃止
処分した財産を債権者に配当すれば、破産手続きは終結します。
配当が完了しなければ再度債権者集会が開催され、調査の結果配当に充てられる財産がないとわかれば廃止です。どちらにしても破産手続きは終了し、「免責審尋」に進みます。
5.免責審尋を受ける
債権者集会や配当が終わったら、そこから1〜2ヶ月程度で免責審尋が行われます。
免責審尋とは、裁判官からの質問に答えたり、免責についての意見・報告に対して破産管財人が意見したりする機会のことです。
免責審尋で質問を受けるのは、たとえば以下のようなことです。
- 氏名・住所・本籍地に誤りはないか
- 申立書類に間違いはないか
- 免責制度を理解しているか
- 自己破産に至ったことについてどのように思っているか
- 今後どのように生活を立て直していくつもりか
- 債権者に返済できなくなったことについて、どのように感じているか
- 借金をした原因を反省しているか(借金の理由がギャンブルや浪費だった場合)
- 免責不許可事由に該当していないか
なお、免責審尋には、案件ごとに行う「個別審尋」と、複数の申立人が一度に裁判官と面接する「集団免責審尋」があります。
個別審尋では、裁判所が指定する日時に裁判官と破産管財人、申立人、代理人弁護士が集まって行われますが、集団免責審尋の場合は全体に対して免責審尋や免責決定についての説明、今後注意すべきことなどが伝えられ、それぞれ個別に質問を受けます。
どちらの形式で行われるのか、どのようなことを聞かれるのかを事前に弁護士に確認し、しっかりシミュレーションしておくと落ち着いて対応できるでしょう。
6.免責許可が決定される
免責審尋で問題ないと判断された場合は免責許可が決定し、住所や氏名が官報に掲載されます。
結果は、免責審尋から1週間〜10日程度で届きます。免責が不許可になった場合も同じように通知されますが、不許可になるケースはまれです。
免責許可を得たあと1ヶ月程度で免責許可の決定は確定し、破産手続きは終了します。つまり、ここでようやく借金がゼロになるということです。
なお、以下の職業に就いていると、破産手続開始決定後一時的に職業・資格制限を受けますが、多くの場合は免責許可が確定することによって復権し、職業・資格制限は解除されます。
- 士業(弁護士・司法書士・税理士など)
- 警備業
- 生命保険募集人
- 公証人
- 教育委員会・国家公安委員会・公正取引委員会の委員など
ただし、復権のタイミングはケースによって異なります。職業・資格制限から復権までの期間については、以下の記事を参考にしてください。
自己破産の完了までにかかる期間
自己破産について専門家に相談してから、破産手続きが完了するまでにかかる期間は以下のとおりです。
- 同時廃止事件は3~4ヶ月
- 管財事件は2ヶ月から1年程度
それぞれ解説します。
同時廃止事件は3~4ヶ月
同時廃止事件の場合、専門家への相談から免責確定までに3〜4ヶ月かかります。
段階ごとにかかる期間の目安は以下のとおりです。
| 相談〜申立て |
2〜3ヶ月程度 |
| 申立て〜破産手続開始決定 |
2週間〜1ヶ月程度 |
| 破産手続開始決定〜免責決定 |
破産手続開始と同時に免責が決定する |
| 免責決定〜免責確定 |
1ヶ月程度 |
3〜4ヶ月程度かかるのが一般的ですが、ケースによっては半年程度かかることもあります。ただ、多くの場合管財事件よりは早く終了します。
管財事件は2ヶ月から1年程度
管財事件の場合、専門家への相談から免責確定までに2ヶ月〜1年程度かかります。
段階ごとにかかる期間の目安は以下のとおりです。
| 相談〜申立て |
2〜3ヶ月程度 |
| 申立て〜破産手続開始決定 |
2週間〜1ヶ月程度 |
| 破産手続開始決定〜免責決定 |
最短2ヶ月程度 |
| 免責決定〜免責確定 |
1ヶ月程度 |
同時廃止事件より管財事件のほうが長くかかる理由は、破産管財人との面談や債権者集会が行われるためです。そのため、中には2ヶ月程度で完了することもありますが、最短でも半年はかかると見積もっておいたほうがよいでしょう。
自己破産の費用相場と支払うタイミング
自己破産にかかる費用には、主に裁判所費用と弁護士費用の2つがあります。手続きの種類や免責不許可事由に該当するかどうかなど、ケースによってかかる費用は異なりますが、最低でもトータルで30万円程度は必要だと思っておきましょう。
- 裁判所に払う費用:3〜53万円程度
- 弁護士に払う費用:30〜80万円程度
それぞれ解説します。
裁判所に払う費用
裁判所に自己破産の申立てを行う際、「予納金」という裁判所に支払う費用が発生します。予納金の金額は手続きの種類によって異なり、ほかにも官報広告費用や郵便切手代、収入印紙代がかかります。
内訳は以下のとおりです。
| 予納金 |
・同時廃止事件:1〜3万円程度
・少額管財事件:20万円程度
・通常の管財事件:50万円程度 |
| 官報公告費用 |
1万〜1万9,000円程度 |
| 郵便切手代 |
・同時廃止事件:5,000円程度
・管財事件:6,000円程度 |
| 収入印紙代 |
1,500円 |
予納金は、同時廃止事件か管財事件かによって大きく異なります。予納金には破産管財人への報酬が含まれており、同時廃止事件では破産管財人が選任されないのに対し、管財事件の場合は少額でも通常でも破産管財人が選任されるためです。
官報公告費用や収入印紙代は、手続きの種類にかかわらず同じ金額がかかります。ただし、郵便切手代は同時廃止事件よりも管財事件のほうがかかる傾向にあり、裁判所によって金額が異なる可能性があるため確認が必要です。
裁判所費用としてかかる金額の合計は、それぞれ以下のとおりです。
- 同時廃止事件:3〜6万円程度
- 少額管財事件:22〜23万円程度
- 通常の管財事件:52〜53万円程度
参照:自己破産の申立てを考えている方へ|裁判所
弁護士に払う費用
弁護士費用は30〜80万円程度かかります。ケースによっては、さらにかかることもあります。
内訳は以下のとおりです。
| 相談料 |
1時間あたり5,000〜1万円程度
※無料の場合もあり |
| 着手金 |
30〜50万円程度 |
| 成功報酬 |
0〜80万円程度 |
相談料は、無料で実施している事務所に相談すればかかりません。着手金や成功報酬も、事務所によってはどちらかを無料にしているところもあります。実際にいくらくらいかかるかは、相談の時点でよく確認するようにしましょう。
なお、着手金は正式に依頼したときに発生する費用です。通常は、着手金の入金が確認されてからでなければ業務に取り掛かってくれません。そして残りを手続き完了後に支払うのが一般的です。
まとまった資金を用意できない場合は、分割払いや後払いに対応している事務所を選ぶことをおすすめします。
自己破産の費用相場と費用を支払えなくても自己破産する方法については、以下の記事を参考にしてください。
自己破産の手続き中にしてはいけないこと
自己破産の手続き中に、以下の行為を行わないようにしましょう。これらはすべて、免責が認められなくなる行為である「免責不許可事由」に該当するためです。
免責不許可事由に該当する場合でも、裁判官の裁量によって免責が認められるケースもありますが、免責が認められなければ借金はゼロになりません。そのため、免責不許可事由に該当する行為は避けたほうが賢明です。
- 財産を隠す・処分する
- 一部の債権者に返済をする(偏頗弁済)
- ギャンブルや浪費をする
- クレジットカードの現金化
- 新たに借金する
- 裁判所に嘘の内容がある書類を提出する
それぞれ解説します。
財産を隠す・処分する
財産を隠したり処分したりしてはいけません。
たとえば、以下の行為が該当します。
- 自分名義の口座をすべて開示・申告しない
- 口座から引き出した現金の使途が不明である
- 資産価値の高い財産や現金を第三者に預けるまたは譲渡する
- 財産の名義を家族や第三者に変更する
自己破産をするなら、自分名義の預貯金口座はすべて開示しなければなりません。没収されたくないからといって隠してしまうと、免責が認められなくなります。
口座から引き出した現金の使途を説明できないケースも要注意です。実際、自己破産を申し立てる前に引き出した預貯金について、使途を説明できなかったために免責不許可になった例もあります。
そのほか、車や貴金属といった価値のある財産や現金を第三者に預けたり譲渡したりすることも、自己破産をするならしてはいけない行為です。たとえば車を知人に譲渡した場合、「その分債権者に分配できる財産が減ってしまう」と考えるためです。
財産の名義を自己破産前に変更することも、基本的には認められません。財産を没収されないために名義を変更すると、財産隠匿行為や説明義務違反行為に該当する可能性がある点に注意しましょう。
なお、財産の譲渡や名義変更については「言わなければバレない」と思うかもしれませんが、自己破産をする2年前までさかのぼって調査されます。そのため不正がバレる可能性が高く、バレたときのリスクも大きいことを念頭に置いておきましょう。
財産隠しの危険性については、以下の記事を参考にしてください。
一部の債権者に返済をする(偏頗弁済)
借金が返済できない状況であるにもかかわらず、一部の債権者にだけ返済したり担保提供したりする「偏頗弁済(へんぱべんさい)」も、自己破産の手続き中にしてはいけないことの1つです。
たとえば、友人や勤務先に迷惑をかけたくないからと、友人や勤務先からの借金だけを返済するケースが該当します。
偏頗弁済が認められない理由は、債務整理の際にすべての債権者を平等に扱うべきとする「債権者平等の原則」に反するためです。
偏頗弁済が判明すると、免責が認められないどころか申し立てすらできなくなるおそれがあります。また、破産管財人が返済を受けた債権者に対して、受け取ったお金の返還を求めることでトラブルに発展する可能性もある点に注意しましょう。
このように、偏頗弁済を行うと大きなリスクを負ってしまいます。どうしても債権者に迷惑をかけたくないなら、整理対象を選べる任意整理を検討するか、弁護士にどうすればよいか相談することをおすすめします。
ギャンブルや浪費をする
ギャンブルや浪費は、自己破産の手続き中だけではなく弁護士に相談した時点でやめるようにしてください。ギャンブルや浪費といった無駄遣いも、免責不許可事由に該当するためです。
何より、自己破産を申し立てておきながらギャンブルや浪費をしているのでは、まったく反省していないと思われるでしょう。
裁判所には裁量免責が認められているため、たとえ免責不許可事由に該当していても、裁判所の判断次第では免責が受けられます。ただし免責を受けられるのは、自己破産したことに対して反省の気持ちがあり、裁判所に対して協力的な姿勢が見られるケースです。
申し立てたあともギャンブルや浪費を続けていては反省していないと判断され、免責が認められにくくなるでしょう。
クレジットカードの現金化
クレジットカードの現金化は、申立前から行わないようにする必要があります。
クレジットカードの現金化も、免責不許可事由に該当する行為であるためです。そもそも、クレジットカード会社の規約で禁止されているため行ってはいけません。
クレジットカードの現金化とは、クレジットカードのショッピング枠で購入した商品を売却し現金を得ることをいいます。よくあるのが、ブランド品やゲーム機、ギフトカードなどを購入してすぐ現金化するケースです。
「言わなければバレないのでは?」と思うかもしれませんが、管財事件では破産管財人が免責不許可事由に該当しないかどうかも細かくチェックします。
同時廃止事件でも、裁判所の書記官によって免責調査が行われることがあるため、過去にクレジットカードを現金化していた場合はバレる可能性が高いでしょう。
注意点は、クレジットカードを現金化した事実を隠さないことです。
過去にクレジットカードを現金化してしまっている場合、隠してもバレるときはバレます。調査によって現金化が発覚するより、自分から正直に話したほうが印象が悪くなりにくく、裁量免責が認められやすくなるでしょう。
新たに借金する
申し立ての1年前から破産手続開始決定までの間に新たな借金をした場合、免責不許可事由にあたる可能性があります。破産手続き中や破産手続き前に借金する=返済できなくなることがわかっていて借金したと考えられるためです。
返済できなくなることがわかっており、自己破産も視野に入れている状態で新たに借金をすると、詐欺罪に問われる可能性もあるため注意しましょう。
自己破産前に借入れをしたときのペナルティについては、以下の記事を参考にしてください。
裁判所に嘘の内容がある書類を提出する
裁判所に嘘の内容のある書類を提出してはいけません。書類の偽造や変造も免責不許可事由にあたるためです。
たとえば、以下のような行為はしないようにしましょう。
- わざと一部の債権者を「債権者一覧表」に記載しなかった
- 財産目録や家計簿に嘘の記載をした
バレないだろうと思っていても、財産や借金、免責不許可事由に該当するかどうかは、破産管財人や裁判所が細かく調査します。
正直に記載していれば裁量免責が認められたようなケースでも、嘘がバレると裁判所や破産管財人から信用されなくなり、免責を受けられなくなる可能性があるため正直に記載するようにしましょう。
何か後ろめたいことがあるなら、嘘をつくのではなく弁護士に相談することをおすすめします。
自己破産できない原因については、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてチェックしてください。
まとめ
自己破産の流れについて解説しました。
自己破産を申し立てるなら、まずは弁護士に相談しましょう。弁護士に相談し、正式に依頼すると債権者からの取り立てが止まります。
借金を返済する必要がなくなることで、落ち着いて手続きを進められるでしょう。また、弁護士に依頼すれば、申立書類の作成や裁判所への申し立ても代わりに行ってくれます。
自己破産の手続きには、同時廃止事件で3〜4ヶ月、管財事件で2ヶ月〜1年程度かかります。急ぐ場合は、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
なお、手続き中には、財産を隠す・処分する行為や偏頗弁済など、行えば免責が認められなくなる免責不許可事由がいくつかあります。免責が無事認められるよう、免責不許可事由に該当する行為を行わないよう注意しましょう。
よくある質問
破産手続きをすると裁判所に行かなくてはならないのでしょうか?
破産手続きを行う場合、以下のとおり
原則2回は裁判所に出向く必要があります。
- 破産手続開始決定前に行われる「破産審尋」
- 免責許可決定前に行われる「免責審尋」
ただし、回数や方法は地方裁判所によって異なります。中には破産審尋を書面だけで行ったり、裁判官との面談を弁護士に任せられたりするところもあるためです。
とはいえ、最低でも1回は出向く必要があると思っておいたほうがよいでしょう。
裁判所に出向く際は、弁護士に同行を依頼できます。日当や出張費がかかりますが、フォローしてもらえるため安心して臨めるでしょう。
破産した場合、賃貸物件は借りられますか?
自己破産をすると、賃貸物件を借りる際の入居審査に通らない場合があります。自己破産をしたことによって信用情報に傷がつくためです。
ただし審査に通りにくくなるのは、信販系やLICC形の家賃保証会社を利用するケースです。独立系の保証会社であれば、信用情報をチェックせず独自の審査基準を用いて入居審査を行うため、自己破産をした場合でも契約できる可能性があります。
なお、自己破産をしたからといって、現在契約している賃貸物件から退去する必要はありません。
家賃を滞納していた場合は、滞納していた家賃も免責の対象になり退去しなければならなくなります。しかし家賃をきちんと支払っていたのであれば、自己破産後もそのまま住み続けられます。
給与や年金は受け取れますか?
破産手続開始決定後に得た給与は、処分の対象にならないため受け取れます。ただし破産手続開始決定時点で受け取りが確定している給与や、破産手続開始決定前に受け取った給与は現金や預貯金として処分の対象になる可能性があります。
なお、所有が認められる現金は99万円まで、預貯金は20万円までです。それを超えると、処分の対象になることを覚えておきましょう。
年金については、公的年金や企業年金などは差押禁止債権に該当するため自己破産をしても通常どおり受け取れます。個人年金については処分の対象になる可能性がありますが、生命保険と個人年金の解約返戻金が合わせて20万円以下なら解約せずに済むでしょう。
注意したいのは、公的年金を担保に公的機関から貸付を受けられる「年金担保貸付」を利用しているケースです。借入れした分を完済しなければ、年金を受け取れない場合があります。