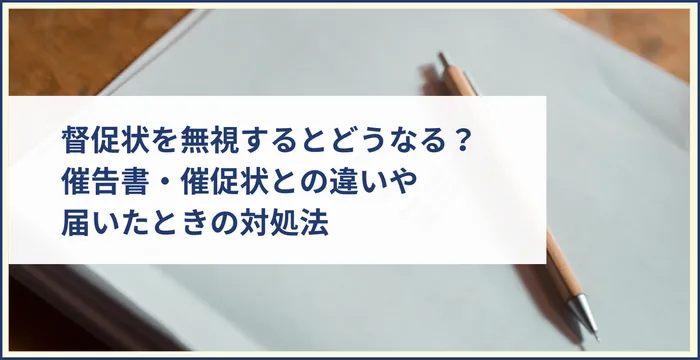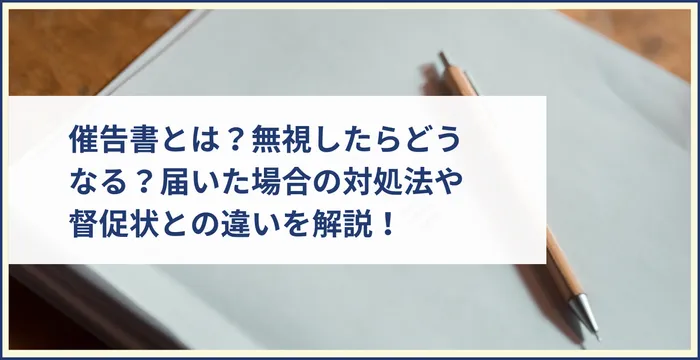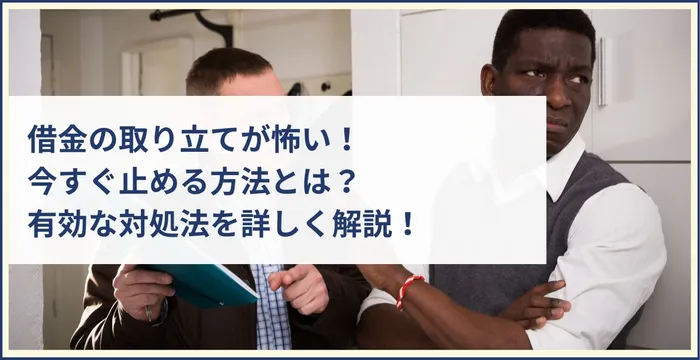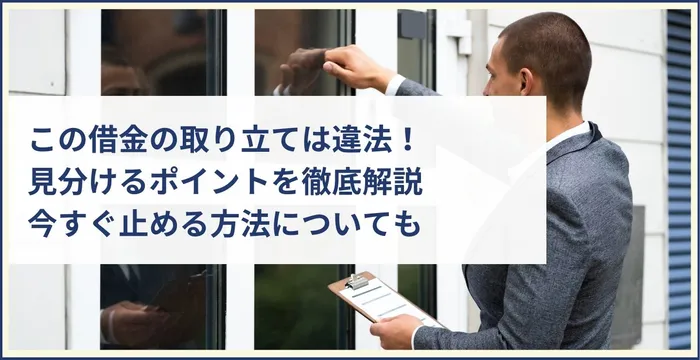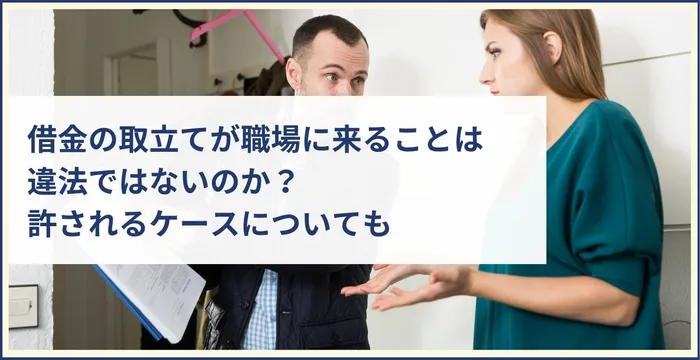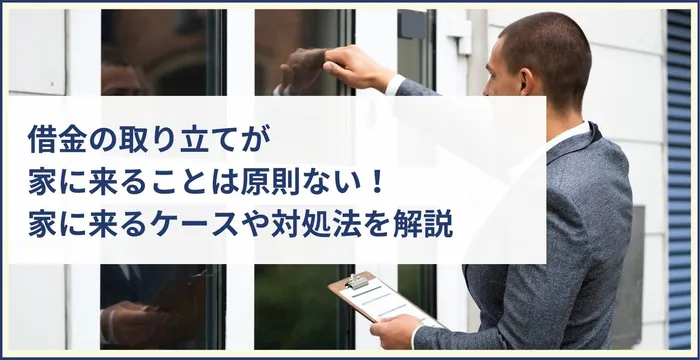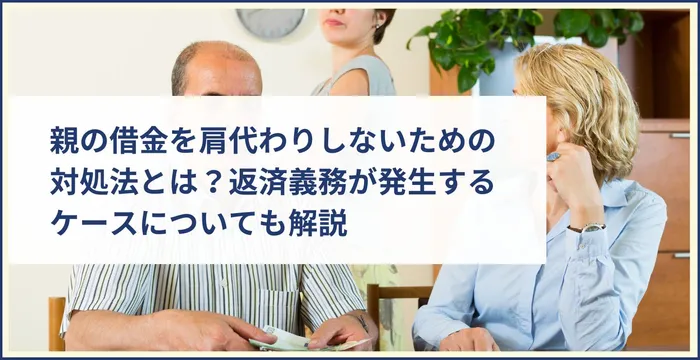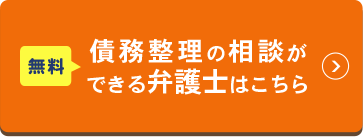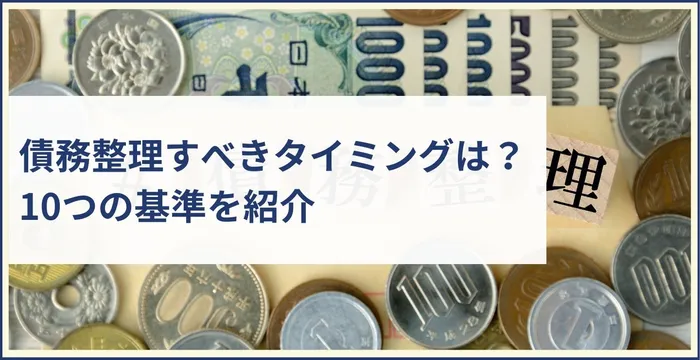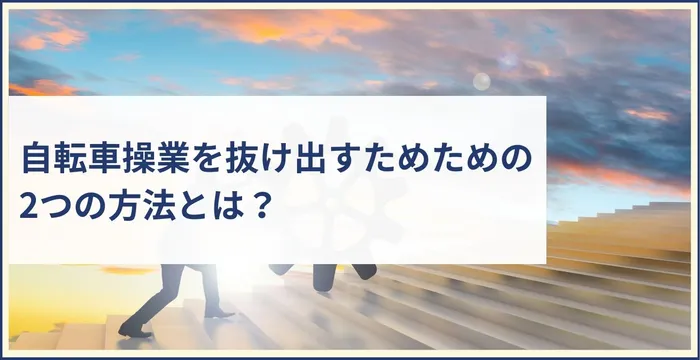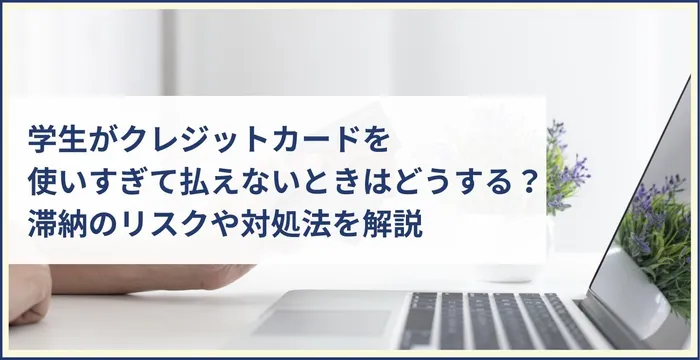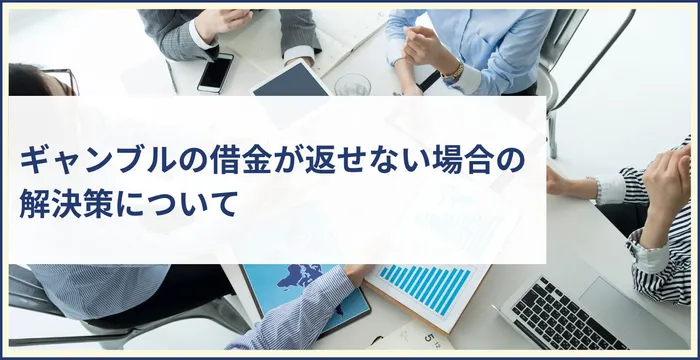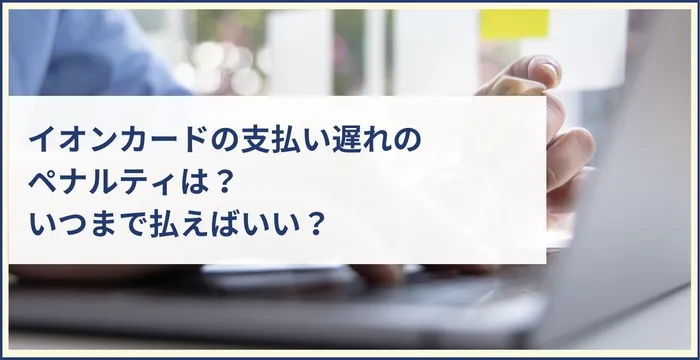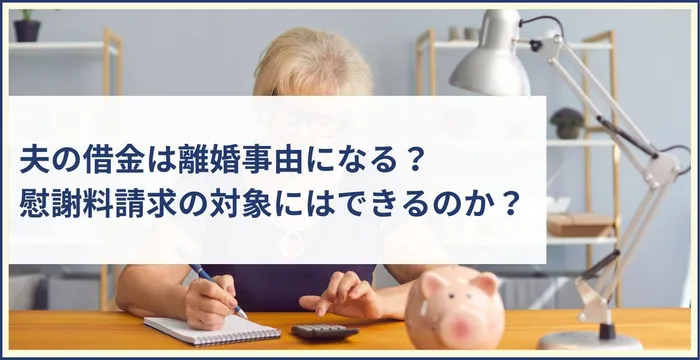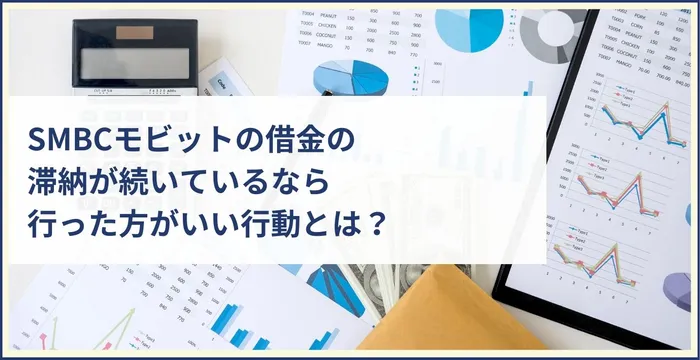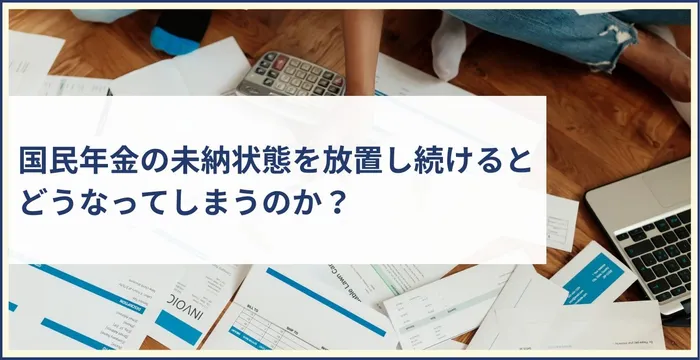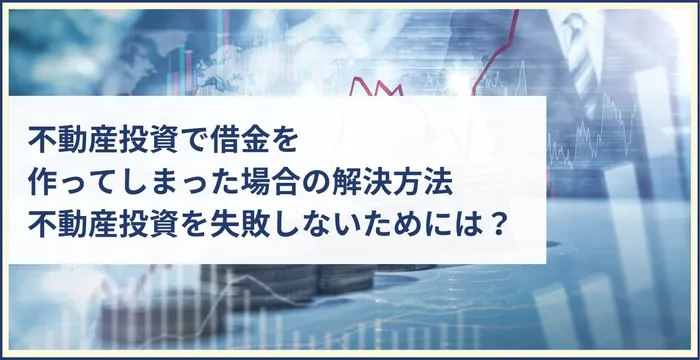借金の取り立てはどのように深刻化していくのか?
借金を滞納すると、債権者から取り立てを受けることになります。
「取り立て」と聞くと、大きな声で恫喝されたり、暴力を振るわれるといったイメージを持つ人も多いかと思います。しかし、そのような取り立て行為は貸金業法第21条で禁止されているので、正規の貸金業者であれば脅迫や暴力を伴う取り立てをおこなうことはありません。
では、実際の取り立てでは、どのような流れでどんな取り立て行為がおこなわれるのでしょうか?
一般的な取り立ての流れは以下のとおりです。
- 電話やメール、SMSによる督促を受ける
- 郵便物による督促を受ける
- 実家や勤務先にも督促がおこなわれる
- 債権回収会社に債権譲渡される
- 保証人・連帯保証人にも督促がおこなわれる
- 裁判所から支払督促が届く
- 給料や財産を差し押さえられる
次の項目から、順を追って詳しく解説します。
参照:e-Govポータル「貸金業法第21条」
1.電話やメール、SMSによる督促を受ける
滞納すると、早ければ返済日の翌日から電話やメール、SMSでの督促が始まります。
督促といっても、その内容は滞納している事実の共有や返済可能日の確認など、事務的な連絡である場合がほとんどです。
また、連絡が来るのは通常、本人の携帯電話のみです。
2.郵便物による督促を受ける
債権者からの電話やメールを無視したり、約束した返済日に入金がないと、今度は郵便で督促状が送られてきます。
督促状は「入金が確認できていないので一度連絡をください」と優しく返済を促す内容から始まり、2通目、3通目と回数が増えるごとに文面が厳しくなっていくことが一般的です。
また、最初のうちは普通郵便で封筒やハガキなどが送られてきますが、滞納期間が2ヶ月程度になると内容証明郵便で催告書が届くようになります。
催告書は督促状よりも厳しい文面で「いますぐ借金全額を一括返済してください。できなければ裁判を起こします」といった内容が書かれていることが一般的です。
3.実家や勤務先にも督促がおこなわれる
督促状や催告書も無視し続けていると、自宅の固定電話や実家、勤務先にも督促の連絡が来ることがあります。
このとき、債務者本人以外が電話口に出たとしても、債権者が社名や借金について口にすることはありません。しかし、何度も身元や要件が曖昧な電話がかかって来たら、家族や同僚に不審がられる恐れがあるでしょう。
また、電話やメール、SMSや郵便による督促をすべて無視すると、貸金業者の担当者が督促のために自宅を訪問することがあります。担当者が訪問した際、同居している家族が対応した場合は、家族に借金の事実を知られてしまう恐れがあるため注意が必要です。
4.債権回収会社に債権譲渡される
あらゆる連絡手段を駆使しても債務者と連絡が取れない場合、債権者は自社での借金回収を諦めて債権回収会社に債権を譲渡することがあります。
債権回収会社・・・借金の回収業務を得意とする専門業者。債権者から債権を譲り受けたり、借金の回収業務を委託されて借金の取り立てをおこなう。
債権回収会社は、元の債権者よりも積極的に借金回収のため動くことが特徴で、裁判を起こしたり自宅訪問による督促も躊躇なくおこないます。
裁判を起こされると、最悪の場合は給料や財産を差し押さえられてしまいますし、自宅訪問による督促を受けると、同居している家族や近所に借金の事実を知られやすくなってしまうでしょう。
5.保証人・連帯保証人にも督促がおこなわれる
借金に保証人や連帯保証人が設定されている場合、滞納が続くと保証人・連帯保証人も督促を受ける恐れがあります。
保証人(連帯保証人)・・・債務者が借金を返済できなくなった際、代わりに返済義務を負う人のこと。
もし、保証人や連帯保証人が債権者の請求どおり返済できなければ、債務者と同様、給料や財産を差し押さえられる恐れがあります。
なお、保証人や連帯保証人が複数設定されている場合、保証人は借金を頭数で割った金額のみ返済することも可能です。しかし、連帯保証人は借金全額に対して返済義務を負っているので、他に何人の保証人・連帯保証人が設定されていても、借金がゼロになるまで督促を受け続けることになります。
6.裁判所から支払督促が届く
借金を長く滞納していると、債権者から裁判を起こされ裁判所から通知が届くこともあります。裁判所から届く通知には主に2つの種類があり、最初に「支払督促」次に「訴状」の順で届きます。
支払督促は、債権者が裁判所へ支払督促の申立てをおこなったことを意味しています。
支払督促を受け取った場合、2週間以内に裁判所へ異議申立書を提出しなければ、支払督促の内容を認めたとして債権者に有利な形で手続きが進んでしまいます。
支払督促を無視すると仮執行宣言付支払督促が届く
支払督促を無視して返済もおこなわない場合、次の段階として裁判所から仮執行宣言付支払督促が届きます。
仮執行宣言付支払督促も支払督促と同様、受け取ってから2週間は裁判所へ異議を申し立てられる期間が設けられています。
ただし、仮執行宣言付支払督促の場合、異議を申し立てないと仮執行宣言付支払督促の内容がそのまま確定してしまうのです。
確定した仮執行宣言付支払督促は、訴訟での判決と同様の効力を持ち、債権者は債務者の財産を差し押さえる権利を得ます。
支払督促に異議を申立てると訴状が届く
支払督促が届いてから2週間以内に裁判所へ異議を申し立てると、支払督促は効力を失います。
しかし、支払督促の効力が消えても安心はできません。支払督促に対して債務者が異議申立てをおこなう場合、ほとんどの債権者は訴訟手続きへ移行し、再び差し押さえをしようとしてくるからです。
債権者が訴訟手続きへ移行すると、裁判所から訴状が届きます。
訴状を受け取った場合、支払督促と同様に裁判所へ異議を申し立てなければ、訴状の内容を認めたとして債権者に有利な形で裁判が進んでしまいます。
訴状の内容に異議を申し立てる方法は、主に以下の2つです。
- 訴状に同封されている口頭弁論期日呼出状に書かれた口頭弁論期日に、裁判所へ出頭する。
- 口頭弁論期日の1週間前までに答弁書を提出する。
ただし、支払督促とは違い、ただ異議を申し立てるだけでは訴状の内容を覆すことはできません。訴状の内容を覆すには、対抗し得る証拠を提出する必要があるのです。
もし訴状が届いても何もせず無視したり、訴状の内容を覆せなかった場合は、債権者に有利な判決が下り、債務者の財産を差し押さえる権利が債権者に与えられます。
7.給料や財産を差し押さえられる
仮執行宣言付支払督促や判決が確定すると、債権者は債務者の財産を差し押さえる権利を得ます。
債権者が差し押さえる財産には、主に以下のようなものがあります。
- 給料
- 銀行口座
- 生命保険の解約返戻金
- 不動産(自宅を含む)
- 車
優先的に差し押さえられるのは、給料と銀行口座内の預貯金です。とくに給料は、一度差し押さえると手取り額の1/4※を毎月回収できるため、多くの債権者が最優先で差し押さえようとします。
※手取り額が44万円を超える場合は、33万円を超えた金額すべてが差押えの対象
もし、給料の差押えを受けてしまったら、勤務先にも裁判所から通知が届き、勤務先に借金の事実を知られるだけでなく迷惑をかけることにもなってしまうでしょう。
違法となる借金の取り立て方法について
借りたのが正規の貸金業者であれば、貸金業法に則って取り立てをおこなうため、脅迫や暴力を伴う取り立てがおこなわれることはありません。
しかし、闇金などの違法業者から借りてしまったり、借りた相手が個人だった場合は、生活や仕事、家族にも影響が及ぶような違法な取り立てを受ける恐れがあります。
この項目では「どのような行為が違法な取り立てに当たるのか」について詳しく解説します。もし、該当する取り立て行為があった場合は、速やかに弁護士や司法書士、警察などに相談しましょう。
違法な取り立て行為の例
借金の取り立て行為には、貸金業法によって禁止行為が定められています。
貸金業法第21条で禁止されている違法な取り立て行為には、以下のようなものがあります。
- 1.21時から翌8時までの時間帯に取り立てをおこなう
- 2.債務者の勤務先など自宅以外の場所へ取り立てをおこなう
- 3.訪問に対して退去するよう意思表示されたのに退去しない
- 4.張り紙や立て看板などで借入状況や私生活に関する事実を周囲に知らせる
- 5.他者から借りるなどして返済資金を調達するよう要求する
- 6.家族など債務者本人以外に返済を指示する
- 7.債務整理開始後(受任通知受け取り後)の督促
- 8.執拗な連絡先強要
次の項目から、それぞれの違法な取り立てについて詳しく見ていきましょう。
1.21時から翌8時までの時間帯に取り立てをおこなう
正当な理由がないにも関わらず、21時から翌8時の間に債務者へ電話・FAXなどで連絡したり、自宅に訪問する行為は違法な取り立てに該当します。
一般的に、深夜や早朝に連絡するのは非常識であり、債務者の私生活を害する行為と考えられているのです。
ちなみに、正当な理由とは「債務者の事情で21時から翌8時の間にしか連絡をとれない」「債務者がずっと連絡を無視している」などが挙げられます。
2.債務者の勤務先など自宅以外の場所へ取り立てをおこなう
勤務先や実家など、債務者の自宅以外の場所へ正当な理由なしに電話・電報・FAXなどで連絡したり、訪問する行為は違法な取り立て行為に該当します。
ただし「自宅ではなく勤務先に連絡して欲しいと債務者が依頼した場合」や「債務者とまったく連絡が取れない場合」などには、正当な理由があると認められるケースもあります。
3.訪問に対して退去するよう意思表示されたのに退去しない
債務者は、住居や勤務先に訪問した債権者に対して「退去してほしい」と申告する権利があります。もし、債務者が退去を求めたにも関わらず、債権者が自宅や勤務先に居座ったり「返済するまで帰らない」などといって取り立て行為を続けた場合は、違法な取り立て行為に該当します。
債権者がいつまでも自宅や勤務先に居座った場合、同僚や近所の人に借金をしている事実を公表するようなものなので、債務者の私生活を害する行為と考えられているからです。
4.張り紙や立て看板などで借入状況や私生活に関する事実を周囲に知らせる
債務者が借金を滞納している事実や、その他プライベートの事情などを、第三者に知らせる行為も違法な取り立て行為に該当します。
例として、自宅のドアや近隣の壁、電柱など、多くの人の目につく場所に「早く返済しろ」「◯◯さんは借金を返済しません」などといった張り紙や立て看板を設置する行為などが挙げられます。
このような行為は債務者を精神的に追い詰め、私生活の平穏を著しく害する行為と考えられているのです。
5.他者から借りるなどして返済資金を調達するよう要求する
債務者に対して、返済資金を工面するために他社から借金するよう要求する行為なども、違法な取り立て行為に該当します。
また、クレジットカードを使って返済するよう強要することも禁止されています。
6.家族など債務者本人以外に返済を指示する
債務者の配偶者や子ども、両親、兄弟姉妹、恋人、友人など債務者以外の第三者に対して、代わりに借金を返済するよう要求する行為は違法な取り立て行為に該当します。
ただし、保証人や連帯保証人は例外です。債務者本人と連絡が取れなかったり、借金を滞納し続けている場合は、保証人・連帯保証人への取り立てが認められています。
7.債務整理開始後(受任通知受け取り後)の督促
債務者が弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、債権者宛てに受任通知が送付されます。
受任通知・・・債権者に対して、弁護士や司法書士が債務者から依頼を受けた旨を知らせる通知
受任通知を受け取った後、正当な理由がないにも関わらず、債権者が債務者へ電話・電報・FAX・訪問などの手段で直接連絡したり、返済を要求する行為は違法な取り立て行為に該当します。
ただし「弁護士が承諾した場合」や「弁護士と連絡が取れなくなっているような場合」には、正当な理由があると判断されます。
8.執拗な連絡先強要
取り立ての協力を拒否した第三者に対し、執拗に協力を依頼するのも違法な取り立て行為に該当します。
例として、本人の配偶者や両親、友人などが断ったにも関わらず「本人に連絡するよういっておいて」と無理やり伝言を頼んだり、本人の居場所や連絡先を聞き出そうとする行為などが挙げられます。
個人間の借金取り立て行為が違法になるケース
ここまで、貸金業法で禁止されている取り立て行為について見てきましたが、貸金業法はあくまでも貸金業者に対して適用されるものです。友人・知人など個人間の借金に関する取り立て行為は、貸金業法の対象外となります。
そのため、前述した違法な取り立て行為の例に該当する取り立てを受けても、相手が個人の場合は違法になりません。
「それなら個人間であれば何をしてもいいの?」と思うかもしれませんが、個人間の借金取り立て行為についても、貸金業法以外の法律に違反すれば違法となります。
貸金業法以外の法律に違反する取り立て行為には、たとえば以下のようなものがあります。
| 出資法違反 |
出資法で定められた上限を超える高金利での貸付 |
| 業務妨害罪 |
職場に何回も連絡するなど、仕事の邪魔をする |
| 脅迫罪・恐喝罪 |
「殺すぞ」「臓器を売るぞ」「家に火をつけるぞ」などと脅して返済を求める |
| 住居侵入・建造物侵入罪 |
住居またはアパートなどの共同住宅に、住人や管理者に無断で侵入する |
| 暴行罪 |
殴る、胸ぐらをつかむなど人体に物理的な力を行使する(拡声器を用いて大声を発する行為も暴行罪にあたるとした裁判例あり) |
| 不退去罪 |
住居などから退去するよう求めたにも関わらず居座る |
| 名誉毀損罪 |
勤務先等に借金のことを言いふらし、社会的評価を害する |
| 器物損壊罪 |
張り紙や落書きをしたり、物を壊す |
上記以外にも、身の危険を感じるような取り立て行為があれば、まずは弁護士や司法書士へ相談して、取り立て行為に違法性があるかどうか確認してもらうことをおすすめします。
違法な取り立て行為を受けた場合の相談先
前項で紹介したような違法な取り立て行為を受けた場合、一人で悩まずに専門機関へ早めに相談することが大切です。
違法な取り立て行為を受けた場合に相談できる専門機関には、以下のようなものがあります。
前述した貸金業法以外の法律に違反する取り立て行為があった場合は、速やかに警察へ相談しましょう。警察に相談することで、厳重注意や逮捕に至る可能性があります。
ただし、正規の貸金業者からも借金がある場合、警察に相談しただけでは解決できません。また、取り立てされているものの、事件性がないと判断されれば積極的な介入を望めないこともあるので、注意が必要です。
取り立て行為が違法かどうかわからない場合や、正規の貸金業者からも借金がある場合は、まず弁護士・司法書士に相談するのがおすすめです。とくに、闇金対応もおこなっている弁護士・司法書士に相談すれば、闇金からの取り立てと借金の問題を一度に解決できます。
当サイトでは、闇金対応と借金問題の解決どちらも扱っている弁護士・司法書士を多数紹介しています。無料相談が可能なのでぜひ気軽に相談してみてください。
相談前に違法な取り立ての証拠を集めておこう
違法な取り立てを弁護士・警察などに相談する場合は、証拠や情報を残すことが大切です。とくに、警察へ相談する場合は、違法な取り立て行為があったという具体的な証拠がないと、積極的に動いてもらえない可能性が高いです。
具体的には、下記のような証拠や情報を残しておくようにしてください。
- 相手の名前(業者名)
- 相手の住所・電話番号などの連絡先
- 相手の銀行口座情報
- やりとりした書類(契約書など)
- 着信履歴
- 留守電メッセージ
- メール履歴
- 防犯カメラまたは自身で録画した映像
- 闇金業者(取立人)との会話や電話の録音
- 嫌がらせのビラや立て看板、張り紙の現物または画像
- 違法な取り立てを受けた日時・内容のメモ
ただし、闇金対応をおこなっている弁護士・司法書士なら、違法な取り立て行為の証拠や情報がない、または少ない場合でも、依頼を受けてくれることが多いです。依頼後に、必要に応じて違法な取り立て行為の証拠集めをサポートしてくれるので、まずは気軽に相談してみるとよいでしょう。
借金の取り立てを止める方法
前項では、借金取り立ての一般的な流れについて紹介しました。
借りたのが正規の貸金業者であれば、脅迫や暴力を伴う取り立てや執拗な嫌がらせを受けることは基本的にありません。
とはいえ、取り立てを無視し続けると、最終的には給料や財産を差し押さえられる恐れがあり、差し押さえを避けるには一刻も早く滞納を解消し、取り立てを止めることが大切です。
次の項目から、借金の取り立てを止める具体的な方法について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
金融機関に相談して返済計画の見直しをおこなう
返済日に返済ができないとわかったら、すぐに金融機関へ連絡し、返済計画を見直してもらえないか相談しましょう。
きちんと返済する意思があることを伝え真摯な態度で事情を説明すれば、返済日や返済額の相談に乗ってもらえたり、督促の一時停止などの対応を取ってもらえる可能性があります。
とくに、長年利用している貸金業者などであれば、返済期間の延長や利息の減免などにも柔軟に応じてもらえる可能性があるでしょう。
ただし、完済までの日数が延びれば、支払う利息額が増えてしまう点には注意してください。
親や友人などにお金を借りて返済する
親や友人に借金のことを打ち明けられるなら、一時的にお金を借りて返済に充てるのも有効な手段です。
返済資金を工面するために新たな借金をする人もいますが、その借金にも利息が加算されるため、結果的に借金総額は増えてしまいます。
しかし、親や友人から無利息や低金利でお金を借りられれば、借金の返済負担を大幅に抑えることも可能です。
なお、借用書がない借金は贈与とみなされ贈与税が課せられる場合もあるので、相手が親や親しい友人であっても、きちんと借用書を作成するとよいでしょう。
債務整理をする
もし、前述した方法でも滞納を解消することが難しいなら、既に自力で取り立てを止めることは難しい状況に陥っていると考えられます。
これ以上状況が悪化する前に取り立てを止めたいなら、一刻も早く借金問題解決の専門家である弁護士や司法書士に相談しましょう。債務整理という手続きによって、借金問題の根本的な解決が可能になります。
債務整理とは、借金の利息や元金をカットや減額できる手続きの総称で、単なる返済の先延ばしではなく借金自体を減額できるのが特徴です。
また、既に提起されている訴訟を中断させたり、一括請求を長期の分割払いに変更できる効果も期待できるので、借金の返済負担を大幅に減らせる可能性があります。
次の項目から、債務整理の種類やその減額効果、債務整理を検討すべきタイミングなどについて、詳しく解説します。
債務整理を行うことで支払いと督促を一時ストップ可能
債務整理を依頼すると、弁護士や司法書士は債権者に対して受任通知を送ります。
債権者が受任通知を受け取ると、債権者から債務者に対する督促はストップします。これは、受任通知を受け取った後の債務者に対する直接の取り立て行為が、貸金業法第21条で禁止されているからです。
なお、債務整理の手続きが完了するまでは、債権者への支払いも一時的にストップできるので、債務者は精神的負担となっていた督促や支払いから解放されます。
債務整理の3つの種類とその減額効果
債務整理には、以下3つの種類があります。
| 任意整理 |
将来利息をカットし、元金のみ3〜5年で分割返済する手続き。月々の返済額を1/2程度まで減らせる場合が多く、場合によっては返済額が1/3以下になる可能性もある。 |
手続きの詳細はコチラ |
| 自己破産 |
20万円以上価値のある財産を手放す代わりに、借金全額の支払義務が免除される手続き。免責が下りれば借金がゼロになる。 |
手続きの詳細はコチラ |
| 個人再生 |
財産を手元に残したまま、借金を約1/5に圧縮し3〜5年で分割返済する手続き。借金総額や資産状況にもよるが、月々の返済額は3〜8万円程度になることが多い。 |
手続きの詳細はコチラ |
どの方法を選択するかによって、借金の減額割合やメリット・デメリット、手続きにかかる期間などが異なります。自分にとって最適な方法を知りたい場合は、弁護士や司法書士に借入状況や収支状況を詳しく説明し、アドバイスをもらうとよいでしょう。
債務整理を検討すべきタイミング
なかには、「自分は債務整理をするべき状況なのか」判断がつかないと悩んでいる人もいるかもしれません。
そこで、この項目では「債務整理を検討すべき10個のタイミング」についてお伝えします。
もし、以下の項目のうちどれか一つでも当てはまるなら、債務整理を検討すべきタイミングが来ていると考えてください。
- 借金返済を滞納しはじめている
- 月々の返済が負担に感じはじめて1年経つ
- 何度も借金を繰り返して「借金癖」がついている
- 「借金返済のための借金」をしていて完済できる見込みがない
- 月々の返済額が月収の1/3以上になっている
- 休職や退職で収入が減ったorなくなった
- 借金をしている会社が3社以上ある【多重債務】
- 利息分の支払いしかできず元本が減らない
- 利息が高すぎると感じた
- 結婚を機に借金を清算したいと感じた
なお、当サイトでは無料相談を受け付けている弁護士・司法書士を多数紹介しているので、まずは気軽に相談して、借金問題に関するアドバイスを受けることをおすすめします。
>>【無料相談】借金問題に詳しい弁護士・司法書士はこちら
債務整理を検討すべきタイミングについてさらに詳しく知りたい人は、以下の記事も併せて参考にしてください。
借金の取り立て代行業者とは?
借金の取り立ては、必ずしも債権者がおこなうとは限りません。
債権者は、自社での回収が困難と判断した借金について「借金の取り立て代行業者」へ回収業務の委託をおこなうことがあります。
借金の取り立て代行業者とは、債権者の代わりに借金の取り立てをおこなう債権回収会社(サービサー)や弁護士などのことです。
債権回収会社・・・法務大臣の許可を得て借金の取立てを専門におこなう業者
借金の取り立て代行業者は、債権者と比べてより積極的な借金の取り立てをおこなうのが特徴です。借金の回収業務を委託された場合、自宅訪問や訴訟提起による取り立ても躊躇なくおこなわれると考えましょう。
代行業者から取り立てを受けた場合も弁護士・司法書士への相談が有効
借金の取り立て代行業者から取り立てを受けた場合も、債権者から取り立てを受けた場合と同様、弁護士や司法書士へ相談することで取り立てを止められます。
弁護士や司法書士へ依頼すると、すぐに債権者へ受任通知が送られます。
受任通知が届くと、債権者のときと同様に、借金の取り立て代行業者から債務者への直接の取り立ては停止します。
その後は、弁護士・司法書士が取り立て代行業者との間に入って交渉してくれるので、債務者は無理のない返済計画で借金を返していけるようになるのです。
違法な取り立て代行業者も存在するので注意
借金の取り立て代行ができるのは、原則として法律に関する専門家だけです。しかし、なかには違法な取り立て代行業者も存在するので、お金を騙し取られないよう注意してください。
下記が、違法な取り立て代行業者の特徴です。
- 法務省のホームページに掲載されていない
- 探偵業者が取り立て行為をおこなっている
- 貸金業法に違反する取り立て行為をおこなっている
前述したとおり、債権回収会社は法務大臣の許可を得て営業している業者です。正規の債権回収会社であれば、法務省のホームページ内に許可番号・営業許可年月日・代表者名・称号・所在地・電話番号などが掲載されています。
そのため、法務省のホームページを見れば、正規の債権回収会社か違法な取り立て代行業者かを判断できます。なお、正規の債権回収会社と同じ名前を名乗る違法な取り立て代行業者も存在するので、業者名だけでなく電話番号などの情報も一致するかどうか、よく確認してください。
また、探偵業者は借金の取り立て代行をおこなえません。
借金の取り立て代行業者も債権者と同様、貸金業法に則って借金の取り立てをおこなっています。そのため、貸金業法で禁止された取り立て行為があれば、違法な取り立て代行業者である可能性が高いです。
まとめ
借金の取り立てと聞くと、大きな声で恫喝されたり、暴力を振るわれるといったイメージを持つ人も多いかと思いますが、正規の貸金業者から借りた場合にそのような取り立てを受けることはありません。
しかし、取り立てを無視し続けると、最終的には給料や財産を差し押さえられる恐れもあるため、一刻も早く滞納を解消し取り立てが止まるよう対処することが大切です。
また、闇金や個人から借金をしている場合は、脅迫や暴力を伴う取り立てや執拗な嫌がらせを受ける恐れもあります。
いずれにせよ、返済に行き詰まり取り立てを受ける状況なら、一度弁護士や司法書士へ相談して借金問題解決のアドバイスを受けるのがおすすめです。
当サイトでは、闇金対応と借金問題の解決どちらも扱っている弁護士・司法書士を紹介しているので、まずは気軽に無料相談を利用してみてください。
借金の取立てに関するよくある質問
借金を滞納すると、大きな声で恫喝されたり、暴力を振るわれるといった取り立てを受けるのですか?
借りたのが正規の貸金業者であれば、脅迫や暴力を伴う取り立てをおこなうことは基本的にありません。ただし、借りた相手が闇金などの違法業者だったり、個人だった場合はそのような取り立てを受ける恐れもあります。
正規の貸金業者からの借金を滞納した場合、どのような取り立てを受けるのですか?
一般的な取り立ての流れは以下のとおりです。
1.電話やメール、SMSによる督促を受ける
2.郵便物による督促を受ける
3.実家や勤務先にも督促がおこなわれる
4.債権回収会社に債権譲渡される
5.保証人・連帯保証人にも督促がおこなわれる
6.裁判所から支払督促が届く
7.給料や財産を差し押さえられる
借金の取り立てを止めるにはどうすればいいのですか?
借金の取り立てを止める方法には、主に以下のようなものがあります。
・金融機関に相談して返済計画の見直しをおこなう
・親や友人などにお金を借りて返済する
・債務整理をする
闇金などの違法業者や個人からの借金を滞納した場合、どのような取り立てを受けるのですか?
借りた相手が闇金などの違法業者や個人だった場合、以下のような取り立てを受ける恐れがあります。
1.21時から翌8時までの時間帯に取り立てをおこなう
2.債務者の勤務先など自宅以外の場所へ取り立てをおこなう
3.訪問に対して退去するよう意思表示されたのに退去しない
4.張り紙や立て看板などで借入状況や私生活に関する事実を周囲に知らせる
5.他者から借りるなどして返済資金を調達するよう要求する
6.家族など債務者本人以外に返済を指示する
7.債務整理開始後(受任通知受け取り後)の督促
8.執拗な連絡先強要
闇金などの違法業者や個人から取り立てについて相談できる専門機関などはありますか?
違法な取り立て行為を受けた場合に相談できる専門機関には、以下のようなものがあります。
・警察
・弁護士・司法書士
・日本貸金業協会
・弁護士会
・国民生活センター
・金融庁
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-