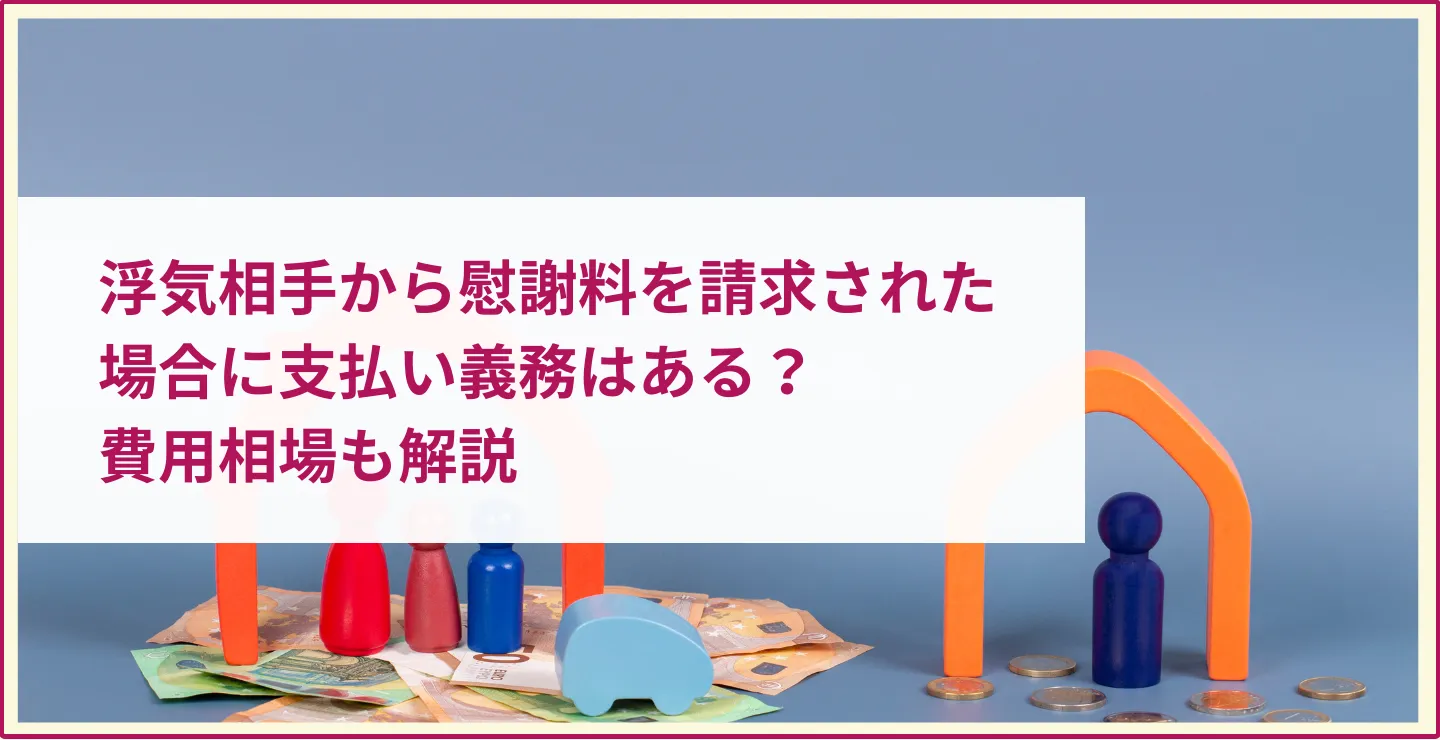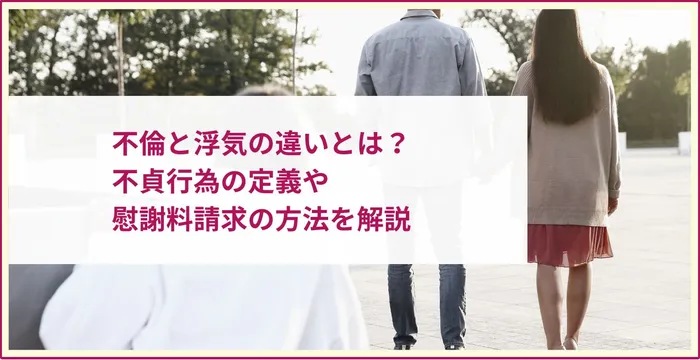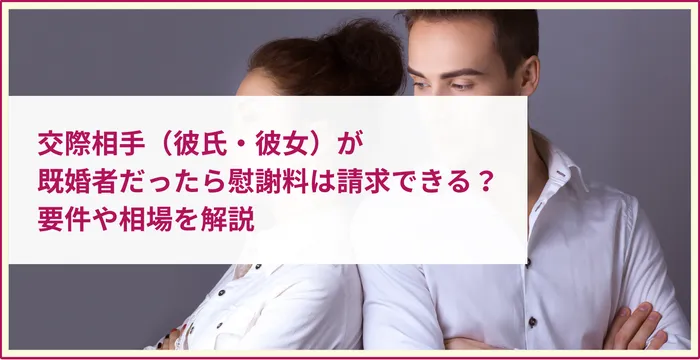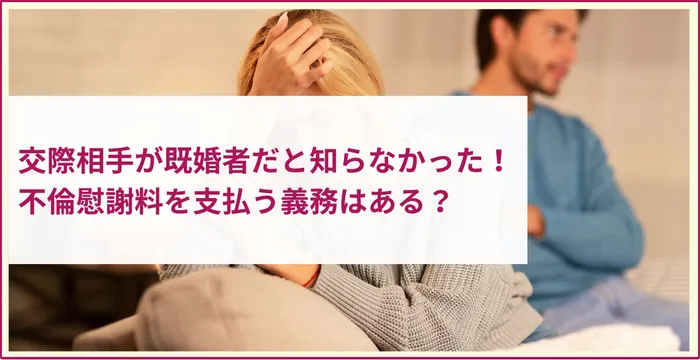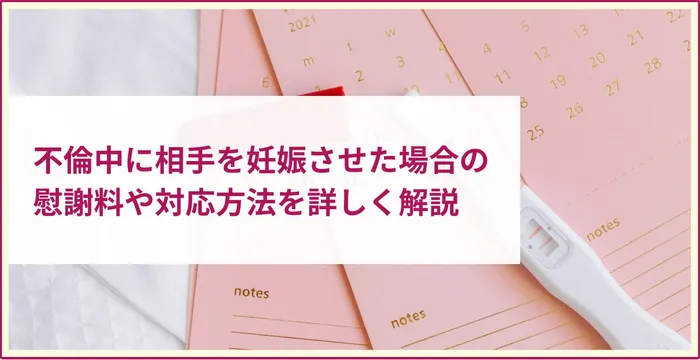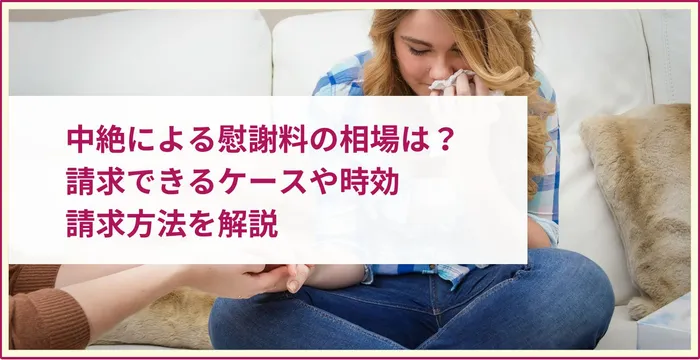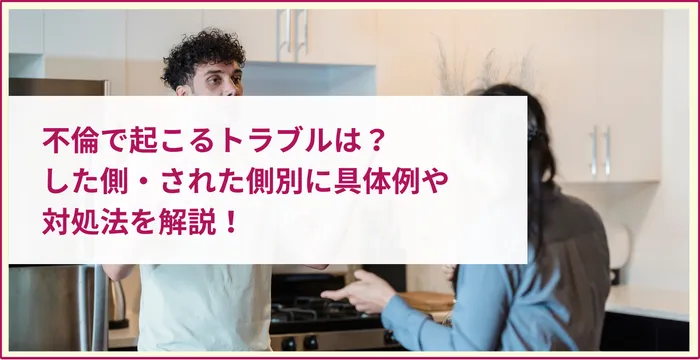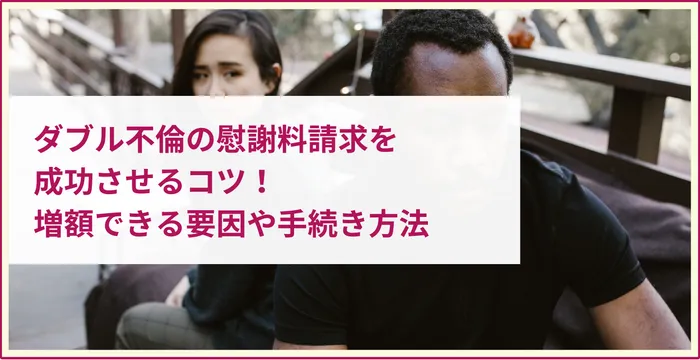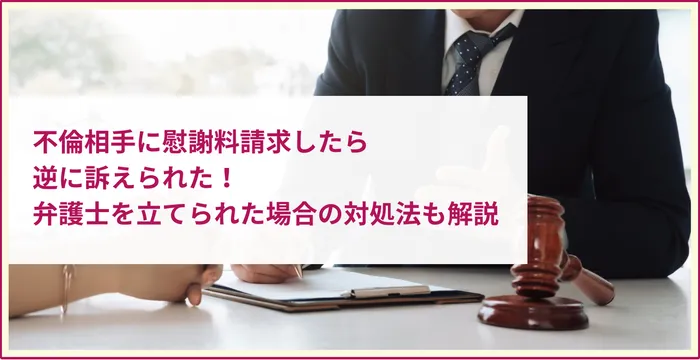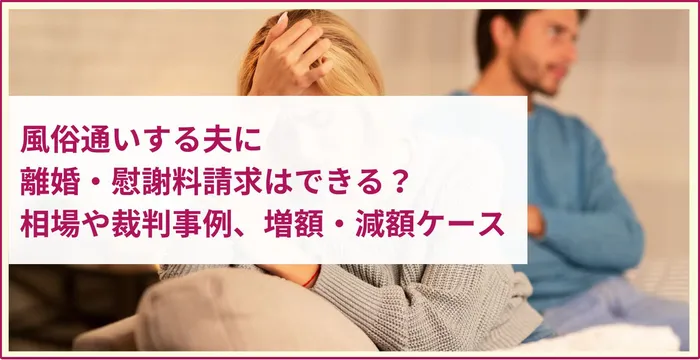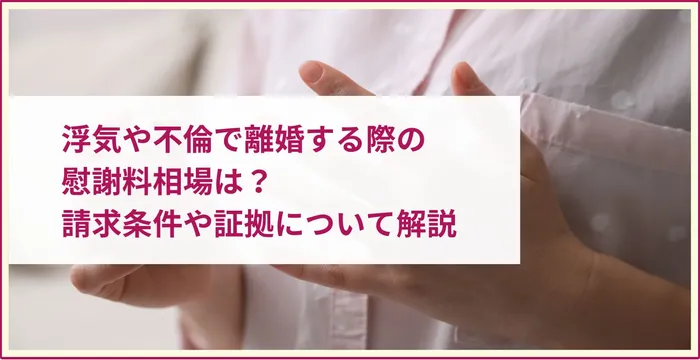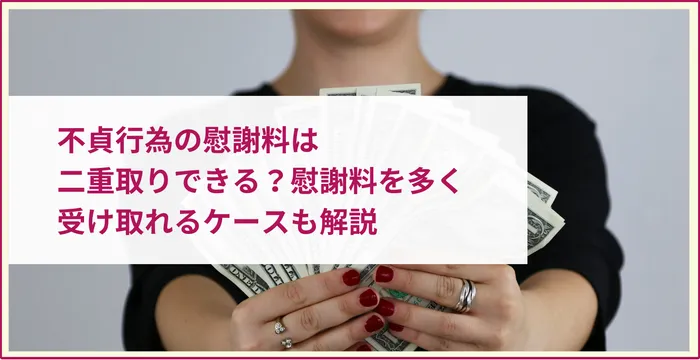浮気相手からの不倫についての慰謝料請求は原則として認められない
不倫に関するトラブルの中には、浮気相手から「時間を返せ」「約束が違う」として慰謝料を請求されるケースがあります。しかし、こうした慰謝料請求は原則として認められていません。
慰謝料とは、加害者の不法行為によって精神的苦痛を受けた被害者が、その損害に対して請求できるお金です。不倫における慰謝料請求もこの考えに基づいており、基本的には不貞行為によって傷つけられた「配偶者」が請求できるものであり、不倫関係にあった浮気相手が請求する立場にはありません。
浮気相手が「浮気をして無駄な時間を過ごした」「離婚すると嘘をつかれた」「別れ方がひどかった」などを理由に慰謝料を請求してきたとしても、それが不倫関係を前提としたものである以上、法律的には慰謝料の支払い義務は発生しません。
民法708条でも、自分の違法行為が原因で損害が発生した場合は、損害賠償請求ができないと定められています。
(不法原因給付)
第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
引用元 民法|e-Gov 法令検索
不貞行為は、浮気の被害者である妻(夫)の婚姻生活の平和を侵害する「不法行為」に該当します。そのため、浮気相手自らの行為(不貞行為)が原因で発生した損害に対しては、慰謝料請求ができないと考えられます。
なお、W不倫のように双方に配偶者がいる場合、それぞれの配偶者が慰謝料を請求する可能性があります。あくまで家族単位の請求ですが、やり取りの形によっては、浮気相手から慰謝料を請求されているように感じられるケースもあります。その場合、当事者同士で損害賠償請求権や求償権を放棄し合い、事実上慰謝料を相殺する形で解決するケースも見られます。
いずれにしても、不倫相手からの慰謝料請求は、通常は法的に認められないものであり、請求されたとしても安易に応じる必要はありません。冷静に法的根拠を確認し、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することが大切です。
不貞行為の定義については、下記の記事も参考にしてみてください。
浮気相手からの慰謝料請求が認められるケース
浮気相手からの慰謝料請求が認められるのは、以下のようなケースです。
- 既婚者であることを隠しており、結婚を匂わせていた
- 浮気相手の妊娠後、中絶を強要するなど不誠実な対応をとった
- 浮気相手に身体的・精神的暴力を振るっていた
- 浮気相手に無理やり関係を迫った
- 夫婦関係が破綻し、浮気相手と重婚的内縁関係にあった
以下の項目から、それぞれの詳しい状況を紹介します。
既婚者であることを隠しており、結婚を匂わせていた
浮気相手に対して既婚である事実を隠し、結婚をほのめかすなどして性的関係を継続していた場合、相手の性的自己決定の自由を侵害したとして「貞操権の侵害」に該当する可能性があります。
貞操権とは、自分の性的自由を決定する権利のことです。誰といつ、どのような性的関係を持つかはそれぞれの自由であり、ほかの人が不当に干渉することは禁止されています。したがって相手を騙して性的関係を続けていた場合、相手の貞操権を侵害していると判断される可能性があります。
貞操権の侵害に該当する可能性があるのは、具体的に以下のような行為です。
- 独身と伝えていた
- 結婚したいと伝えて体の関係をせまった
- 結婚する気がないにも関わらず婚約した
- 浮気の分別ができない、かつ結婚の判断もつけられない年齢の相手に手を出した
貞操権の侵害があるとみなされれば、慰謝料請求も認められる可能性があります。
貞操権侵害については、下記の記事も参考にしてみてください。
浮気相手の妊娠後、中絶を強要するなど不誠実な対応をとった
浮気相手を妊娠・中絶させた場合、慰謝料請求が認められる可能性があります。
ただし、浮気相手と妊娠についてしっかりと話し合い、合意のうえで中絶した場合などは慰謝料の請求ができません。妊娠・中絶を理由に浮気相手が慰謝料を請求できるのは、以下の2つのパターンです。
|
概要
|
具体的なケース
|
|
①妊娠・中絶の責任を持つ一人として配慮すべき義務を怠った
|
|
妊娠を告げたものの、相手が話し合いを避けて中絶が遅くなった
|
|
相手の不誠実な対応で、中絶のタイミングを逸してしまった など
|
|
②妊娠・中絶自体に、相手の権利を侵害する行為があった
|
浮気相手を脅して中絶を強要した
|
|
浮気相手に暴力を働き流産させた
|
|
相手の意思に反して避妊しなかった など
|
特に「②妊娠・中絶自体に、相手の権利を侵害する行為があった」に該当する場合、慰謝料の請求に応じるだけでなく、刑事的な責任を負う可能性もあります。不倫によって妊娠が発覚した場合や、中絶による慰謝料の相場などはこちらの記事もあわせてご覧ください。
浮気相手に身体的・精神的暴力を振るっていた
浮気相手との関係性において、暴力や暴言などの身体的・精神的な暴力を加えていた場合、それが不倫関係であっても重大な問題となります。相手が被った心身の被害に対しては、慰謝料請求が認められる可能性があり、不倫とは別の法的責任を問われることになります。
具体的には、下記のような罪に問われる可能性があります。
- 平手打ちや突き飛ばすなどの暴力を加える:暴行罪
- 怪我を負わせる:傷害罪
- 暴力によって不貞行為を継続させる:不同意性交罪、強制性交等罪、強制わいせつ罪など
なお、暴力が1回であっても、その内容や程度によっては暴行罪や傷害罪に該当する可能性があります。さらに、暴力が継続的に行われていた場合、暴力によって不倫関係を無理やり継続させたなどの場合には、その悪質性から刑事責任がより重く問われたり、DV防止法などの特別法の適用対象になることもあります。
浮気相手に無理やり関係を迫った
不倫関係の有無にかかわらず、浮気相手に対して同意のない性的関係を強要した場合は、性的暴行・準強制性交等罪などの刑事事件として扱われる可能性があります。また、精神的苦痛に対する慰謝料請求といった民事上の責任も生じるおそれがあります。
上司と部下など相手が立場上断りにくい状況にあったり、力関係を利用して関係を持ったりした場合も、性的同意に基づかない行為として認められれば、慰謝料請求や刑事告発の対象となる可能性があります。
夫婦関係が破綻し、浮気相手と重婚的内縁関係にあった
もとの夫婦関係が破綻しており、浮気相手と重婚的内縁関係が続いていた場合も、慰謝料請求が認められる可能性があります。
そもそも内縁とは、婚姻届を出していないものの、婚姻の意思を持って共同生活を行っている関係性をいいます。内縁に法律上の定義はありませんが、以下の項目に該当する場合は内縁関係があると認められる可能性が高いでしょう。
- 婚約している、結婚式を挙げたなどの事実がある
- 3年以上にわたって共同生活を営んでいる
- 家計を共にしているなど、共有財産がある
- 社会的に夫婦だと認知されている
- 子どもを認知している
- 住民票や社会保険など、公的手続きで内縁関係を表明している など
長期間にわたる内縁関係は、法律上婚姻に準じた一定の保護が認められています。
そのため、法律婚と同様に、不当に内縁関係を破棄した場合や、内縁関係にある相手以外との不倫があった場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。
ただし、内縁期間が短期間である場合や、破棄が正当な理由による場合には、法律上の保護が十分に及ばないことがあります。
内縁関係の成立や期間には明確な基準がなく、慰謝料請求の可否は個別の事情によって判断されるため、内縁の相手から慰謝料請求を受けた場合は、まず弁護士に相談することをおすすめします。
浮気相手に支払う慰謝料相場
浮気相手に対して慰謝料の支払い義務が生じたとしても、請求された金額が適切であるとは限りません。
慰謝料に関しては、裁判になった場合の相場はある程度決まっていますが、協議によって決める場合は金額に上限がありません。そのため、法外な金額を提示されるおそれもあります。
とはいえ、慰謝料の金額は双方の合意で決まるため、法外な金額を請求された場合は冷静に交渉すると良いでしょう。
慰謝料の金額はケースバイケースですが、おおよその金額は下記を参考にすると良いでしょう。
- 貞操権の侵害を犯した:50万~200万円
- 浮気相手が妊娠・中絶した:数十万~100万円
- 重婚的内縁関係だった:数十万〜300万円
- 暴力を振るわれた:50万~300万円
次の項目から、慰謝料相場の詳しい条件や判例を紹介します。
貞操権の侵害を犯した:50万~200万円
貞操権の侵害に該当する場合、慰謝料の相場は50万〜200万円ほどです。
先述したとおり、貞操権利の侵害に該当するのは、既婚者であることを黙って交際していた場合や、結婚をほのめかして性交渉をせまった場合などです。ただし、よほど浮気相手に非がなく、貞操権を侵害した側の違法性が高いケースでない限り、高額な慰謝料は認められないでしょう。
慰謝料が認められた事例としては、「既婚者であることを隠して未成年の女性と交際し、出産にいたった」「妻子がいることを隠し、避妊もせず浮気相手を妊娠・中絶させた」などのケースです。このような既婚者であることを隠していたうえに、相手が妊娠や中絶をした場合は慰謝料が高額になりやすいでしょう。交際期間や浮気相手の年齢など、そのほかの条件にによっても金額が異なります。
また反対に、以下のような条件に該当する場合は、そもそも貞操権利の侵害に該当せず慰謝料の請求が認められない可能性もあります。
- 双方とも成人しており、調べればすぐに既婚者だとわかる状況だった
- キスやハグのみなど、浮気相手と性交渉を行っていない
- 浮気相手に結婚する意思がなく、「結婚しよう」などと言われたこともない
- 浮気相手からの積極的なアプローチで交際に至った
貞操権侵害による慰謝料請求の判例
貞操権侵害による慰謝料請求の判例は下記のとおりです。
【慰謝料100万円】
既婚男性と独身女性が約2年間にわたり交際していたケースです。男性は自身が独身であると偽り、女性に対して結婚を持ちかけていました。さらには、妻から届いたメールを「妹からのもの」と偽るなどして、既婚の事実を巧妙に隠していました。
女性が別れを切り出した際、男性はそれを引き止めようとするなど、関係の継続を望んでいた様子も見られました。その後、男性は別居中だった妻との関係を修復し、妻が妊娠するに至ります。
一方、女性は最後まで男性が独身であると信じており、将来の結婚を前提に交際していました。両親や職場にも結婚の話をしていたことから、その信頼は深かったといえます。
裁判所は、こうした経緯を踏まえ、女性の貞操権を侵害したとして、慰謝料100万円の支払いを命じました。(東京地方裁判所 平成27年1月7日判決)
【慰謝料500万円】
既婚男性と独身女性が約12年間にわたって交際していた事案です。男性は自らが既婚者であることを一切明かさず、女性に対して将来の結婚を約束していました。女性は男性を独身と信じ、長年にわたって結婚への期待を抱き続けていました。
交際の中で、女性は男性との子を2度中絶し、3回目に妊娠した子どもを出産しました。男性はその出産を知った後、関係を解消しようとしましたが、女性が認知請求の裁判を起こしたことから、最終的に任意認知に応じました。
女性は20代から30代という人生の重要な時期を、男性との関係に費やしており、裁判所はこれを「貴重な時間を捧げた」と評価。男性の行為が重大な貞操権侵害にあたるとして、慰謝料500万円という高額な賠償額が認定されました。 (東京地方裁判所 平成19年8月29日判決)
貞操権侵害による慰謝料の金額は、主に男性側の行為にどれだけの違法性があったかによって判断されます。特に、以下のような要素が重視されます。
- 交際期間の長さ
- 女性が男性の既婚事実を知っていたかどうか
- 既婚者であることを隠すために男性が行った偽装や工作の有無
- 男性が結婚の意思を示していたか
- 女性が将来的な結婚をどれほど真剣に信じていたか
- 女性が妊娠・出産した回数と、それに対する男性の対応
- 結婚への期待が女性の家族や職場など、周囲に与えた影響の大きさ
これらの事情を総合的に考慮し、男性の行為が女性の貞操権を侵害するものと評価された場合には、慰謝料が認定されます。違法性が高いと認められるほど、慰謝料の金額も高額になる傾向があります。
浮気相手が妊娠・中絶した:数十万~100万円
浮気相手を妊娠させ、中絶もさせた場合、慰謝料相場は数十万円〜100万円ほどです。
妊娠・中絶は必ずしも片方のみに責任であるとは言い切れないため、多くの慰謝料を請求できないケースもあります。「浮気相手の妊娠後、中絶を強要するなど不誠実な対応をとった」でも紹介したように、浮気相手と事前にしっかりと話し合い、双方が納得したうえで中絶をしたのであれば慰謝料の請求は認められないでしょう。
しかし先述したように、既婚者であることを隠していたり、相手の合意なしに肉体関係をせまったりした場合は、慰謝料が高額になる可能性があります。
過去に慰謝料の請求が認められた事例としては、「求婚されていたにも関わらず、妊娠時に不当な対応をされ精神的な損害を負った」「既婚者であるとあえて伝えず交際を続け、妊娠・中絶にいたった」などが挙げられます。
中絶による慰謝料請求の判例
中絶による慰謝料請求の判例は下記のとおりです。
【慰謝料50万円】
原告の女性が妊娠した際、被告の男性は出産を拒否し、「産むなら一人で産んでほしい」と突き放すような態度をとり、話し合いにも応じませんでした。女性は中絶手術を選ばざるを得ず、精神的・身体的に大きな苦痛を受けることになりました。
両者は同棲中、避妊をせずに性行為を行っており、同棲を解消した後に妊娠が発覚しています。
裁判所は、被告が妊娠に対して無責任な態度を取り、女性に重大な決断を一方的に委ねたことが違法であると判断。女性の受けた損害に対して、被告に慰謝料50万円の支払いを命じました。加えて、弁護士費用として5万円の支払いも命じられています。(東京地方裁判所 平成24年5月16日判決)
【慰謝料160万円】
原告の女性は、被告の男性から求婚を受けたうえで、避妊せずに交際を続けた結果、妊娠しました。ところが、妊娠が判明すると、被告は「子どもを産んでも認知しない」などと冷たく突き放し、態度を急変させました。
裁判所は、妊娠の可能性を認識しながら責任を取るつもりがなかった点、そして妊娠後の誠実さを欠いた対応が女性に深刻な精神的苦痛を与えたと認定。父親としての責任を放棄した行為は重大であるとし、慰謝料160万円の支払いを命じました。(東京地方裁判所 平成27年7月31日判決)
中絶に関する慰謝料は、当事者の行動や妊娠後の対応など、さまざまな事情を総合して判断されます。慰謝料に影響を及ぼす具体的な要素は下記のとおりです。
|
妊娠の経緯と責任
|
・被告が避妊を怠った、または避妊なしの性交を強要した
・妊娠の可能性を認識していたか
|
|
妊娠後の対応
|
・妊娠後の話し合いの有無とその内容
・「産むなら一人で産め」などの無責任・冷酷な発言
|
|
被害者の受けた苦痛
|
・中絶による身体的・精神的ダメージの程度
・中絶を強いられた状況だったかどうか
|
|
結婚や将来の約束
|
・婚約または結婚を前提とする関係性だったか
|
|
出産や養育への責任逃れ
|
・出産・認知・養育などの責任を放棄したか
|
これらの要素が重なるほど、違法性が強く認められ、慰謝料の額も高くなる傾向があります。
重婚的内縁関係だった:数十万〜300万円
浮気相手と重婚的内縁関係にあった場合、慰謝料相場は数十万円〜300万円ほどです。
重婚的内縁関係で慰謝料の請求が認められるのは、もとの夫婦関係が破綻しており、内縁関係の一方的な解消をせまった場合です。浮気相手に支払う慰謝料相場としてはもっとも高く、なかには400万円ほどの支払いが認められた事例もあります。
重婚的内縁関係の相場が高い理由としては、もとの夫婦関係が破綻しているのであれば、法律の保護の対象となるためです。夫婦のどちらかが浮気をして慰謝料を請求されたパターンと同等に扱われるため、慰謝料の金額が高くなりやすいでしょう。
内縁の破棄による慰謝料請求の判例
内縁の破棄による慰謝料請求の判例は下記のとおりです。
【慰謝料300万円】
原告女性は、被告男性に妻子がいることを知りながらも、「妻とは別れて自分と結婚する」という言葉を信じて関係を持ち、その後、被告の子を出産しました。しかし、被告は突然一方的に原告との関係を断ち、婚約や事実婚に相当する内縁関係を破棄しました。
裁判所は、被告の行動が原告の人格的利益を侵害するものであり、社会通念上許されるものではないと判断。慰謝料300万円と弁護士費用30万円の支払いを命じました。
(京都地方裁判所 平成10年10月27日判決)
【慰謝料400万円】
原告女性は、既婚者である被告男性と交際し、被告の子を出産しました。被告は離婚調停を申し立てた後、原告と3年間にわたり事実上の同居生活を送っていましたが、突如宗教に傾倒し、原告と別居。さらに別の女性と結婚したため、原告は「婚約不履行」および「不法行為に基づく慰謝料」を請求しました。
裁判所は、法律上の婚姻関係が実質的に機能していない「形骸化」した状態にあったと判断し、原告と被告との関係は重婚的内縁関係にあたると認定。そのうえで、内縁関係を一方的に解消した被告の行為には「悪意の遺棄」が認められるとして、慰謝料400万円の支払いを命じました。(大阪高等裁判所 平成7年7月30日判決)
相手が婚姻中だった場合でも、婚姻関係が事実上破綻していた(=形骸化していた)と認められれば、内縁として法的保護の対象になります。
また、内縁破棄による慰謝料については、下記のような要素を総合的に考慮して、慰謝料の有無や金額が判断されます。
|
交際・同居の期間
|
内縁関係が長期間にわたっていた場合、精神的・経済的損害が大きいと判断されやすい。
|
|
婚姻に近い実態があったか
|
家族同然の生活を送っていた、周囲に夫婦と認識されていたなど、実質的な婚姻関係に近いほど慰謝料額が増加する傾向にある。
|
|
破棄の理由・経緯
|
一方的・突然の破棄や、他の異性との再婚などがあると、相手方の行為の違法性が高く評価されやすい。
|
|
被害者の精神的・経済的損失
|
婚約や将来の結婚を信じて仕事を辞めた、出産・育児を一人で背負ったなどの場合、損害が大きいとみなされる可能性がある。
|
|
妊娠・出産の有無
|
子どもをもうけていた、または中絶を強いられた場合には、特に大きな精神的苦痛が認められやすい。
|
暴力を振るわれた:50万~300万円
浮気相手との関係の中で身体的な暴力を受けた場合の慰謝料の相場は、50万円〜300万円程度です。暴力の内容や回数、後遺症の有無によって金額は変動します。
ただし、「不倫関係」であったという事情が加わることで、慰謝料額の判断にも影響が出ます。たとえば、浮気相手が既婚者であり、その配偶者から慰謝料請求を受けている場合、被害者側にも落ち度があるとして慰謝料が減額される可能性があります。
「被害者に落ち度があるから」と暴力が正当化されるわけではありませんが、暴力を受けた側であっても、関係の経緯や配偶者の有無などによっては、望んだ金額の慰謝料を得られない場合もあります。
不倫と交際中の暴力が絡んだ事案で慰謝料が減額された判例
不貞行為の被害者である妻から浮気相手に対し慰謝料請求があったものの、交際中の暴力が認められたことで、慰謝料が減額された判例です。
【慰謝料70万円】
婚姻期間4年5ヵ月、子ども2人を育てていた夫婦において、妻(原告)は、1年間にわたって夫と不倫関係を続けていた女性(被告)に対して400万円の慰謝料を請求しました。
しかし裁判では、被告女性が「離婚しないなら関係を終わらせたい」と交際中に伝えていたにもかかわらず、夫から暴力を振るわれていたと主張。裁判所はこの暴力の事実を一定程度認定し、不倫に対する加害性の軽減要因と判断して、慰謝料の減額を認めました。
その一方で、原告が子ども2人を引き取り、養育していることが情状として考慮され、最終的に被告に対して70万円の慰謝料支払いを命じました(東京地方裁判所 平成28年2月18日判決)
不倫関係において暴力があった場合、慰謝料請求の可否や金額にはさまざまな事情が考慮されます。主な判断要素は以下のとおりです。
|
増額要因
|
減額要因
|
・暴力の継続性や身体的被害の深刻さ
・うつ症状・生活への支障など、精神的被害の大きさ
・妊娠・中絶・出産などの身体的影響
・被害者が関係解消を望んでいたにもかかわらず暴力が続いた など
|
・既婚者と知りながら交際を継続したなど、被害者側にも一定の落ち度があったと場合
・暴力が一時的・偶発的なものであった場合
・暴力の事実が客観的に立証されにくい場合
|
不倫関係の中での暴力は、一般的なDVよりも判断が複雑になります。裁判所は、不貞行為の違法性と暴力の違法性を区別して判断するため、個別の事情が強く影響します。
浮気相手から慰謝料請求をされた場合の対処法
浮気相手から慰謝料請求された場合は、下記のような対処をしましょう。
- 浮気相手と話し合って状況を確認する
- 男女トラブルに強い弁護士に相談する
何に対する慰謝料請求なのかをきちんと把握し、必要に応じて弁護士に相談することが重要です。それぞれの項目について詳しく解説していきます。
浮気相手と話し合って状況を確認する
浮気相手から慰謝料を請求されたら、まずは浮気相手と話し合いの場を設け「どのような名目で慰謝料を請求しているのか」「どのような事実があったのか」などを確認することが大切です。
浮気相手が「離婚すると約束した」「不倫で多くの時間を無駄にしてしまった」といった理由のみで慰謝料を請求しているのであれば、支払い義務が発生する可能性は低いでしょう。
しかし、以下のような証拠をもとに慰謝料の請求を行っている場合は、支払い義務が発生する可能性があります。
- 独身であると嘘を付き、性的関係を結んだことがわかるやり取りや音声など
- 浮気相手に暴力を働き、中絶や妊娠をさせたとわかる音声や動画、記録など
- 内縁関係を不当に破棄したことがわかる音声や動画、記録など
もし慰謝料の支払い義務が生じないような名目だったとしても、相手の請求を無視したり失礼な対応を取ったりすると、さらなるトラブルにつながりかねません。まずは相手の主張をしっかりと聞き、話し合いでの解決を目指すことが大切です。話し合いで合意が得られた場合は、後に紛争が起きないように内容を示談書にまとめておきましょう。
ただし、相手の怒りを抑えるために「全額支払う」「慰謝料は必ず払う」などと安易に伝えるのは避けましょう。やり取りを録音されており、合意書や念書にサインを求められて撤回できなくなる可能性も少なくありません。
男女トラブルに強い弁護士に相談する
下記のような場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
- 請求内容が法的に認められる可能性がある場合
- 浮気相手が家族に危害を加えるなどのトラブルに発展しそうな場合
- 浮気相手が感情的・攻撃的な様子を見せている場合
弁護士であれば、請求が妥当かどうかを判断し、浮気相手との交渉も代理で行ってくれます。たとえ支払いが避けられない場合でも、状況によっては慰謝料の減額を目指すことができます。合意に至った際は、後のトラブルを防ぐために示談書の作成も依頼できます。
また、相手が脅迫やストーキングなどに及んでいる場合は、刑事告訴などの対応についても適切なアドバイスを受けられます。
法的な知識がないまま対応してしまうと、不利な状況に陥るリスクがあります。男女トラブルに詳しい弁護士であれば、実績を活かした適切な対応が期待できるでしょう。
不倫で起こるトラブルについては、下記の記事も参考にしてみてください。
浮気相手から慰謝料請求された際に弁護士に依頼するメリット
浮気相手から慰謝料を請求されたら、まずは弁護士に相談し、今後どのように対応するべきかアドバイスをもらうとよいでしょう。弁護士に相談するメリットは、以下のとおりです。
- 適正な慰謝料金額での交渉が可能
- 家族や周囲に浮気がバレるのを防げる
- 早期解決を目指せる
- 嫌がらせをされても適切に対応できる
- 示談書等の書類作成を頼める
次の項目から、それぞれのポイントを紹介していきます。
適正な慰謝料金額での交渉が可能
慰謝料は交際の状況や相手に与えた精神的な苦痛など、さまざまな要因によって金額が決定します。おおまかな相場は決まっているものの、明確な基準はないため専門知識のない人が適正な金額を見極めるのは難しいでしょう。
不倫問題に精通した弁護士は、過去の裁判例や経験などから適切な慰謝料の金額を熟知しています。浮気相手から請求された慰謝料が妥当なものかを判断し、必要に応じて減額交渉をすることも可能です。「最初の請求段階では、あえて相場よりも高い金額を請求する」というケースも多くあるため、すぐに条件を鵜呑みにせず、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
家族や周囲に浮気がバレるのを防げる
浮気相手から慰謝料を請求された場合、自分で対応しようとすると感情的なやり取りがエスカレートし、相手が家族や勤務先などに事実を漏らしてしまうリスクがあります。
特に、「慰謝料を支払わなければバラす」といった形で脅された場合、冷静な対応ができず、不本意な形で話が広まってしまうおそれもあります。
弁護士に依頼すれば、相手とのやり取りをすべて代理で行ってもらえるため、直接連絡を取る必要がありません。さらに、守秘義務のある第三者を間に挟むことで、感情的な対立を避け、相手が軽率に情報を漏らすリスクを減らすことができます。
交渉の内容も法律に基づいて整理されるため、落ち着いて問題を解決することができ、家族や職場など、周囲に浮気の事実が知られるリスクを最小限に抑えることが可能です。
早期解決を目指せる
慰謝料の請求を受けたとき、弁護士を通さずに当事者のみで解決を目指すこともできます。しかし、話し合いが難航したり言った・言わないのトラブルに発展したりと、解決までに多くの時間がかかるケースも少なくありません。
弁護士はしっかりと状況を把握したうえで、双方にとって最善の解決策を提案できます。さまざまなパターンにおける交渉方法を把握しているため、どのよう状況であっても早期解決を実現しやすいでしょう。解決までの時間が長引くと、慰謝料請求された事実が家族や会社などにバレてしまうリスクもあるため、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
嫌がらせをされても適切に対応できる
慰謝料請求によって浮気相手との関係性が悪化し、嫌がらせを受けたり職場や自宅付近に付きまとわれたりするケースもあります。最初は些細な嫌がらせであっても、慰謝料の請求に応じるかどうかを決めかねている間にエスカレートし、取り返しのつかない事態になってしまう可能性もゼロではないでしょう。「浮気相手がこちらに対して敵意を持っている」「攻撃的な態度を取ってくる」と感じる場合は、すみやかに弁護士に相談することが大切です。
弁護士に相談すると、嫌がらせをされたらすぐに対応してもらえるため、精神的な負担を減らすことができます。また罪に該当するような重大な嫌がらせを受けたときや、身の危険を感じたときなどは迅速に警察へ相談できるメリットもあります。
示談書等の書類作成を頼める
当事者同士で話し合いを行い、慰謝料の金額や支払い条件などについて合意が得られたときは示談書を作成します。
示談書とは、和解契約の内容を証明する法的効力を持った書類のことです。決まった様式はなく、自分で作成することもできますが、法的に有効な形式・内容とするには専門知識が必要となります。自分で作成したものの「表現が曖昧で第三者が内容を正しく理解できない」「情報が不十分でさまざまな解釈ができてしまう」など、トラブルに発展するケースも少なくありません。
弁護士であれば、それぞれのケースに応じた的確な示談書をすぐに作成できます。示談書の内容によって後で後悔しないように、書類作成は弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。
浮気相手からの慰謝料請求に対応する弁護士費用
浮気相手から慰謝料を請求された際に弁護士へ依頼する場合、費用の目安は以下のとおりです。
- 相談料:5,000円/30分
- 着手金:15万〜30万円程度
- 報酬金:減額できた金額の10〜20%
- 実費:交通費や書類取得費用など
- 日当:1〜2万円/日(出廷などが必要な場合)
たとえば、200万円の慰謝料請求に対して、弁護士の交渉により50万円にまで減額できた場合、差額150万円が減額分となります。報酬金が減額分の15%とすると、報酬金は「150万円 × 15% = 約22.5万円」です。着手金が20万円だった場合、弁護士費用合計は約42.5万円(+実費)となります。
相手から請求された200万円を50万円まで下げられた上で、弁護士費用が約40万〜45万円で済むのであれば、実質的な負担は大きく軽減されたといえるでしょう。
また、慰謝料は原則として一括払いを求められることが多いですが、金額が大きい場合には分割払いの交渉も可能です。ただし、当事者間で話し合うと「完済まで長く関係が続くのを避けたい」といった理由から交渉がこじれることもあります。
弁護士を通じて交渉すれば、分割払いだけでなく、支払い期間の延長や支払総額の再調整が認められるケースもあります。費用面に不安がある場合でも、まずは一度相談してみることをおすすめします。
まとめ
そもそも慰謝料とは、加害者の不法行為によって精神的な苦痛を受けた場合、損害賠償として被害者に支払われるお金のことです。多くの場合、浮気相手は不貞行為を行った「加害者」に該当するため、慰謝料を請求される側であることが一般的です。
しかし、自分が浮気相手に何らかの不法行為を行っていた場合、反対に浮気相手から慰謝料を請求される可能性があります。慰謝料請求が認められるのは、以下のようなケースです。
- 既婚者であることを隠しており、結婚を匂わせていた
- 浮気相手の妊娠後、中絶を強要するなど不誠実な対応をとった
- 浮気相手に身体的・精神的暴力を振るっていた
- 浮気相手に無理やり関係を迫った
- 夫婦関係が破綻し、浮気相手と重婚的内縁関係にあった
慰謝料の相場は、交際の状況や違法性の程度などによって異なり、数十万〜300万円ほどと幅があります。請求された慰謝料が適切な金額であるかを判断するには、過去の裁判や法律など、専門的な知識が必要となるでしょう。
浮気相手から慰謝料を請求されたときは、すぐに「全額支払う」などと言うのは避け、まずは弁護士に相談することをおすすめします。