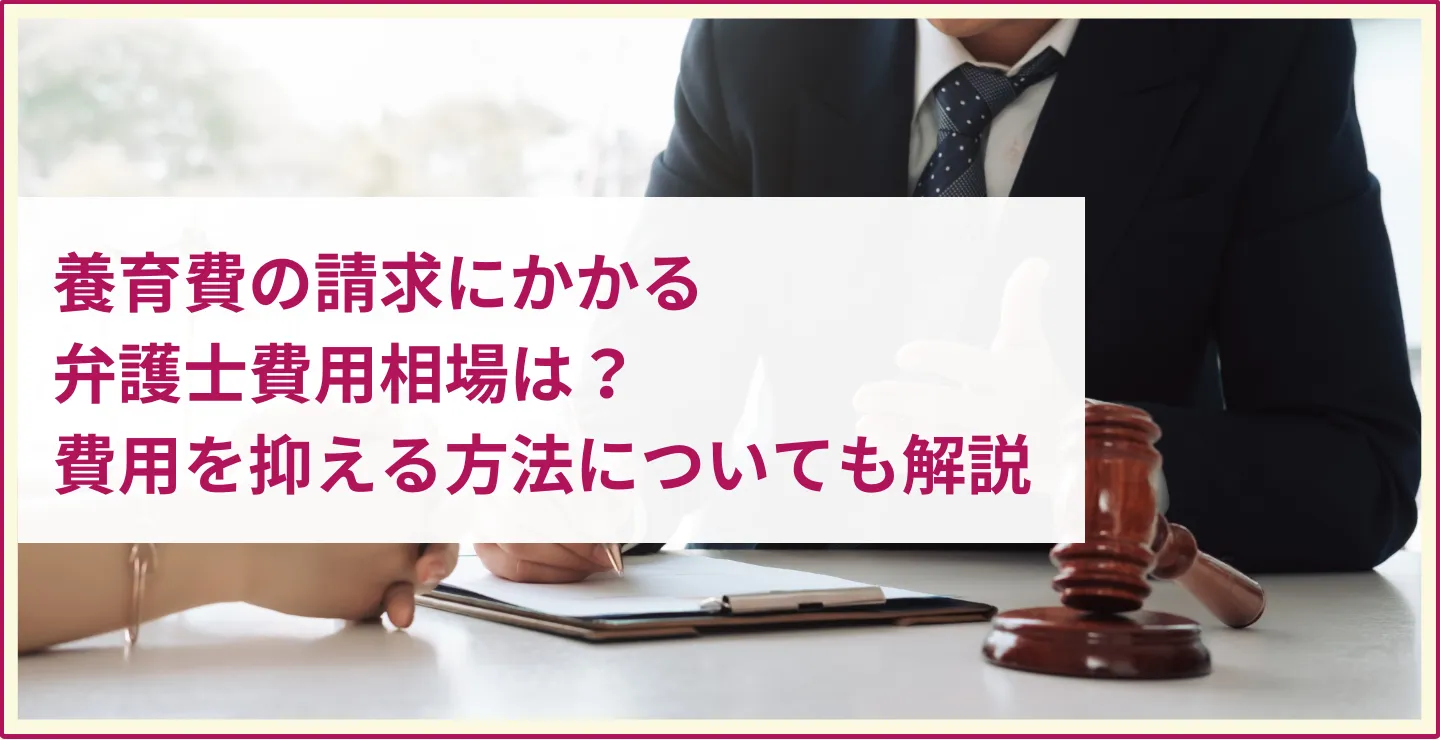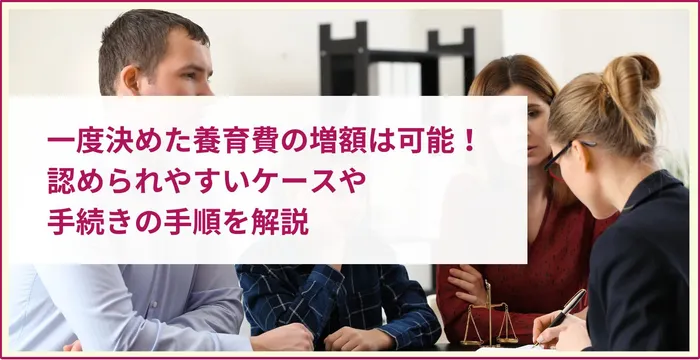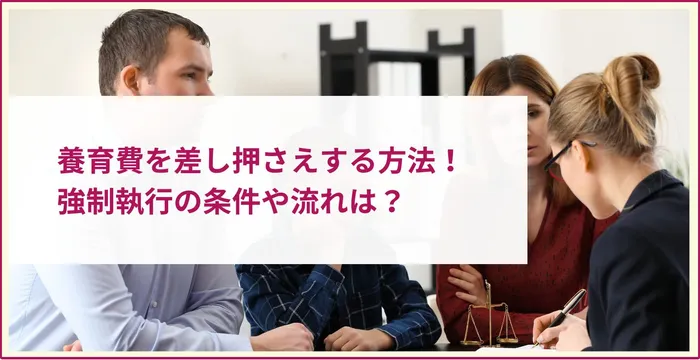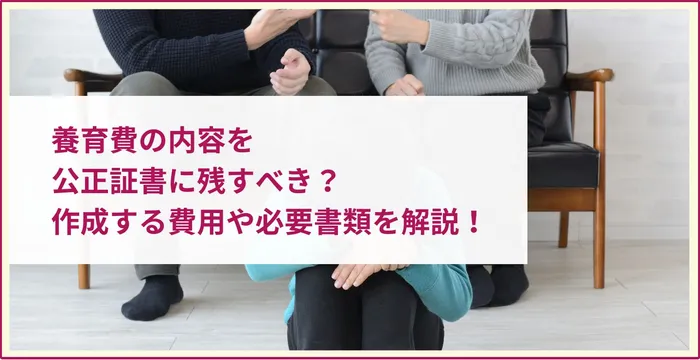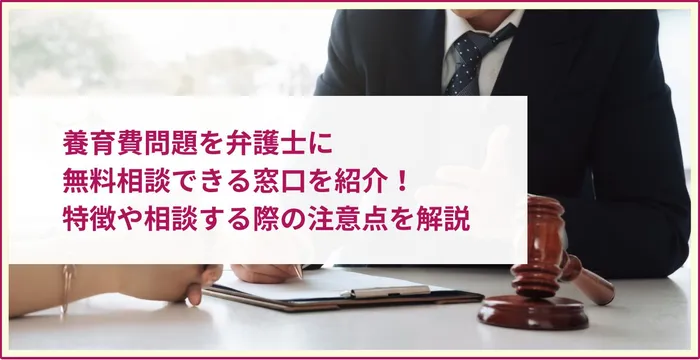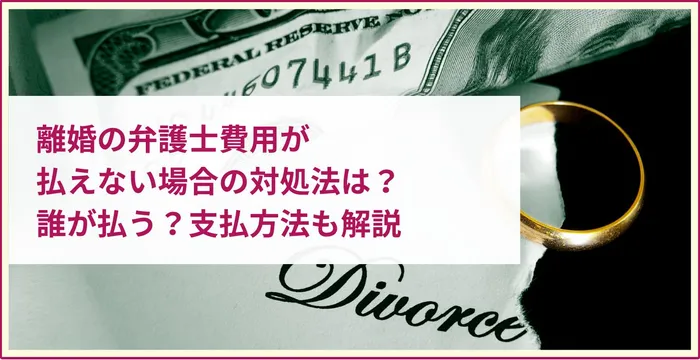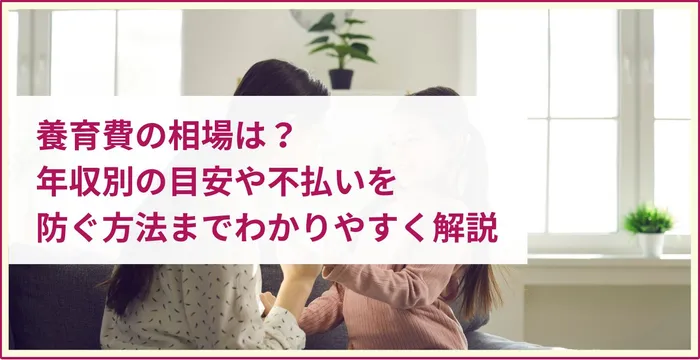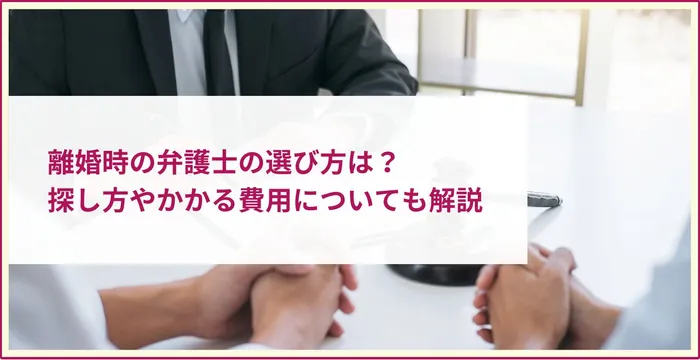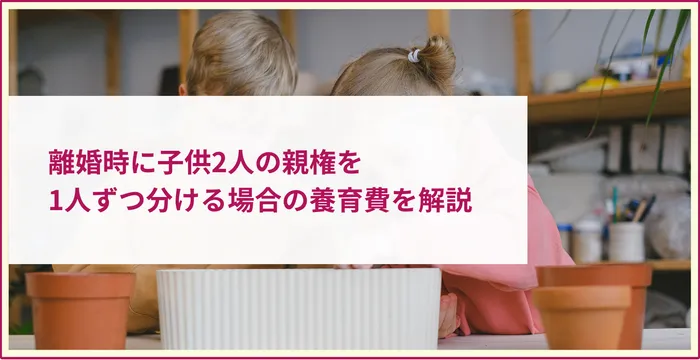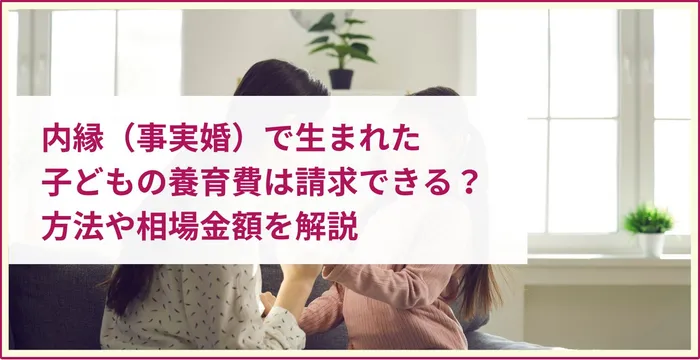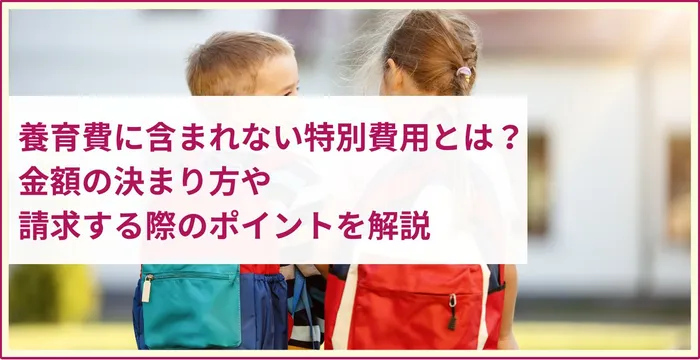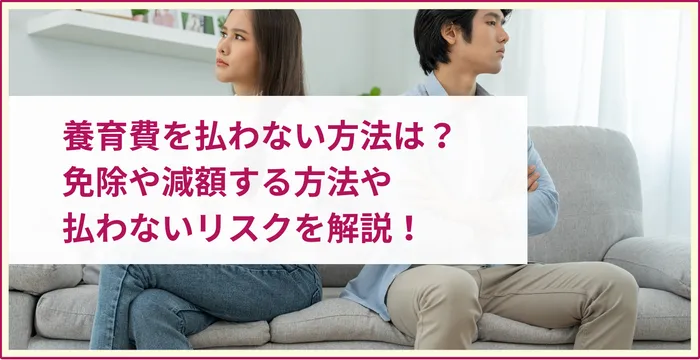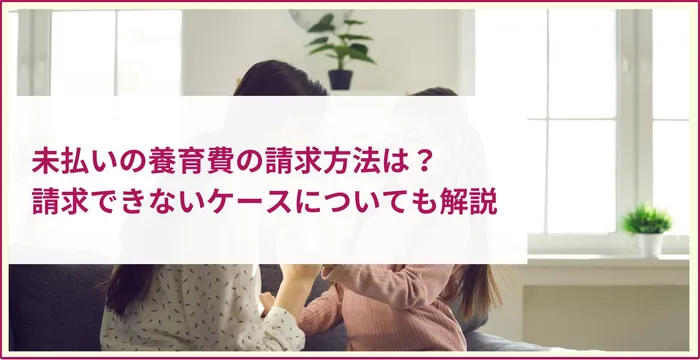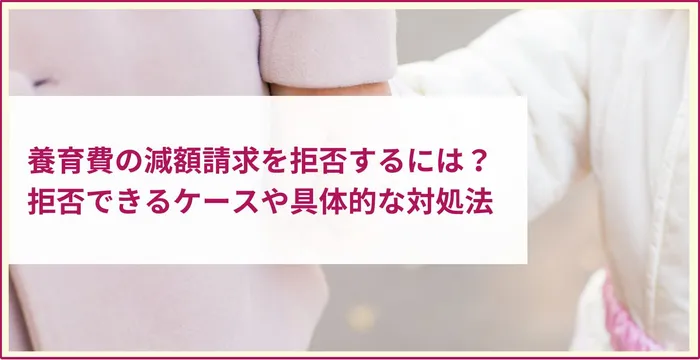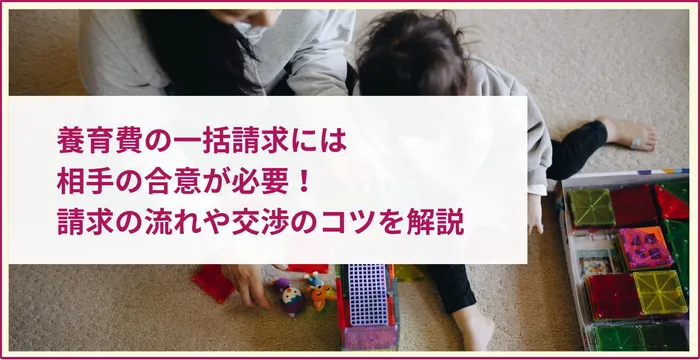養育費に関する弁護士費用の内訳
養育費に関して弁護士のサポートを得ようとした場合、かかる弁護士費用の内訳と相場は以下のとおりです。
養育費に関する弁護士費用の内訳
| 内訳 |
相場 |
| 相談料 |
初回は30~60分まで無料
超過分や2回目以降は30分につき5,000~10,000円 |
| 着手金 |
10~60万円 |
| 報酬金 |
基本10~30万円と得た経済的利益の10~20% |
| 日当・実費 |
事案によって異なる |
それぞれどのような費用で、相場はどのくらいなのかを詳しく解説します。内訳を把握することで、着手金と報酬金の合計額が同額の場合は、着手金の低いほうを選ぶべきであることなどがわかるはずです。
相談料|依頼を相談する際に支払う
弁護士費用のうち、相談料とは、弁護士が相談に応じるサービスの対価です。法律相談では、以下のような疑問や悩みを弁護士に相談できます。
- 養育費を請求したいが、どのように請求すればよいか
- 相手と直接話し合うことが難しいが、養育費は請求できるか
- 養育費を請求したいが、いくら請求できるか
- 結婚していないが、父に対して養育費を請求できるか
- 養育費の請求を受けたが、金額は適切か
- 養育費は子どもが何歳まで請求できるのか
- 養育費を請求したが、支払わないと言われてしまった
- 一度決まった養育費を増額したいが、できるか
- 一度決まった養育費を減額したが、できるか
- 養育費が支払われないが、どうしたらよいか
もちろん、弁護士に相談できる疑問や悩みは上記のものに限られません。弁護士への相談は、単に疑問や悩みを解決できるだけでなく、対応してくれた弁護士に依頼するかどうかの検討材料にもなります。
相談料の相場は、30分ごとに5,000~10,000円程度です。ただし、初回相談は30分や60分まで無料としている弁護士も少なくありません。
初回相談が無料なら、時間の制約はあるものの費用を気にすることなく弁護士への相談が可能です。
着手金|実際に依頼する際に支払う
弁護士費用のうち、着手金とは、弁護士に対応を依頼するためにかかる費用です。
弁護士は、養育費について対応を依頼されると、相手方(子どもの父または母)との交渉や調停、審判、訴訟のために状況を整理し、書面を作成するなどの対応をとらなければなりません。
着手金は、上記のような対応について弁護士が費やすことになる時間や労力への対価ともいえます。また、依頼者側からすると、着手金は弁護士に依頼するときにかかる初期費用です。
しかし、弁護士が対応しても、依頼者が望む結果になるとは限りません。仮に養育費を実際に受け取れなかったり、途中で弁護士を解任したりしても、着手金は返金されない点に注意してください。
養育費に関して弁護士に対応を依頼する場合の着手金の相場は、解決の段階に応じて以下のとおりです。
養育費に関する着手金の相場
| 解決の段階 |
着手金の相場 |
| 示談交渉 |
10~50万円 |
| 調停・審判 |
20~50万円 |
| 訴訟 |
20~60万円 |
上記のとおり、示談では比較的低額に収まる可能性があるものの、調停や審判、訴訟などに移行すると高くなる可能性があります。
示談から調停に移行すると10万円加算、調停が不成立で訴訟に移行するとさらに10万円加算となる場合もあります。
示談交渉から依頼しても、訴訟から依頼しても弁護士費用は同じといったケースも少なくありません。
訴訟に至る可能性を考慮すると、できるだけ早い段階で弁護士に対応を依頼しておいたほうが、よりご自身の負担を抑えながら適正な解決を見込めるでしょう。
報酬金| 依頼が解決した際に支払う
弁護士費用のうち報酬金とは、依頼者が受けた利益に応じて支払う費用です。
具体的には、養育費の内容が示談や調停、審判、訴訟で決まった場合に、養育費の有無や金額に応じて報酬金を支払います。
弁護士によって報酬金の算定方法は異なるものの、報酬金の相場は、養育費の分担内容が決まった際の基本報酬である10~30万円に加えて、得た経済的利益の10~20%です。
具体的な算定方法のイメージを以下の表に示します。
養育費に関する報酬金の算定イメージ
| 解決段階 |
報酬金の算定 |
| 示談交渉 |
基本報酬:10万円
経済的利益に応じた金額:獲得した(減額できた)5年分の養育費の16% |
| 調停・審判 |
基本報酬:20万円
経済的利益に応じた金額:獲得した(減額できた)5年分の養育費の16% |
| 訴訟 |
基本報酬:30万円
経済的利益に応じた金額:獲得した(減額できた)5年分の養育費の16% |
仮に養育費を請求するため弁護士に依頼し、示談で月額5万円の養育費の支払いを受けることとなった場合には、基本報酬10万円に経済的利益に応じた金額として5年分の養育費(300万円)の16%である48万円が加算された58万円が報酬金となります。
もし示談で養育費の支払いを受けられず、調停・審判や訴訟に移行せず弁護士の対応が終了した場合、報酬金は基本報酬の10万円のみです。
繰り返しになりますが、上記は報酬金の算定方法のイメージであり、実際には弁護士によって異なります。報酬金の算定方法は、必ず契約する前に弁護士から十分な説明を受けてください。
日当・実費|弁護士が活動する際に必要なお金
着手金や報酬金は知っていても、日当と実費がどのようなものかを把握している方はそれほど多くありません。
日当とは、弁護士の時間を拘束した時に発生する費用です。例えば、調停や訴訟で弁護士が裁判所に出頭するときは弁護士の時間を拘束するため、日当が発生することがあります。
日当の具体的な金額の計算方法は弁護士によって異なりますが、例えば往復2時間を超え4時間の範囲であれば3~5万円、往復4時間を超える場合は5~10万円程度が目安(旧弁護士報酬基準)です。
日当の算定例
| 拘束時間 |
日当の相場(目安) |
| 往復2時間超え4時間 |
3~5万円 |
| 往復4時間超え |
5~10万円 |
実費とは、弁護士が養育費に関して対応を進める際に実際にかかる費用をいいます。例えば、以下の費用が実費です。
- 調停・審判や訴訟を申し立てるときの収入印紙代(申立ての手数料、記録謄写の手数料)
- 調停・審判や訴訟を申し立てるときの郵便切手代(内容証明郵便などを含む)
- 打ち合わせや裁判所など、事務所以外に移動が必要な場合の交通費
- 裁判所に提出する戸籍全部事項証明書や住民票などの交付手数料
日当は裁判所と弁護士事務所との距離や手続きの所要時間、実費は養育費の金額や子どもの人数、裁判所などによって異なるため、相場を示すのは困難です。支払うタイミングも弁護士によって異なります。
日当・実費について気になる場合は、契約前に弁護士に確認してください。
ちなみに、実費は弁護士に依頼せずご自身で同様の対応をする場合にもかかる費用であり、厳密には弁護士費用とはいえません。ただし、対応を弁護士に依頼する以上は、弁護士に実費を支払う(預ける)必要があります。
離婚と養育費の交渉を一緒に依頼した場合の弁護士費用
離婚と養育費の交渉をあわせて弁護士に依頼した場合の弁護士費用の相場は、離婚が決まる段階に応じて変動します。
弁護士費用の相場
(離婚と養育費)
| 離婚が決まる段階 |
弁護士費用 |
| 協議離婚 |
約80万円~ |
| 調停離婚 |
約100万円~ |
| 裁判離婚 |
約150万円 |
ただし、離婚と養育費をあわせて依頼しても一律に離婚問題として取り扱い、弁護士費用の計算方法が変わらない弁護士も少なくありません。
なお、養育費は父母である夫婦の離婚だけでなく、未婚の子についても問題になることがあります。詳しくは未婚のまま養育費の交渉を依頼した場合で解説しているので、あわせて参考にしてください。
協議離婚 │ 約80万円〜
裁判所の手続きである調停や訴訟に至らず、弁護士を通じて夫婦の離婚が決まった場合、離婚の形態は協議離婚です。弁護士に離婚と養育費をあわせて依頼し、協議離婚した場合の弁護士費用の相場を以下の表にまとめました。
|
|
示談
|
調停
|
訴訟・審判
|
|
着手金
|
10~20万円
|
20~30万円
|
30~40万円
|
|
基本報酬金
|
30万円
|
30万円
|
30万円
|
|
養育費分の報酬金
|
獲得(減額)した5年分の養育費の15%
|
仮に獲得した養育費が月額2万円とすると、弁護士費用は基本着手金30万円、基本報酬金30万円、養育費分の報酬金19.2万円(月額2万円×12ヶ月×5年×16%)の合計額である79.2万円です。
ただし、養育費分の着手金があったり、報酬金を計算する際の割合が10%であったりなど、算定方法は弁護士によって異なります。
消費税や実費も考慮すると、離婚と養育費をあわせた弁護士費用として、協議離婚では80万円以上を想定するとよいでしょう。
離婚調停 │ 約100万円〜
夫婦だけでは離婚や養育費について話し合いがまとまらない場合、離婚するかどうかや養育費の内容を決めるためには、原則として家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。
離婚調停とは、離婚に関する問題について、2人の調停委員を通じて夫婦間で話し合う制度です。離婚するかどうかや養育費のほか、親権や財産分与、年金分割など離婚に関連する問題について話し合いができます。
調停委員を通じて夫婦間で話し合った結果、離婚が成立した場合は調停離婚です。弁護士に離婚と養育費をあわせて依頼し、調停離婚した場合の弁護士費用の相場を以下の表にまとめました。
離婚と養育費をあわせた弁護士費用の相場
(調停離婚)
| 内訳 |
相場 |
| 基本着手金 |
45万円 |
| 基本報酬金 |
30万円 |
| 養育費分の報酬金 |
獲得(減額)した5年分の養育費の16% |
仮に獲得した養育費が月額2万円とすると、弁護士費用は基本着手金45万円、基本報酬金30万円、養育費分の報酬金19.2万円(月額2万円×12ヶ月×5年×16%)の合計額である94.2万円です。
ただし、調停期日の出頭について弁護士の日当が発生する場合もある点には注意してください。
消費税や実費・日当も考慮すると、離婚と養育費をあわせた弁護士費用として、調停離婚では100万円以上を想定するとよいでしょう。
離婚裁判 │ 約150万円
調停でも夫婦間で離婚するかどうかや養育費の内容について話し合いがまとまらない場合、最終的には離婚の裁判(離婚訴訟)で決着を図ります。
離婚訴訟は、法律で定められた離婚原因の有無について夫婦双方が主張立証し、裁判官が離婚するかどうかを判断する手続きです。離婚訴訟では、裁判官に養育費の分担内容を定めてもらうこともできます。
弁護士に離婚と養育費をあわせて依頼し、離婚訴訟に至った場合の弁護士費用の相場は以下の表のとおりです。
離婚と養育費をあわせた弁護士費用の相場
(離婚裁判)
| 内訳 |
相場 |
| 基本着手金 |
75万円 |
| 基本報酬金 |
30万円 |
| 養育費分の報酬金 |
獲得(減額)した5年分の養育費の16% |
仮に獲得した養育費が月額2万円とすると、弁護士費用は基本着手金75万円、基本報酬金30万円、養育費分の報酬金19.2万円(月額2万円×12ヶ月×5年×16%)の合計額である124.2万円です。
訴訟に至った場合も、調停と同様に弁護士が裁判所に出頭し、日当が発生する場合もある点に注意してください。また、調停よりも訴訟は実費が高くなる可能性があります。
消費税や実費・日当も考慮すると、離婚と養育費をあわせた弁護士費用として、裁判離婚では150万円程度を想定するとよいでしょう。
養育費の交渉のみを依頼した場合 │ 40〜150万円
夫婦間で離婚することは決まったが、養育費について話し合いがまとまらないケースもあります。このようなケースでは、弁護士に養育費の交渉のみを依頼します。
弁護士に養育費の交渉のみを依頼した場合の弁護士費用相場は、以下の表のとおりです。
弁護士費用の相場
(養育費のみ依頼)
|
示談 |
調停 |
訴訟・審判 |
| 着手金 |
10~20万円 |
20~30万円 |
30~40万円 |
| 基本報酬金 |
30万円 |
30万円 |
30万円 |
| 養育費分の報酬金 |
獲得(減額)した5年分の養育費の15% |
仮に月額2万円の養育費を受け取ることとなった場合、弁護士費用は、示談解決で58~68万円程度、調停解決で68~78万円程度、訴訟・審判解決で78~88万円程度となるでしょう。
もちろん、実際には養育費の金額や具体的な算定基準によって変動するため、あくまでも参考としてください。
未払いの養育費回収を依頼した場合 │ 養育費回収額の30%
示談(協議・交渉)や調停、審判、訴訟などで養育費の金額が決まっていても、実際には養育費が支払われないことも少なくありません。このような場合には、以下に挙げる債務名義と呼ばれる書面があれば、裁判所を通じて強制執行(差し押さえ)をすることにより、相手の財産から強制的に養育費を回収できます。
- 強制執行認諾条項付公正証書の正本
- 調停調書の正本
- 和解調書の正本
- 審判の正本
- 判決の正本
弁護士に養育費の回収を依頼した場合の弁護士費用の相場は、報酬金として、回収額の30%程度です。ただし、30%が相場といっても、以下のとおり具体的な算定方法は弁護士によって異なります。
- 4年分の養育費の30%を一括で支払う
- 毎月の養育費の30%を5年間分割で支払う
- 毎月の養育費の30%を支払いが終わるまで分割で支払う
仮に回収できた養育費が月額5万円でその30%を5年間分割して支払うケースでは、月額15,000円の弁護士費用を5年間支払うといったイメージです。合計額は90万円となります。
養育費回収は、債務名義があれば、着手金無料で依頼できる弁護士も少なくありません。この場合、もし相手に支払いができるほどの財産がなかったなど回収に失敗しても、実費を除いて費用の負担はありません。
一方、口約束しかしておらず、債務名義と呼ばれるものがなければ着手金が必要になるケースもある点は注意してください。また、強制執行の手続きを進めるうえで相手の所在や財産の調査が必要な場合は、別途費用の請求がある可能性もあります。
なお、債務名義があっても5万円程度の着手金が必要で報酬金は回収金額の16%といったケースもあるなど、弁護士によって算定方法は異なります。養育費の回収を弁護士に依頼する際は、契約前に、費用について十分な説明を受けてください。
養育費の増額や減額を依頼した場合 │ 着手金20万円と変更額の2年分の10%
一度養育費の金額を決めても、その後に父母が同意して増額や減額をすることができます。しかし、調停を経ても父母の意見が合わないときに増額や減額を実現するには、養育費の変更が必要な程度に事情の変更があったと審判で認められなければなりません。
養育費の増額や減額が認められる可能性がある事情の変更(ケース)は、以下のとおりです。ただし、最終的には裁判所が判断するため、以下の事情変更があっても変更が認められない可能性はあります。
- 公立高校への進学を想定して養育費の金額を決めたが、その後、子どもが私立高校に進学した
- 傷病や会社都合の離職(失業)などで、父または母の収入が大きく減少した
- 父または母の収入が大きく増加した
- 離婚後、父または母が再婚して子どもをもうけた
- 子どもの養子縁組で養親ができた
養育費の増額や減額についての弁護士費用の相場は、着手金は20万円、報酬金は変更額の2年分の10%程度です。
仮に当初の養育費が月額5万円で月額3万円に減額できた場合、変更額(月額2万円)の2年分(48万円)の10%は約5万円となります。着手金20万円とあわせて、弁護士費用は約25万円です。
ただし、減額の場合は報酬金を10%ではなく一律15万円と計算する弁護士も少なくありません。その場合、着手金20万円と報酬金15万円の合計額である35万円が弁護士費用です。
養育費の変更を弁護士に依頼する際は、契約前に、費用について十分な説明を受けてください。
一度決めた養育費の増額を検討している方は、ぜひ以下の記事で詳しい情報を確認してください。
また、養育費の強制執行については以下の記事で詳しく解説しています。
公正証書の作成を依頼した場合 │ 15万円
公正証書とは、法律実務の長いキャリアを持つ公証人が、依頼者の依頼に応じて作成する書面です。
公正証書は公務員である公証人が作成した公文書なので、夫婦間で作成した離婚協議書や和解書などの私文書と比べて、なりすましではなく当事者本人の意思で作成されたという高い証明力(形式的証明力)を持ちます。
また、債務者(養育費を支払う側)が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている公正証書は強制執行認諾条項付公正証書と呼ばれ、調停や審判、訴訟といった裁判所の手続きをしなくても強制執行(差し押さえ)ができる債務名義となります。
裁判所での手続きをしなくてもすぐに差し押さえ(強制執行)ができる点で、公正証書の作成は非常に有用です。
公正証書の作成を弁護士に依頼すると、弁護士は公正証書案の作成や公証人・公証役場との日程調整などの対応をしてくれます。その際の弁護士費用の相場は、15万円程度です。
弁護士によってはその半額である8万円程度で対応してもらえる場合もありますが、弁護士だけでなく公証人に支払う報酬(手数料)などの実費を考慮すると、15万円程度かかると考えておくとよいでしょう。
未婚のまま養育費の交渉を依頼した場合 │ 90万円〜
未婚のまま子どもを授かり、父である男性に養育費を支払ってもらいたいというケースがあります。しかし、認知していない場合は法律上の父子関係がないため、養育費を請求するのは困難です。
そのようなケースでは、父である男性に市区町村の役所に認知届を提出してもらうことが必要となります。しかし、任意に認知しない場合は、調停を経て認知訴訟を提起しなければなりません。
未婚のまま養育費の交渉を依頼した場合、状況に応じて弁護士費用の相場は以下のとおりです。
弁護士費用の相場
(未婚養育費)
| 状況 |
相場 |
| 強制認知(認知訴訟) |
50万円程度 |
| 養育費請求調停 |
40万円程度 |
弁護士によって異なりますが、着手金30万円以上、認知の報酬金30万円、養育費の報酬金が16%といったケースがあります。また、強制認知を得るうえで10万円程度のDNA鑑定費用(実費)が必要になるケースもある点に注意してください。
そのため、未婚のまま養育費に関する交渉を弁護士に依頼する場合、90万円以上かかると想定しておくとよいでしょう。
もっとも、相手が任意に認知し、養育費を支払うなど示談交渉のみで解決する場合には、90万円以下の負担に収まる可能性もあります。
未婚養育費について弁護士に依頼する際は、契約前に、費用について十分な説明を受けてください。
公正証書の重要性や作成にかかる費用、必要書類については、以下の記事で詳しく解説しています。
養育費に関する弁護士費用を支払えない場合はどうする?
養育費に関する弁護士費用は、低くても数十万円かかります。弁護士費用の支払いが難しい場合は、以下に挙げる3つの方法を検討してください。
なお、調停は、訴訟と比べて手続きを進めるハードルは高くありません。弁護士のサポートを受けず、家庭裁判所からの案内を受けながら自分で調停を申し立てる方法も考えられます。
しかし、平日に家庭裁判所への出頭が難しい、自分でやるのは不安が大きいなどの事情がある場合は、弁護士への依頼がおすすめです。養育費に関して弁護士に相談するメリットは後述しているので、ぜひあわせてご覧ください。
無料相談を利用する
初回相談に限り、30分や60分まで無料で法律相談に対応している弁護士も少なくありません。そして、無料相談を利用したからといって必ずしもその弁護士に依頼する必要もありません。
弁護士に相談して不安や疑問を解消でき、今後の方向性が定まった場合は、弁護士に依頼せず自分で対応を進めることもできます。無料相談で弁護士に対応を依頼しない場合、当然、弁護士費用はかかりません。
ただし、弁護士に依頼せず自分で対応を進める場合、後述する養育費に関して弁護士に相談するメリットを得られない点に注意が必要です。
無料相談を充実したものとしたうえで、弁護士に依頼するかどうかは慎重に検討しましょう。
法テラスを利用する
法テラス(日本司法支援センター)とは、国が設立した法律トラブルを解決するための支援機関です。経済的に余裕のない方は、無料の法律相談や弁護士に依頼する費用の立替制度を利用できます。
法テラスに弁護士費用を立替えてもらえると、弁護士費用相当額を一括ではなく分割での支払いが可能です。ただし、立替えてもらうには収入が一定以下などの基準があるため、利用できるかどうかは法テラスに相談して確認しください。
法テラスの利用条件や利用時の支払方法、注意点などは、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
分割払いができる法律事務所に依頼する
法律事務所によっては、弁護士費用について分割払いができるものもあります。実際に相手から養育費を支払ってもらったタイミングで支払える報酬金ならともかく、特に着手金について支払いに困るケースは少なくありません。
このような場合、原則として契約後に一括で支払う着手金などについて、分割払いに対応してくれる法律事務所への相談がおすすめです。
法律事務所のWebサイトでは分割払いに対応するとの記載がなくても、実際に相談すると対応してくれる場合もあります。法律相談をする際は、必要に応じて分割払いの相談もしましょう。
養育費に関して弁護士に相談するメリット
養育費に関して弁護士に対応を依頼すると、安くない費用の負担があります。しかし、弁護士に相談や依頼するメリットは、以下のとおり大きいです。
たしかに費用の負担はあるものの、メリットも十分に把握したうえで弁護士に依頼するかどうか検討してください。
相手方との話し合いを任せられる
弁護士に養育費に関する対応を依頼すると、弁護士が相手方と電話や対面、メール、書面などで交渉します。そのため、依頼者自身が直接相手方と話し合いをする必要はありません。
離婚の理由として性格の不一致が多いなか、実際に離婚に踏み出す頃か離婚後に、相手と顔を合わせて十分な話し合いができるケースは多くないでしょう。DVやモラハラにより、話し合いそのものが困難なケースもあります。
こうした状況で、法律と交渉のプロである弁護士が相手方との交渉を進めてくれる点は、弁護士に対応を依頼する大きなメリットです。
適正な金額の養育費を受け取れる可能性が高い
実務上、養育費は東京と大阪の家庭裁判所裁判官による司法研究の結果提案された改定標準算定表(令和元年版)をもとに金額が定められます。
例えば、14歳以下の子ども1人で母の収入は0円、父の(給与収入)は500万円の場合、改定標準算定表(令和元年版)によると標準的な養育費は月額6~8万円です。
ただし、養育費の金額は多様な事情を考慮して定めるべきなので、必ずしも標準的な養育費の金額の範囲内に収める必要はありません。例えば、協議や調停、審判の結果、算定表で示された枠を超えた月額10万円で決まることもあります。
とはいえ、算定表も通常の事情はすでに考慮されたものものです。したがって、示された幅を超えるには、算定表によることが著しく不公平となるような特別な事情がある場合に限られると考えられています。
そのような特別な事情があり、特別な事情を考慮した適正な金額の養育費を受け取るためには、弁護士による強力なサポートが必要といえるでしょう。
養育費の相場は、以下の記事で詳しく解説しています。
相手が養育費を滞納した場合の対策もしてくれる
養育費は、一度取り決めてもその後に約束どおりの支払いがないケースが多いです。そのため、養育費は特に相手からの支払いを確実にするための対応が求められます。
具体的には、審判や訴訟がなくても強制執行ができる公正証書の作成や、家庭裁判所から支払いを促す履行勧告を申し立てるといった対応です。相手の財産を把握しておくことも大切です。
弁護士に対応を依頼した場合、上記のような対策や対応について案内してくれるため、より確実に養育費の支払いを受けることにつながります。
養育費問題に強い弁護士の選び方
すべての弁護士が養育費問題に強いわけではありません。そのため、養育費問題について依頼する際は、以下のように養育費問題に強い弁護士を選ぶことが大切です。
ぜひ実践して、養育費問題に強い弁護士に対応を依頼してください。
以下の記事では、さらに詳しく離婚に強い弁護士の選び方を解説しています。ぜひあわせて参考にしてください。
養育費請求など離婚問題に強みを持つ
養育費問題に強い弁護士とは、養育費の請求や増額・減額、回収などの問題について対応した実績がある弁護士といえます。通常、弁護士は離婚そのものや財産分与、慰謝料などの離婚問題全般を取り扱っているため、離婚問題に強い弁護士も養育費に強い弁護士です。
弁護士を選ぶ際は、ツナグ離婚弁護士のような弁護士検索サイトや弁護士事務所のWebサイトで、離婚問題に注力しているかどうか確認してみてください。
養育費問題を解決した実績が豊富
養育費の請求や増額・減額、回収などの問題について対応した実績が豊富な弁護士なら、一定の安心感を持って依頼できます。
対応実績は、法律相談の際に直接弁護士に質問するほか、解決事例が掲載されている場合はWebサイトでも確認できます。
同じような事案で、依頼者に有利な解決を実現できた弁護士が望ましいです。
さまざまな解決方法を提案してくれる
養育費問題に対応した実績が豊富でも、弁護士によっては対応の方向性に違いが出ることがあります。
例えば、公正証書の作成までは不要と考えている弁護士では、公正証書の作成は積極的に案内してくれないでしょう。また、和解より裁判を重視する弁護士では、訴訟前の和解にも積極的ではないでしょう。
公正証書の作成には費用がかかりますし、和解と裁判とではどちらが有利な解決を期待できるかは不確実です。したがって、どちらの対応が正しいかは一概に評価できません。
依頼者としては、状況や意向に応じて、多様な解決方法を提案してくれる弁護士を選ぶことが大切です。
まとめ
養育費に関して弁護士に相談や対応を依頼すると、弁護士に交渉を任せられるほか、適正な金額の養育費を受け取れる可能性が高くなり、支払いを確実にするための対策もしてくれる場合があるなど多くのメリットがあります。
養育費に関する弁護士費用のうち、法律相談料は初回30~60分までは無料のケースが多いです。着手金は10~60万円、報酬金は基本報酬金が10~30万円、経済的利益に応じた金額が獲得(減額)できた額の5年分の16%程度などと設定されています。
また、公正証書の作成サポートは15万円程度、養育費の回収(強制執行)は回収額の30%程度が相場です。
示談から訴訟までを弁護士に依頼した場合と訴訟から弁護士に依頼した場合とでは、どちらも弁護士費用が同じになるケースもあります。そのため、可能な範囲はご自身で対応しようと考えている方も、早めに弁護士に相談し、必要であれば早めに対応を依頼することも大切です。
弁護士費用の算定方法や実費の支払いタイミング、分割払いの対応の可否は、弁護士によって異なります。初回は無料相談ができる弁護士も多いため、弁護士への依頼を検討している方は、上記の点も説明を受けるようにしましょう。
養育費の弁護士費用に関するよくある質問
養育費に関する弁護士費用を払うのは誰ですか?
原則、
弁護士に依頼した人自身の負担で支払います。
養育費を支払わないなど、「相手のせいで弁護士に依頼せざるを得なくなった」といった状態でも、弁護士に依頼するかどうかは依頼者が決めたことだからです。
したがって、養育費に関する弁護士費用を相手方に請求するのは困難で、負担するのは依頼者となります。
もっとも、法テラスの制度を利用することで、一度法テラスが弁護士費用を立替えて支払ってくれる場合があります。
養育費の弁護士費用はいつ払いますか?
弁護士費用の内訳に応じて、以下のとおりです。
弁護士費用を支払うタイミング
| 内訳 |
タイミング |
| 着手金 |
委任契約を締結した後、弁護士が対応に着手する前 |
| 報酬金 |
協議や調停、審判、訴訟で養育費の内容が確定したとき |
| 日当・実費 |
着手金と同時、発生の都度、事件終了時など弁護士によって異なる |
ただし、特に着手金は分割払いなどの相談に応じる弁護士もいるため、支払いが難しいときは弁護士に相談してください。
養育費の回収にはどのくらいの期間がかかりますか?
あくまでも目安ですが、債務名義の有無や相手の財産の把握状況に応じて以下のとおりです。
養育費の回収にかかる期間
(目安)
| 状況 |
期間 |
| 債務名義があり、相手の預貯金や勤務先がわかる |
1~2ヶ月程度 |
| 債務名義はあるが、相手の預貯金や勤務先がわからない |
3~6ヶ月程度 |
| 債務名義もなく、相手の預貯金や勤務先もわからない |
6ヶ月以上 |