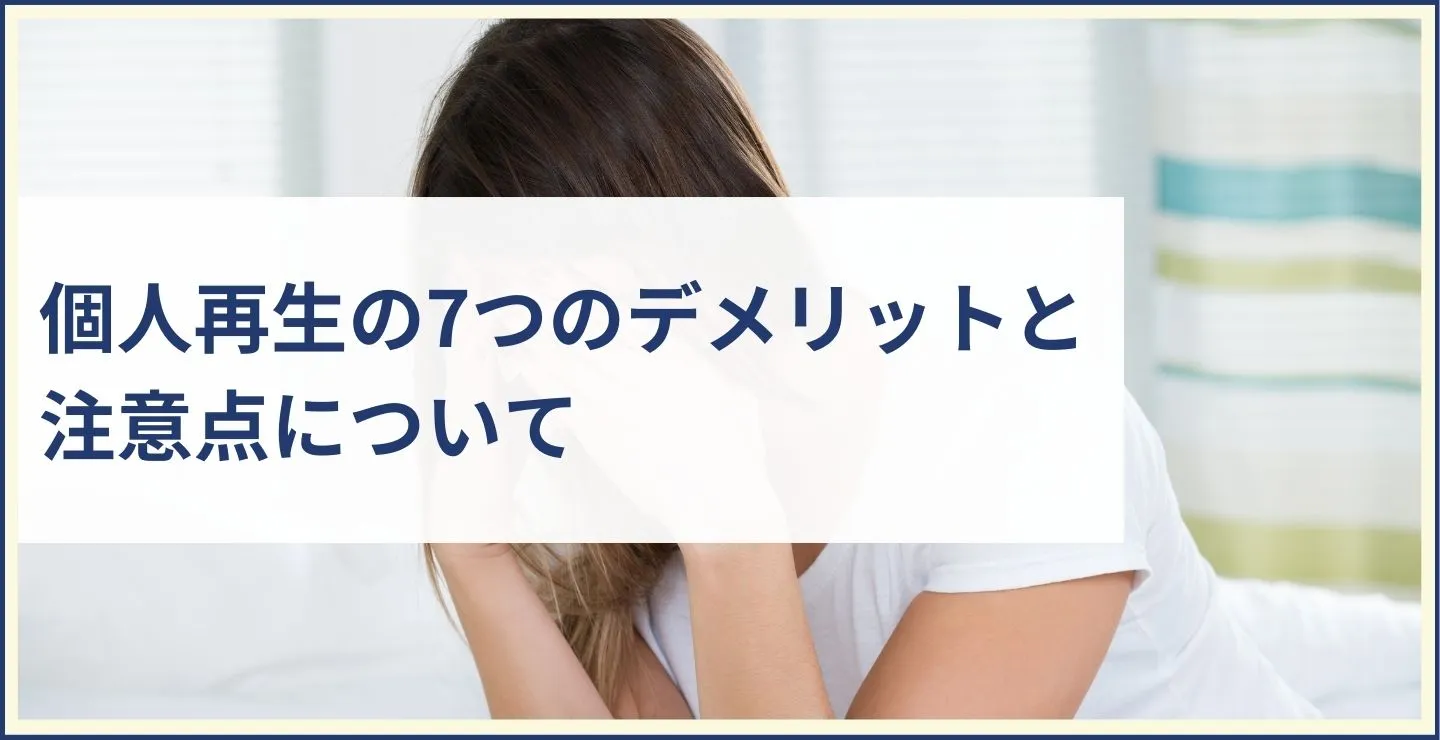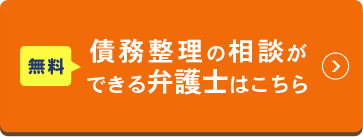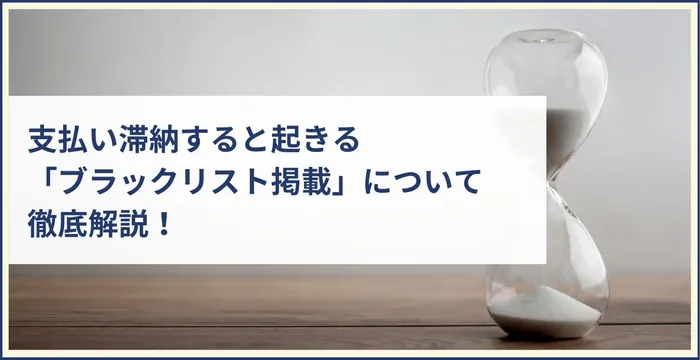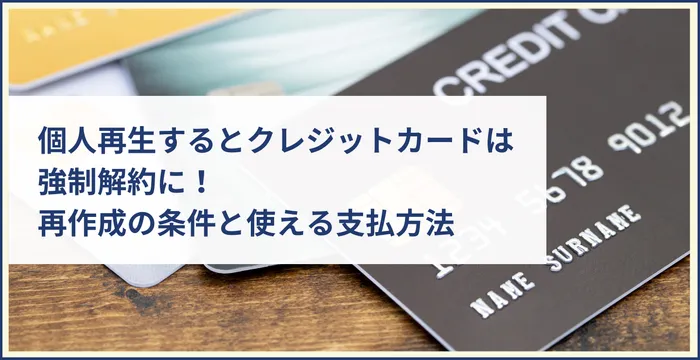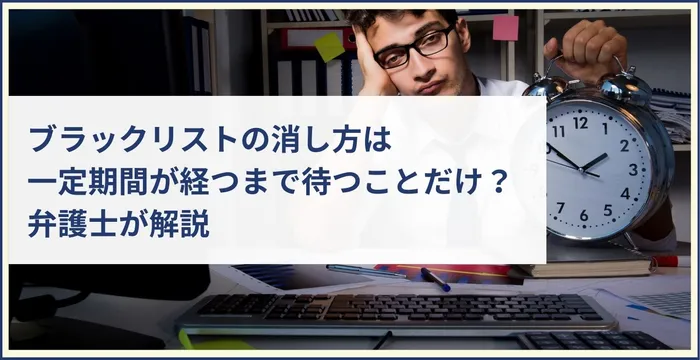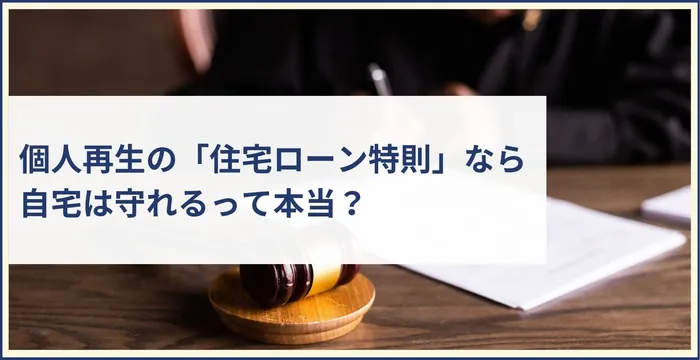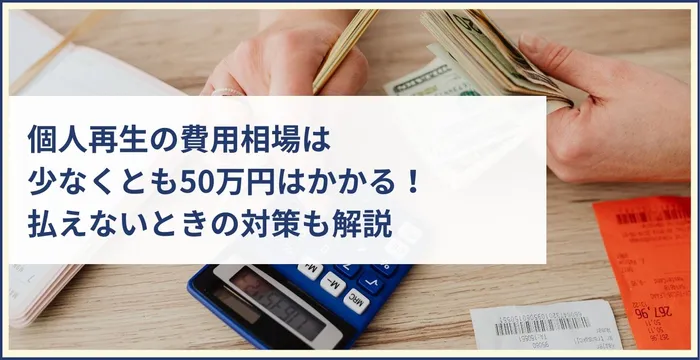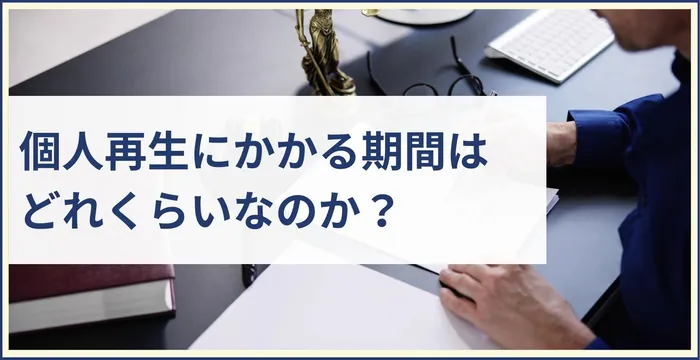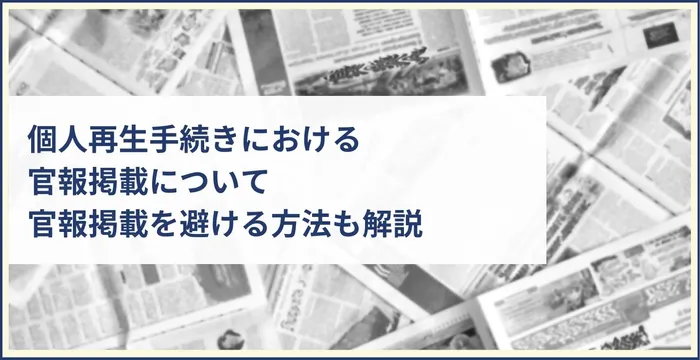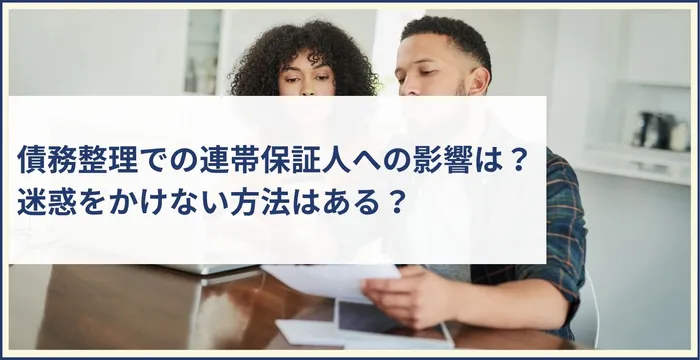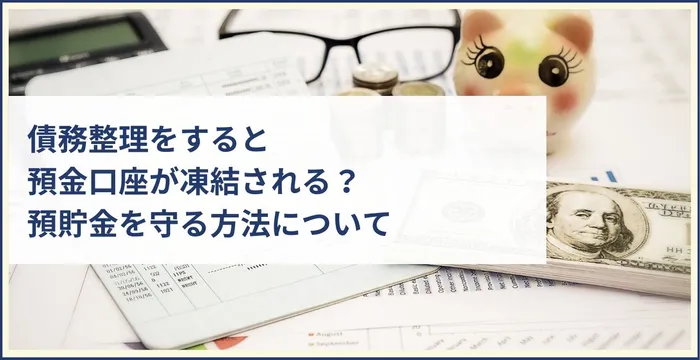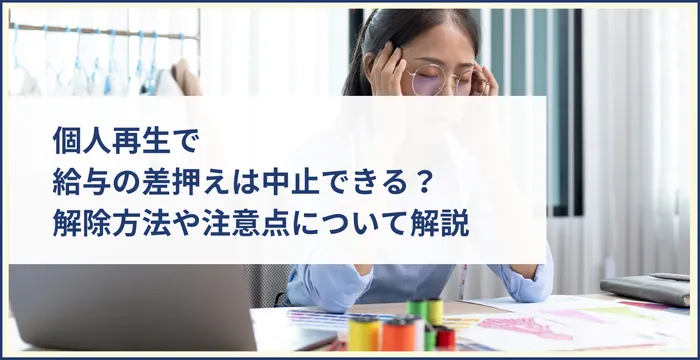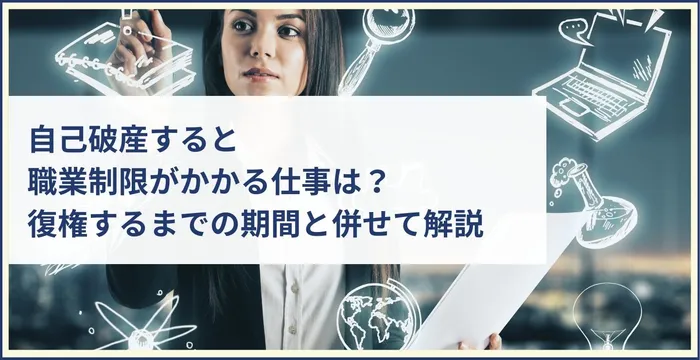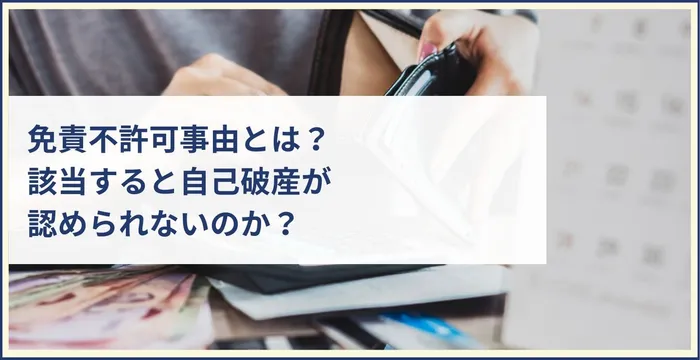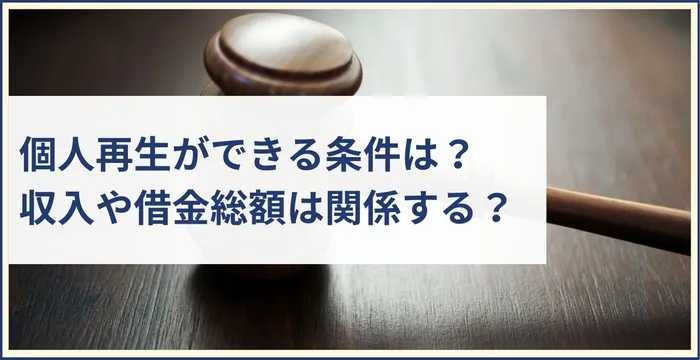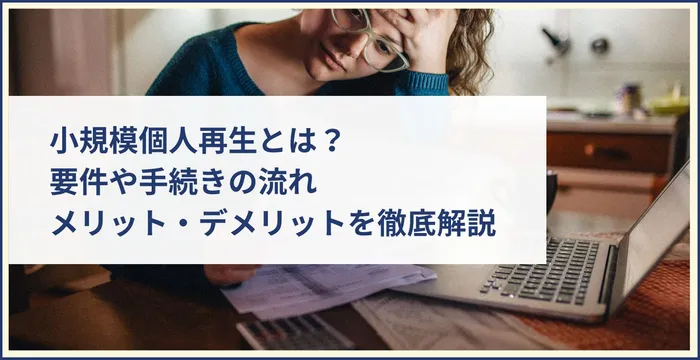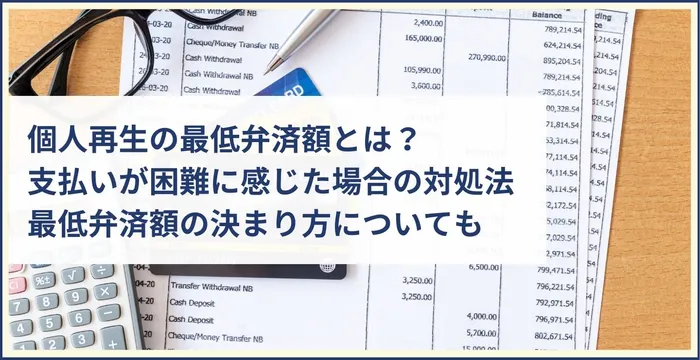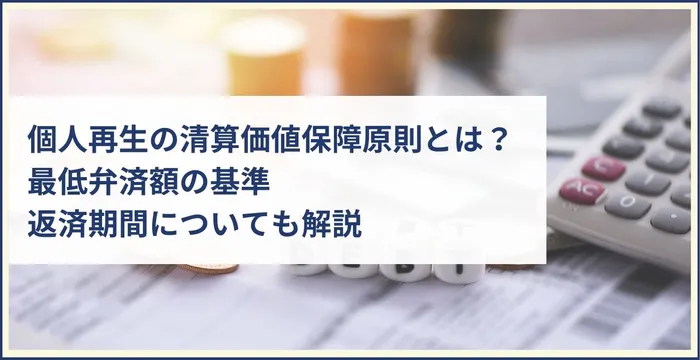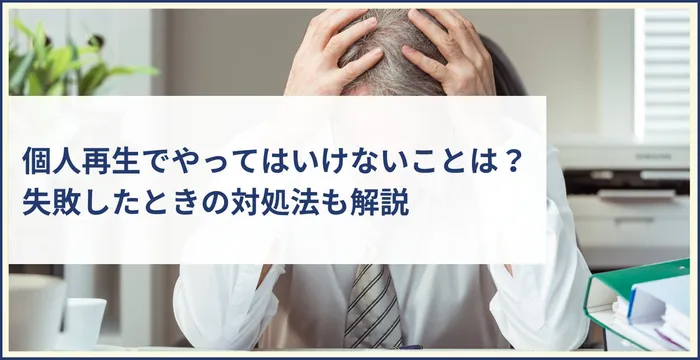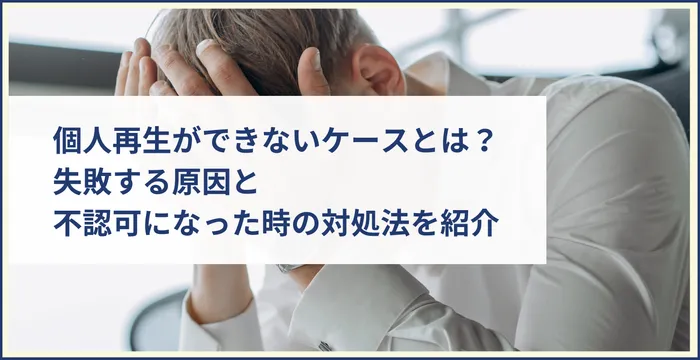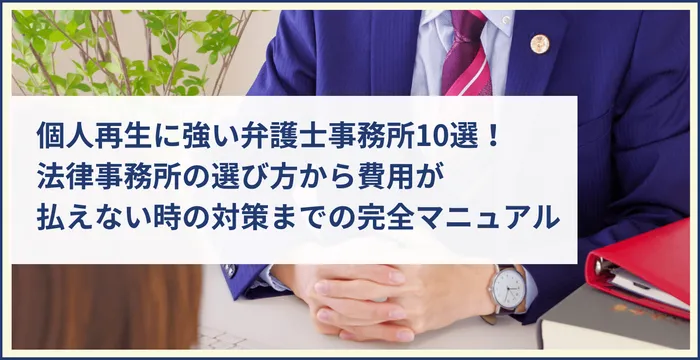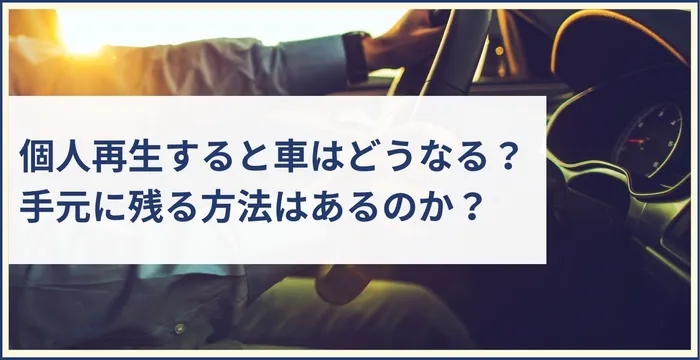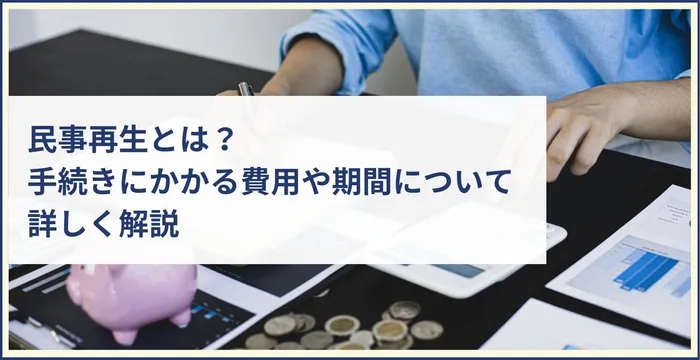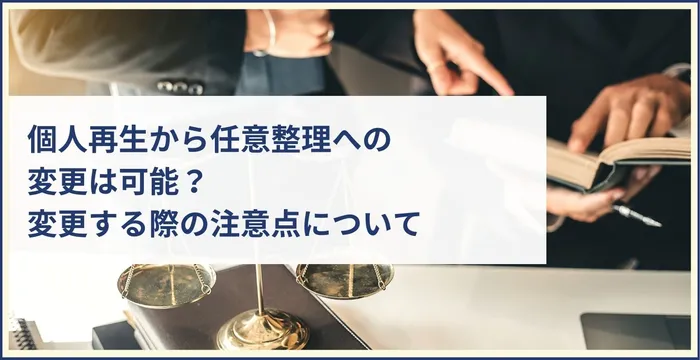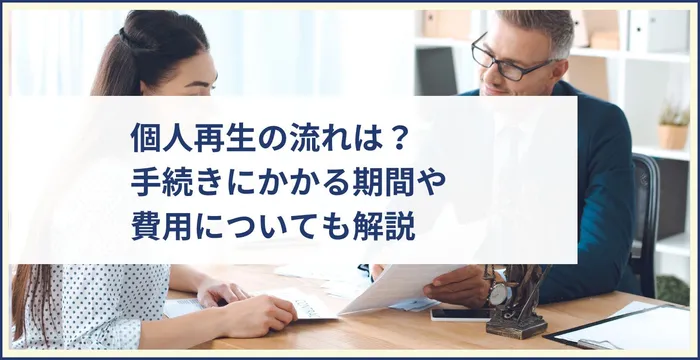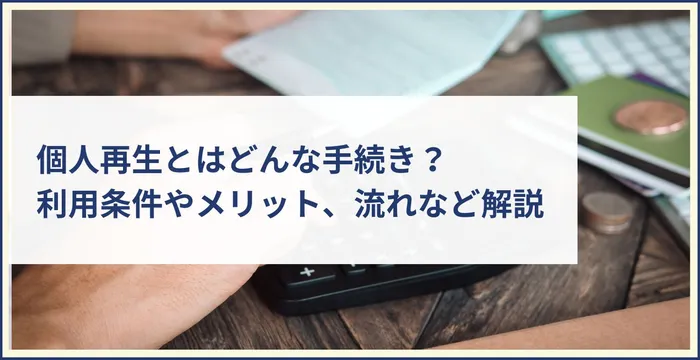個人再生にはデメリットがさまざま!デメリットを十分に把握してから手続きするべきかを検討しよう
まずは、個人再生のデメリットを整理していきましょう。
- いわゆる「ブラックリスト入り」に状態になる
- 返済中のものは引き上げられる可能性がある
- 他の債務整理手続きよりも費用が高額になりやすい
- 他の債務整理手続きよりも手間がかかりやすい
- 官報に掲載される
- 連帯保証人に請求が移行する
- 一時的に銀行口座が凍結される可能性がある
- 個人再生の対象とした債権者から「社内ブラック」として扱われる可能性がある
いわゆる「ブラックリスト入り」に状態になる
個人再生をすると、信用情報機関に「個人再生をした」という履歴が登録され、いわゆる「ブラックリスト入り」の状態になります。「ブラックリスト」とは通称で、実際にそういった帳簿はありませんが、信用情報に金融トラブルの履歴が登録されることを、一般的に「信用情報にキズがついた」「ブラックリストに載った」などと表現します。
信用情報とは、個人の収入や住宅情報、借入履歴や返済履歴などをまとめた情報で、国に指定された信用情報機関が管理しています。クレジットカードや各種ローン、保証業務といった「信用供与」を行う信販会社や、金融業者等の貸付審査で利用されるのが一般的です。
信用情報にキズがつくと、金融業者やクレジットカード会社にとって「リスクの高い顧客」とみなされる可能性があるため、次のような影響が発生しやすくなります。
- ローンが組めなくなる
- クレジットカードが使えなくなる
- 賃貸審査で不利になることがある
- 保証人になれなくなる
- スマホ端末の分割払いができなくなる
現代社会では当たり前になっているサービスが使えなくなる可能性があるので、不便に感じやすくなるでしょう。
個人再生によるブラックリスト入りの期間は最長5年〜7年
個人再生をはじめとした金融トラブルに関する履歴は、最長5~7年で削除されます。そのため、ブラックリスト入りの期間は最長5年〜7年ですが、その登録期間や内容は信用情報機関ごとに異なります。
たとえば、消費者金融系の「JICC」では、2019年10月1日以降の登録から「契約中および契約終了後5年以内」とされています。銀行系の「KSC」では、以前は最長10年まで登録されていましたが、2022年11月の運用変更により、現在は「個人再生の開始決定日から7年以内」に短縮されました。
このように、登録期間には一定の見直しも行われており、過去情報とは異なる点もあるため、正確な知識を得ることが重要です。
| 信用情報機関 |
主な加盟業者 |
登録される情報 |
登録期間 |
| 株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
クレジットカード会社、消費者金融が中心 |
個人再生の申立て情報は登録されない
(※関連する債務情報が間接的に登録される場合あり) |
個人再生の登録なし |
| 日本信用情報機構(JICC) |
消費者金融、銀行が中心 |
個人再生を申し立てした事実 |
2019年10月以降:契約期間中+減額後の残債を完済後5年以内
(※それ以前は個人再生の申し立て日から5年以内) |
| 全国銀行個人信用情報センター(KSC) |
銀行、信用金庫、信用組合が中心 |
個人再生の開始決定が出た事実 |
2022年11月以降:開始決定日から最長7年以内
(※それ以前は最長10年以内) |
※個人再生に伴い滞納などがあれば、別途事故情報が登録される。
信用情報の登録は永続的なものではなく、期間を過ぎると自動的に削除されます。自分の登録状況を確認したい場合は、各信用情報機関に対して「情報開示」を請求することで確認可能です。
ブラックリスト状態が解除されれば、再びローンやクレジットの利用が可能になるケースもあります。
返済中のものは引き上げられる可能性がある
下記のように、ローンを完済してない高価なものがあるときは、個人再生をすると引き上げられてしまう恐れがあります。
- 車
- 住宅
- パソコンやスマホなどの電子機器
- ブランド品
- ペット
これには、ローンで購入した商品の「所有権」が関係しています。ローン返済中の商品の所有権は、支払いが完了するまでローン会社にあります。債務者が本当の意味で商品を自分のものにできるのは、商品代金をすべて支払い終えたときです。
そのため、返済が滞ると個人再生の有無に関係なく、ローン会社は所有権に基づいてローンで購入した商品を引きあげることが可能です。
引きあげられた商品は、売却処分され未払い分の支払いに充てられます。もし、未払い分の金額より引きあげられた商品の売却益が少なければ、差額分は個人再生の対象にしてもらうことになります。
なお、債務整理のうち、任意整理は対象とする債務を自分で選ぶことができます。言い換えれば、特定の債務を除外可能です。
一方、個人再生と自己破産は対象を選べません。原則全ての債務を対象にする必要があります。
たとえば、任意整理なら連帯保証人付きの債務を除外して迷惑をかけないようにできますが、個人再生はそれができないということになります。
住宅ローン特則を利用すれば持ち家を残しつつ個人再生を行える
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは、住宅ローンだけを個人再生の減額対象から外し、マイホームを手放さずに他の借金だけを減額できる制度です。残した住宅ローンは再生計画に組み込み、今まで通りまたは返済スケジュールを調整したうえで、返済を続けます。
自己破産のように家を失うリスクを回避できるので、個人再生の大きなメリットの一つです。ただし、この制度はすべてのケースで使えるわけではなく、利用には以下の条件を満たす必要があります。
| 条件 |
概要 |
| 住宅ローンで借入れた資金であること |
建設・購入・改良のためのローンで、抵当権が設定されているもの |
| 本人名義で所有している住宅であること |
再生申立人自身が所有し、実際に住んでいる建物 |
| 住宅を他の借金の担保にしていないこと |
車や事業用ローンの担保に住宅を使っていないこと |
| 滞納がある場合は6ヶ月以内に申立て |
保証会社による代位弁済があった場合、6ヶ月以内に手続を開始している |
上記の条件を満たせば、住宅ローンは通常通り返済を続けつつ、他の債務だけを個人再生で大幅に減額できます。持ち家を守りたい方には非常に有効な選択肢といえるでしょう。
他の債務整理手続きよりも費用が高額になりやすい
個人再生は費用が高く、総額でおおむね30~70万円ほどかかります。
債務整理の中で費用相場を比べると、自己破産よりは安いものの、任意整理よりは基本的に高くなります。
| 手続きの種類 |
費用相場 |
費用の内訳 |
| 任意整理 |
1社あたり4万円程度+減額報酬(減額幅の10%程度) |
・弁護士などへの報酬 |
| 自己破産 |
30万円程度~100万円程度 |
・弁護士などへの報酬
・裁判所への手数料 |
| 個人再生 |
30万円程度~70万円程度 |
・弁護士などへの報酬
・裁判所への手数料 |
具体的な内訳は、裁判所に支払う手数料(予納金)と、弁護士などに支払う報酬に分けられます。
【裁判所への手数料(予納金)】
- 収入印紙代(申立手数料として):1万円程度
- 官報掲載料:1万4,000円程度
- 郵便切手代:2,000~4,000円程度
- 個人再生委員の報酬※:15万~25万円程度
個人再生委員とは、裁判所が選任する第三者の専門家です。弁護士であることが多く、手続きが適正に進むよう監督や助言を行う役割を担います。
債権者との調整や再生計画の妥当性を判断する際に選任されることがあり、申立人と裁判所の橋渡し的な存在となります。選任されるか否かは裁判所によって異なりますが、選任された場合は追加の費用(報酬)が発生することも頭に入れておきましょう。
他の債務整理手続きよりも手間がかかりやすい
個人再生は手続きが複雑で、場合によっては自己破産より手間がかかります。手続きのおおまかな流れは以下の通りです。
- 債務額の確認~書類の準備作成:1~3ヶ月程度
- 裁判所への申し立て~個人再生手続開始の決定:1ヶ月程度
- 個人再生手続開始の決定~再生計画の提出:2~3ヶ月程度
- 再生計画の提出~裁判所の認可、返済開始:1~3ヶ月程度
上記の間に、個人再生委員との面談、債権の調査、債権者からの意見聴取もしくは書面決議など、さまざまな手続きが入ります。申し立てから個人再生による返済開始まで、おおむね6ヶ月程度かかるでしょう。
ただし、履行テストが行われる場合はさらに6ヶ月間手続きに時間がかかります。履行テストとは、個人再生の手続き中に「再生計画どおりに返済を継続できるかどうか」を確認するために行われるテストです。
具体的には、裁判所からの指示に基づき、原則6ヶ月分の予定返済額を事前に積み立てることで、支払い能力を証明します。これができないと、再生計画が認可されないため、重要なステップの一つです。
履行テストが行われる場合は、申し立て後すぐに始まります。基本的に、東京地裁に申し立てた場合は履行テストが実施されますが、地域によっては履行テストが行われないケースもあります。
そのため、申し立てる際は履行テストが必要か確認しておくと良いでしょう。
なお、司法書士に依頼した場合、代行してもらえるのは各種書類の準備・作成までです。裁判所への出頭も代行してもらいたい場合は、弁護士に依頼するようにしましょう。
官報に掲載される
個人再生を行うと、官報という国の機関紙に情報が掲載されます。つまり、個人再生を行った事実は公表されるということです。
掲載される具体的な内容は、次の通りです。
- 氏名
- 住所
- 個人再生の決定日
- 手続きの内容
- 管轄の裁判所
官報は県庁所在地の販売所で購入可能で、図書館・インターネットでも閲覧可能です。見ようと思えば誰でも見られるので、借金のことを誰にも知られたくない場合は大きなデメリットといえるでしょう。
ただし、官報を普段から見るのは行政関係者や金融機関など限られた人達であり、閲覧目的も法制度に関する情報が中心です。そのため、官報に掲載されたからといって、周囲にバレるとは限りません。
大半の人は官報の存在自体を知らないため、そこから借金がバレる可能性は低いといえます。
連帯保証人に請求が移行する
連帯保証人付きの債務がある場合、個人再生をするとその連帯保証人に請求が移行します。連帯保証人は主債務者と同等の返済責任を負うため、請求を拒めません。
法的に問題ないとはいえ、連帯保証人に迷惑をかけることになり、関係性の悪化や何らかのトラブルになる恐れもあるでしょう。
なお、連帯保証人が負担するのは減額分のみですが、どのように返済を行うかでプロセスが変わります。
連帯保証人が一括返済を行う場合、支払うのは減額後の残債ではなく、元々あった残債全額です。主債務者は、減額された残債を連帯保証人に対して支払うことになります。
一方、連帯保証人が分割払いをする場合、主債務者の返済と同時進行で行われます。2つの返済が元々の残債額に達した時点で、返済は終了です。
たとえば、1,000万円の残債を個人再生で200万円まで減額したとします。
一括返済をする場合、まずは連帯保証人が1,000万円を債権者に支払い、その後に主債務者から200万円を再生計画に基づいて返済してもらいます。再生計画とは、個人再生で裁判所が認可した、減額後の返済スケジュールのことです。
一方で分割払いをする場合、連帯保証人の返済と、主債務者の返済を同時進行で行います。連帯保証人が800万円、主債務者が200万円を支払えば返済は完了です。
主債務者は減額された残債を支払うことに変わりありませんが、連帯保証人にとっては「自分が一括でいくら支払う必要があるのか」という点で違いがあります。
一時的に銀行口座が凍結される可能性がある
借入先の銀行や信用金庫、農協などで口座を開設している場合、個人再生を行う旨を伝えると、その口座は一時的に凍結される可能性があります。口座が凍結されると、入出金や振込、引き落としなどが一切行えなくなります。
口座が凍結されるのは、残債との相殺に充てるための預金残高を、債務者に引き出されないようにするためです。口座凍結期間は1~3ヶ月程度で、通常は保証会社が金融機関に代位弁済を行った後に凍結が解除されます。
ただし、金融機関によっては代位弁済が行われた後も、借入金が全額返済されるまで凍結が解除されない場合もあるので注意が必要です。
個人再生の対象とした債権者から「社内ブラック」として扱われる可能性がある
社内ブラックとは、各社が自社内で管理している信用情報に、個人再生をしたという履歴が掲載されている状態のことを指します。ただし、この「社内ブラック」は、信用情報機関のように公的に存在が確認されているものではありません。
各金融機関が保有する社内情報の取り扱いは公表されていないため、個人再生をしたからといって、必ずしも社内ブラックになり審査に落ちるとは限らないのが実情です。とはいえ、もし債務整理の情報が社内で保管されているとすれば、その履歴をもとに「返済能力に不安がある」と判断され、新たな借入やクレジットカードの審査に通りづらくなることも考えられます。
また、社内ブラックへの掲載期間は会社によって異なるため、信用情報機関のブラックリストのように〇年といった目安はありません。一定の要件を満たすことで社内ブラックが解除される会社もあれば、半永久的に社内ブラックが掲載され続ける会社もあります。さらに、社内ブラックとみなされた情報がグループ会社間で共有されている可能性もあるため、過去に取引のない会社でも審査に影響が出ることがあります。
このように、「社内ブラック」は存在すると断言できるものではないものの、審査に影響を与えるリスクがある点には注意が必要です。
個人再生を検討するべきケース
債務整理の中で個人再生を選ぶべき主なケースは、次の3つです。
- 高額債務で大幅な減額が必要な場合
- 自己破産のデメリットを許容できない場合
- 自己破産ができなさそうな場合(免責不許可事由がある場合)
任意整理では生活を立て直せないものの、自己破産ができない・したくないときに検討するのが基本です。
それぞれ詳しく解説していきます。
高額債務で大幅な減額が必要な場合
ブラックリスト期間が短く、対象とする債務を自分で選べる任意整理は、デメリットの少なさを重視する際に選択肢として検討されることの多い方法です。
しかし、任意整理で減らせる可能性があるのは将来利息(これから支払うはずの利息)だけであり、元本は減らないのが一般的です。当然、個人再生より減額幅は少なくなります。
債務の総額が大きい場合には、任意整理だけでは返済負担があまり軽くならないこともあるため、その場合は個人再生も視野に入れてみるとよいでしょう。
自己破産のデメリットを許容できない場合
減額幅だけを見れば、残債を全て帳消しにする自己破産が最大です。しかし、自己破産は減額効果が大きい分、デメリットも重いといえます。
自己破産にあって個人再生にないデメリットとしては、以下の2つが挙げられます。
- 財産がほぼ全て差し押さえられる(強制処分される)
- 手続き中に職業制限を受ける
それぞれ詳しく見ていきましょう。
家などの財産処分を避けたい
自己破産の場合、差し押さえ禁止の財産を除き、20万円以上の価値のある財産はほぼ全て処分され、債権者への弁済に充てられます。
手元に残せる財産は、以下の通りごくわずかです。
- 99万円以下の現金
- 生活に最低限必要な家財
- 給与(手取り額の3/4かつ33万円まで)
- その他、裁判所が認めた最低限の財産
個人再生ではそもそも財産の強制処分自体がないため、原則的には、ローン返済中の財産を除き自由に財産を残せるといえます。また、先述した住宅ローン特則もあるので、ローン返済中であっても住宅の処分も避けられる可能性が高いでしょう。
ただし、手元に残す財産が多いと、後述する清算価値保証原則によって減額幅が小さくなるので注意しましょう。
職業制限を避けたい
自己破産は、裁判所での手続き中(免責の許可決定が下りるまで)に一部の資格・職業を制限されます。
対象となる資格・職業のうち、主なものは以下の通りです。
| ジャンル |
職業制限を受ける仕事・役職の具体例 |
| 士業系 |
弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取扱士、通関士など |
| 公職系 |
人事院の人事官、教育委員会の教育委員、公正取引委員、公証人、人事院の人事官、都道府県の公安委員など |
| 団体役員系 |
商工会議所、日本銀行、信用金庫、金融商品取引業、労働派遣業など |
| その他の仕事 |
警備員、生命保険募集人、質屋経営者、旅行業務取扱いの登録者・管理者、建築業経営者、廃棄物処理業者、調教師、騎手、風俗業管理者など |
免責の許可決定には長くて1年以上かかり、制限も同じ期間続きます。個人再生なら、このような制限はありません。
なお、自己破産による資格・職業制限を受けても、それが原因で解雇されると不当解雇になります。該当する資格・職業に就いている場合、事情を説明して配置替えなどの対応をしてもらうことになるでしょう。
自己破産ができなさそうな場合(免責不許可事由がある場合)
自己破産には、免責が認められなくなる「免責不許可事由」があります。事由に該当すると、原則自己破産ができないというルールです。
具体的な項目は以下の通りです。
| 免責不許可事由 |
概要 |
| 不当な破産財団価値減少行為 |
財産隠しや損壊など |
| 不当な債務負担行為 |
破産前提の借入など |
| 不当な偏頗為 |
特定の債権者を優先して返済するなど |
| 浪費または賭博その他の射幸行為 |
ギャンブルやFX、贅沢品の購入など |
| 詐術による信用取引 |
返済能力を偽って借入した場合など |
| 業務帳簿隠滅等の行為 |
業務や財産に関する書類の隠蔽・偽造など |
| 虚偽の債権者名簿提出行為 |
裁判所へ嘘の債権者名簿を提出すること |
| 調査協力義務違反行為 |
裁判所の調査に協力しないこと |
| 管財業務妨害行為 |
破産管財人などを不正に妨害すること |
| 7年以内の免責取得 |
7年以内に自己破産や給与所得者等再生を認可されている場合 |
個人再生には上記のような免責不許可事由がないため、自己破産ができないときの代替手段として利用するケースが多々あります。
ただし、免責不許可事由があるからといって、免責が一切許可されないわけではありません。「裁量免責」といって、裁判官の裁量で特別に許可を貰えるケースがあります。
裁量免責がもらえるかどうかは個別の状況によるため、まずは弁護士・司法書士に相談してみましょう。
個人再生のデメリットを軽減するための対策
個人再生は借金を大幅に減額できるメリットがある一方、ブラックリスト入りの影響でクレジットカードや割賦払いなどが利用できなくなったり、銀行口座が一時的に凍結されたりといったさまざまなデメリットがあります。
しかし、以下のような対策を講じれば、個人再生のデメリットによる影響を軽減することが可能です。
- ブラックリスト入りによるキャッシュレス決済についてはデビットカードを代用する
- スマートフォンは一括払いで購入する
- 賃貸契約の際には信販系以外の保証会社の物件を探してもらう
- マイカーローンを組む際には自社ローンを利用する
- 個人再生の費用は分割払いに対応してもらえる弁護士・司法書士に依頼する
- 銀行口座の凍結については引き落とし口座を変更しておく
ここからは、それぞれの対策について1つずつ詳しく解説していきます。
ブラックリスト入りによるキャッシュレス決済についてはデビットカードを代用する
デビットカードとは、決済と同時に連携した銀行口座から利用代金が引き落とされる即時払い式のカードです。ブラックリスト入りの状態になると、クレジットカードを新規発行をする際に審査に通りづらくなるほか、これまで利用していたクレジットカードもすべて強制解約される恐れがあります。
しかし、デビットカードであればブラックリスト入りの状態でも利用を継続できます。デビットカードは即時決済なのでクレジットカードとは違って借入金の返済にはあたらず、本人の信用力も問われないためです。
決済のタイミングや1回払いしか利用できない点はクレジットカードと異なりますが、基本的にはクレジットカードとほぼ同じように使えるので、デビットカードを作っておけば個人再生後もキャッシュレス決済でスムーズに支払いができます。
スマートフォンは一括払いで購入する
個人再生でブラックリスト入りの状態になったとしても、一括払いであればスマートフォンを購入できます。スマートフォンの機種代を分割で支払う場合は、割賦販売契約の際に信用情報機関への照会が行われるため、ブラックリスト入りの状態では審査に通りづらくなります。
しかし、現金一括払いなら本人の信用力は問われません。個人再生をした後もスマートフォンの購入や回線契約は制限されないため、現金一括払いなら問題なく機種変更が行えます。
賃貸契約の際には信販系以外の保証会社の物件を探してもらう
個人再生後に賃貸契約をする際は、信販系以外の保証会社を通した賃貸物件を探してもらいましょう。前述の通り、個人再生を行うと最長5~7年はブラックリスト入りの状態が続きますが、その間はアプラスやセゾン、ジャックスなどの信販系の保証会社を通した賃貸物件への入居は困難になります。
信販系の保証会社は信用情報機関に加盟しており、賃貸契約の審査の際に信用情報機関への照会が行われます。そのため、ブラックリスト入りの状態だと審査に通りづらくなるでしょう。しかし、信用情報機関に加盟していない信販系以外の保証会社であれば、信用情報の調査が行われないため、ブラックリスト入りの状態であっても審査に通る可能性があります。
また、もともと保証会社不要な賃貸物件も信用情報の影響を受けないため、個人再生後も問題なく入居可能です。ブラックリスト入りの状態だからといって、賃貸契約の審査が一切通らないというわけではないので、不動産会社に事情を説明して条件に合う賃貸物件を一緒に探してもらいましょう。
マイカーローンを組む際には自社ローンを利用する
個人再生をするとブラックリスト入りする影響により、住宅や車などローンの審査にも通りにくくなります。しかし、車の購入でマイカーローンを利用する際、カーディーラーや中古車販売店が提供する「自社ローン」であれば、ブラックリスト入りの状態でも審査に通過する可能性があります。
これは、カーディーラーや中古品販売店は信用情報機関に加盟しておらず、自社ローンの審査の際に信用情報機関への照会を行われないためです。ただし、自社ローンにはカーディーラーや中古品販売店の独自の審査基準があるため、自社ローンを利用するにはその審査基準をクリアする必要があります。
返済能力が低いと判断されれば審査に通らない可能性が高いため、必ずしも自社ローンを利用できるわけではありません。
個人再生の費用は分割払いに対応してもらえる弁護士・司法書士に依頼する
個人再生にかかる費用を工面するのが難しい場合は、分割払いに対応してもらえる弁護士や司法書士に依頼しましょう。個人再生をする場合、裁判所へ支払う実費と弁護士・司法書士へ支払う着手金や成功報酬などで合計30~70万円程度の費用がかかるのが一般的です。
これらの費用は一括で支払うのが原則ですが、弁護士・司法書士事務所によっては着手金や成功報酬の分割払いに対応してくれるところもあります。分割払いに対応してもらえる弁護士・司法書士に依頼すれば、今すぐ個人再生の費用を全額用意するのが難しい場合でも、裁判所に支払う費用さえ用意できれば個人再生の手続きが進められるでしょう。
銀行口座の凍結については引き落とし口座を変更しておく
銀行口座の凍結に対しては、事前に引き落とし口座を変更しておくことで対処できます。個人再生で一時的に凍結される可能性があるのは、個人再生の対象となる金融機関の口座のみです。
借入のない金融機関の口座であれば凍結されずにそのまま使い続けられますし、口座開設も問題なく行えます。給与の振込先口座や家賃・光熱費などの引き落とし口座を個人再生の対象とする金融機関で開設している場合は、あらかじめ借入のない別の金融機関の口座に変更しておきましょう。
個人再生をするには要件を満たす必要がある
個人再生で借金を減額するためには、主に以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 安定した収入があること
- 債務が5,000万円以下であること
- 債権者の同意が必要なこと(小規模個人再生の場合)
ここからは、それぞれの要件について1つずつ詳しく解説していきます。
安定した収入があること
大幅な減額ができるとはいえ、再生計画に基づき返済を行う必要があるため、本人に安定した収入が必要になります。
収入形態ごとの目安は以下の通りです。
| 収入の種類 |
個人再生を受けられる目安 |
| 正社員 |
基本的に利用が認められやすい |
| 個人事業主 |
3ヶ月に1回の割合で、再生計画に基づいて返済できる収入がある |
| アルバイト |
雇用が相当期間継続しており、今後も継続して雇用される見込みがあ |
| 年金受給者 |
老齢年金は対象となることが多いが、障害年金の場合は障害の程度などから個別に判断される |
上記のように、継続的かつ安定した収入があれば、正社員・派遣・アルバイト・フリーランスといった雇用形態に関係なく、個人再生が利用できる可能性はあります。
ただし、無職や専業主婦(主夫)など債務者本人に収入がない場合は、たとえ同居家族に収入があったとしても個人再生は利用できません。生活保護受給者も、生活保護費を借金の返済に充てることは認められていないので基本的には利用できないのが一般的です。
また、収入はあっても短期のアルバイトや派遣を繰り返していたり、短期間で転職や休職を繰り返していたり、短期間の離職が続いていたりする場合は個人再生が認められない可能性があります。
債務が5,000万円以下であること
個人再生の手続きができるのは、再生債権にかかる債務総額が5,000万円以下の人のみです。再生債権とは、個人再生手続開始前に発生した一般優先債権・共益債権以外の債権を指します。
個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が五千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。
引用元:e-Govポータル「民事再生法 第221条第1項」
再生債権にかかる債務としては、以下のものが挙げられます。
- 銀行や貸金業者からの借金
- 個人間の借金
- 各種ローン
- 利息
- 遅延損害金
- 養育費
- 婚姻費用
- 損害賠償金
再生債権が5,000万円を超える場合は、より手続きが難しく、主に法人が利用する「民事再生手続き」を行わなければいけません。
ただし、住宅ローン特則を利用する場合の住宅ローンと、担保付き債権が差し押さえで回収できる金額については、差し引いて判断します。
たとえば、債務総額が6,000万円で、そのうち住宅ローン残債が1,500万円、300万円の車を担保にしたローン残債が500万円あるとします。
この場合、「6,000万円-1,500万円-(500万円-300万円)=4,300万円」なので、個人再生を申し立てることが可能です。
なお、住宅ローン特則を利用しない場合、つまり住宅を手放す場合は、他の担保付き債権と同じように判断します。上記の例で住宅の担保価値が700万円だった場合、差し引き後は「6,000万円-(1,500万円-700万円)-(500万円-300万円)=5,100万円」となるので、個人再生はできなくなります。
また、滞納分の税金や保険料などの一般優先債権や、個人再生後に発生する養育費などの共益債権にかかる債務は個人再生手続きの対象外であるため、債務総額にはカウントされません。
債権者の同意が必要なこと(小規模個人再生の場合)
個人再生には「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の2種類あります。簡単にいえば、前者は通常の手続き、後者は簡易的な手続きです。
小規模個人再生を利用する場合は債権者からの同意が必要になります。小規模個人再生では、裁判所に再生計画案を提出した後、その再生計画案に対して債権者が同意するかどうかの書面決議が行われます。
ここで以下の2つの要件を両方とも満たした場合のみ、債権者からの同意があったとみなされ、そのまま個人再生手続きを進めることができます。
- 再生計画案に反対した債権者の数が半数未満であること
- 再生計画案に反対した債権者の債権額が全体の2分の1を超えていないこと
たとえば、債権者が3社であれば、2社の同意が必要です(債権者の過半数)。
また、負債額が1,000万円だった場合、同意した債権者に対する負債額が、合計で500万円を超えている必要があります(負債額の過半数)。
再生計画案に反対した債権者の数が半数以上である場合、または再生計画案に反対した債権者の債権額が全体の2分の1を超えている場合は、債権者の同意を得られなかったとして個人再生の手続きが廃止されてしまいます。
債権者の同意が得られないという理由で個人再生が廃止されるケースは比較的少ないのが実情ですが、確実に同意が得られるとは限らないので注意が必要です。
個人再生をする前に必ず確認しておくべきこと
個人再生の手続きを行う前には、必ず以下のポイントをチェックしておきましょう。
- 借金がすべてなくなるわけではない
- 個人再生の対象とする借金は選べない
- 税金や養育費などは減額されない
- 借金が必ず1/5程度になるわけではない
ここからは、それぞれのポイントについて1つずつ詳しく解説していきます。
借金がすべてなくなるわけではない
個人再生は、自己破産のように借金が全額免除されるわけではありません。個人再生をすれば借金を大幅に減額できますが、減額された後の借金を返済する義務は残るため、借金を完済するまで返済生活が続きます。
再生計画通りに返済できないと再生認可が取り消しとなり、減額された借金が元に戻ってしまう恐れがあります。そのため、個人再生後も収支管理を徹底し、支払い期日に遅れないように返済を続けていくことを心掛けましょう。
個人再生の対象とする借金は選べない
個人再生では、任意整理のように整理対象とする借金を選べません。全ての借金が個人再生の対象となるため、ローンが残っている財産を所有している場合や保証人・連帯保証人が設定されている借金がある場合は、財産や保証人・連帯保証人への影響は避けられません。
ただし、住宅ローン返済中の住宅については、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで住宅ローンを個人再生の対象から除外できます。住宅ローン特則をうまく利用して、住宅の引き上げや保証人・連帯保証人への影響を回避しましょう。
税金や養育費などは減額されない
個人再生で借金の減額が認められたとしても、滞納した税金や未払いの養育費など下記に該当するものは減額されません。
| 一般優先債権 |
・税金、国民年金保険料、社会保険料、健康保険料、下水道料金、罰金などの公租公課
・従業員に支払う給料や退職金
・再生手続開始前に滞納していた6ヶ月分の水道光熱費
・葬式の費用
|
| 共益債権 |
・再生手続開始後に発生する将来の養育費
・再生手続開始後に発生する家賃や水道光熱費
・破産や民事再生の手続きにかかる費用
|
| 非減免債権 |
・債務者が悪意によって加えた行為に基づく損害賠償請求権
・故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
・夫婦の婚姻費用や扶養家族の生活費、子どもの養育費の請求権 |
税金や保険料などの「一般優先債権」や、再生手続開始後に発生する将来の養育費などの「共益債権」にかかる債務は、そもそも個人再生の手続きの対象外です。再生計画には組み込まれないため、個人再生手続きにかかわらず全額支払い義務を負います。
また、滞納分の養育費や婚姻費用などの「非減免債権」は、個人再生手続きの対象となる再生債権の一種であるため、銀行や貸金業者からの借金などと同様に再生計画には組み込まれます。しかし、借金の減額は認められないため、個人再生後も全額返済しなければなりません。
借金が必ず1/5程度になるわけではない
個人再生は借金を1/5程度まで減額できるという情報をネットでよく見かけることが多いですが、実は借金が必ず1/5程度になるわけではありません。個人再生では、手続き後も最低限返済しなければならない「最低弁済額」が民事再生法で定められており、これは最低でも100万円となっています。
最低弁済額は、住宅ローンを除く債務総額に応じて以下のように決まっています。
| 債務総額(住宅ローンを除く) |
最低弁済額 |
| 100万円未満 |
債務総額と同じ(減額なし) |
| 100万円以上500万円以下 |
100万円 |
| 500万円超1.500万円以下 |
債務総額の1/5 |
| 1,500万円超3,000万円以下 |
300万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 |
債務総額の1/10 |
この表を見ても分かるように、債務総額が500万円以上の場合は1/5~1/10程度まで減額できる可能性がありますが、債務総額が500万円以下の場合は必ずしも1/5程度まで減額できるとは限りません。
最低弁済額は最低でも100万円となっているため、債務総額が100万円以下の場合は一切減額されず、個人再生を行う意味はありません。
また、多額の財産を持っている場合や収入が多い場合は、民事再生法に基づく基準が適用されず、最低弁済額が上がるケースがあります。最低弁済額を決める基準は以下の3つあります。
| 最低弁済基準 |
住宅ローンを除く債務総額に応じて最低弁済額が決まる |
| 清算価値保障基準 |
一定の価値がある財産をすべて現金化した場合の金額(清算価値)以上の支払いが求められる |
| 可処分所得基準 |
年収から年金や社会保険料、最低生活費を差し引いた可処分所得の2年分以上の支払いが求められる |
小規模個人再生の場合は「最低弁済基準」「清算価値保障基準」のいずれか高い方、給与所得者等再生の場合は「最低弁済基準」「清算価値保障基準」「可処分所得基準」のいずれか高い方が最低弁済額となります。
下記のケースで見てみましょう。
【債務総額が1,500万円ある場合】
・「最低弁済基準」が適用されれば借金を1/5の300万円まで減額できる
・小規模個人再生で財産の清算価値が1,000万円ある場合は「清算価値保障基準」が適用されるため、最低弁済額は1,000万円になる
このように、債務総額や財産・収入状況によっては、1/5程度まで減額できなかったり、一切減額されなかったりするケースもあるので注意が必要です。
個人再生の注意点|やってはいけないことは?
個人再生は借金の大幅な減額が可能な一方で、自己破産よりも生活上の制限が少ないことから、自己破産が難しい場合に検討されやすい債務整理方法といえます。
ただし、手続きをするうえで注意しなければならないこともたくさんあるので、よく確認してから手続きを開始するとよいでしょう。
個人再生をおこなううえでの注意点は、以下のとおりです。
- 虚偽の申告をする
- 再生計画案の提出期限を守らない
- 特定の債権者に優先して返済する
- 履行テストで再生計画通りに返済しない
- 隠れて借入をする
これらの注意点を守らないと、最悪の場合は個人再生の手続きが認められない恐れもあるので注意してください。
虚偽の申告をする
個人再生の申立てをする際には、裁判所へ借入先や財産、収入額といった内容を記した書類の提出が必要です。
もし、これらの内容について虚偽の申告をすると、不当・不誠実な申立てとして、個人再生の申立てが認められなくなる恐れがあります。
意図的に一部の債権者だけ申告しないなど、虚位の申告をするのは絶対にやめましょう。また、意図的でなくても申告漏れなどがあると手続きの遅れなどに繋がる恐れがあるため、提出書類は入念にチェックしたうえで提出するようにしましょう。
再生計画案の提出期限を守らない
個人再生では、どのくらい借金を減額し、どのように返済していくかを示す再生計画案を作成し、裁判所へ提出する必要があります。
この再生計画案の提出には、期限が定められています。
期限までに再生計画案を提出できなかった場合、個人再生の手続きが打ち切られてしまう恐れもあるので注意が必要です。
特定の債権者に優先して返済する
なかには「迷惑をかけたくない」として、友人や家族、仕事の取引先などからの借金だけはいままでどおり返済して、それ以外の借金を個人再生で減額しようと考える人もいるかもしれません。
しかし、特定の債権者にだけ優先的に返済することは「偏頗弁済」と呼ばれ、個人再生が認められなくなる原因となる恐れがあります。
偏頗弁済をしてしまうと、債権者の間に不平等が生まれてしまい、すべての債権者を平等に扱わなければならないという個人再生の原則に反するとされているからです。
個人再生の手続きをスムーズにおこなうためにも、特定の債権者にだけ優先的に返済すること(偏頗弁済)はやめましょう。
履行テストで再生計画通りに返済しない
前述のとおり、多くの裁判所が個人再生の申立て後に履行テストを実施しています。
もし、履行テストの支払いが途中でできなくなってしまった場合は、裁判所に再生計画案を認めてもらえず、個人再生ができなくなってしまうので注意してください。
隠れて借入をする
個人再生の手続き開始後に、生活が苦しくなり借入をして生活費を補填したいと考える人は少なくありません。
しかし、手続き開始後に借入をしてしまうと「最初から個人再生するつもりで借入をした」とみなされ、個人再生が認められない原因となる恐れがあります。
そのため、なかには隠れて借入をおこなおうとする人もいますが、隠れて借入をおこなったことが発覚すれば、当然裁判所からの心証が悪くなります。最悪の場合、個人再生手続きが無効になる恐れもあるので、隠れて借入をするのは絶対にやめましょう。
まとめ
個人再生は大幅な減額を見込めますが、それなりにデメリットも重くなります。とくに、ブラックリスト入りは生活にも大きな影響があるでしょう。
個人再生で後悔しないためには、債務整理のプロである弁護士・司法書士に相談し、メリットとデメリットをしっかりと把握してから実行することが大切です。
当サイトでも借金問題を専門としている弁護士・司法書士を紹介しているので、個人再生を行うときはぜひ参考にしてください。まずは無料相談を利用し、自分の状況に最適なアドバイスを聞いてみましょう。
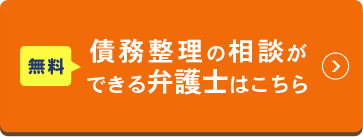
個人再生のよくある質問
個人再生とはどのような手続きですか?
個人再生とは、裁判所に申し立て、借金を最大1/10まで減額できる手続きです。
個人再生のメリットはなんですか?
任意整理(将来利息のカット)より減額効果が大きく、自己破産(残債の全額免除)よりデメリットが小さいことです。大幅な減額が必要なものの、自己破産ができない・したくないときにおすすめできます。
個人再生にはどのようなデメリットがありますか?
最長で約7年間程度ブラックリストになることや、官報への掲載、保証人のへの請求移行が挙げられます。特にブラックリスト期間中は、クレジットカードやローンが使えなくなるので、日常生活で不便に感じることも多いでしょう。
個人再生の費用相場や手続き期間はどのくらいですか?
費用はさまざまな条件で変わり、おおむね30万~70万円ほどかかります。手続き期間も個々のケースによりますが、依頼から和解成立までは半年程度が一般的です。
個人再生をするべきか悩んでいます。どこに相談したらよいですか?
個人再生の実績が豊富な法律事務所への相談をおすすめします。当サイトでも、無料相談可能な法律事務所を紹介しています。無料相談を利用して、あなたに合った借金の解決方法をアドバイスしてもらうとよいでしょう。→
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
個人再生のデメリットとして家族へ影響があることはありますか?
個人再生を行っても、家族もクレジットカードや分割払いが利用できなくなる、家族名義の財産も処分されてしまうといった直接的な影響は基本的にありません。しかし、以下のように家族にも影響が及ぶケースも存在するので注意が必要です。
- 借金返済のために、家賃や食費、娯楽費、子供の教育費などの支出の削減が必要な場合もある
- 家族が保証人・連帯保証人になっている場合、その家族が借金を肩代わりすることになる
- ローン返済中の債務者名義の車が没収され、同居家族も車が使えなくなる
- ブラックリスト期間中は子供の奨学金の保証人になれない
- 同居家族が使用していた家族カードが使えなくなる
個人再生をしたことは会社にバレるのでしょうか?
個人再生の手続きを行っても、裁判所や債権者から会社に通知が送られることはないので、個人再生を行った事実が会社にバレることは通常ありません。しかし、会社から借金をしている場合は、裁判所から債権者である会社に通知が届いてしまうので確実にバレます。
ただ、個人再生がバレたとしても、個人再生を理由とした解雇は認められていないため、個人再生後も同じ会社で働き続けられます。個人再生を会社にバレたくないという理由で債権者一覧に勤務先の会社を記載しなかった場合、申立ての棄却や刑事罰に問われるリスクがあるので絶対にやってはいけません。
個人再生できないケースはあるのでしょうか?
個人再生にはさまざまな要件があるため、どんな場合でも利用できるわけではありません。個人再生ができない主なケースとしては、以下のようなものがあります。
- 再生債権にかかる債務の総額が5,000万円を超えている
- 継続的かつ安定した収入が見込めない
- 生活保護を受給している
- 多額の財産を所有している
- 小規模個人再生で債権者の同意が得られなかった
- 裁判所への申立て費用が準備できない
- 個人再生の手続き後に新たな借入をした
- 財産や債権者を正確に報告しなかった
- 特定の債権者に借金を返済した
- 提出期限までに再生計画案を提出しなかった
個人再生で失うものは何ですか?
個人再生をしても、財産や仕事などを失うことは基本的にありません。ただし、ローン返済中の財産は債権者に引き上げられてしまう可能性があります。
個人再生の成功率はどのくらいですか?
裁判所が公表している司法統計によると、個人再生の成功率は例年90%を超えています。
| 令和5年度 |
92.2% |
| 令和4年度 |
92.1% |
| 令和3年度 |
92.7% |
| 令和2年度 |
93.4% |
| 令和元年度 |
93.7% |
しかし、7~8%程度の人が個人再生に失敗しているのも事実です。個人再生を成功させた人の多くは弁護士や司法書士に依頼しているため、個人再生を検討している場合は借金問題に強い弁護士や司法書士に相談しましょう。
参照:司法統計年報 | 裁判所