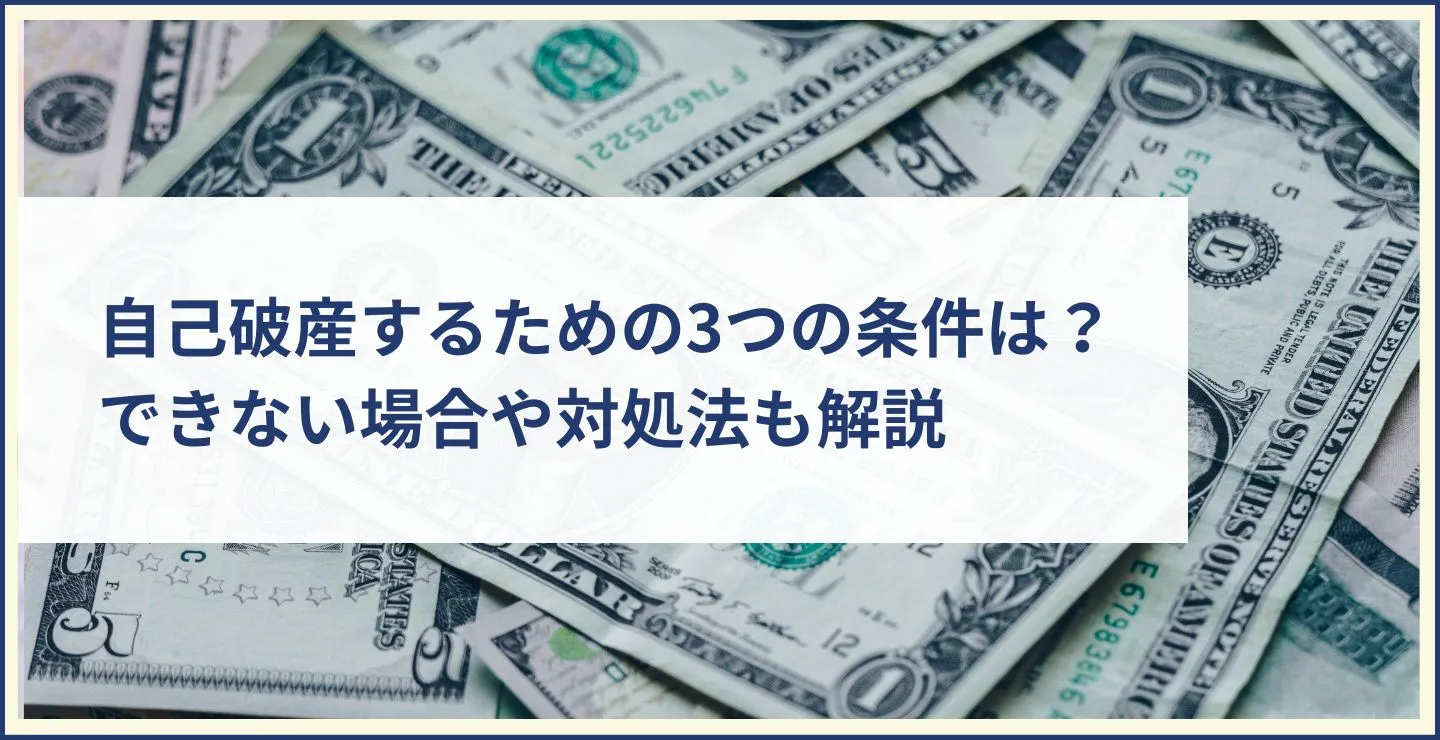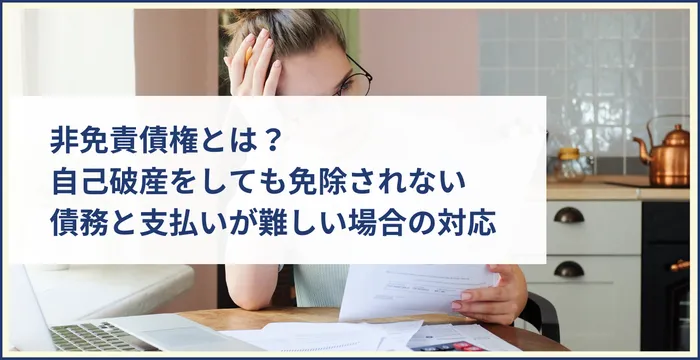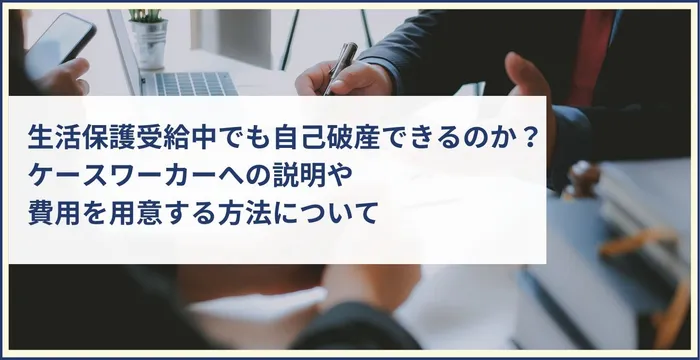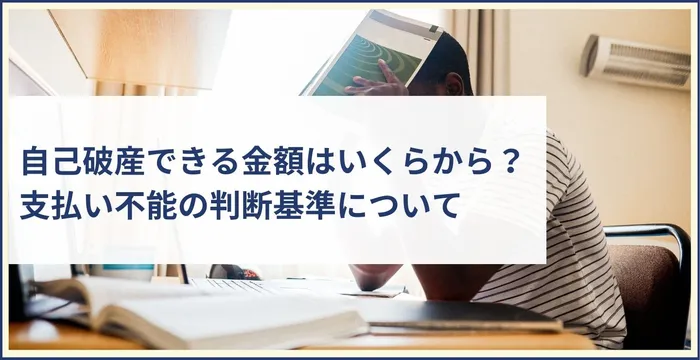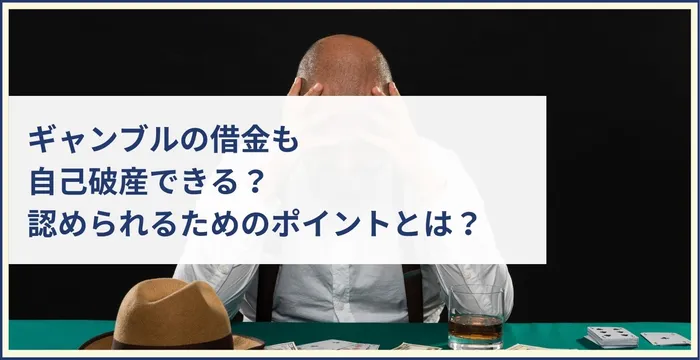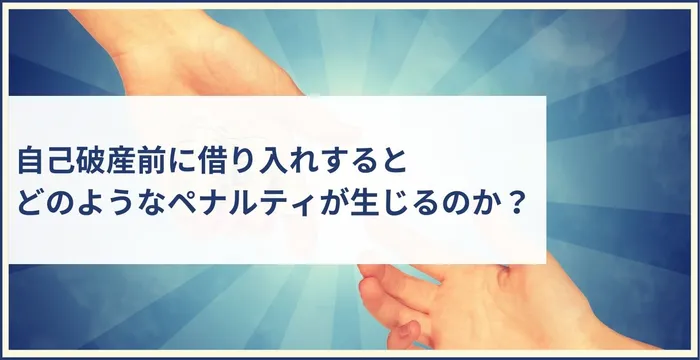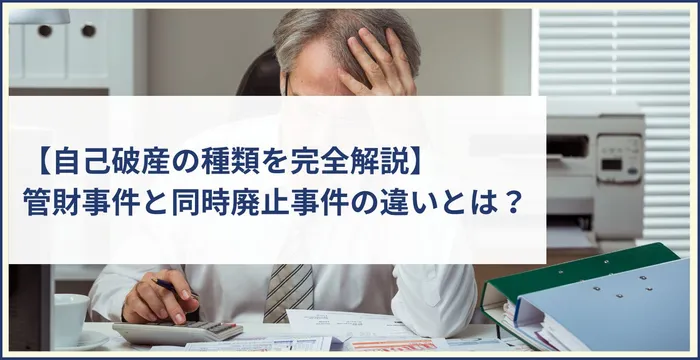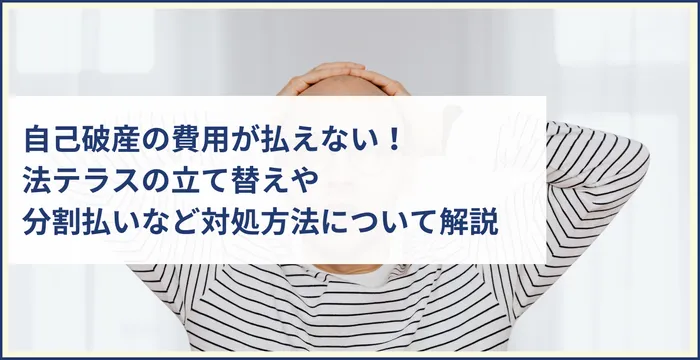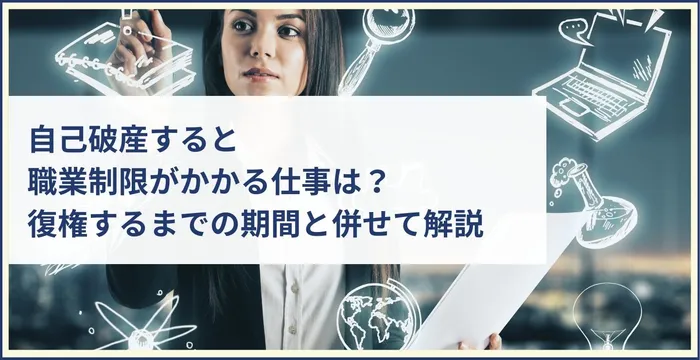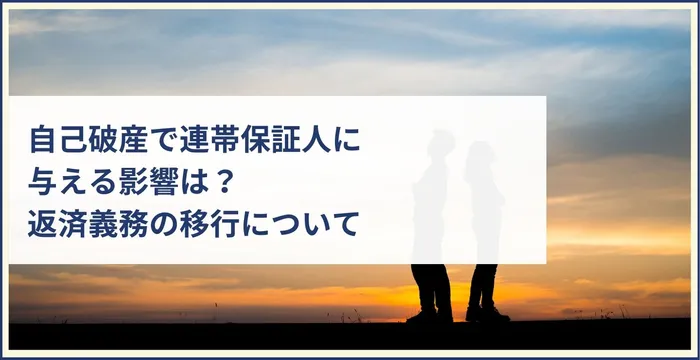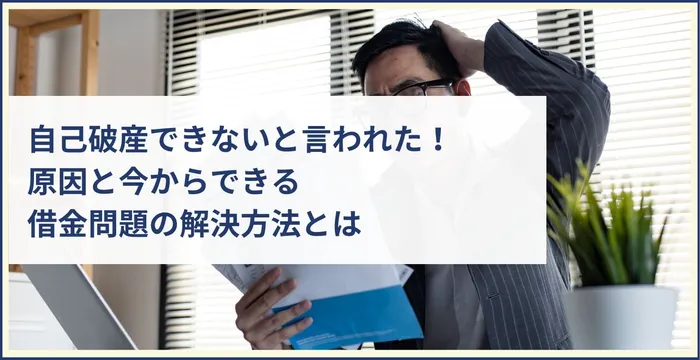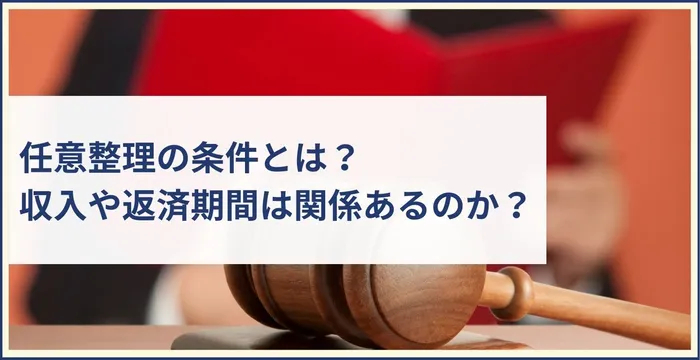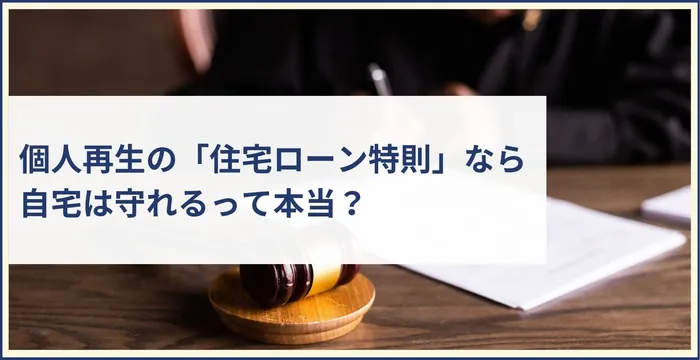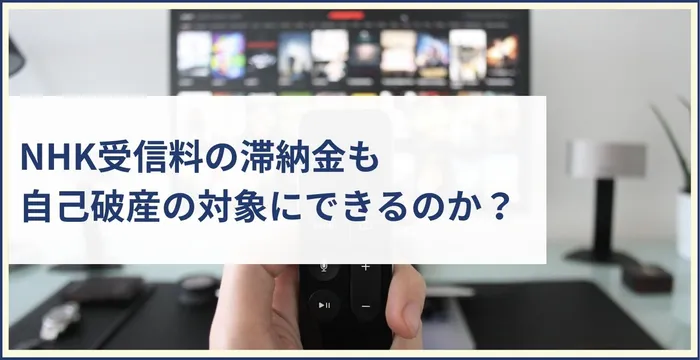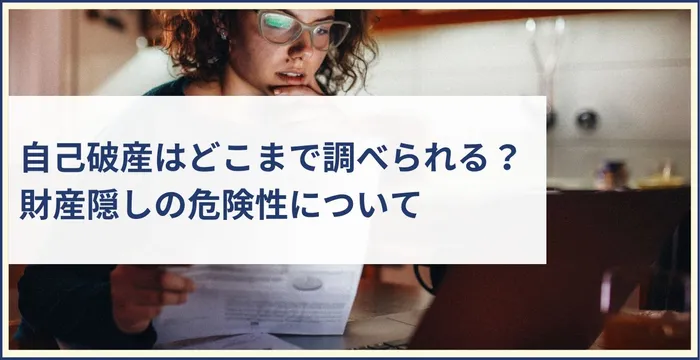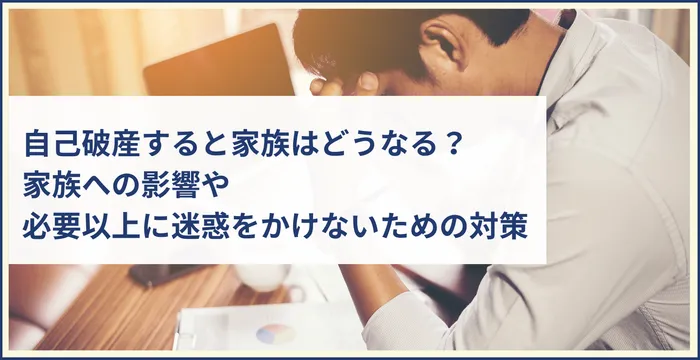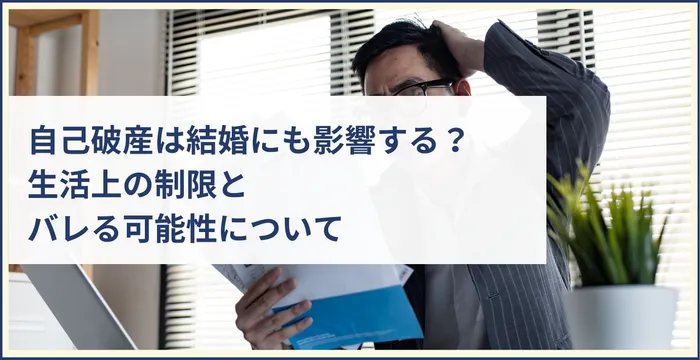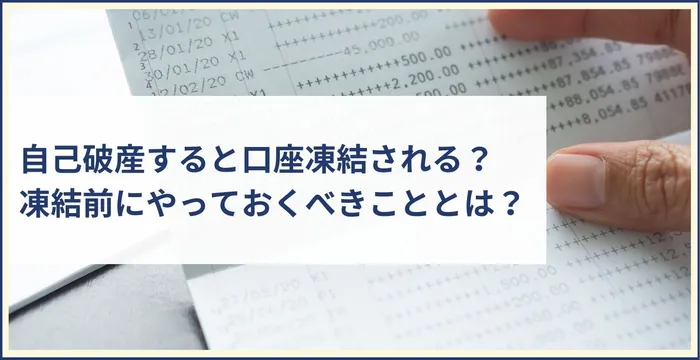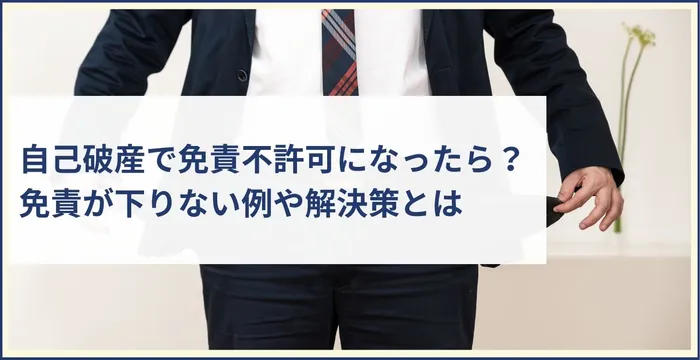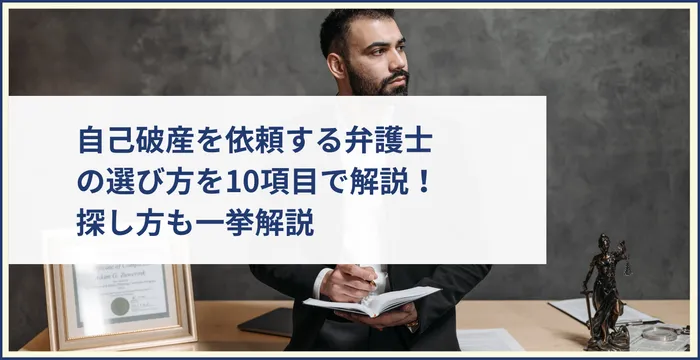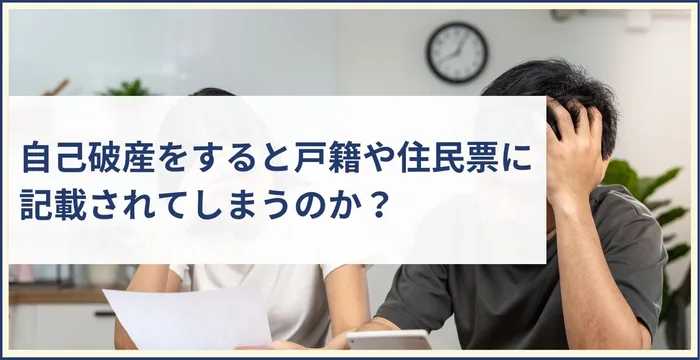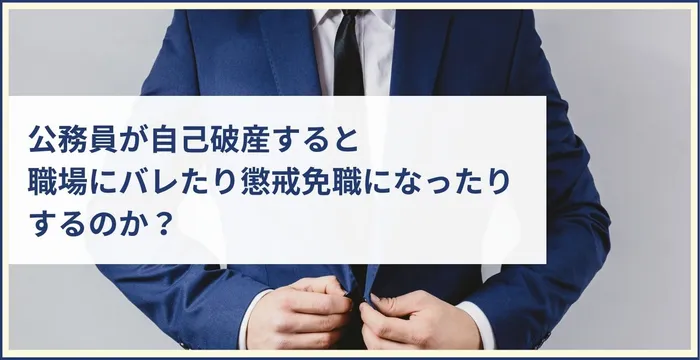自己破産するための条件3つ
自己破産は、どのようなケースでもできるわけではありません。
自己破産するためには、以下の3つの条件を満たしている必要があります。
- 借金が返済不能な状態になっている
- 借金が非免責債権のみではない
- 免責不許可事由に当てはまらない
1. 借金が返済不能な状態になっている
まず、借金が返済不能な状態に陥っている必要があります。
返済不能といえるかどうかは、以下の要素から総合的・客観的に判断されます。
- 借金総額とその内容
- 財産総額とその内容
- 収入・支出の金額
- 生活状況
借金総額の目安は、3〜5年での完済が難しいかどうかです。ただし借金総額の基準は明確にはされておらず、あくまでも目安です。実際に返済不能かどうかは裁判所が個別に判断します。
また、返済不能の状態が一時的なものではなく、継続していなければなりません。たとえば、長期的に支払えない状況に陥っているなら返済不能といえますが、たまたま出費がかさんで支払いできなくなっただけであれば「返済不能」とはいえないでしょう。
2. 借金が非免責債権のみではない
抱えている債務が「非免責債権」のみではないことも自己破産の条件のひとつです。
非免責債権とは、免除の対象にならない債務のことです。つまり、自己破産をしても免除されず、全額支払いが残ります。
非免責債権には、たとえば以下のものがあります。
- 税金(住民税・固定資産税・所得税・消費税など)
- 国民健康保険料
- 国民年金保険料
- 養育費
- 婚姻費用
- 一部の損害賠償請求権(飲酒運転による交通事故や詐欺、暴力、いじめなど)
- 従業員への給与や預り金、退職金(事業を営んでいる場合)
- わざと債権者名簿に記載しなかった債権
- 罰金
抱えている債務が非免責債権だけでどうしても支払えない場合は債務整理を検討するのではなく、たとえば住民税や固定資産税なら市区町村役場の税務担当部署、養育費であれば元配偶者に相談しましょう。分割払いを認めてもらえる可能性があります。
非免責債権の詳細については、以下の記事を参考にしてください。
3. 免責不許可事由に当てはまらない
「免責不許可事由」に当てはまらないことも、自己破産の条件としてあげられます。
免責不許可事由とは、該当すると借金が免除してもらえなくなる事項のことです。借金を負った理由や免責したい理由が免責不許可事由に該当すると、原則として自己破産が認められなくなります。
免責不許可事由にあたるのは、以下のような行為です。
- 財産を没収されるのを回避するため、財産を隠したり身近な人に譲ったりした
- 不利な条件で借り入れをしたり、クレジットカードの現金化を行ったりした
- 特定の債権者だけに返済した
- ギャンブルや浪費によって多額の借金を負った
- はじめから自己破産をするつもりで借金をした
- 帳簿を隠したり作り変えたりした
- 嘘の債権者一覧表を提出した
- 裁判所の調査に協力しなかった
- 破産管財人の業務を不正に妨害した
- 7年以内に自己破産したことがある
- 破産手続上の義務に違反した
ただし免責不許可事由に該当するからといって、必ずしも自己破産が認められないとは限りません。免責不許可事由に該当するとしても、免責を許可するかどうかは裁判所が判断するためです。
詳しくは、「免責不許可事由に該当しても自己破産が可能な場合もある(裁量免責)」で後述します。
参照:破産法第252条|e-Gov法令検索
自己破産の条件に当てはまる具体的なケース
ここからは、自己破産の条件に当てはまる具体的なケースを見ていきましょう。以下のケースに該当する場合、自己破産の条件を満たしているといえます。
- 長期入院が原因で借金の返済ができない状態である
- 失業してしまい公共料金を滞納している
- 生活保護を受給している
- 奨学金の返済が難しい状態にある
長期入院が原因で借金の返済ができない状態である
長期入院が原因で借金をした場合や、病気で収入が途絶えたためにもともとあった借金が返済できなくなったときは、自己破産できる可能性があります。
医療費や入院費用、働けない間の生活費などを工面するためにした借金は、免責不許可事由にも非免責債権にもあたらないためです。そのため、裁判所が返済不能と判断すれば自己破産は可能です。
なお、自己破産をする場合、弁護士に依頼していても一度は裁判所に出向かなければなりません。
しかし入院中で外出できないときは、出廷できない事情を弁護士に書面で説明してもらい、裁判所に認めてもらうことで、入院したまま破産手続きを進められることがあります。病気が原因で動けないときは、裁判所に出向けないことも含めて弁護士に相談するとよいでしょう。
失業してしまい公共料金を滞納している
失業によって収入が途絶え、公共料金を支払えないほど困窮している場合も、自己破産が認められる可能性があります。電気代やガス代、上水道料金といった公共料金は、自己破産で免除されない非免責債権に該当しないためです。
ただし公共料金は、多少滞納しただけでは金額がそれほど大きくならないことが多く遅延損害金の利率も低いため、公共料金だけを滞納している状況なら自己破産が適しているとはいえないケースもあります。
公共料金に加え、たとえば消費者金融からの借金やクレジットカードの利用料金なども長期間滞納しており、今度も支払えそうにないケースであれば、自己破産を検討する必要があるでしょう。
なお、公共料金のうち、下水道料金は非免責債権に該当します。そのため、自己破産をしても支払いが免除されないことを覚えておきましょう。
生活保護を受給している
生活保護受給中に自己破産することは可能です。たとえば、生活保護によって生活自体は安定してきたものの、過去の借金を支払えず滞納しているという場合は自己破産を検討するとよいでしょう。
むしろ、生活保護受給中に債務整理をするなら、自己破産しか選択できません。任意整理や個人再生といったほかの債務整理方法では、手続き完了後に借金が残り返済が必要になるためです。
| 任意整理 |
債権者との交渉によって借金の利息や遅延損害金をカットしてもらう手続き。残った借金を3〜5年程度で完済する必要がある。 |
| 個人再生 |
裁判所に申し立て、再生計画案を認めてもらうことで借金総額を5分の1〜10分の1程度に減額してもらう手続き。残った借金を原則3年で完済する必要がある。 |
税金で成り立っている生活保護費で借金を返済する行為は、「経済的に困窮している人を保護し、最低限の生活を保障する」という生活保護制度の趣旨に反します。そのため生活保護を受給している人には、返済義務の残る任意整理や個人再生は行えません。
もし、任意整理や個人再生をして生活保護費で返済すれば、生活保護費が受給できなくなるのはもちろん、すでに受給した生活保護費の返還や徴収金の支払いを要求されるおそれがあります。過去の借金も含め、生活保護費での返済はやめておきましょう。
なお、自己破産をしたからといって生活保護費の受給に影響することはありませんが、生活保護受給中に自己破産をする場合は、担当のケースワーカーに相談することをおすすめします。
生活保護受給中に自己破産する場合のケースワーカーへの説明や費用の捻出方法については、以下の記事を参考にしてください。
奨学金の返済が難しい状態にある
奨学金の返済が難しい場合、返済不能な状態であれば自己破産が可能です。返済義務のある奨学金は借金であり、非免責債権には該当しないためです。
ただし親に連帯保証人になってもらっているときは、親に対して残債が一括請求されてしまう点に注意しましょう。
返済できなければ、親もまた債務整理を検討しなければならなくなります。そのため、自己破産の手続きに入る前に親に相談すべきでしょう。
なお、親が連帯保証人になる人的保証制度ではなく、保証機関が連帯保証する機関保証制度を利用しているケースであれば、自己破産をしても親に影響を与えることはありません。
参照:機関保証制度について|独立行政法人日本学生支援機構
自己破産の条件に当てはまらない具体的なケース
ここからは、自己破産の条件に当てはまらないケースを紹介します。
以下に該当する場合、自己破産が認められない可能性があります。
- 借金額が少ない
- 療養中だが、収入を得られる見込みがある
- 税金や社会保険料を滞納しているのみ
- 借金のほとんどがギャンブルや浪費である
- 自己破産開始前に自らの財産を隠した
- 詐術による信用取引をした
- 帳簿の隠匿や偽造を行った
- 廉価処分を行った
- 偏頗弁済に該当する
- 裁判所に虚偽の債権者一覧表を提出した
- 過去7年以内にすでに自己破産済み
- 予納金の支払いができない状態である
借金額が少ない
借金額が少ない場合、前述した「借金が返済不能な状態になっている」という条件を満たしておらず、自己破産が認められない可能性があります。通常、借金額が少なければ返済できると判断されやすいためです。
借金額が少ないと判断されやすいのは、以下のようなケースです。
- 借金総額が100万円以下
- 借金総額が年収の3分の1以下に収まっている
借金額が少なくても、収入が少なかったり働けない事情があったりなど、客観的に見て返済不能であると判断できるケースであれば自己破産できることもあります。
しかし、借金額が多いケースに比べ、返済不能と判断されにくいことは理解しておきましょう。
なお、返済不能かどうかは、借金額だけでなく以下の要素も含めて総合的に判断されます。
- 毎月の返済額
- 収入・支出
- 預貯金額
- 加入している生命保険の解約返戻金の有無
- 不動産の保有状況
返済不能かどうかの判断基準については、以下の記事を参考にしてください。
療養中だが、収入を得られる見込みがある
療養中でも、収入を得られる見込みがあるなら返済不能と判断されず、自己破産ができない可能性があります。
たとえば以下のようなケースです。
カードローンで借り入れした50万円を返済中に過労で倒れ、数週間入院した。一時的に収入が減少し、さらに医療費で家計が苦しくなったが、職場復帰したあとも入院前と同じ条件で勤務しているため安定した収入がある。
上記の例では、借金総額が50万円と少なく、入院によって収入は減少したものの、一時的なものであり職場復帰後は入院前と同じ収入を得ています。
そのため長期的に返済できなくなっているといえず、返済不能とは判断されない可能性が高いでしょう。
また、このようなケースであれば、仮に自己破産できたとしても、自己破産をするメリットよりデメリットのほうが大きい可能性があります。
一時的な収入の減少を補いたいなら、債務整理よりも緊急小口資金や総合支援資金(生活支援費)といった、公的支援を検討したほうがよいでしょう。
| 緊急小口資金 |
低所得世帯が緊急かつ一時的に生活に困窮した場合に、10万円を限度に貸付を受けられる制度。返済猶予は2カ月、連帯保証人なし・無利子で借りられる。 |
総合支援資金
(生活支援費) |
失業や収入の減少で生活に困窮している低所得世帯を対象とした貸付制度。原則3カ月間、生活費として月15万円または20万円を上限に貸付を受けられる。 |
収入の減少が一時的なものであれば、このような制度で十分カバーできる場合もあるでしょう。
ただし、貸付を受けるには収入や返済の見通しが立つかといった条件があり、審査に通らなければなりません。詳細は、各市区町村の社会福祉協議会で確認してください。
税金や社会保険料を滞納しているのみ
滞納している債務が税金や社会保険料といった非免責債権のみの場合は、自己破産ができません。前述した、「借金が非免責債権のみではない」という条件をクリアできていないためです。
非免責債権には、以下のものが該当します。
- 税金(住民税・固定資産税・所得税・消費税など)
- 国民健康保険料
- 国民年金保険料
- 養育費
- 婚姻費用
- 一部の損害賠償請求権(飲酒運転による交通事故や詐欺、暴力、いじめなど)
- 従業員への給与や預り金、退職金(事業を営んでいる場合)
- わざと債権者名簿に記載しなかった債権
- 罰金
たとえ200万円や300万円という高額の滞納があっても、それらの債務がすべて非免責債権に該当するなら全額自力で支払っていかなければなりません。
しかし自己破産できないのは、債務がすべて非免責債権だったケースです。非免責債権以外にも借金があり、返済できない状況になっているなら自己破産が認められる可能性があります。
なお、非免責債権を支払えないからといって、税金や社会保険料を支払うために借金をし、納付したあとに自己破産するのは絶対にやめましょう。はじめから自己破産をするつもりで借金をする行為は、免責不許可事由に該当するためです。
自己破産が認められないだけでなく、詐欺破産罪という罪に問われるおそれがあります。
借金のほとんどがギャンブルや浪費である
借金のほとんどがギャンブルや浪費だった場合、自己破産できない可能性があります。「免責不許可事由に当てはまらない」という条件を満たせなくなるためです。(破産法第252条第1項第4号)
ギャンブルや浪費の具体例は以下のとおりです。
- ギャンブル(パチンコ・スロット・競馬・競艇・競輪など)で大負けした
- 株・FXなどに多額の資金を投資した
- 1回あたり2万円以上の外食を繰り返した
- キャバクラ・ホストクラブで豪遊した
- ブランド品や時計、宝石などを購入した
- ソーシャルゲームで大金を課金した
たとえば消費者金融から借りた200万円を競馬につぎ込み、返済できなくなったようなケースをいいます。
このような理由でつくった借金は、子どもや生活のためにした借金とは異なり、絶対に必要だったとはいえません。そのため、自己破産を認めてもらえない場合があることを覚えておきましょう。
ギャンブルで負った借金の自己破産が認められるためのポイントについては、以下の記事を参考にしてください。
自己破産開始前に自らの財産を隠した
没収されるのを回避する目的で自己破産前に自らの財産を隠す「財産隠し」も、自己破産が認められなくなる可能性のある行為です。借金の原因がギャンブルや浪費だったケースと同様に、免責不許可事由に該当するためです。(破産法第252条第1項第1号)
財産を隠せばその分債権者に配当する財産が減り、債権者が不利益を受けます。詐欺破産罪に問われるおそれもあるため、絶対に行わないようにしましょう。
財産隠しに該当するのは、たとえば以下のようなケースです。
- 預金を没収されるのを防ぐため、お金を引き出しタンス預金をした
- 複数ある預金口座のうち、一部の預金口座の存在を黙っておく
- 破産手続きが終わるまで、身近な人に貴金属やブランド品を預かってもらう
- 不動産や自動車の名義を自己破産直前に変更する
- 解約返戻金の振込先に他人名義の預金口座を指定する
- 手放したくない財産を自己破産直前に贈与した
- 自己破産直前に離婚し、元配偶者に財産分与した
破産管財人は、申立書を精査するのはもちろん、申立人・代理人からの意見聴取や転送された郵便物の確認、預金口座の照会などを行い財産を徹底的に調査します。そのため上記のような方法で財産隠しを企てても、バレてしまう可能性は高いでしょう。
自己破産を成功させたいなら、疑われるような行動はくれぐれも行わないようにしましょう。
詐術による信用取引をした
自己破産を申し立てる1年前から破産手続開始決定の日までに借金をすると、自己破産が認められなくなる可能性があります。詐術による信用取引をしたとして、免責許可事由に該当するためです。(破産法第252条第1項第5号)
たとえば、借金を借金で返す自転車操業に陥っており、借金を繰り返した結果自己破産の手続きに入った場合、近い将来返済できなくなり、自己破産をせざるを得なくなることは本人もよくわかっていたと考えられます。
そのため、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら借金をしたとみなされ、自己破産が認められなくなるおそれがあります。
なお、借りた当初は本当に返済するつもりがあったとしても、返済能力がない状態で借り入れをすること自体がペナルティの対象になり得る点に注意しましょう。
自己破産前に借り入れをした場合のペナルティについては、以下の記事を参考にしてください。
帳簿の隠匿や偽造を行った
わざと帳簿を隠匿したり偽造したりすると、免責不許可事由のひとつである「帳簿隠匿行為等」に該当し、自己破産が認められなくなるおそれがあります。(破産法第252条第1項第6号)
たとえば個人事業主なら、自己破産の際に確定申告書や帳簿関係を提出する必要があります。
単なる記帳ミスであれば問題にならないと考えられますが、財産を隠す目的で意図的に数字を偽ったり隠匿したりすると、裁判所が破産者の資産状況を把握しづらくなり破産手続きに影響が出ます。
その場合、自己破産できなくなるだけでなく破産詐欺罪に問われる可能性もあるため、絶対に行わないようにしましょう。
廉価処分を行った
廉価処分を行った場合も免責不許可事由に該当し、自己破産できなくなる可能性があります。(破産法第252条第1項第2号)
【廉価処分とは】
ヤミ金のような高利業者から借金をしたり、クレジットカードの現金化などを行ったりして自己破産を遅らせること。
クレジットカードの現金化とは、クレジットカードのショッピング枠を使って購入した商品を、安い金額で換金する行為をいいます。
よくあるのは、ギフトカードやゲーム機、ブランド品といった換金率の高い商品を購入したあと、買取業者に買い取ってもらって現金を得るパターンです。
クレジットカードの現金化は、消費者庁や金融庁が注意喚起を行っており、各クレジットカード会社も禁止している行為です。一時的に現金を得られてもその場しのぎにしかならないため、いくら現金が必要でも行わないようにしましょう。
当然、ヤミ金にも手を出してはいけません。ヤミ金に手を出すと、法外な金利を適用されたり、悪質な取り立ての被害に遭ったりする危険性があります。
また、ヤミ金は自己破産の対象にならないため、自己破産ができたとしても問題が残ってしまいます。万が一ヤミ金業者から借金をしてしまったときは、一刻も早く弁護士に相談しましょう。
参考:クレジットカード現金化について|消費者庁
偏頗弁済に該当する
偏頗弁済に該当する行為を行ったときも、自己破産ができなくなる場合があるため注意しましょう。
【偏頗(へんぱ)弁済とは】
特定の債権者だけに返済すること。免責不許可事由にあたり、免責が認められなくなる可能性があるほか、返済を受けた債権者は受け取った金銭を破産管財人に返還する必要がある。(
破産法第252条第1項第3号)
偏頗弁済には、たとえば以下のようなケースが該当します。
- 保証人に迷惑をかけたくないため、自己破産前に保証人にだけ一括返済する
- 返済不能に陥ってから、親や友人、会社など、自己破産したことを知られたくない人にだけ返済する
自己破産前に行った返済がすべて偏頗弁済にあたるとは限りません。
しかし、まだ返済期日が来ていないにもかかわらず、自己破産の影響を与えないよう一部の債権者だけに返済する行為は、ほかの債権者にとって不公平で利益を害する行為であるといえるでしょう。
裁判所に虚偽の債権者一覧表を提出した
裁判所に虚偽の債権者一覧表を提出すると、自己破産が認められなくなる場合があります。嘘の内容を記載し提出する行為は、免責不許可事由に該当するためです。(破産法第252条第1項第7号)
【債権者名簿とは】
自己破産を申し立てるときに申立書の添付書類として提出する書類のことで、債権者全員の名称や現在の借入残高、借り入れの原因などが記載される。
たとえば、迷惑をかけたくないからといって親や友人、会社などの特定の債権者をわざと記載しなかったり、実際には取引のない債権者を記載したりといったケースをいいます。
なお、わざとではなくミスによって一部の債権者が一覧表から漏れていた場合に債権が免責されるかどうかは、記載漏れに気づいたタイミングによって異なります。
| 記載漏れに気づいたタイミング |
概要 |
| 破産手続開始決定前 |
速やかに裁判所に報告し、上申書・修正した債権者一覧表を提出すれば問題なく進められる。 |
| 破産手続開始決定後 |
【同時廃止事件の場合】
上申書・修正した債権者一覧表を裁判所に提出し、記載が漏れていた債権者に「開始決定通知書」を送付すれば問題なく進められる。
【管財事件の場合】
破産管財人に上申書・修正した債権者一覧表を提出し、以下の対応を依頼すれば問題なく進められる。
・記載が漏れていた債権者への「開始決定通知書」の送付
・裁判所への「新たに知れたる債権者等への発送報告書」の提出 |
| 免責許可決定確定後 |
以下の事情を考慮したうえで免責が許可されるかが決まる。
・記載漏れに破産者の故意・過失があったか
・破産者に故意・過失があった場合、その過失が軽微かどうか
・記載が漏れていた債権者が破産手続きの開始を知っていたか |
記載漏れに気づいたら、速やかに裁判所に報告しましょう。意見申述期間が終わるまでであれば、裁判所や破産管財人に上申書と修正した債権者一覧表を提出することで問題なく進められます。
ただし、免責許可決定確定後はすでに手続きが終結しているため、記載漏れに気づいても債権者一覧表の修正ができません。
免責が許可されなければ、記載が漏れていた債権者には免責の効力が及ばないため、通常どおり借金の返済を継続しなければならない点に注意しましょう。
過去7年以内にすでに自己破産済み
過去7年以内に自己破産し、免責許可を受けている場合、免責不許可事由に該当します。つまり、前回から7年以上経過していない自己破産は原則として認められません。(破産法第252条第1項第10号)
そのほか、7年以内に以下の決定を受けているケースも同様です。
- 個人再生手続きのうち「給与所得者等再生」を申し立て、再生計画の認可決定を受けた
- 個人再生後に事情によって返済できなくなり、「ハードシップ免責」の適用を受けた
給与所得者等再生とは、会社員や公務員を対象とした個人再生手続きのことをいい、ハードシップ免責とは、個人再生後の返済が免除される制度をいいます。
前回の自己破産や個人再生から7年経っていないからといって、必ずしも自己破産が認められないとは限りません。たとえば、どうしても今自己破産を行わなければならない事情があるときは、裁判所が自己破産を認めてくれる可能性もあります。
ただし、1回目の自己破産と自己破産をするに至った原因が同じ場合は、認めてもらいにくい点に注意しましょう。1回目も2回目も原因がギャンブルだった場合、反省していないと判断されるためです。
また、2回目以降の自己破産は、同時廃止事件ではなく管財事件になる傾向がある点も要注意です。
| 同時廃止事件 |
破産手続が開始するとともに廃止される手続きのこと。破産管財人が選任されないため、管財事件よりも手間や費用がかからない。処分が必要になるほどの財産がなく、免責不許可事由もない場合に適用されることが多い。 |
| 管財事件 |
裁判所によって破産管財人が選任され、破産管財によって財産を調査・処分される手続き。破産管財人への報酬が発生する分費用が高くなる。一定の財産を所有している場合や免責不許可事由に該当するケースで適用されることが多い。 |
同時廃止事件と管財事件との違いについては、以下の記事を参考にしてください。
予納金の支払いができない状態である
予納金の支払いができなければ、自己破産は難しいでしょう。
予納金とは、自己破産を申し立てるときに裁判所に支払う費用のことです。金額は、手続きの種類によって異なります。たとえば同時廃止事件であれば2万円程度で済む場合もありますが、管財事件になると20〜50万円程度かかります。
内訳は以下のとおりです。
| 申立手数料 |
1,500円程度 |
| 郵便切手代 |
4,400円程度 |
| 官報公告費 |
1万〜1万9,000円程度 |
| 破産管財人への報酬 |
20万〜50万円程度
【内訳】
・同時廃止事件:0円
・管財事件:50万円程度
・少額管財事件:20万円程度
|
官報公告費とは、国の機関紙である「官報」に自己破産の事実や破産者の氏名・住所などを掲載する際にかかる費用です。
また、少額管財事件とは、財産はあるものの管財事件にするほどでもないときに適用される手続きです。
弁護士や司法書士などの専門家に手続きを依頼するなら、上記の費用に加えて専門家費用も別途かかることを念頭に置いておきましょう。
費用の捻出が難しいときは申立てまでに積み立てるか「法テラス」を利用する
前項で解説したとおり、専門家に手続きを依頼するなら予納金に加え、専門家費用がかかります。
弁護士に自己破産手続きを依頼するときの費用相場は、20万〜80万円程度です。費用の捻出が難しい場合は、以下の方法を試してみましょう。
- 依頼した専門家に相談し、申し立てまでに積み立てる
- 「法テラス」を利用する
弁護士事務所の中には、弁護士費用を分割で支払うのと同時に、予納金を積み立てられるところもあります。この場合、ある程度お金を積み立てたところで申立てを行ってくれるため、相談の時点で費用が用意できてなくても問題ありません。
ただし対応は事務所によって異なるため、そのような対応をしてくれるかどうかは相談の際に確認するようにしてください。
法テラスとは、費用の問題で専門家への依頼が難しい人を対象に、無料の法律相談や専門家費用の立替えを行っている国の機関です。生活保護受給中なら予納金の援助を受けられるほか、専門家費用を免除してもらえる可能性もあるため、相談してみるのもよいでしょう。
参照:無料法律相談・弁護士等費用の立替|日本司法支援センター法テラス
自己破産の費用が払えないときの対処法については、以下の記事を参考にしてください。
免責不許可事由に該当しても自己破産が可能な場合もある(裁量免責)
前章で解説したとおり、免責不許可事由に該当すると原則として自己破産は認められません。破産法では、「免責不許可事由に該当しない場合に自己破産を認める」と定められているためです。
ただし以下のとおり、裁判所には「裁量免責」が認められており、最終的に免責を許可するかどうかの判断は裁判所に委ねられています。
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
引用元 破産法第252条第2項|e-Gov法令検索
そのため、免責不許可事由に該当していても自己破産できるケースもありますが、その場合、自己破産が認められるとしても管財事件が適用されるのが一般的です。
管財事件では、裁判所が選任した破産管財人によって面談や財産調査が行われ、自己破産に至った経緯や借金の理由、債務状況を細かく確認されます。中には、反省文を求められるケースもあります。
重要なのは、破産管財人の調査には積極的に協力し、面談でも誠実に対応することです。
破産管財人は、面談での破産者の様子や事情、反省文の内容などから「免責許可を決定すべきかどうか」を判断するためです。破産管財人が免責許可すべきと判断すれば免責は許可され、借金はゼロになります。
なお、裁量免責となる可能性があるのは、以下のようなケースです。
- ビットコインを購入していたが、自己破産の直接の原因ではなかった
- 買い物依存症が原因で大量に買い物をしてしまった
- クレジットカードの現金化を行ったが少額だった
- 仕事の付き合いで競艇をしていた
- パチンコが原因で借金をしたが、金額が大きくなく本人に反省の姿勢が見られる
- 生活保護受給中にギャンブルや飲酒が原因で借金をしたが病気のため働けず、生活を再建するには自己破産しかなかった
- 過去7年以内に自己破産をしているが、十分に反省している
ただし、上記と同様のケースだからといって、必ずしも免責が受けられるとは限りません。免責となる可能性があるかどうかは、弁護士にアドバイスをもらうのがよいでしょう。
自己破産をするのに注意が必要な人
自己破産が認められれば、非免責債権以外の借金はゼロになります。しかし、働いている環境や自己破産後にどうしたいかなど、状況によっては自己破産を選択するのに慎重になったほうがよいケースもあります。
以下に該当する人は、よく考えてから自己破産を選択するようにしましょう。
- 職業制限に対応できない人
- 自宅を残したい人
- どうしても残したい財産がある人
- 保証人へ迷惑がかかるのが嫌な人
職業制限に対応できない人
職業制限に対応できない人は、自己破産の解決方法を検討したほうがよい可能性があります。自己破産を行うと一部の職業に制限がかかり、一定期間就業できなくなるためです。
職業・資格制限を受けるのは、たとえば以下のような職業です。
- 士業(弁護士・司法書士・税理士など)
- 警備員
- 生命保険募集人
- 一部の公務員(教育委員会・公正取引委員会の委員など)
- 銀行の取締役・執行役・監査役
- 保険会社の取締役・執行役・監査役
- 派遣元責任者 など
上記の職業に就けなくなるのは、破産手続開始決定から復権するまでです。ほとんどのケースは免責決定後に復権できますが、数カ月間は就業できなくなるため生活に影響が出る人も少なくないでしょう。
また、場合によっては、勤務先に事情を話して職業・資格制限を受けていても勤務できる部署に異動させてもらう必要性も出てきます。
自己破産したことを知られてしまうという問題も発生するため、勤務先に知られたくないなら、自己破産ではなく任意整理や個人再生といったほかの債務整理方法を検討すべきでしょう。
復権するまでの期間については以下の記事を参考にしてください。
自宅を残したい人
自宅を残したい人も、自己破産には慎重になったほうがよいでしょう。自己破産をすると、住宅をはじめ、基本的には以下にあげるもの以外の財産を没収されてしまうためです。
| 現金 |
99万円以下 |
| 差押え禁止財産 |
・生活必需品(家財道具・寝具・衣類など)
・仏壇や位牌
・印鑑
・年金受給権
・生活保護受給権
・児童手当受給権 |
| 新得財産 |
破産手続開始決定後に取得した給料など |
| 破産管財人が放棄した財産 |
・市場価値がない、または低いもの
・買い手がつかない財産
・売却までに時間がかかる財産
・多額の管理費用がかかる財産 |
このうち、99万円以下の現金や差押え禁止財産、新得財産を「自由財産」といいます。
なお、住宅ローンが残っており、抵当権が設定されている場合、自宅は破産手続開始決定後競売にかけられます。
自宅を残したいなら、整理対象を選べる任意整理や、「住宅ローン特則」を利用すれば住宅を残したまま債務整理できる可能性のある個人再生を検討したほうがよいでしょう。
どうしても残したい財産がある人
車や高級時計など、どうしても残したい財産がある人も自己破産を検討する際には注意が必要です。
前項でも解説したとおり、自己破産をする場合に手元に残せる財産は限られているためです。どうしても残したい財産があるなら、自己破産を選択しないほうがよいかもしれません。
ただし、自己破産には「自由財産拡張制度」というものがあります。
【自由財産拡張制度とは】
自由財産以外の財産でも、裁判所に認めてもらうことで一定の財産を「自由財産」として扱えるようになる制度。
拡張が認められ、自己破産後も手元に残せる可能性があるのは以下のような財産です。
- 合計20万円以下の預貯金
- 合計20万円以下の生命保険解約返戻金
- 評価額20万円以下の車
- 支給見込額の8分の1が20万円以下の退職金
- 居住用家屋の敷金返還請求権
- 電話加入権
不動産や有価証券など、上記以外の財産は原則拡張が認められません。ただし、事情により拡張が必要・相当といえる場合は、例外的に拡張が認められる可能性があります。
なお、自由財産の拡張が必要になるのは、管財事件になったケースです。同時廃止事件になるケースでは、そもそも破産者が処分できるような財産を所有していないため、自己破産をしても財産を失う心配がありません。
保証人へ迷惑がかかるのが嫌な人
保証人つきの借金があり保証人に迷惑をかけたくない人は、自己破産を選択しないほうがよい場合があります。自己破産をすると、非免責債権以外の債務全てが整理対象になるためです。
保証人つきの借金がある状態で自己破産すると、債権者は保証人に残債を一括請求します。保証人は返済を拒否できないため、もし支払う資力がなければ保証人も債務整理を検討しなければならなくなるでしょう。
家族や友人、会社の関係者などに保証人になってもらっているなら、自己破産をする前にまず保証人に相談しましょう。もしくは、任意整理で借金問題を解決できないか考えてみることをおすすめします。
任意整理は、債務整理の中で唯一整理対象を選択できる方法です。保証人つきの借金を整理対象から外して任意整理すれば、保証人に迷惑がかかることはありません。
自己破産で連帯保証人に与える影響については、以下の記事を参考にしてください。
自己破産できない場合の対処法
自己破産の条件に該当せず、自己破産できないときは、以下の方法も検討してみましょう。
自己破産できない原因と、今からできる借金問題の解決方法については以下の記事を参考にしてください。
即時抗告(異議申立て)
免責不許可事由に該当し、免責が許可されなかった場合は、「即時抗告(異議申立て)」をする方法があります。
【即時抗告(異議申立て)とは】
免責不許可の決定をした地方裁判所に対し、不服を申し立てること。免責を許可するか、再度検討してもらうことが可能。即時抗告をしても決定が覆らない場合、地方裁判所の上級裁判所である高等裁判所にて再審理が行われる。
即時抗告をしても、結果が変わるとは限りません。しかし裁判所の決定が覆る可能性はゼロではないため、諦めず即時抗告を行うのもひとつの手段でしょう。
注意点は、即時抗告を行えるのは免責不許可決定を受けた日から1週間以内である点です。迷っていると、あっという間に期限が過ぎてしまいます。
決定に納得がいかないときは、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
任意整理
自己破産ができない場合、任意整理で問題を解決できないか検討してみましょう。
任意整理は、債権者と直接交渉する手続きです。和解できれば利息や遅延損害金をカットしてもらえる可能性があり、残った借金は3〜5年程度で完済します。
債権者と和解できる条件は以下のとおりです。
- 安定した収入がある
- 任意整理後3〜5年程度で完済できる
- 給料や財産を差し押さえられていない
また、任意整理には以下のようなメリット・デメリットがあります。
| メリット |
・借金の原因を問われない
・裁判所が関与しないため手続きが比較的簡単
・整理対象を選べる
・職業・資格制限を受けない
・官報に載らない |
| デメリット |
・元金自体は減額されないのが原則
・返済義務が残るため安定収入が必要
・債権者が交渉に応じてくれない場合もある
・ブラックリストに載る |
任意整理では、借金の原因が問われません。たとえばギャンブルや浪費が原因で借金をつくってしまったケースでも、債権者と和解できれば任意整理が可能です。
ただし交渉に応じるかどうかは債権者次第であり、必ずしも任意整理できるとは限らない点に注意が必要です。
また、任意整理では利息や遅延損害金はカットできても、肝心の元金は原則減額されません。そのため、借金総額や収入によっては任意整理では問題を解決できない可能性があります。
自己破産と同様に、ブラックリストに載るというデメリットもあります。
任意整理の条件や任意整理できるケース・できないケースについては、以下の記事を参考にしてください。
個人再生
自己破産ができないなら、個人再生を検討するのもよいでしょう。
個人再生は、裁判所に個人再生後の返済計画を指す「再生計画案」を提出し、借金の減額を認めてもらう債務整理方法です。自己破産とは異なり返済義務は残るものの、住宅ローンを除く借金総額を5分の1〜10分の1程度に減額できる可能性があります。
個人再生の条件は以下のとおりです。
|
小規模個人再生手続 |
給与所得者等再生手続 |
| 概要 |
個人事業主・フリーランスなどが対象の個人再生手続き |
会社員・公務員などが対象の個人再生手続き |
| 条件 |
・借金総額が5,000万円以下
・返済できる見込みがある |
・借金総額が5,000万円以下
・返済できる見込みがある
・継続的な収入があり、その金額の変動が小さい |
| 個人再生後の最低弁済額 |
最低弁済額・清算価値のうち多い金額 |
最低弁済額・清算価値・2年分の可処分所得のうち多い金額 |
最低弁済額は、以下のように借金総額に応じて決まっています。
| 借金総額 |
最低弁済額 |
| 100万円未満 |
借金総額 |
| 100万円以上500万円以下 |
100万円 |
| 500万円超1,500万円以下 |
借金総額の5分の1 |
| 1,500万円超3,000万円以下 |
300万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 |
借金総額の10分の1 |
清算価値は所有している財産の合計額、可処分所得は収入から税金や社会保険料などを差し引いた手取り収入のことです。
なお、個人再生には以下のようなメリット・デメリットがあります。
| メリット |
・借金の原因を問われない
・自宅を残せる可能性がある
・ローンが終わっていれば車も残せる
・職業・資格制限を受けない |
| デメリット |
・返済義務が残るため安定収入が必要
・所有している財産や収入が多い場合は個人再生後の返済額が高額になる可能性がある
・整理対象を選べない
・官報に掲載される
・ブラックリストに載る |
個人再生も任意整理と同様に、借金の原因がギャンブルや浪費などであっても問題ありません。自宅や車を残せる可能性がある点や職業・資格制限を受けないところもメリットです。
ただし返済義務は残るため、安定した収入が必要です。また、個人再生後の返済額には所有している財産や収入が影響するため、たとえば高級車を所有している場合や高収入を得ているケースでは、思ったより借金が減額されないことがある点に注意しましょう。
なお、整理対象を選べない・官報に載るといったデメリットは自己破産と同じです。
個人再生で住宅を残せる「住宅ローン特則」については、以下の記事を参考にしてください。
まとめ
自己破産の条件について解説しました。
自己破産が認められるためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 借金が返済不能な状態になっている
- 借金が非免責債権のみではない
- 免責不許可事由に当てはまらない
たとえば自分では「もう返済できない」と思っていても、裁判所が返済不能であると判断しなければ自己破産はできません。
また、債務が税金や国民健康保険料、養育費といった、自己破産で免除されない「非免責債権」だけの場合も自己破産の対象にはなりません。
そのほか、免責が許可されない可能性のある「免責不許可事由」に該当しないことも条件のひとつです。
ただし、免責不許可事由については、該当していても裁判官が免責すべきと判断したときは免責を受けられる可能性があるため、当てはまったからといって自己破産できないとは限りません。
自己破産が認められない場合でも、即時抗告や任意整理、個人再生といった方法で問題を解決できることもあります。自分のケースで免責を受けられるかどうかがわからないときや、自己破産が認められない可能性があるときは、弁護士に相談するとよいでしょう。
自己破産の条件に関するよくある質問
家族の収入は自己破産できるかどうかに関わってくる?
家族の収入が自己破産できるかどうかを左右することはありません。
破産者と家族が同一生計の場合、家族の給料明細や確定申告書などの提出を求められますが、それはあくまでも裁判所が家計の流れを把握するためです。
たとえ家族が高収入でも、だからといって自己破産できなくなったり家族の財産が没収されたりといったことはありません。
生活保護受給者でも自己破産はできますか?
生活保護受給者でも、自己破産は可能です。むしろ、任意整理や個人再生といったほかの方法では返済義務が残ってしまうため、債務整理をするなら自己破産しか選択できません。
生活保護制度の趣旨は、「生活に困窮する受給者を保護し、最低限度の生活を保障する」というものです。そのため、生活保護費での借金返済は禁止されています。
専業主婦でも自己破産はできますか?
専業主婦でも自己破産は可能です。自己破産は、任意整理や個人再生のように安定収入を条件としていないためです。
ただし自己破産をする際は、裁判所費用や弁護士費用などがかかります。そのため、費用が用意できなければ申し立ては難しいでしょう。
費用に不安があるときは法テラスの無料法律相談や立替制度を活用し、法テラスと契約している弁護士に依頼することをおすすめします。
年金受給者でも自己破産はできますか?
年金受給者でも自己破産は可能です。定期的に収入があっても、返済不能に陥っており借金が非免責債権のみではない、免責不許可事由にあたらないといった条件を満たしていれば自己破産は認められます。