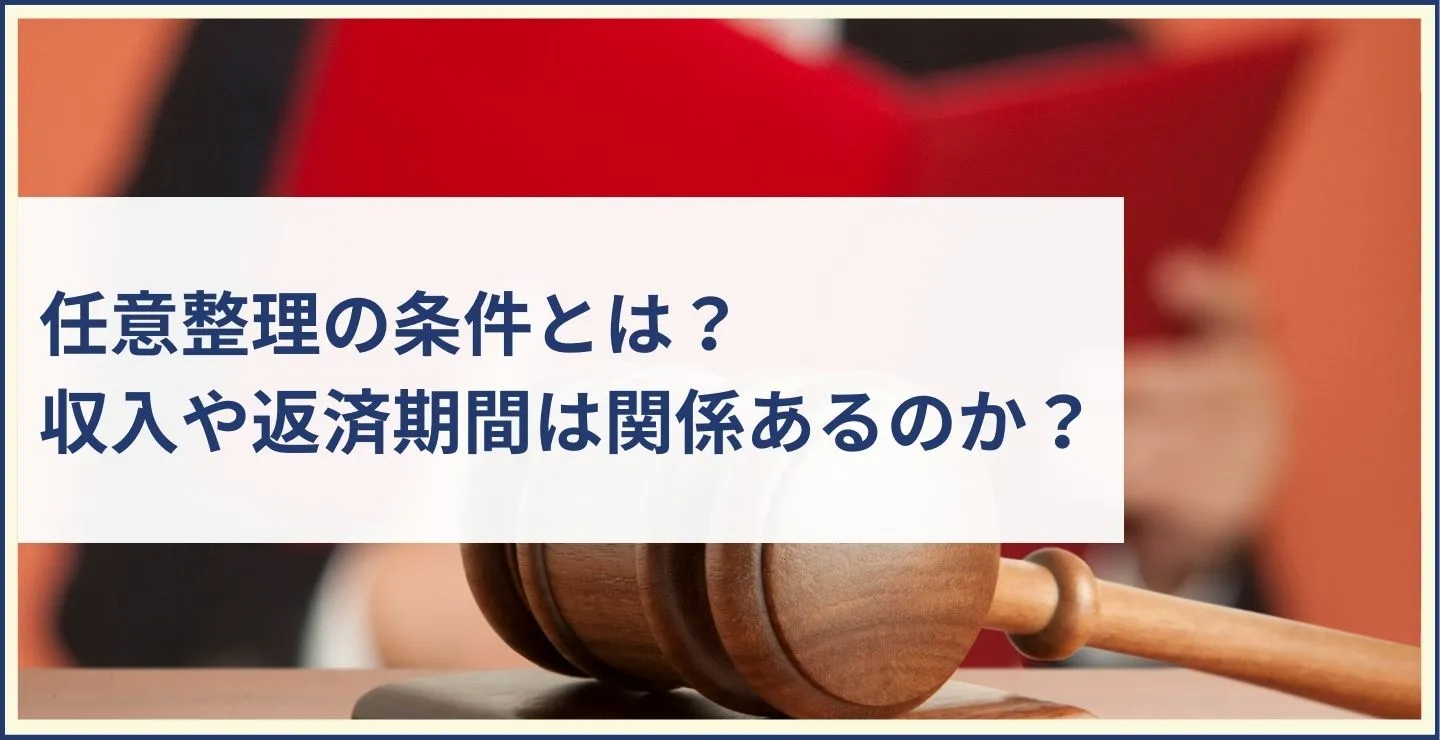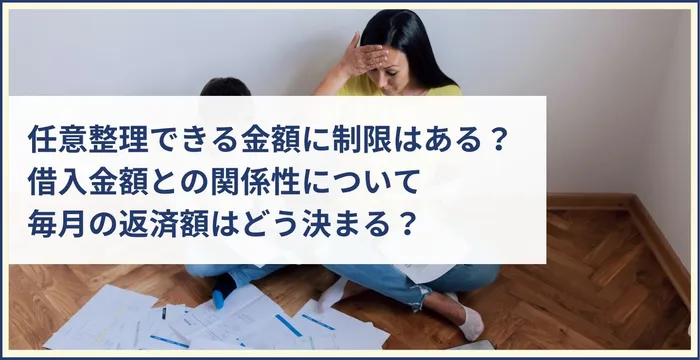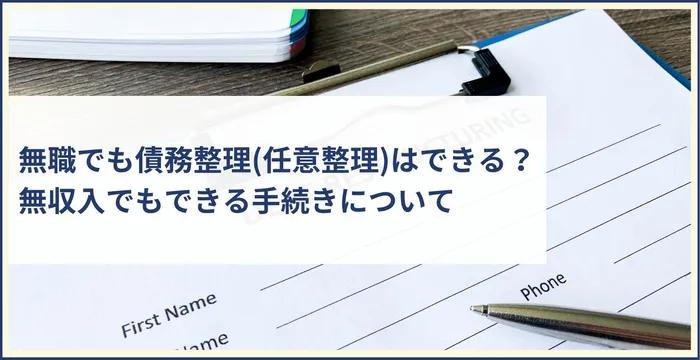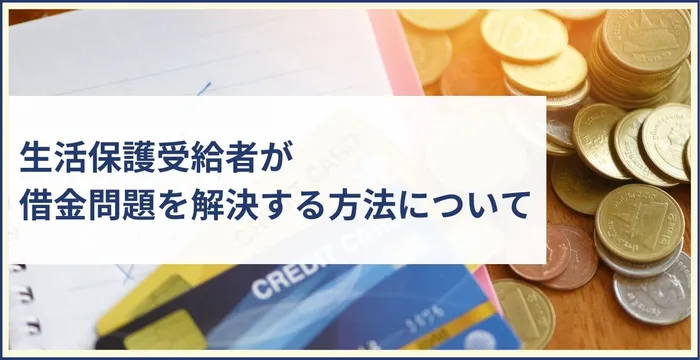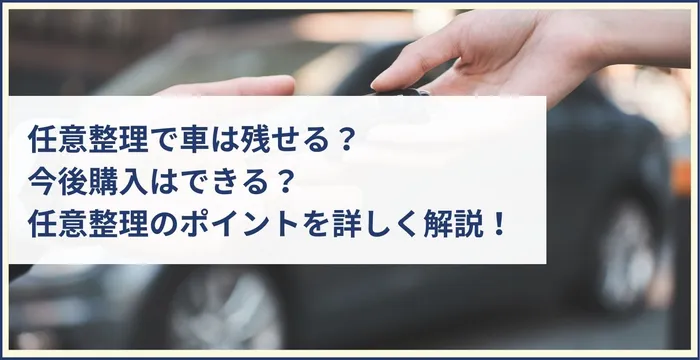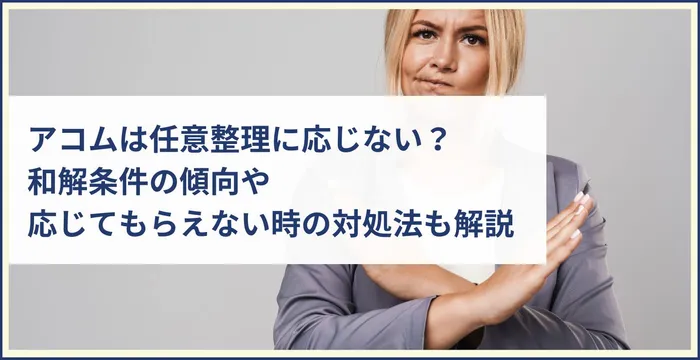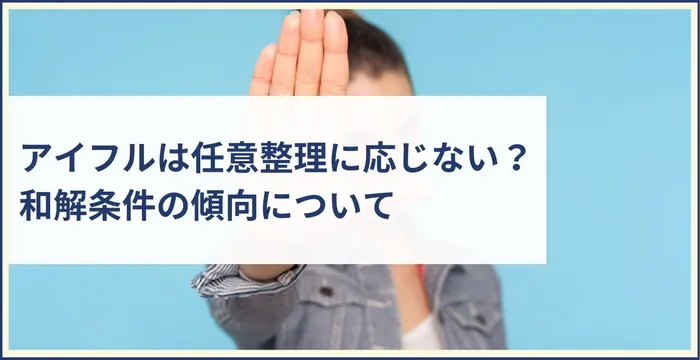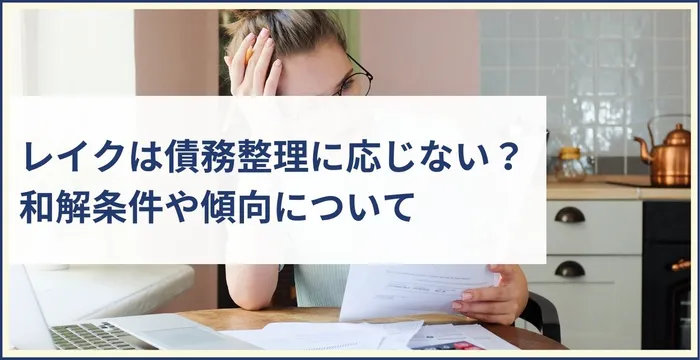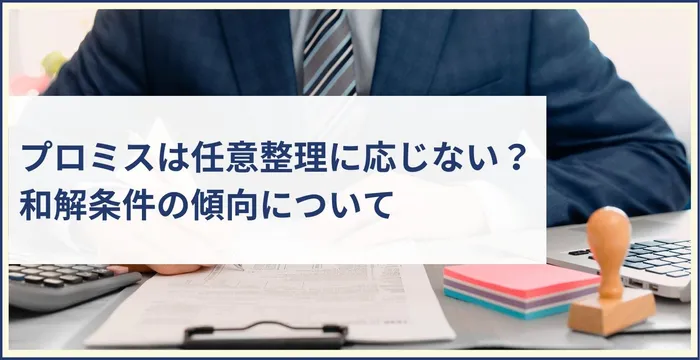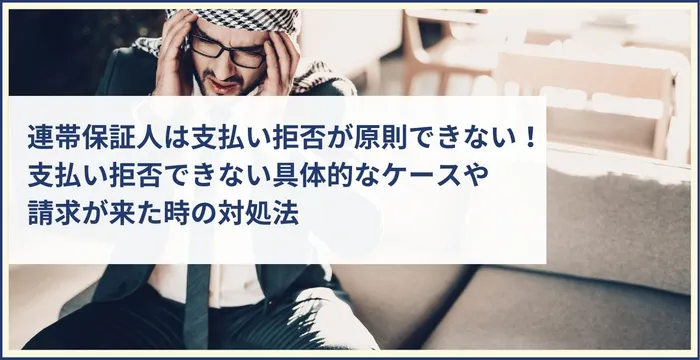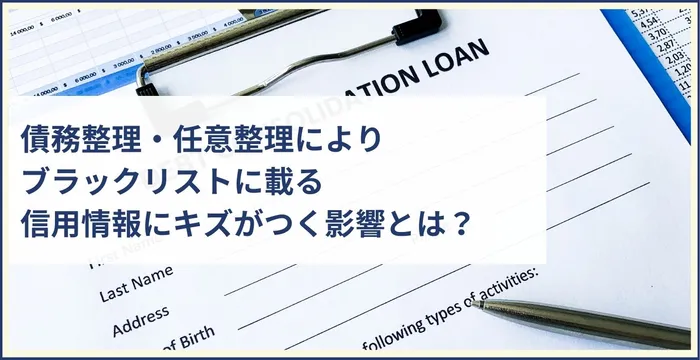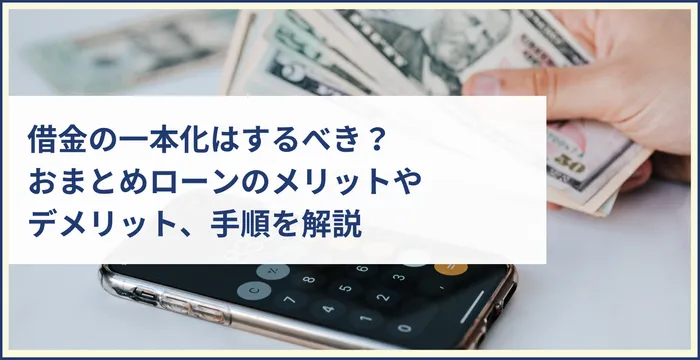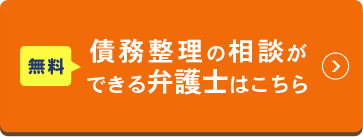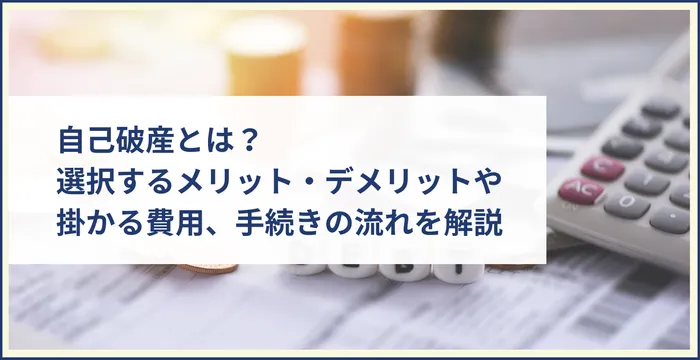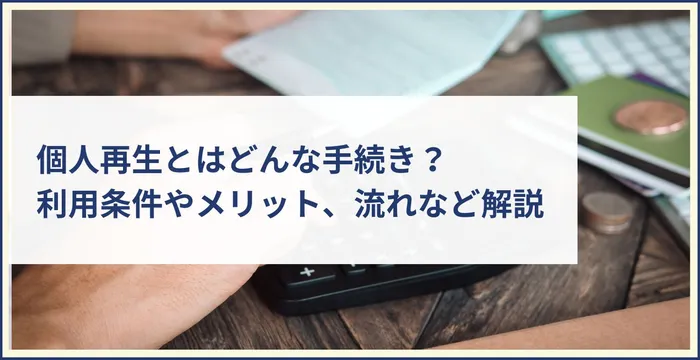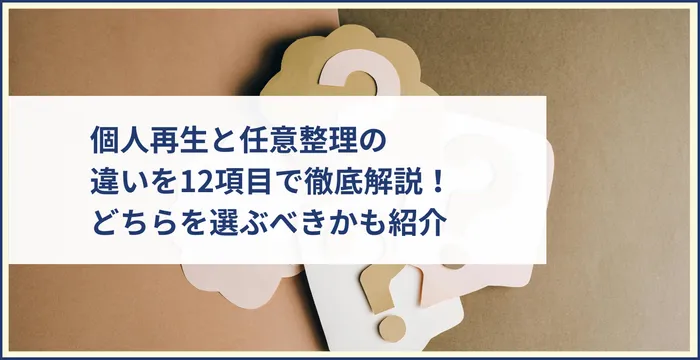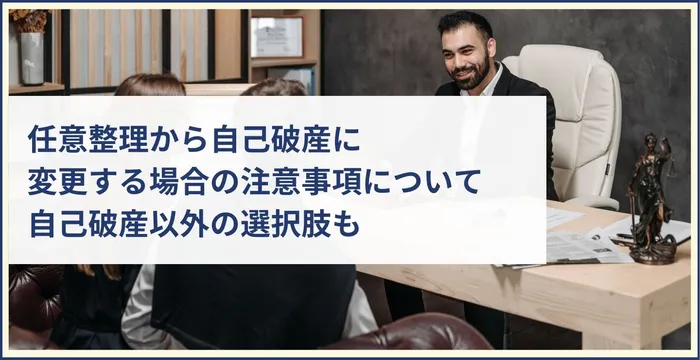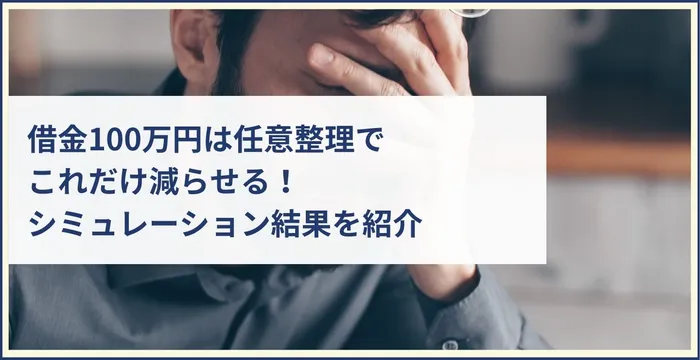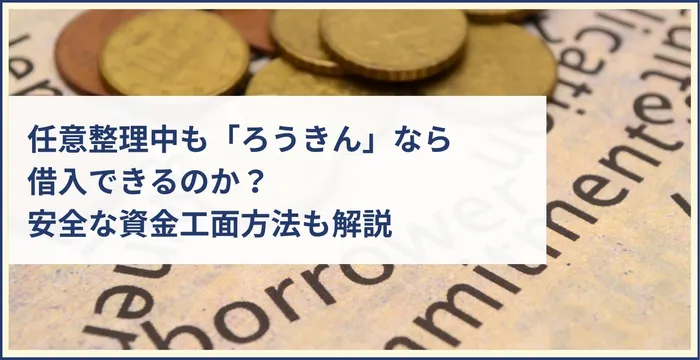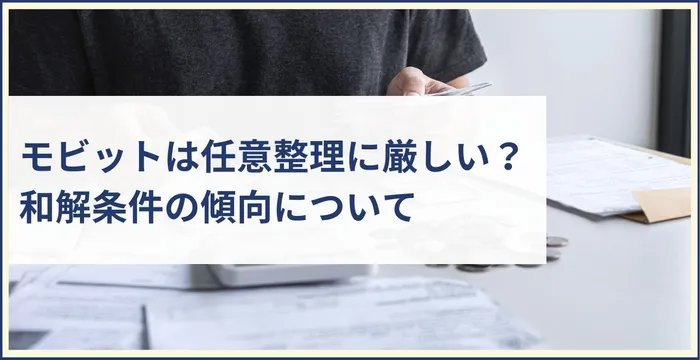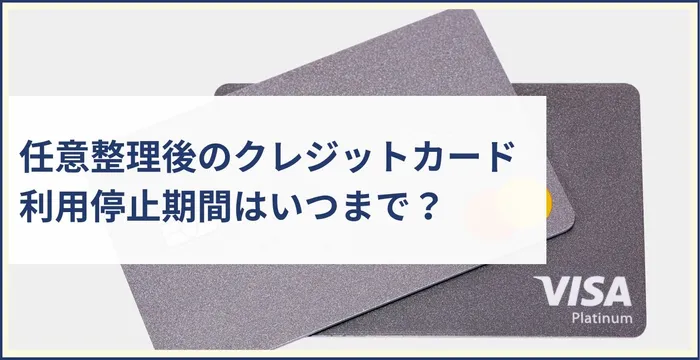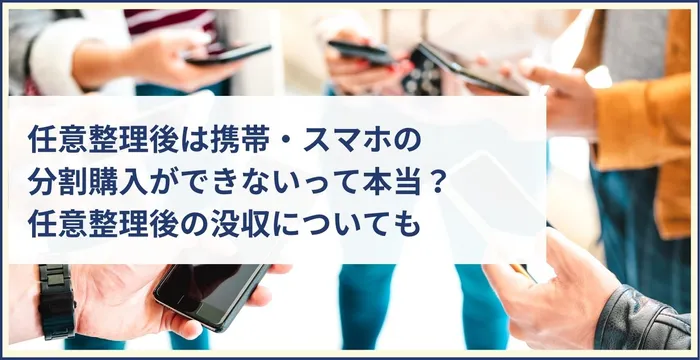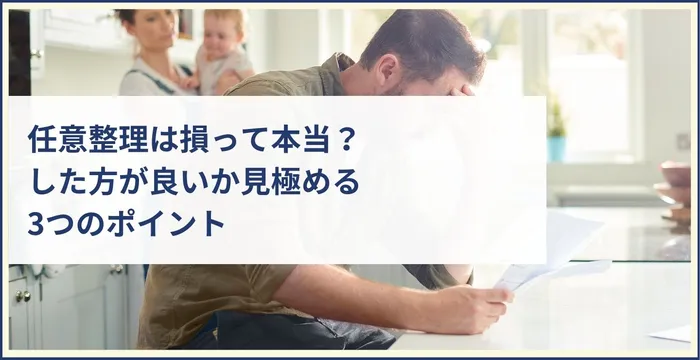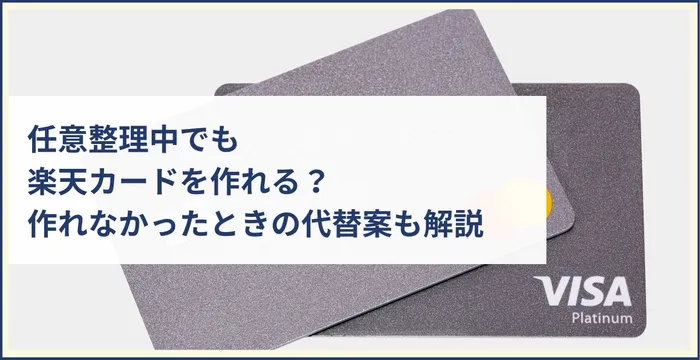任意整理ができる条件とは?
前提として、「任意整理をするには〇〇の条件を満たさなければならない」という条件は明確に定められていません。というのも、任意整理はあくまで債権者との交渉であり、債権者が和解に応じてくれるのであれば、どのような状況でも任意整理は原則可能といえるためです。
とはいえ、任意整理の特性上、下記すべてを満たしている場合でなければ手続きは難しいといえます。
- 安定した収入があること
- 原則3年〜5年程度で完済できる借金額であること
- 滞納による強制執行が行われていないこと
上記のいずれか1つでも満たせない場合には、任意整理をするのは難しいです。ここからは、任意整理の条件として上記3点を解説していきます。
安定した収入があること
任意整理は借金自体を減らせる手続きではありません。そのため、任意整理をした後も毎月の返済は必須です。
和解条件にもよりますが、任意整理の場合には元金自体を3年〜5年程度で完済できるように毎月の返済額が見直されるのが一般的です。つまり、3年〜5年程度で完済できるように、安定した収入があることが任意整理の条件の1つといえます。
安定した収入があるかどうかについては、その証明のため以下の書類提出を求められることが一般的です。
3〜5年以内に完済できるだけの安定した収入があるかどうかの基準は「収入-支出」で計算できます。
毎月の収入から生活に必要な費用をすべて差し引き、余ったお金を返済にあてた場合、3〜5年以内に完済できる見込みがあるかがひとつの基準です。
また、安定した支払い能力があれば、雇用形態に決まりはありません。アルバイトやパート、年金受給者や派遣社員であっても、任意整理が可能です。
ただし、雇用形態に関わらず安定した収入があることを証明する書類の提出が必要です。
原則3年〜5年程度で完済できる借金額であること
前提として、任意整理の対象とする借金の金額に制限はありません。そのため、借金をどれだけ抱えていたとしても、債権者が和解に応じれば任意整理は可能です。
とはいえ、任意整理をすると元金を3年〜5年程度で完済できるような条件に見直されるのが一般的です。そのため、3年〜5年程度で完済できないほどの借金がある場合には、任意整理できない可能性があります。
たとえば、任意整理によって毎月の返済額が3万円まで減額されれば完済できる人を想定します。この場合で3年〜5年間返済を続けた場合、102万円〜180万円が返済可能な総額となり、借金が180万円を超えている場合には任意整理が認められない可能性があるのです。
滞納による強制執行が行われていないこと
借金を滞納したまま放置して、給料や財産の差し押さえがおこなわれてしまうと、任意整理で和解しようとしても債権者は応じてくれないのが一般的です。
債権者からすれば、このまま給料を差し押さえていれば確実に借金を回収できるので、和解に応じるメリットがほとんどないからです。
そのため、任意整理での解決を希望している人は、給料や財産の差し押さえがおこなわれる前に、できるだけ早めに弁護士や司法書士に相談し、手続きを開始するようにしてください。
もし、すでに給料や財産の差し押さえがおこなわれた後なら、任意整理での解決は困難になると考えられます。自己破産や個人再生などの法的手続きで対処する必要があります。
任意整理できない可能性もある!任意整理ができない典型的なケース
前述したように、任意整理は債権者と交渉をする手続きです。そのため、交渉が難航してしまえば、債権者と和解ができずに任意整理できないこともあります。
「〇〇だと絶対に任意整理ができない」とは言い切れませんが、一般的には下記のようなケースは任意整理が難しいとされています。
- 無職で収入がない場合
- 生活保護者の場合
- 借金が多すぎる場合
- 2回目以降の任意整理の場合
- 任意整理に応じない業者の場合
いずれか1つでも該当する場合、任意整理できないことも考えられます。ここからは、任意整理できない典型的なケースについて、それぞれ解説していきます。
1.無職で収入がない場合
任意整理後は借金の負担が軽減されるものの、基本的には3年〜5年間は返済を続けなければならないため、債務者に借金を返済できるだけの収入があることが必要です。
そのため、無職で収入がない場合は任意整理をすることは難しいでしょう。
ただし、以下のようなケースでは、無職であっても任意整理できる可能性があります。
- 専業主婦(主夫)で配偶者が定職に就いている
- 現在は無職だが就職先が内定している
- 親や親族が代わりに返済をしてくれる
- 年金を受け取っている
- 過払い金で借金を完済・大幅に減額できる見込みがある
和解案に応じてもらえるかどうかは債権者次第になりますが、仮に無職でも上記に該当する方は、弁護士や司法書士に相談してみるとよいでしょう。
2.生活保護者の場合
生活保護を受給している方は、生活保護費も働いて得た収入を借金の返済にあてることはできません。生活保護という制度は、日本国民の最低限度の生活を保障するための制度だからです。
生活保護を受給しながら、働いて自立を目指す方もいます。そんな方も生活保護を受給している以上は、借金の返済にあてられませんので注意してください。
なお、生活保護を受給している場合には、任意整理ではなく自己破産を検討してみてください。生活保護の受給を検討している方であっても自己破産は可能ですし、生活保護受給中でも自己破産ができます。
自己破産費用は生活保護受給中の方であれば、法テラスに相談をすることで20万円を上限に立て替えてくれます。
そして、自己破産手続きが終えた後も生活保護を受給しているのであれば、建て替え費用を返済する必要はありません。
3.借金が多すぎる場合
任意整理は将来利息がカットされるものの、一般的に3年〜5年間かけて元金を返済しなければならない手続きです。
そのため、3年〜5年で返済計画が立てられないほど多額の借金を抱えている場合、任意整理は難しいといえます。
もし、弁護士や司法書士へ任意整理を依頼した時点で、任意整理後の返済が可能な収入を確保できていなければ、収入を増やすか支出を減らして、収支を改善するよう指示されるのが一般的です。
弁護士や司法書士の指示どおり収支が改善できない場合、任意整理後に返済できる目処が立たないため、任意整理できないのが基本です。
どうしても返済が難しい場合は、自己破産や個人再生など、他の債務整理へ方針変更することも視野に入れるとよいでしょう。
4.2回目以降の任意整理の場合
一度は任意整理で和解したのに、その後に生活状況などが変わって返済できなくなり、再び任意整理をしたいと考える人もいるかもしれません。
任意整理に回数制限はないため、2回目以降の任意整理をすること自体はとくに問題ないでしょう。
しかし、2回目以降の任意整理となると、前回より厳しい条件での和解を迫られる可能性が高く、場合によっては和解できないこともあります。
一度任意整理で約束した条件を守れなかったわけですから、債権者からすれば「また約束を破られるかもしれない」と疑ってかかるのは当然といえます。
また、1回目の任意整理で既に将来利息のカットは済んでいるので、2回目以降の任意整理では分割返済のメリットしかない場合がほとんどです。そのため、支払う費用に対してメリットが薄いとして、法律事務所から任意整理を止められる場合もあります。
前回の和解条件では返済が厳しい状況に陥っているなら、別の債務整理へ方針変更を考えるほうが賢明かもしれません。
5.任意整理に応じない業者の場合
任意整理はあくまでも「任意の交渉事」であり、任意整理に応じるか否かを決める選択権は債権者にあります。
実際のところ、会社の方針で任意整理に応じないとしている業者は少なくなく、債権者に拒否されてしまっては任意整理はできません。
また、任意整理の交渉には応じてくれるものの、以下のような厳しい条件での和解を迫ってくる業者もいます。
- 和解後の将来利息を全カットは不可。年利5%の将来利息込みでないと和解できない。
- 将来利息のカットは可能だが、返済は一括払いに限る。
- 将来利息のカットは可能だが、残元金の1/3~1/2の金額を頭金として支払わなければならない。
この場合、業者の要求どおりに支払えるなら和解は可能ですが、できない場合は交渉不成立となり任意整理は難しいでしょう。
なお、以下の記事では貸金業者ごとに任意整理に応じてもらえるかどうかを解説しています。和解に応じる傾向などのポイントもまとめているので、ぜひ参考にしてください。
任意整理をする場合に事前に確認しておくべきこと
任意整理をする場合、条件以外にも確認しておくべきことがあります。その例をまとめましたので、まずは確認してみてください。
- 任意整理が可能な借金であるか
- 任意整理の対象とする借金に保証人・連帯保証人がついていないか
- 最長5年間いわゆるブラックリスト入りになっても任意整理するべき
そもそもですが、任意整理の対象にできない支払いもあります。また、任意整理にはデメリットもあるため、デメリットを十分に把握したうえで本当に手続きをするべきかを考えておくことが大切です。
ここからは、任意整理をする場合に事前に確認しておくべきことについて、それぞれ解説していきます。
任意整理が可能な借金であるか
任意整理の対象となるのは、一般的に以下のような借金です。
- 消費者金融などからの借金
- カードローン
- クレジットカードのリボ払い・分割払い
- 住宅ローン・自動車ローン
- 個人から借りたお金 など
以下のような借金は「非免責債権」といい、任意整理ができません。
- 公共料金(電気・ガス・水道など)
- 税金や社会保険料(国民健康保険料・国民年金保険料・介護保険料など)
- 慰謝料、養育費などの損害賠償金
- 婚姻費用
- 従業員の給与
- 債権者名簿に記載しなかった債権
- 交通違反などによる罰金 など
上記は原則として任意整理ができません。そのため、任意整理以外の方法で、支払い負担を減らすことを考えるべきです。
なお、税金や社会保険料の一部などに関しては、市区町村や税務署などの窓口で相談することで分割払いにしてもらえる可能性があります。また養育費などの損害賠償のうち、当事者間で話し合いができるものは減額や分割といった相談をしてみるのもよいでしょう。
任意整理の対象とする借金に保証人・連帯保証人がついていないか
任意整理をする場合、その借金に保証人や連帯保証人を立てていないかを確かめておきましょう。
保証人や連帯保証人を立てている借金を任意整理した場合、自身の返済負担は減らせますが、代わりに保証人や連帯保証人が債権者から督促を受けます。
債権者は主債務者が「任意整理をした=返済不能になった」と判断するため、代わりに借金を返済するよう連帯保証人に要求してくるのです。
主債務者は弁護士や司法書士へ依頼しているため、債権者が主債務者へ直接取立てをおこなうことはありません。
しかし、その効力が連帯保証人にまで及ぶことはないので、連帯保証人への直接取立ては貸金業法違反になりません。よって、連帯保証人は債権者からの督促を拒否できないのです。
連帯保証人が設定されている借金を任意整理する場合、連帯保証人に迷惑がかかるというデメリットを受け入れる必要があるのです。どうしても連帯保証人に迷惑をかけられない場合は、連帯保証人が設定された借金を対象から外して任意整理するのも一つの方法です。
最長5年間いわゆるブラックリスト入りになっても任意整理するべきか
任意整理をすることにはさまざまなデメリットがありますが、なかでも注意するべきはいわゆるブラックリスト入りになることです。
前提から説明すると、ブラックリストの存在が金融機関から公表されているわけではありません。「ブラックリスト入り」はあくまで一般的に使われている表現であり、「信用情報として返済能力を疑われるような情報が残っている状態」のことを指します。
信用情報とは、ローンやクレジットカードなどの利用履歴のことです。「個人信用情報機関」という国内に3社ある機関で保管・管理されており、消費者金融やクレジットカード会社、銀行などに共有されます。
任意整理をすると、その履歴が信用情報として登録されます。任意整理の履歴が信用情報として残っている場合、金融機関から返済能力を疑われる可能性があり、その場合にはローンやクレジットカードなどの審査に通りません。
任意整理においては、最長5年間信用情報として履歴が残ります。そのため、任意整理をしてから最長5年間は、クレジットカードやローンの審査に通りづらくなってしまうのです。
いまは利用の予定がないとしても、将来的に住宅ローンや自動車ローンを利用したいと考える可能性もあります。その場合に任意整理の履歴によって、それらローンの利用が制限されてしまう可能性も十分に考えられます。
任意整理後の生活にも支障をきたす可能性もあるため、ブラックリスト入りになったとしても任意整理をするべきかを十分に検討したうえで、任意整理の手続きを進めてみてください。
任意整理できないときはどうすればいい?任意整理以外の借金問題を解決する対策
ここまで解説したように、自身の状況や債権者の判断によっては任意整理ができないケースもあります。任意整理ができずに借金を放置してしまうと、債権者から訴訟を起こされ、最悪の場合は給料や預貯金口座などの財産を差し押さえられるおそれもあります。
そのため、任意整理ができないからといって借金問題を放置するのは絶対に避けるべきです。そこで、任意整理できない場合でも借金問題を解決するための対策について、ここからは紹介していきます。
- おまとめローンを利用する
- 他の債務整理手続きを検討する
おまとめローンを利用する
そもそもですが、任意整理は弁護士や司法書士に依頼するのが一般的な手続きであるため、費用や手間がかかりやすいです。そのため、可能であれば任意整理をせずに借金問題を解決するのが理想といえます。
「借金自体が減らなければ完済は難しい」といった場合は除きますが、「毎月の返済額が減れば完済の見込みがある」というケースであれば、任意整理ではなくおまとめローンの利用を検討することも1つの手です。
おまとめローンとは、複数からの借入を1社にまとめるための返済専用のローン商品のことです。返済専用であるため、追加で借入することはできず、毎月の返済を問題なく続けられれば借金を着々と減らせます。
また、借入先を1社にまとめられれば、月々の返済額を抑えられるのが一般的です。実際に返済する金額は借入残高や金融機関によって変わりますが、毎月の返済額を数千円〜数万円程度減らせることに期待できます。
なお、おまとめローンを利用するには、金融機関の審査に通過しなければなりません。「すでに滞納を繰り返している」といった場合には審査に落ちてしまうことも考えられるため、「まだ滞納はしていないが、このままでは将来的に滞納してしまう」という場合にはおまとめローンを検討してみてもよいでしょう。
他の債務整理手続きを検討する
任意整理できない場合は、他の債務整理手続きを検討するのも1つの手です。
そもそも、債務整理とは利息や元金をカットや減額したり、一括請求を長期の分割払いへ変更するなどして、借金の返済負担を大幅に減らせる手続きの総称です。
債務整理には、任意整理を含めて主に3つの方法があり、債務者の状況によって最適な解決方法は異なります。そのため、まずは無料相談などを利用して弁護士や司法書士へ直接相談し、自分の状況に合った方法を提案してもらうとよいでしょう。
A.自己破産
| 手続きの概要 |
20万以上の価値ある財産を手放す代わりに借金を全額免除してもらう |
| 条件 |
・借金総額が返済可能額を上回っている
・借金が免責不許可事由に該当しない
・自己破産や個人再生をしてから7年が経過している
・借金がゼロになれば生活再建の目処が立つ
・自己破産手続きに協力的
|
| 費用の目安 |
50万円~90万円 |
| 減額効果 |
免責が下りれば借金がゼロになる |
| 主なデメリット |
・一定の財産が処分される
・いわゆる「ブラックリスト入り」になる
・連帯保証人を設定している場合は請求がいく
・担保を処分される恐れがある
・一定期間の資格制限がある
・官報に掲載される
・免責不許可となった場合は市町村役場に通知される
|
自己破産とは、裁判所を介しておこなう手続きで、20万円以上の価値ある財産をすべて手放す代わりに、借金全額の返済義務を免除してもらえる方法です。
債務整理の3つの方法の中で、最も借金を減額できる方法ですが、家や車などの財産を所有している場合は失う恐れがあります。
ちなみに、任意整理と同じく一定期間は信用情報機関に事故情報が登録されます。
なお「自己破産をすると近所や勤務先に知られてしまうのでは」と気にする人もいますが、基本的には同居している家族以外に知られることはないので安心してください。
B.個人再生
| 手続きの概要 |
20万以上の価値ある財産を手放さずに借金を約1/5に減額し、3〜5年で分割返済する |
| 条件 |
・定職に就いていて安定収入がある
・減額後の借金を3年程度で完済できる
・住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下
・履行テストで問題なく支払いができる
・債権者が個人再生に反対していない
・過去2年間の年収の変動割合が20%未満
・多額の財産を保有していない
・債権者を漏れなく申告している
・再生計画を期限内に提出している
|
| 費用の目安 |
50万円~90万円 |
| 減額効果 |
借金総額や資産状況にもよるが、月々の返済額は3〜8万円程度になることが多い |
| 主なデメリット |
・一定の財産が処分される
・いわゆる「ブラックリスト入り」になる
・連帯保証人を設定している場合は請求がいく
・担保を処分される恐れがある
・官報に掲載される
|
個人再生とは、裁判所を介しておこなう手続きで、20万円以上の価値ある財産を手放さずに借金を約1/5に圧縮し、3〜5年で分割返済する方法です。
自己破産のように借金がゼロにはならないものの、家や車などの財産を手元に残せるというメリットがあります。
なお、自己破産同様、一定期間は信用情報機関に事故情報が登録される点や、同居している家族に秘密で手続きするのは難しい点に注意しましょう。
自己破産→個人再生の順で考えるのが一般的
一般的に、任意整理が難しい場合、まずは自己破産で解決できるかどうか考えていきます。最初から個人再生の利用を検討することはありません。
任意整理での解決が難しい場合、債務者は返済できない借金を抱えていると判断されるため、より借金の減額率が高い自己破産で解決可能か検討します。
しかし、自己破産には財産の没収や資格制限など、さまざまなデメリットがあります。個々の状況によっては自己破産で借金がゼロになっても、自己破産のデメリットによって生活再建が困難となってしまう人もいるでしょう。
そのような人のためにあるのが、個人再生という債務整理手続きです。個人再生は「財産を手元に残せる」「資格制限がない」など、自己破産のデメリットを避けながら任意整理以上に借金の負担を軽減できる手続きです。
一方で、個人再生は自己破産と同等の手続き費用がかかるにも関わらず、借金が100万円以上残ってしまう手続きでもあります。ゆえに、自己破産をしてもほとんどデメリットがない場合、個人再生を利用することはまずありません。
以上のような理由から、任意整理での解決が難しい場合は、自己破産→個人再生の順で検討するのが一般的とされています。
なお以下の記事では、任意整理から自己破産に移行する場合の注意点を解説しています。自己破産のリスクや、本当に生活の再建を目指せるのかなども説明しているので、ぜひ参考にしてください。
まとめ
任意整理手続きは他の債務整理手続きとは異なり、法的強制力がない交渉です。
そのため、今回お伝えした条件を満たしているからといって、必ず任意整理が和解までいくとは限りません。
債権者によっては、任意整理の手続きが始まった時点で訴訟へ発展させる場合もあります。もしも訴訟に発展してしまえば、給与や財産の差し押さえになりかねません。
ただ、弁護士に任意整理を相談することで、債権者が任意整理に応じてくれるのかどうかの簡単な判断ができます。もちろん、債務者の状況によっても異なるため一概には言えません。
今回紹介した条件を満たしている方が、任意整理を検討していても必ず弁護士などの専門家に依頼しましょう。自分で任意整理手続きを行っても良いですが、訴訟発展リスクが高くなります。
任意整理に応じない債権者との取り引きであっても、弁護士に相談をすれば債務者に最適なプランを提案してくれます。今回お伝えした任意整理の条件を満たしているのであれば、ぜひ任意整理の検討を始めてみてはいかがでしょうか。
任意整理のよくある質問
フリーターなのですが、任意整理できますか?
長期的に安定した収入があれば可能です。
まずは借入と収入がわかる資料を持って、弁護士の無料相談を利用してみることをおすすめします。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
生活保護を受けているのですが、任意整理できますか?
生活保護受給中は、生活保護費も働いて得た収入も、借金の返済にあてることはできません。
そのため、借金の返済に困った場合は自己破産を検討してください。
自己破産費用は生活保護受給中の方であれば、法テラスに相談をすることで20万円を上限に立て替えてくれます。
任意整理の途中で返済が難しくなったらどうしたらよいですか?
無断で滞納すると、債権者から利息を含めた残債を一括請求されるのが通常です。
そのため、返済が難しいと感じたらすぐに担当の弁護士へ相談しましょう。
任意整理は弁護士と司法書士どちらに依頼するべきですか?
借金の金額が絶対に140万円を超えないのなら、司法書士の方が費用は安く済む可能性があります。
しかし、140万円を超える可能性があるなら最初から弁護士へ依頼するのがよいでしょう。
また、債務整理に関しては、弁護士の方が経験が豊富である場合が多いです。
FAQ
・年金受給者は任意整理できる?
・契約書とかがなくても任意整理できる?