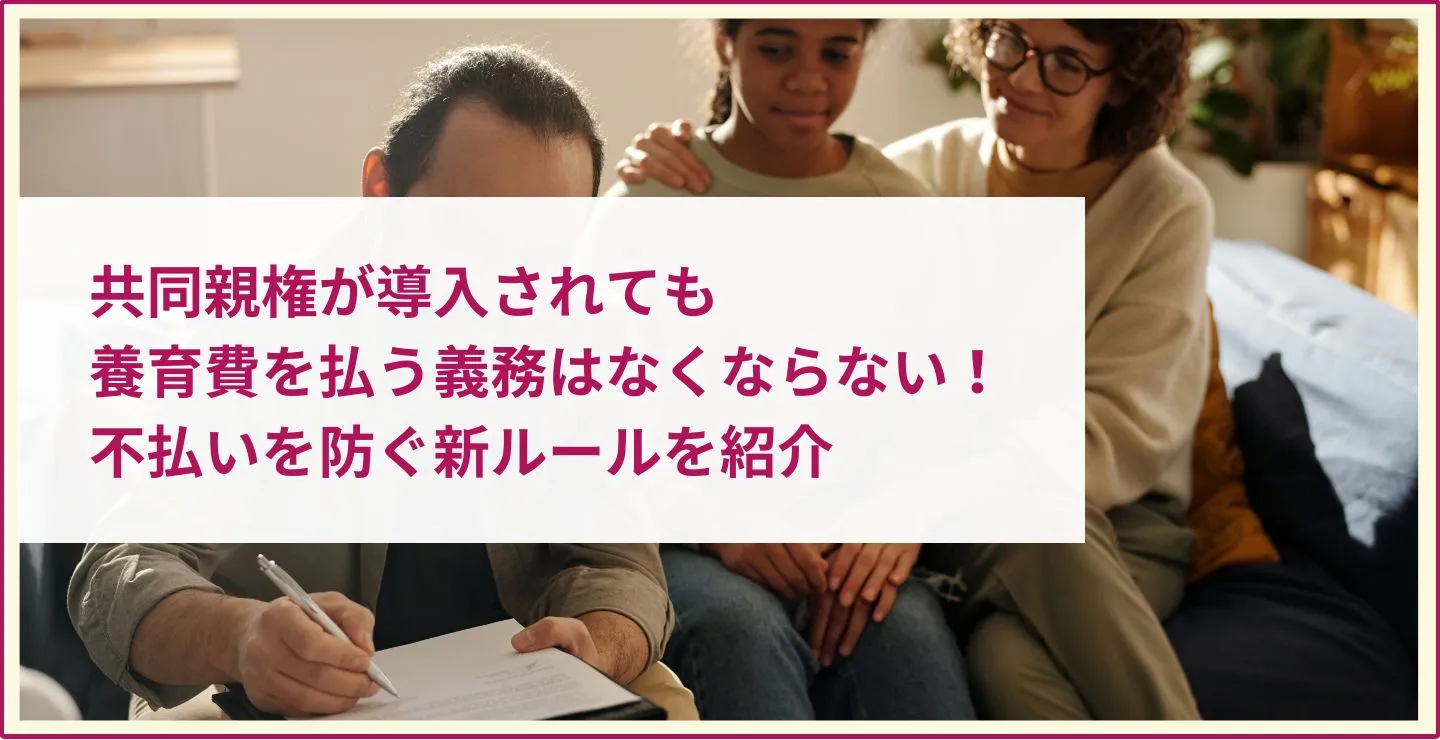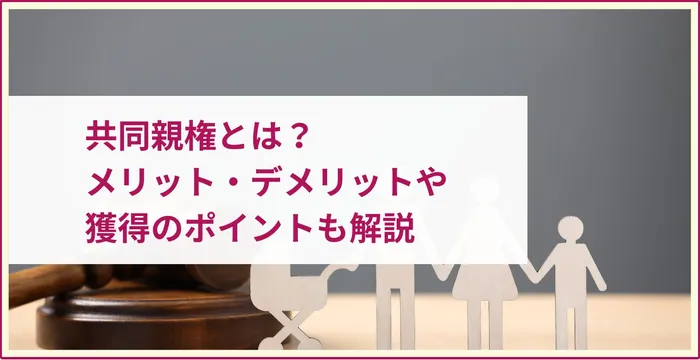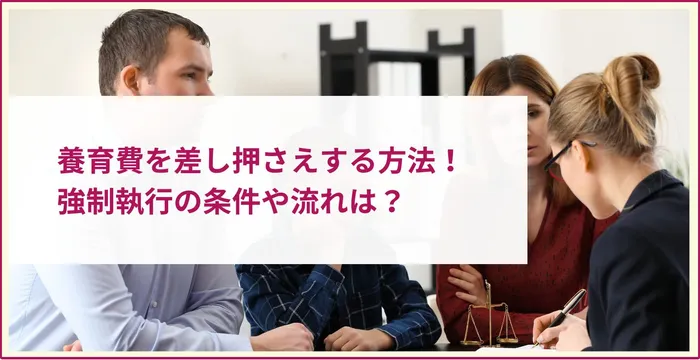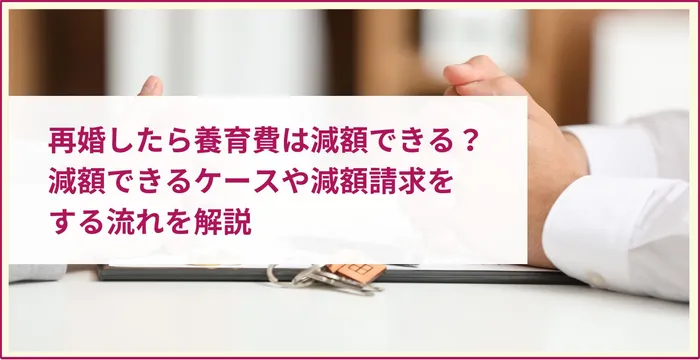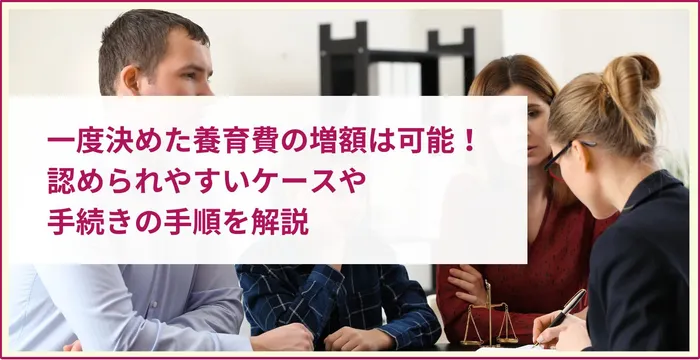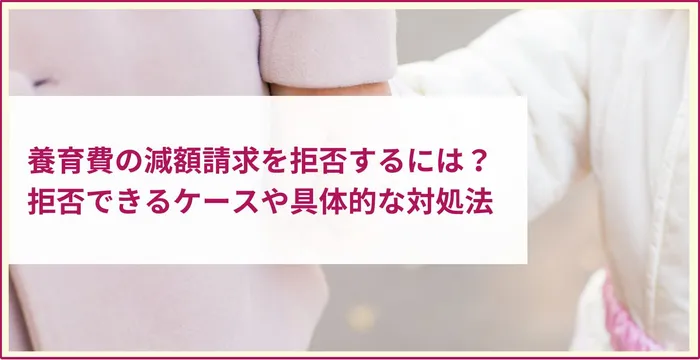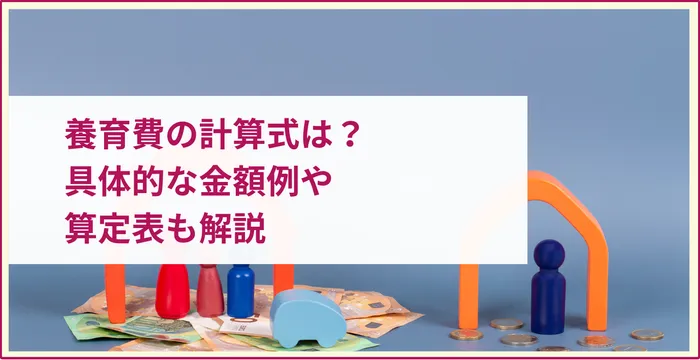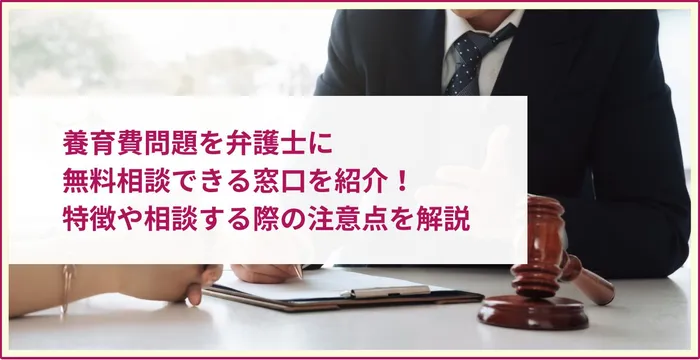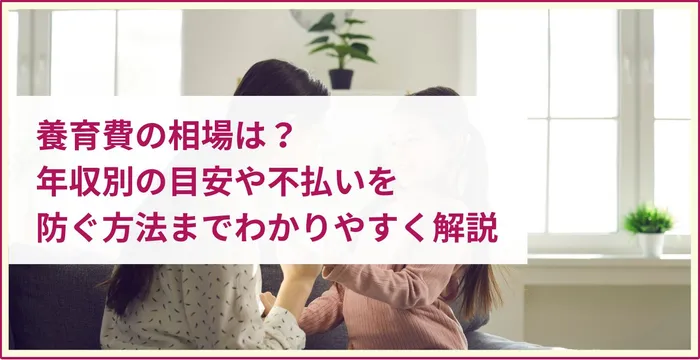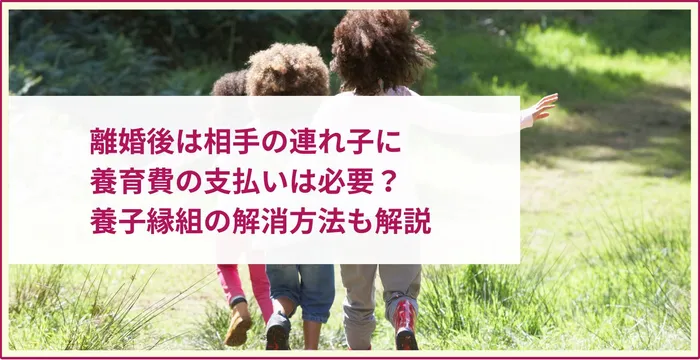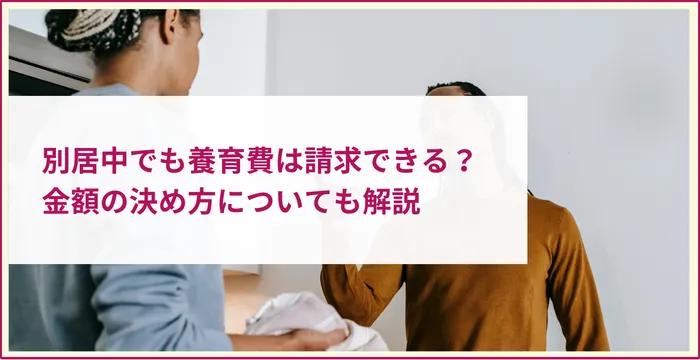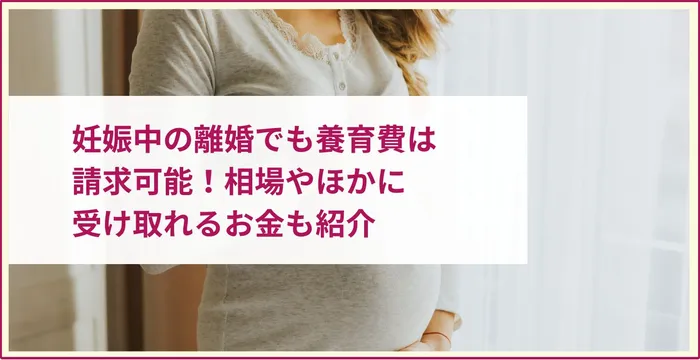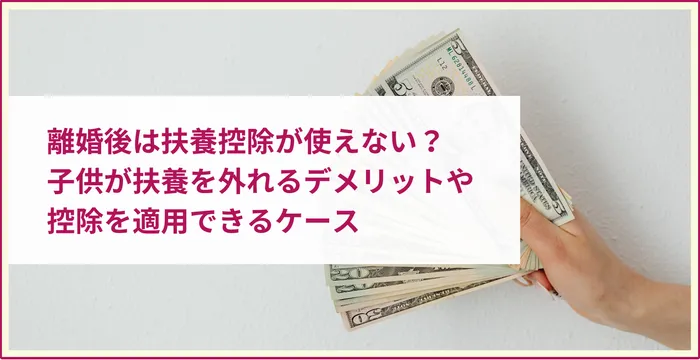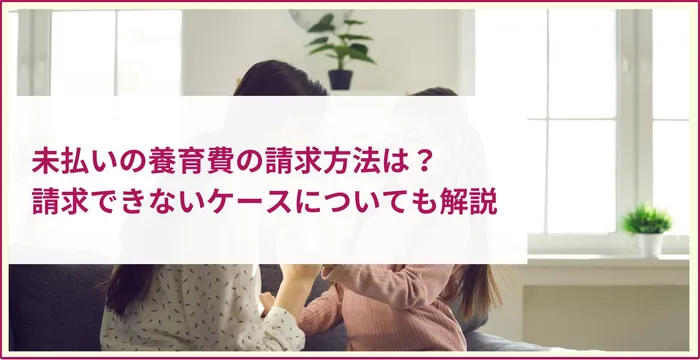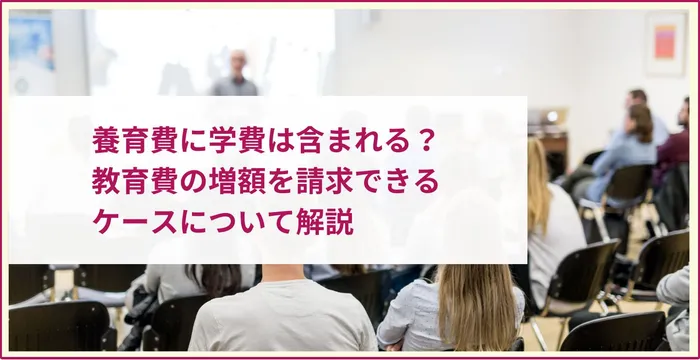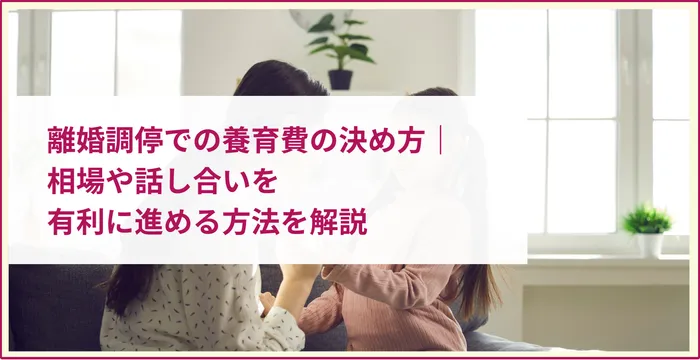2026年5月までに選択できるようになる共同親権においても、養育費の支払義務がなくなることはありません。
法改正により、離婚時・離婚後の話し合いや家庭裁判所の手続(調停・審判)で養育費の金額を決めていなくても、一定の金額までは離婚日から養育費を請求できるようになります。さらに、養育費は先取特権となるため、家庭裁判所での手続きや公正証書がなくても相手の財産を差し押さえられるようになります。
共同親権とは、離婚後も父母の双方が親権者として、子どもの利益のために監護・教育をする義務を負う制度です。
子どもにとっては離婚後も父母の双方に監護・教育を請求できる点でメリットがありますが、離婚後の父母にとっては必ずしも子どもの監護・教育について意見が一致するわけではないなどの問題があります。
親権や養育費について大幅な改正が間近に迫っていますが、実際に改正後、共同親権でどのようなトラブルが起こるのかは未知数です。
疑問や不安がある場合や、離婚を検討している方は、弁護士のサポートを得ながら子の利益を図ることが大切です。
本記事では、上記のような共同親権や養育費の概要、両者の関係について詳しく解説しています。
共同親権とは、子どもの両親がそれぞれ親権を持てるようになる新制度
共同親権が選べるようになる新たな法制度でも、通常は別居親に支払義務があることは変わりません。むしろ、離婚時・離婚後に金額が決まっていなくても一定金額の請求や差し押さえができるため、養育費の支払が確保される仕組みとなっています。
以降では、共同親権はいつ始まるのか、これまでと何が違うのかといった共同親権の詳細を解説します。
なお、共同親権については以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひあわせてご覧ください。
共同親権は2026年5月までに施行予定
共同親権を始め、法定養育費など離婚・親子に関する重要な法改正は、2026年5月までに施行されます。つまり、2026年5月までには新たな制度の運用が開始されるということです。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条から第十八条まで及び第十九条第一項の規定は、公布の日から施行する。
引用元 民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)附則第1条
ちなみに、法律の改正がすぐに適用されない理由は、急に重要な制度が変更されると混乱が生じるほか、今回のように制度の詳細を法務省などの行政機関が定める必要があるなど、準備や周知に期間が必要だからです。
共同親権とは、子どもの親権者が父母の2人であることをいいます。改正前も父母の婚姻中は共同親権でしたが、改正により離婚後も共同親権を選べるようになりました。
共同親権を選択できるようになった背景は、国会で審議された際の当時の法務大臣の説明によると以下のとおりです。
この法律案は、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正しようとするものであります。
引用元 国会議事録検索システム
要するに、離婚後の子どもに関する社会情勢を背景に、子の利益を確保するために共同親権が設けられました。
ただ、より現実的には国際社会において日本に対する共同親権の導入に関するプレッシャーがあったことも指摘されています。
実際、2020年7月にはブリュッセルにおける欧州議会本会議で「日本当局に対し、共同親権の可能性に向けた国内法令改正を促すとともに、自らが批准した児童の権利条約へのコミットメントを守ることを求める」といった内容を含む決議が採択されていました。
参照:家族法制部会 参考資料2-7(資料の作成者は外務省欧州局政策課)
単独親権との違いは重要事項の決定に双方の合意が必要になる点
共同親権、つまり父母の双方が親権者となることで、従来の単独親権と具体的に何が異なるのかといった疑問を抱く方も少なくありません。
共同親権では、離婚後も、子どもの利益のために監護・教育をする義務を父母の双方が負います。従来の単独親権では、父母の一方しか監護・教育義務を負いませんでした。
子どもの立場では、監護・教育について1人ではなく2人に保障されることとなります。
しかし、子どもの監護・教育について必ずしも父母の意見が一致するわけではありません。
改正後の民法では、監護・教育に関する日常行為は単独でできますが、そうでない行為は共同でしなければならないとされています。
法律上必ずしも明確ではありませんが、法務省が公表するパンフレットでは、日常行為に当たらない行為として次の行為が挙げられています。
- こどもの転居
- 進学先の決定
- 心身に重大な影響を与える医療行為の決定
- 財産の管理
上記のような行為で父母の意見が一致しない場合は、家庭裁判所での手続きを経て、単独で親権を行うことができるようになります。
共同親権では、親権者を誰にするかでは争わなくても、転居や進学先、医療行為、財産管理について父母の意見が一致せず、法的紛争が生じる可能性がある点に注意が必要です。従来の単独親権では、上記のような行為も単独ですることができました。
共同親権か単独親権かは協議により選択可能
共同親権を選択できるようになるといっても、必ずしも良い面だけではないことは前述のとおりです。
しかし、改正法の施行後は必ず共同親権にしなければならないわけではなく、単独親権と共同親権のどちらにするかの選択ができます。
もし父母の話し合いで決まらない場合は、従来どおり家庭裁判所の手続きを経て親権者を決めてもらいます。裁判離婚の場合も同様です。
家庭裁判所が単独親権と共同親権のどちらかを判断する際、以下のような事情があるときは単独親権にしなければならないとされています。(改正後の民法第819条第7項)
- 子どもの心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき
- 父母間のDV・モラハラなどで共同親権が困難と認められるとき
共同親権が導入されても養育費の負担はなくならない
共同親権が導入され、仮に離婚後父母の双方が親権者となっても、養育費の負担はなくなりません。親(父母)である以上は、父母が結婚しているかどうか、親権があるかどうかにかかわらず、養育義務があるためです。
現行の法制度では、養育費を支払うのは、いわゆる以下のような人といった認識が広がっていました。
- 子どもと別居している親(別居親)
- 親権者ではない親(非親権者)
例えば、養育費は別居親が監護親(同居親)に、あるいは非親権者が親権者に支払うものといった認識です。
民法改正法により、2026年5月までには離婚後の共同親権を選択できるようになります。
共同親権では非親権者がいないため、どちらが養育費を支払うのか、もしかして養育費がなくなるのかといった疑問を抱く方も少なくないでしょう。
結論、共同親権でも、親(父母)である以上は養育費を負担しなければなりません。そもそも養育費は、親権者かどうか、結婚しているかどうかにかかわらず、親が分担すべきものだからです。
実際、単独親権が前提である改正前の民法でも、父母は離婚時に子の監護に要する費用(養育費)の分担について話し合って決めることとされていました(改正法施行前の民法第766条第1項)。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
引用元 民法第766条第1項
そして、共同親権を選択できるようになった改正後の民法では、以下のとおり親の責務が法律に明記されました。
(親の責務等)
第八百十七条の十二 父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。
2 父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。
引用元 改正後の民法第817条の12
つまり、父母である以上、父母には婚姻関係にかかわらず以下2つの義務があるということです。
- 子を養育する義務
- 自己と同程度の生活を維持できる程度に扶養する義務
離婚したからといって、子どもの養育や扶養をする義務がなくなるわけではありません。
新たなルールで養育費の不払いは防ぎやすくなる
2026年5月までには共同親権を選択できるようになるほか、より養育費が確実に支払われるようなルール・制度が開始します。
先取特権や法定養育費といった難しい言葉が並びますが、いずれも重要な制度です。わかりやすく解説するため、ぜひ理解してください。
他の債権より優先して差し押さえられる「先取特権」の付与
民法改正法が施行されると、養育費は、先取特権となります。
先取特権とは、他の債権よりも優先して相手の財産から先に取ることができる(回収できる)権利です。例えば、相手に金融機関からの借金があって自己破産をする場合でも、その借金(金融機関)より先に養育費を回収できます。
また、先取特権となったことで、調停や審判、訴訟といった手続きをとることなく、地方裁判所での手続きだけで相手の給与や預貯金、不動産を差し押さえられるようになります。
従来、養育費が支払われないために相手の財産を差し押さえる際は、父母で取り決めた養育費の約束があっても、事前に債務名義を取得して地方裁判所に提出する必要がありました。債務名義の例は以下のとおりです。
- 調停調書正本(離婚調停または養育費請求調停のもの)
- 家事審判書正本(養育費請求審判のもの)
- 確定判決正本(離婚訴訟などのもの)
- 執行証書(養育費を支払わないときはすぐに強制執行に服する旨の記載がある公正証書)
そのため、父母で取り決めた養育費の約束があっても、債務名義がなければ家庭裁判所で調停や審判、訴訟をしたうえで、地方裁判所に差し押さえの手続きを申し立てる必要がありました。
改正後は、債務名義が不要な先取特権(担保権)の実行という手続きで差し押さえが可能です。
ただし、例えば離婚協議書など、養育費の先取特権があることを証する文書の提出が必要です。具体的に必要な文書は個別具体的な状況によって異なるため、弁護士への相談をおすすめします。
先取特権は、不動産における担保(抵当権)のようなものです。抵当権は自動的には発生しませんが、先取特権は相手の意思とは関係なく自動的に発生します。
一定の養育費を請求できる「法定養育費制度」の新設
また、民法改正法が施行されてからは、話し合い(協議)や調停、審判、判決がなくても、離婚日から法定養育費(特例養育費)の支払いを請求できるようになります。
(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)
第七百六十六条の三 父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。
一 父母がその協議により子の監護に要する費用の分担についての定めをした日
二 子の監護に要する費用の分担についての審判が確定した日
三 子が成年に達した日
引用元 改正後の民法第766条の3第1項
改正前は、養育費を請求しても話し合いや家庭裁判所の手続きで金額を決めることが前提であり、実際に支払いを受けるまで時間がかかることがありました。
しかし、改正後は法務省が決めた方法で法定養育費(特例養育費)の金額の計算が可能です。その結果、話し合いなどで具体的な金額を決めることなく、離婚日からすぐに請求できます。
法務省は、2024年11月22日に検討会を設置・開催し、法定養育費(特例養育費)の計算方法について専門的な検討を進めています。第1回の検討会で配布された資料を見ると、第1回は検討の視点や留意点、勘案すべき事情や参考とすべき検討資料などについての考え方を整理する段階でした。
いまだ計算方法の案すら示されていない段階ですが、いずれにしても、法務省は「子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額」などの事情を基礎に計算方法を決めます。
ちなみに、法定養育費は法定といっても本来の養育費ではありません。配偶者からのDVがあるなど、養育費を決める話し合いが困難な場合などを想定して創設された補充的なものです。
実際、法定養育費の金額で請求できるのは、話し合いや家庭裁判所の手続きで具体的な金額が決まるか、子どもが成人するまでのいずれか早い時までとされています。
離婚後における共同親権の適用と養育費の調整方法
離婚後共同親権や養育費について、具体的な適用関係を解説します。
- 離婚済みでも共同親権は適用できる
- 基本的に養育費の増額・減額などの影響はない
- 養子縁組・収入増減などの特別な事由があれば、養育費は調整される
- 養育費の取り決めなく離婚した場合は、交渉・調停で金額を調整できる
結論、離婚後に共同親権を選択したことによる養育費への影響はほとんどありません。
離婚済みでも共同親権は適用できる
2026年5月までに改正法が施行されますが、改正法の施行までに離婚した場合も、施行後に共同親権に変更できる可能性はあります。
しかし、共同親権への変更には、家庭裁判所に審判を申し立てる必要があるほか、「子どもの利益のため必要がある」と認められることが条件です。
基本的に養育費の増額・減額などの影響はない
共同親権を選択したからといって、基本的に養育費の額が増減するといった影響はありません。
養育費の増減については改正前のとおりで、協議や調停、審判で変更すること自体は可能です。ただし、父母の意見が一致しないときは、家庭裁判所の判断に委ねられます。
養子縁組・収入増減などの特別な事由があれば、養育費は調整される
養育費の増減について父母の意見が一致しないとき、家庭裁判所の判断に委ねられることは、先ほど解説したとおりです。
しかし、一般的には新たに養子縁組をした、病気やケガなどで大きく収入が変動したといった事情があれば、養育費の増減は認められることがあります。
養育費の増減ができるケースについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひあわせてご覧ください。
養育費の取り決めなく離婚した場合は、交渉・調停で金額を調整できる
養育費の取り決めをせずに離婚した場合、父母間の交渉(協議)や家庭裁判所での手続き(調停・審判)で金額を取り決めます。
養育費の具体的な金額を決める方法は自由ですが、家庭裁判所での手続き(調停・審判)では、標準算定表を使って決めるのが一般的です。
養育費の金額の計算方法について、詳しくは以下の記事でご確認ください。
なお、改正法が施行されてから離婚した場合は、前述のとおり、具体的な金額の取り決めがなくても法定養育費の請求が可能です。
一方で、改正法が施行される前に離婚した場合は、法定養育費の請求はできません。(民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)附則第3条第2項)
2 新民法第七百六十六条の三(新民法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日前に離婚し、婚姻が取り消され、又は認知した場合については、適用しない。
引用元 民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)附則第3条第2項
養育費についての困りごとは弁護士に相談しよう
2026年5月に共同親権に関する制度の改正が施行されたとすると、離婚後の親権の制度が改正されるのは77年ぶりとなります。養育費についても、先取特権の付与や法定養育費制度の創設など、大きな改正が待っています。
特に養育費については、従来よりも確実に支払ってもらえるような改正となりました。しかし、制度が変わっても、新しい制度を知り、状況に応じて利用できなければ意味がありません。
養育費についてのお悩みや困りごとは、養育費問題に詳しい弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士への相談や依頼に費用はかかりますが、適正な養育費の金額を取り決め、不払いへの対策もとることができます。
ただし、相談・依頼する弁護士は、養育費に関する実績が豊富な弁護士を選ぶようにしてください。経験豊富な弁護士を選ぶことで、養育費に関する問題に対してより的確なアドバイスや対応を期待できます。
養育費に関して弁護士に無料で相談できる窓口や相談時の注意点、弁護士の選び方などは、ぜひ以下の記事をご覧ください。
まとめ
2026年5月までに、離婚後の共同親権を選択できるようになります。共同親権を選択したことによって、養育費の負担がなくなることや、金額が増減するといった影響はありません。
一方で、法改正によって先取特権が付与されたり、法定養育費制度が創設されたりなど、養育費に関して新たな制度が開始される予定です。
改正法の施行が迫るなか、離婚時にどのような選択をすればよいのか、養育費はどうなるのかと不安な方は、弁護士に相談することをおすすめします。
共同親権導入後の養育費に関するよくある質問
共同親権を持つ親が再婚したら、養育費は減額になる?
原則として父母の話し合い次第ですが、家庭裁判所が判断する場合は、再婚しただけで養育費が減額されるケースはそれほど多くありません。
もっとも、再婚すると配偶者を扶養する義務も負うため、再婚が養育費を減額する理由になることはあります。
また、再婚後にその親が連れ子と養子縁組をしたり、新たに子どもを設けたりした場合には、扶養すべき子が増えるため、減額理由になることもあります。
養育費を支払わない人が多いって本当?
本当です。
厚生労働省が実施した平成28年度 全国ひとり親世帯等調査の結果によると、現在も養育費を受けていると回答したのは母子世帯で全体の24.3%、父子世帯で全体の3.2%という結果でした。
養育費の目安はいくら?
厚生労働省が実施した
平成28年度 全国ひとり親世帯等調査の結果によると、養育費の平均月額は母子世帯で43,707円、父子世帯で32,550円でした。
ただし、家庭裁判所の実務上、養育費の目安は標準算定表を使って算定します。標準算定表は、父母の収入や子どもの人数、年齢によって標準的な養育費の額を計算する仕組みです。
養育費の相場については、以下の記事で詳しく解説しています。
https://clamppy.jp/rikon/column/youikuhi/188