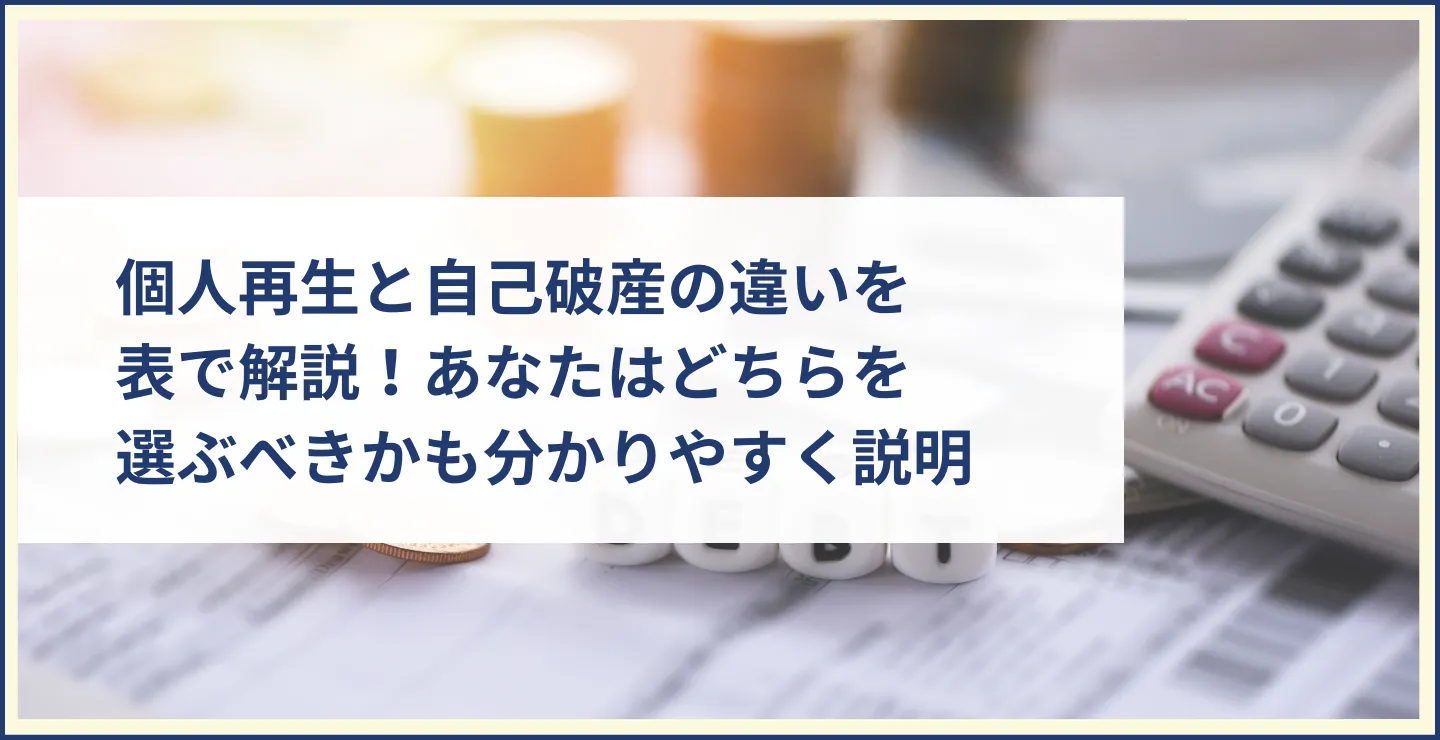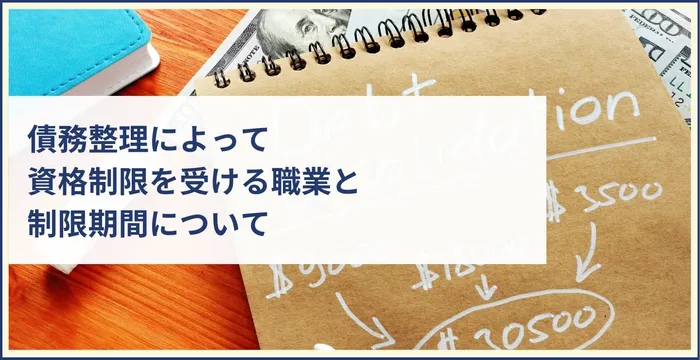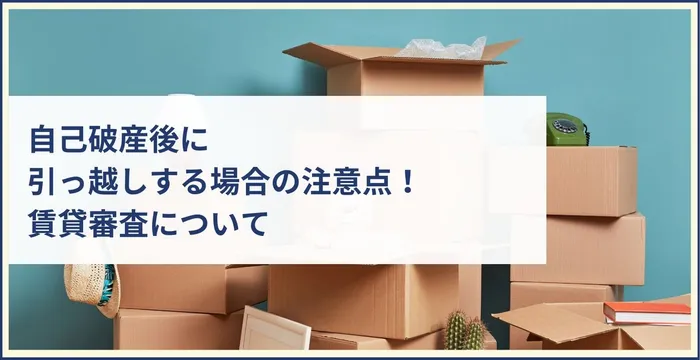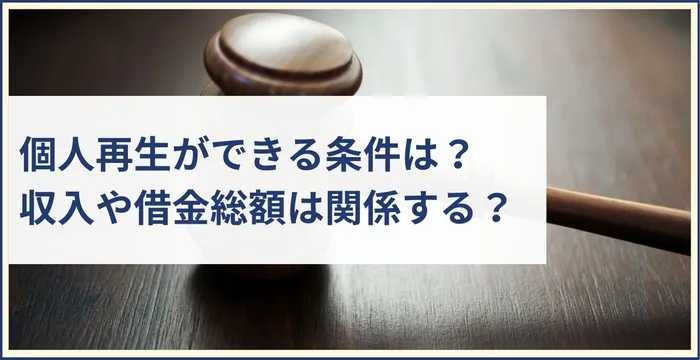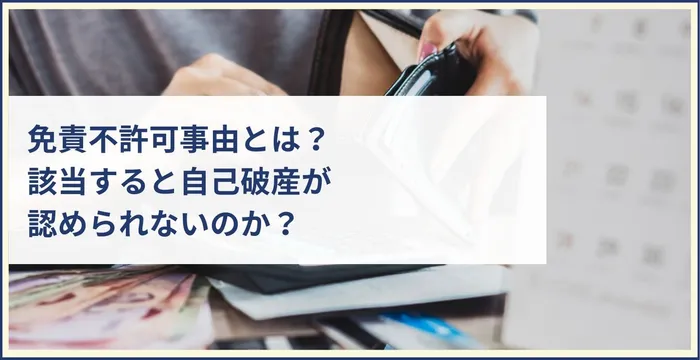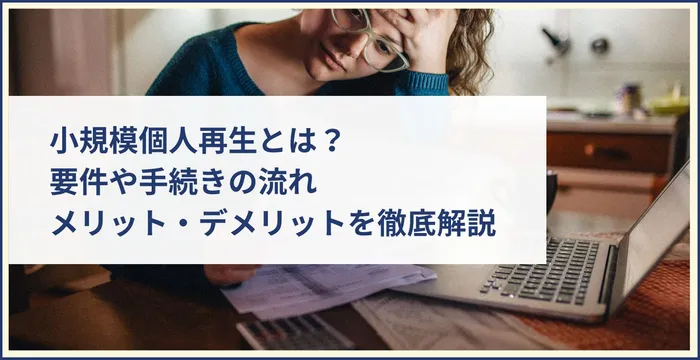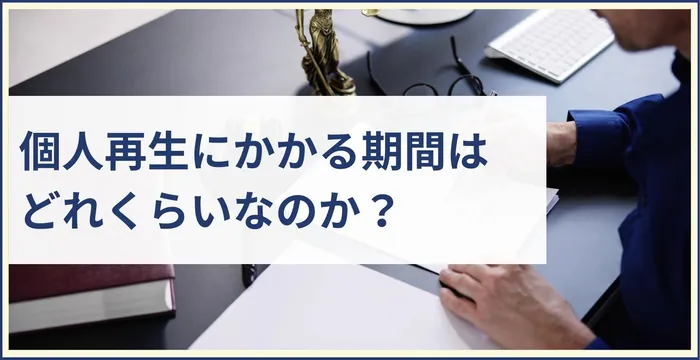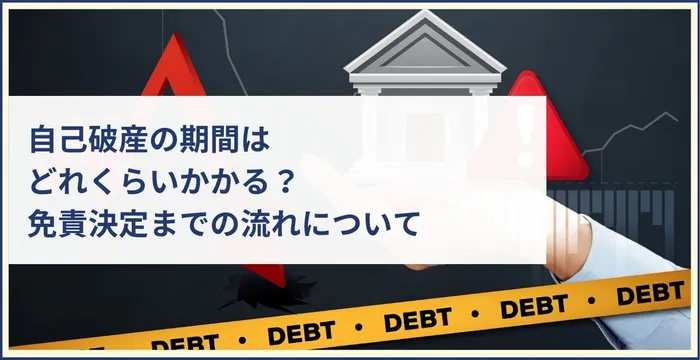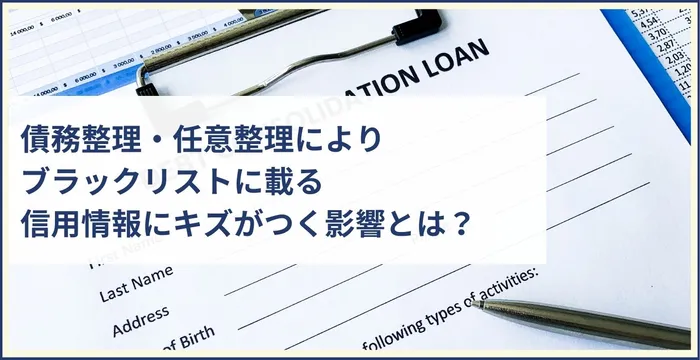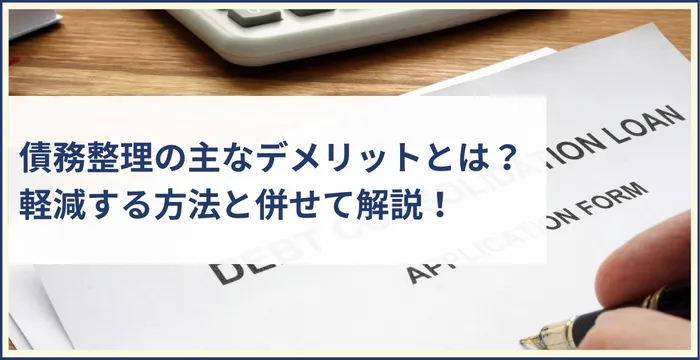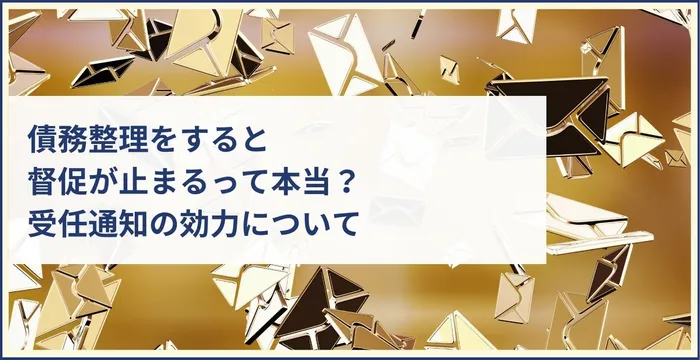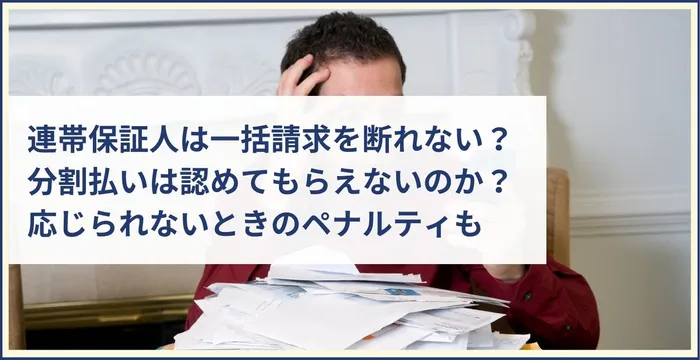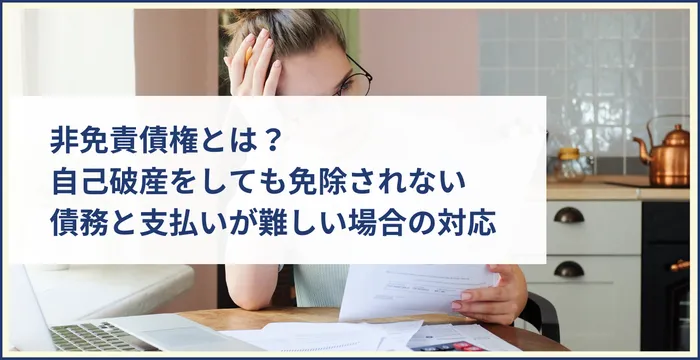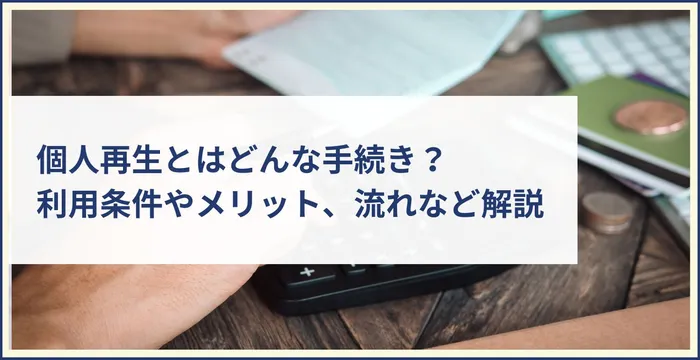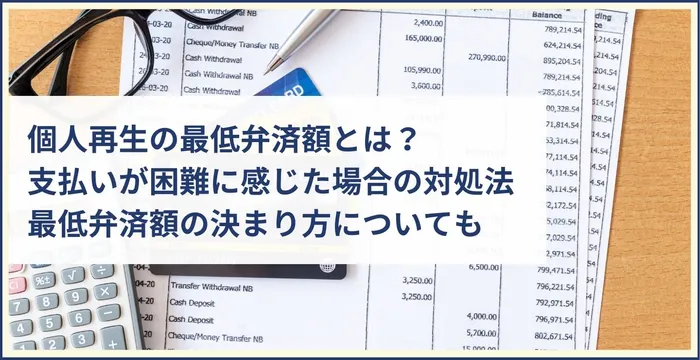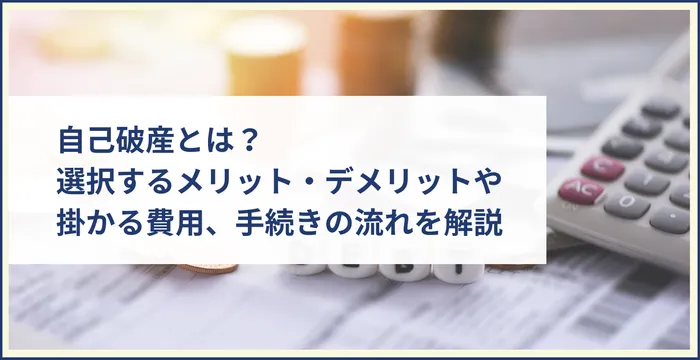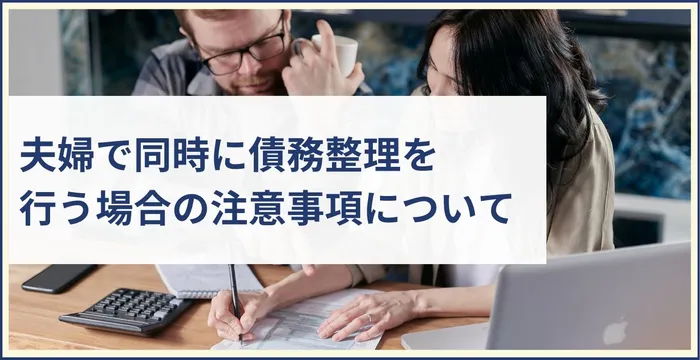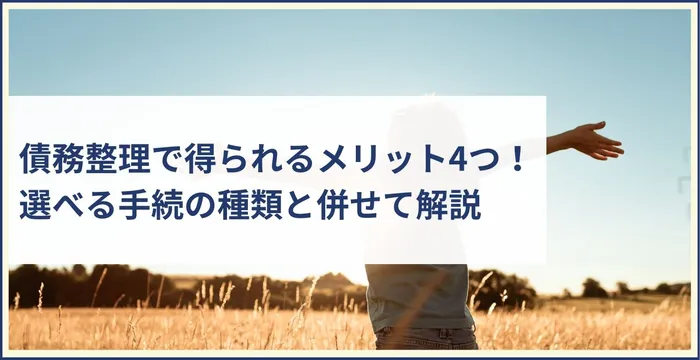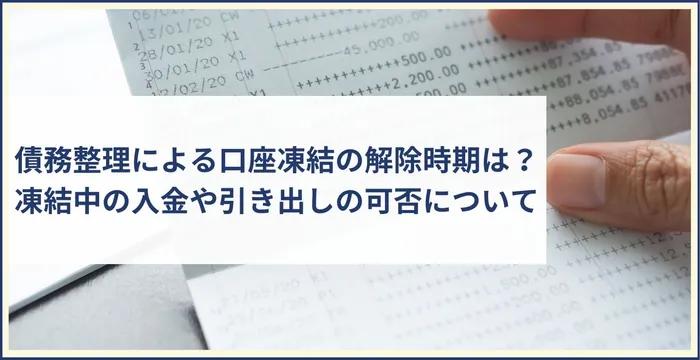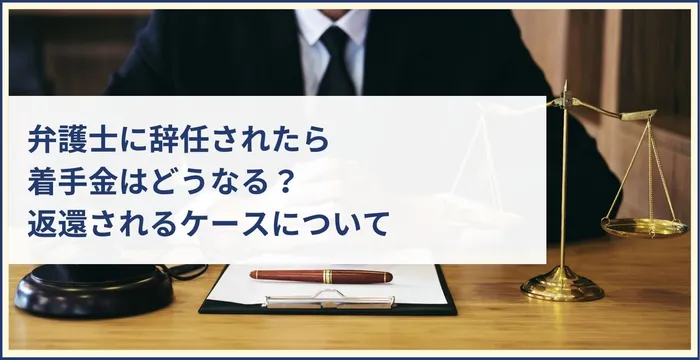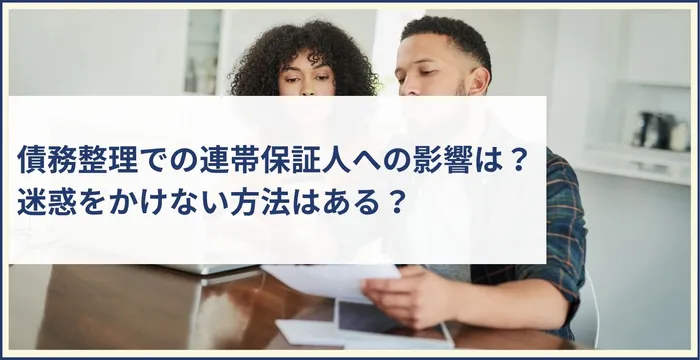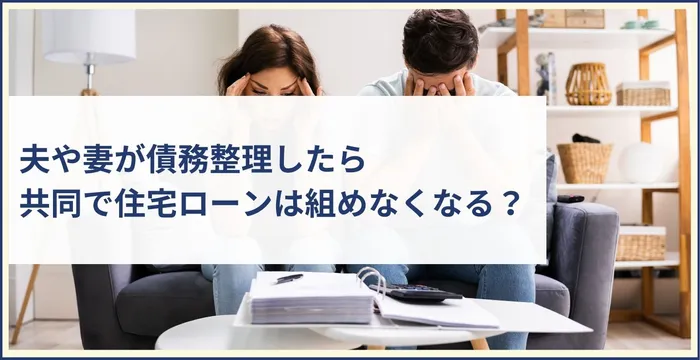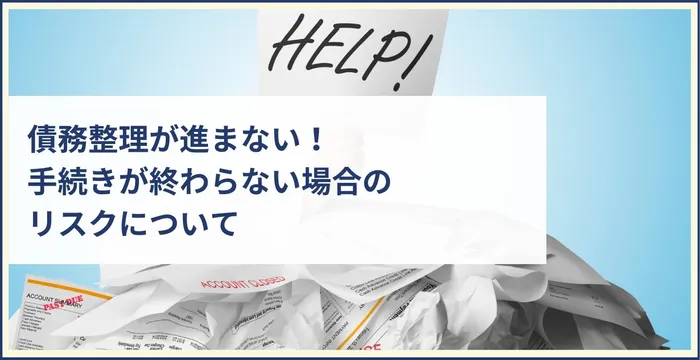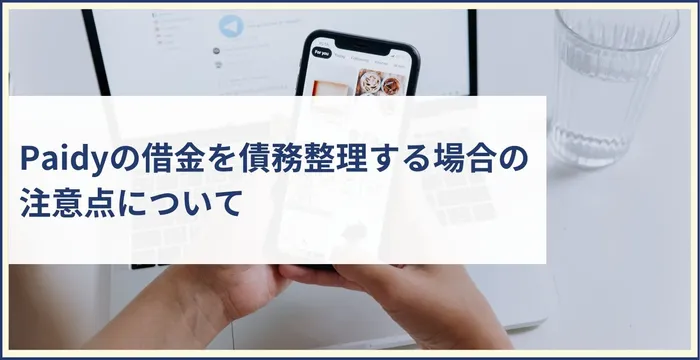個人再生と自己破産の違いを10項目で解説
個人再生と自己破産はどちらも裁判所を通じて手続きをする債務整理の1つですが、両者には以下のような違いがあります。
| 違い |
個人再生 |
自己破産 |
| 借金 |
借金を1/5~1/10程度減額できる(最低でも100万円は借金が残る) |
借金が全額免除される(非免責債権は除く) |
| 財産 |
ローン返済中の財産以外は手元に残せる |
一定の財産を除いて処分の対象になる |
| 職業の資格制限 |
なし |
一部あり |
| 引っ越しや旅行の制限 |
なし |
あり |
| 安定した収入 |
必要 |
不要 |
| ギャンブルや浪費による借金 |
減額可能 |
免責不許可事由に該当するため、免責許可が下りない可能性が高い |
| 債権者の同意 |
小規模個人再生の場合は必要 |
不要 |
| 手続き・弁護士費用 |
50~90万円程度 |
30~30万円程度 |
| 手続きにかかる期間 |
6ヶ月~1年半程度 |
3ヶ月~1年程度 |
| 住宅ローンの保証人への影響 |
住宅ローン特則を利用すれば保証人への影響を避けられる |
保証人への影響は避けられない |
ここからは、それぞれの違いについて1つずつ詳しく解説していきます。
1.借金が減るか免除されるか
| 債務整理 |
借金の減額幅 |
適用条件 |
| 個人再生 |
借金を1/5~1/10程度まで減額可能。
ただし、減額後の借金は3~5年かけて返済が必要 |
住宅ローンを除く借金総額が5,000万円以下 |
| 自己破産 |
借金の返済義務が免除され、手続き完了後は返済の必要なし |
特に上限なし(ただし免責不許可事由に該当しないことが条件) |
個人再生と自己破産の1個目の違いは、借金が減るか返済義務そのものが免除されるかという点です。個人再生では、借金を1/5~1/10程度まで減額できますが、減額後の借金は3年(最長5年)かけて自力で返済しなければなりません。
それに対して自己破産では、借金の返済義務が免除されるため、手続き後は借金の返済から解放されます。なお、個人再生の場合は、住宅ローンを除く借金の総額が5,000万以下でないと手続きができません。
2.財産を手元に残せるか
| 債務整理 |
残せる財産 |
| 個人再生 |
ローン返済中の住宅や車などを除くすべての財産
※住宅ローン特則を利用すれば、ローン返済中の住宅も手元に残せる |
| 自己破産 |
・評価額が20万円以下の財産
・99万円までの現金
・法律で差し押さえが禁止されている財産(日常生活や仕事、礼拝に欠かせないもの、年金・生活保護・児童手当の受給権など) |
個人再生の場合、減額後の借金は返済しなりませんが、財産は原則として手元に残したまま手続きが行えます。原則、ローンが残っている住宅や車は処分の対象となりますが、個人再生では「住宅ローン特則」が利用できます。
住宅ローン特則を利用するための要件を満たしていれば、住宅ローンを減額せず従来通り返済を続ける代わりに、住宅を手元に残したまま個人再生を行うことが可能です。
それに対して自己破産は、借金が帳消しになる代わりに、評価額が20万円を超える財産は原則として処分の対象となります。ただし、生活や仕事、礼拝に欠かせない財産や年金・児童手当などの受給権、99万円以下の現金などの一定の財産は、評価額が20万円を超える場合でも手元に残しておくことが可能です。
3.職業の資格制限があるか
| 債務整理 |
資格制限の有無 |
| 個人再生 |
なし |
| 自己破産 |
一部あり(免責許可が下りるまで特定の職業・資格が制限される) |
個人再生には職業の資格制限がないため、手続きを行っても仕事に影響を与えることは一切ありません。それに対して自己破産では、免責許可が下りるまで一定の職業・資格が制限されるため、一時的に仕事ができなかったり、資格を失ったりする場合があります。
免責許可とは、裁判所に自己破産することを許可されることです。自己破産は、申告すれば誰でも許可が下りるわけではありません。
財産や収入の有無などさまざまな情報を調査したうえで、最終的に裁判所が自己破産の可否を決定します。
自己破産で制限される主な職業・資格は以下の通りです。
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 公認会計士
- 宅地建物取引士
- 中小企業診断士
- 公証人
- 警備員
- 生命保険外交員
- 会社役員(取締役、執行役員、監査役など)
免責許可が下りた後は職業の資格制限が解除されるため、復職して働けるようになります。
4.引っ越しや旅行に制限がかかるか
| 債務整理 |
引っ越し・旅行の制限 |
| 個人再生 |
制限なし |
| 自己破産(管財事件) |
手続き中は裁判所の許可が必要(無許可の場合、免責が下りない可能性あり) |
| 自己破産(同時廃止事件) |
制限なし(手続きと同時に破産手続きが終了するため) |
自己破産は、申請時点で所有している財産状況に応じて2種類の手続き方法に分かれます。基準は裁判所によって異なりますが、一般的には下記時の基準で判断されることが多いです。
| 管財事件 |
・20万円以上の価値がつく財産がある
・33万円以上の現金がある |
| 同時廃止事件 |
上記に当てはまらず、換価して債務の返済に回すだけの財産がない |
個人再生の場合は引っ越しや旅行に制限がありませんが、管財事件の場合は財産の隠匿や逃亡を防ぐため、手続き中は裁判所からの許可を得てからでないと引っ越しや旅行ができません。
裁判所の許可を得ずに引っ越しや旅行をすると、免責許可が下りなくなる可能性があるので注意が必要です。一方で同時廃止事件として処理される場合は、破産手続き開始決定と同時に破産手続きが終了するため、引っ越しや旅行に制限はかかりません。
5.安定した収入が必要か
| 債務整理 |
収入の要件 |
| 個人再生 |
継続的かつ安定した収入が必要(正社員でなくても可) |
| 自己破産 |
収入の要件なし(無職や生活保護受給者でも可) |
個人再生の場合は、減額された後の借金を返済していかなければならないため、継続的かつ安定した収入が必要になります。この条件に当てはまっていれば、正社員でない場合や年金受給者でも手続きが可能です。
ただし、アルバイトやパート、個人事業主は正社員に比べて収入が不安定になりやすいため、下記の条件を満たしていることが必要です。
| 勤務形態 |
条件 |
| アルバイトやパート |
・長期間にわたって勤めている
・短期バイトで点々とした働き方でない |
| 個人事業主 |
・継続的に反復した収入がある
・3ヶ月に一回程度でも返済を続けられるだけの収入がある |
無職や専業主婦(主夫)などの収入がない人や、生活保護受給者(受給中の借金返済が認められていないため)は個人再生を利用できません。また、収入が不安定な場合や今後受け取り続けられるとは限らない障害年金を受給している場合は、個人再生が認められない可能性があります。
それに対して自己破産の場合は、免責許可が下りれば借金を返済する必要がなくなるため、収入や職業の要件は一切ありません。そのため、下記のように個人再生が利用できない人でも手続きが可能です。
- 収入が不安定・少ない人
- 無職や専業主婦(主夫)
- 障害年金・生活保護受給者
6.ギャンブルや浪費による借金でも申し立てができるか
| 債務整理 |
ギャンブル・浪費の借金の扱い |
| 個人再生 |
申し立て可能 |
| 自己破産 |
免責不許可事由に該当するため、免責許可が下りない可能性あり |
個人再生では借金の原因は問われないため、ギャンブルや浪費によって抱えた借金であっても申し立てが可能です。それに対して自己破産の場合、ギャンブルや浪費は免責不許可事由に該当するため、自己破産を申し立てても免責許可が下りず、借金を減額できない可能性があります。
ただし、ギャンブルや浪費で作った借金でも、借金額や自己破産に至った経緯によっては裁判所の裁量で免責が認められるケースもあります。「反省している態度が見受けられる」「更生の可能性がある」と認められれば裁量免責が下りやすくなる傾向です。
弁護士に相談すれば、裁量免責を受けるために必要なことを教えてもらえます。免責不許可事由で自己破産したい場合は必ず弁護士に相談しましょう。
7.債権者の同意が必要か
| 債務整理 |
債権者の同意の必要性 |
| 小規模個人再生 |
必要(過半数の同意が必要) |
| 給与所得者等再生 |
不要 |
| 自己破産 |
不要 |
自己破産の場合は、債権者の同意を得なくても手続きが行えます。しかし、個人再生(小規模個人再生)の場合は債権者の過半数の同意を得なければなりません。
個人再生には、収入の安定度に応じて下記の2種類があります。
| 項目 |
小規模個人再生 |
給与所得者等再生 |
| 条件 |
・住宅ローンを除く5.000万円以下の債務
・安定した収入がある(非正規の収入でも可) |
・住宅ローンを除く5.000万円以下の債務
・毎月安定した給与収入があり、その収入額の変動が少ない(正社員などの固定給) |
| 雇用形態 |
・個人事業主
・アルバイト・パート
・正社員 |
・正社員
・アルバイト・パート |
| 債権者の同意の必要性 |
必要 |
不要 |
| 手続き後の返済額 |
下記のうちどちらか高い金額
・最低額の100万
・借金総額の1/5~1/10 |
下記のうち最も高い金額
・最低額の100万
・借金総額の1/5~1/10
・可処分所得2年分 |
小規模個人再生では、債務者が裁判所に提出した再生計画案が債権者に送付され、同意するかどうかの決議が行われます。そこで債権者の頭数の過半数の反対がある場合、または反対した債権者の債権額が半額を超える場合は個人再生の認可が受けられません。
ただし、個人再生で債権者の同意が必要になるのは小規模個人再生のみで、給与所得者等再生を行う場合は自己破産と同様に債権者の同意なく手続きを進めることが可能です。上記の表の通り、小規模個人再生と給与所得者等再生では手続き後に残る借金が異なるため、返済額に納得しない債権者がいる場合は認可されない可能性があります。
以下では、毎月30万円の収入(可処分所得)がある人が1000万円の借金を個人再生した場合、小規模個人再生と給与所得者等再生では返済額にどのくらい違いがあるのかまとめました。
小規模個人再生
(借金総額の1/5~1/10) |
100~200万円 |
給与所得者等再生
(可処分所得2年分) |
720万円 |
可処分所得とは、給与所得から税金などを差し引いた金額のことです。手続き後の返済額を比べると、給与所得者等再生の方が500万円以上多く、借金総額のうち2/3程度も残っています。
小規模個人再生は、正社員のように安定した収入があっても申告者が希望すれば利用可能です。しかし、債権者はなるべく多くの債権を回収したいと考えるため、給与所得者が小規模個人再生を希望しても反対される可能性があります。
特に、申請するまでに返済されていなかったり、給与収入が高額だったりする場合は反対されやすい傾向です。反対された場合は借入先に交渉しに行く方法もありますが、どうしても同意してくれない場合は給与所得者等再生での申請が必要でしょう。
8.手続き・弁護士費用の違い
個人再生と自己破産の8個目の違いは、手続きや弁護士への依頼にかかる費用です。個人再生では総額50~90万円程度、自己破産の場合は総額30~130万円程度の費用がかかります。
|
個人再生 |
自己破産 |
| 裁判所費用 |
2~30万円程度 |
2~50万円程度 |
| 弁護士費用 |
50~60万円程度 |
30~80万円程度 |
| 合計額 |
50~60万円程度 |
50~130万円程度 |
個人再生・自己破産でかかる裁判所の内訳は下記の通りです。
| 裁判所にかかる費用 |
個人再生 |
自己破産 |
概要 |
| 予納金 |
1万2,000~1万4,000円 |
1万〜1万5,000円 |
裁判所に納める。官報の掲載するための費用。 |
| 収入印紙代 |
1万円程度 |
1,500円程度 |
裁判所に申し立てるための手数料 |
| 郵券代 |
3,000〜5,000円 |
3,000〜5,000円 |
債権者へ個人再生を申し立てたことを知らせるための郵便切手代 |
| 個人再生委員の報酬 |
15~25万円 |
‐ |
個人再生委員に支払う報酬 |
| 破産管財人報酬 |
‐ |
20~50万円程度 |
管財事件・少額管財事件になった場合、破産管財人に支払う |
個人再生委員は、個人再生を申請した人の財産を調べたり再生計画書のアドバイスをしたりなど、手続き全体の監督・サポートを行います。一方で破産管理人とは、自己破産した人の財産を換価し、債権者に振り分ける手続きを行う人のことです。
裁判所が当事者とかかわりのない弁護士の中から選定します。個人再生・自己破産でかかる弁護士費用の内訳は下記の通りです。
| 弁護士にかかる費用 |
個人再生 |
自己破産 |
概要 |
| 相談料 |
1万円~ |
1万円~ |
依頼前に相談する際に発生する費用。1時間ごとに料金が加算される |
| 着手金 |
30万円程度 |
30~50万円程度 |
交渉結果に関わらず最低限支払わなければならない金額 |
| 報酬金 |
20~30万円 |
20~30万円 |
依頼していた交渉が成功した場合の報酬 |
9.手続きにかかる期間の違い
自己破産は、個人再生と比べて手続きが早く終わる傾向があります。
| 債務整理 |
手続きにかかる期間 |
| 個人再生 |
6ヶ月~1年半程度 |
| 自己破産(管財事件) |
6ヶ月~1年程度 |
| 自己破産(同時廃止事件) |
3ヶ月程度 |
個人再生は手続きが複雑で、申し立ての準備や手続きに時間がかかります。裁判所によっては手続き後に返済を続けられるかどうかを確認する「履行テスト」が6ヶ月程度行われる場合もあるため、手続きが終わるまで1年以上かかるケースもあります。
自己破産の場合は、手続きが「同時廃止事件」「管財事件」のどちらで処理されるのかによって期間が大きく異なります。管財事件として処理された場合は、破産管財人の選任や面談、破産者の財産や債務調査、債権者集会などが行われるので時間がかかる傾向です。
一方、同時廃止事件として処理された場合は破産管財人の選任が必要なく、破産手続き開始決定と同時に破産手続きが終了するため、短期間で手続きが終了します。
10.住宅ローンの保証人への影響を避けられるか
| 債務整理 |
住宅ローンの保証人への影響 |
| 個人再生 |
なし |
| 自己破産 |
あり |
前述のとおり個人再生では、「住宅ローン特則」を利用することで住宅を手放さずに手続きが行えます。住宅ローン特則を利用すると住宅ローンは減額されず、債務者が従来通り住宅ローンの返済を続けていくことになるため、保証人への影響を回避できます。
一方、自己破産では住宅ローンの返済が免除されるため、保証人が債務者の代わりに住宅ローンの支払い義務を負うことになります。
個人再生と自己破産の共通点は主に4つ
個人再生と自己破産の共通点は、主に以下の4つが挙げられます。
- ブラックリストに載る
- 督促が止まる
- 保証人に全額請求される
- 減額・免除されない借金がある
ここからは、それぞれの共通点について1つずつ詳しく解説していきます。
1.ブラックリストに載る
個人再生や自己破産などの債務整理を行うと、クレジットカードやローンなど申込や契約情報を保管している信用情報機関に金融事故として記録されます(ブラックリストの入りの状態)。
一度ブラックリスト入りの状態になると、5~7年経過するまで事故情報は削除されません。削除されるまでの間は、下記のような一定の行為が制限されます。
- クレジットカードの作成・利用ができない
- 新たな借り入れやローンの契約ができない
- スマホ・携帯電話を分割で購入できなくなる
- 賃貸契約の審査に通らない可能性がある
- 保証人になれない
なお、自分がブラックリストに登録されているかどうかは、次の3つの信用情報機関に信用情報を開示請求することで、確認できます。
| 機関 |
確認できる信用情報 |
手数料 |
| 株式会社シー・アイ・シー(CIC) |
・クレジットカード/信販会社/消費者金融の利用状況
・携帯電話端末の分割払い |
・インターネット:500円
・郵送:1,500円~1,650円 |
| 株式会社日本信用情報機構(JICC) |
・クレジットカード/消費者金融の利用状況
・携帯電話端末の分割払い |
・スマホアプリ:1,000~1,300円
・郵送:1,300円 |
| 全国銀行個人信用情報センター(KSC) |
・銀行や信用金庫/信用組合の利用状況
・信用保証協会への滞納 |
・インターネット:1,000円
・郵送:1,679円~1,800円 |
また、ブラックリストだけでなく、国が発行する機関紙である「官報」にも名前や個人再生・自己破産をした事実が掲載されてしまいます。これは、すべての債権者に対して個人再生や自己破産の手続きをとっていることを伝えるためです。
官報は、インターネットで検索すれば誰でも見れてしまうため、家族や職場の人にもばれてしまう可能性があることを頭に入れておきましょう。
2.督促が止まる
個人再生や自己破産の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると、債権者に「受任通知」という通知書が送付されます。貸金業者や債権回収業者は、受任通知を受け取った後に債務者に対して直接督促することが貸金業法で禁止されているため、その後の取り立て・督促はできません。
消費者金融やクレジットカード会社、信販会社、債権回収業者から取り立てを受けていた場合は、受任通知後に督促が完全にストップします。ただし、銀行や信用金庫など貸金業法が適用されない金融機関や個人から借金していた場合は、受任通知後の督促が禁止されていません。
そのため、弁護士や司法書士に依頼した後も督促を受ける可能性があります。
3.保証人に全額請求される
主債務者が個人再生や自己破産を行うと、借金の返済義務が保証人に移るため、保証人は債権者から一括請求を受けることになります。個人再生や自己破産で減額・免除されるのは主債務者の債務のみで、保証人の債務は減額・免除されません。そのため、保証人には借金全額の返済義務が残ります。
ただし、個人再生の場合は主債務者も減額された後の借金を返済しなければならないため、保証人が負担するのは主債務者が返済すべき金額を差し引いた部分になります。なお、主債務者が個人再生や自己破産をした場合、保証人は主債務者に対して求償権を行使することができません。
求償権とは、債務者本人に代わって支払った債務について、債務者本人に対して弁済分の返還を請求できる権利のことです。
通常、保証人が主債務者の借金を肩代わりした場合、保証人は主債務者に対して求償権を行使できます。しかし、主債務者が個人再生や自己破産を行った場合、主債務者は減額・免除された分の借金を返済する義務が消滅します。
そのため、保証人が代わりに支払ったとしても、主債務者に対して返済を求めることはできません。このように借金やローンで保証人を立てていた場合、個人再生や自己破産を行うと保証人に多大な迷惑をかけてしまうため、手続きを行う前には保証人と十分に相談することが望ましいといえます。
4.減額・免除されない借金がある
個人再生や自己破産を行っても、すべての借金が減額・免除されるわけではありません。「非免責債権」に該当する以下のものは減額・免除の対象外になります。
| 租税等の請求権 |
国税・地方税・公的年金・健康保険料・下水道料金など |
| 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 |
DVやモラハラ、名誉毀損などの慰謝料、詐欺や横領、窃盗を働いたことによる賠償金 |
| 故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権 |
・飲酒運転や煽り運転など、危険運転致死傷罪が成立するような交通事故で人を死亡・ケガさせた場合の賠償金
・人に暴力を振るって死亡・ケガさせた場合の賠償金 |
| 扶養義務に係る請求権 |
未成熟の子どもに対する養育費、妻・夫への婚姻費用 |
| 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権・預り金返還請求権 |
個人事業主が個人再生や自己破産を行った場合の従業員の給料や退職金 |
| 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権 |
故意または過失によって債権者名簿に記載しなかった債権者に対する債務 |
| 罰金等の請求権 |
罰金、科料、過料、交通違反の反則金、追徴金、刑事訴訟費用など |
なお、借金の中に非免責債権に該当するものがあっても、個人再生や自己破産の手続き自体は可能です。非免責債権に該当する借金は減額・免除されないだけで、非免責債権に該当しない借金であれば減額・免除されます。
個人再生のメリット│借金を1/5〜1/10程度に減らせる
個人再生を行うメリットとしては、主に以下の3つが挙げられます。
- 借金を1/5〜1/10程度に減らせる
- 車や住宅を手元に残せる可能性がある
- 仕事や私生活への影響を最小限に抑えられる
ここからは、それぞれのメリットについて1つずつ詳しく解説していきます。
借金を1/5〜1/10程度に減らせる
個人再生を行えば、先述の通り借金を1/5~1/10程度まで減額することが可能です。個人再生で減額できる金額は、借金の総額によって異なります。
| 借金の総額 |
最低弁済額(個人再生後に返済しなければならない金額) |
| 100万円未満 |
借金額と同額 |
| 100万円以上500万円以下 |
100万円 |
| 500万円超1,500万円以下 |
借金額の1/5 |
| 1,500万円超3,000万円以下 |
300万円 |
| 3,000万円超5,000万円以下 |
借金額の1/10 |
個人再生後は、最低弁済額を3年かけて返済していくことになります。特別な事情があれば、返済期間を最長5年まで延長できるため、無理のない範囲で借金を返済可能です。
ただし、住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円を超える場合は個人再生の申し立てができないため、返済できない場合は自己破産を検討する必要があります。また、借金の総額が100万円未満と比較的少額である場合は、費用や手間がかかる割にほとんど恩恵が受けられない、または費用倒れしてしまう可能性があるので注意が必要です。
車や住宅を手元に残せる可能性がある
個人再生の場合、ローンを完済していれば車や住宅を手元に残したまま借金を減額できます。ローンの返済がまだ終わっていない車は、ローン会社や金融機関が所有権を持っているため、個人再生を行うと処分の対象になります。
住宅ローン返済中の住宅も抵当権が設定されているため、原則は処分の対象です。しかし、住宅ローン特則を利用すれば、従来通り住宅ローンの返済を続けることを条件に住宅を手放さずに済みます。
住宅ローン特則を利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 個人再生を行う本人が対象の住宅を所有している(共有名義でも可)
- 建物の床面積の2分の1以上が居住用である
- 個人再生を行う本人が対象の住宅に居住しているか、居住予定である
- 対象の住宅に住宅ローン以外の抵当権がない
- 税金などの滞納で対象の住宅が差し押さえされていない
- 保証会社による代位弁済から6ヶ月以上経過していない
仕事や私生活への影響を最小限に抑えられる
個人再生では、自己破産とは違って職業の資格制限がありません。自己破産では制限を受ける仕事・役職に就いている人でも、個人再生なら一時的に仕事ができなくなったり、解任されたりする心配がないため、安心して仕事を続けられます。
また、個人再生なら手続き中の引っ越しや旅行で裁判所の許可を得る必要がなく、破産管財人に郵便物を見られる心配もないため、私生活への影響も最小限に抑えられます。
自己破産のメリット│借金の返済義務を免除できる
自己破産を行うメリットとしては、主に以下の2つが挙げられます。
- 借金の返済義務がなくなる
- 一定の財産は手元に残せる
ここからは、それぞれのメリットについて1つずつ詳しく解説していきます。
借金の返済義務がなくなる
自己破産なら、先述の通り裁判所から免責許可が下りれば、借金の返済義務を免除できます。借金がゼロになり、借金の返済から解放されるため、生活の立て直しに集中できるでしょう。
ただし、免責不許可事由があると自己破産を申し立てても免責許可が下りず、借金の返済義務が残ってしまうケースもあります。免責不許可事由とは、自己破産の際に借金の返済義務が免除されない原因・事情のことです。
主に以下のようなケースが免責不許可事由に該当します。
- ギャンブルや浪費、投機的な取引(先物取引・FXなど)によって多額の借金を抱えた場合
- 故意に財産を隠匿・破壊したり、他人に贈与したりした場合
- 特定の債権者にだけ借金を返済したり、財産を担保として差し出したりした場合
- 信用取引で購入した商品を直ちに換金した場合
- 自己破産の1年以内に詐術を使って新たに借金したり、信用取引を行ったりした場合
- 財産目録や債権者一覧に虚偽の記載をした場合
- 裁判所に対する説明を拒絶したり、虚偽の説明をしたりした場合
- 前回の自己破産で免責許可決定が確定した日から7年経過していない場合
ただし、免責不許可事由に該当する場合でも、先述したように裁判所の判断で免責が許可される「裁量免責」という制度があるため、借金額や自己破産に至る経緯が考慮されて免責許可が下りるケースもあります。
一定の財産は手元に残せる
自己破産を行ってもすべての財産が処分されるわけではありません。処分の対象となるのは、原則として評価額が20万円を超える財産です。
また、破産法で定めた自由財産と裁判所が認めた自由財産であれば、評価額が20万円を超える場合でも処分の対象外となります。
<破産法で定めた自由財産>
- 99万円までの現金
- 法律で差し押さえが禁止されている財産(日常生活や仕事、礼拝に欠かせないもの、年金・生活保護・児童手当の受給権など)
- 自己破産の手続きが開始された後に取得した財産
- 破産財団が放棄した財産(換金できる見込みがない財産)
<裁判所が認めた自由財産>
- 残高が20万円以下の預貯金
- 見込額が20万円以下の生命保険の解約返戻金
- 処分の見込額が20万円以下の車
- 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下の退職金債権
- 支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の7
- 居住している家屋の敷金債権
- 電話加入権
管財事件の自己破産であれば、裁判所に自由財産の拡張を申し立てることで、本来よりも多くの財産を手元に残せる可能性もあります。
個人再生と自己破産、どちらを選ぶべき?
個人再生と自己破産のどちらを選ぶべきかは、それぞれのメリットやデメリットを理解し、借金額や借金の理由、職業、安定した収入の有無、手放したくない財産の有無などを総合的に考慮した上で判断することが大切です。
| 個人再生がおすすめなケース |
自己破産がおすすめなケース |
| 継続的で安定した収入があり、借金が減額されれば完済の見込みがある |
莫大な借金を抱えており、個人再生を行っても完済できる見込みがない |
| 住宅ローンの返済がまだ終わっておらず、住宅の処分や保証人への一括請求を避けたい |
安定した収入がなく、今後も借金の返済に充てられるだけの安定した収入が得られそうにない |
| 住宅や車、保険などの財産を手元に残しておきたい |
住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円を超えており、個人再生が利用できない |
| 浪費やギャンブルで多額の借金を抱えている |
住宅や高級車などの高額な財産を持っていない |
| 自己破産で資格制限を受ける職種に就いている |
資格制限を受けない職種に就いている |
| 車を仕事で使うため、手放したくない |
税金や養育費など、自己破産しても支払いが免除されないものがない |
| 保証人がついている借金があり、保証人に迷惑をかけたくない |
すぐに借金をゼロにしたい |
個人再生は、継続的かつ安定した収入があり、財産を手元に残したまま借金の負担を減らしたい人に向いています。原則として財産の処分がないため、>住宅や高級車、貴金属、株式、保険など高額な財産を手元に残しておきたい人は個人再生がおすすめです。
ローン返済中の財産は処分の対象になるものの、住宅については「住宅ローン特則」を利用することで、住宅の処分や保証人への影響を回避可能です。
一方で自己破産は、個人再生を利用できる要件を満たしていない人や、個人再生で借金を減額できたとしても支払い能力が乏しく、完済の見込みがない人に向いています。
個人再生では借金が減額されても返済義務は残るため、莫大な借金を抱えている人や一定の収入がない人は返済が滞ってしまったり、5年以内に完済できなかったりする可能性があります。
自己破産では借金がゼロになるため、完済の見込みが立たない場合は自己破産を選ぶべきだといえます。
まとめ
個人再生と自己破産はどちらも裁判所を通じて手続きを行う債務整理の1つですが、さまざまな違いやメリット・デメリットがあります。個人再生と自己破産のどちらを選ぶかによって結果が異なってくるため、それぞれの特徴やメリット・デメリットを知り、自分の状況に適した手続きを選ぶことが大切です。
ただ、個人再生と自己破産のどちらを選ぶべきかどうか個人で判断するのは難しいうえ、債務整理の手続きも非常に複雑で手間も時間もかかります。そのため、債務整理を検討している場合は、早めに借金問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
個人再生と自己破産の違いに関するよくある質問
個人再生と自己破産、どちらのほうが家族にバレにくい?
個人再生と自己破産はどちらも家族にバレるリスクがありますが、どちらかというと個人再生の方がバレるリスクが低いです。個人再生や自己破産が家族にバレる主な理由は以下の通りです。
- 弁護士や裁判所からの郵便物を家族に見られた
- 官報を家族に見られた
- 家族から借金している
- 家族が保証人になっている
- 同居家族の協力が必要な書類の提出を求められた
- ブラックリスト入りによって、クレジットカードやローンが利用できない
- 住宅や車などの財産を没収された
特に自己破産の場合、住宅や車などの一定の価値がある財産はすべて手放さなければならないため、それがきっかけで同居する家族や保証人となっている家族にバレてしまうケースが多いです。
しかし、個人再生であれば原則として財産の処分がなく、住宅ローンが残っている場合でも住宅ローン特則を利用すれば処分されずに済むため、財産の没収によって家族にバレるリスクは自己破産と比較して低いといえます。
個人再生後、自己破産に切り替えや変更はできる?
個人再生をした後、自己破産に切り替え・変更することは可能です。ただし、自己破産へ切り替え・変更するには、支払い不能な状態に陥っていることを裁判所に認めてもらう必要があります。
また、支払い不能な状態であっても、以下に当てはまる場合は自己破産への切り替え・変更はできません。
- 給与所得者再生で再生計画許可決定が下りてから7年経過していない
- ハードシップ免責が確定してから7年経過していない
ハードシップ免責とは、個人再生の再生計画が認可された後、再生計画通りに返済するのが困難な状況に陥った場合、返済金額の3/4以上の返済を行っていれば、残りの借金の返済義務が免除になる制度のこです。
給与所得者再生やハードシップ免責を利用したことがある場合は、7年経過するまで待つ必要があります。