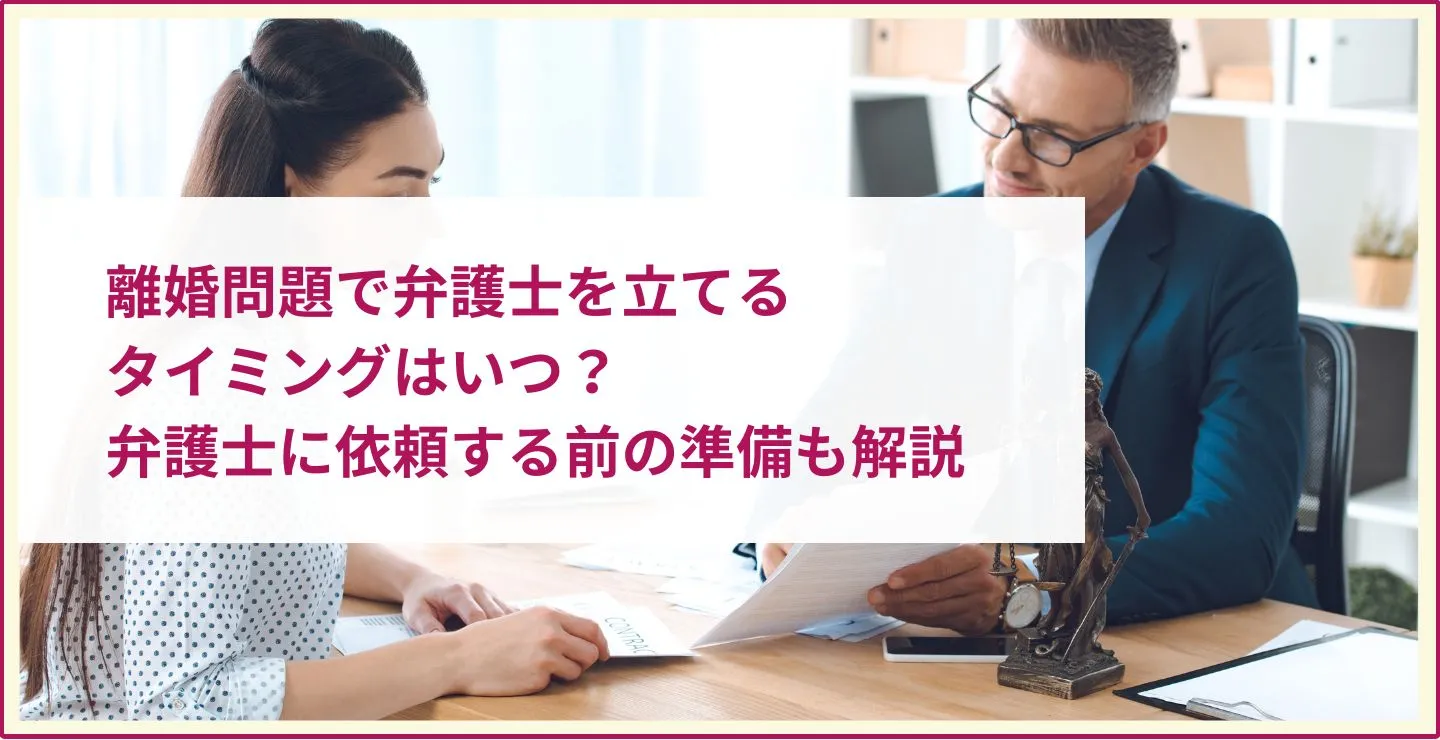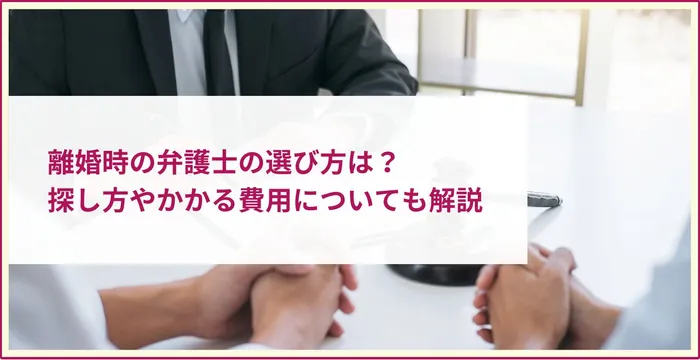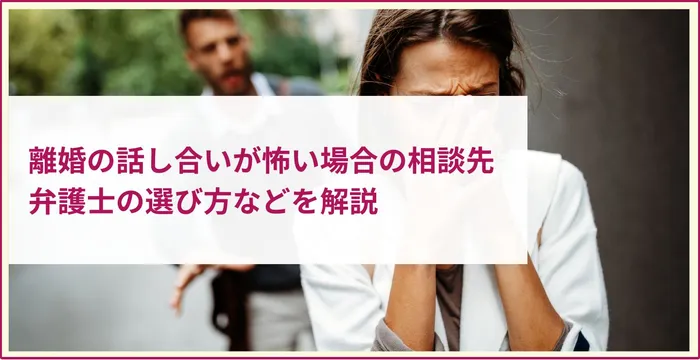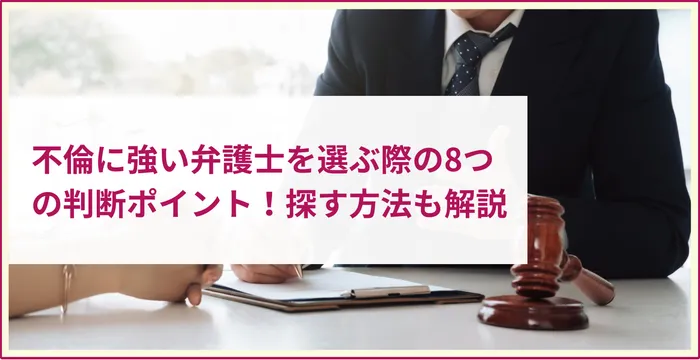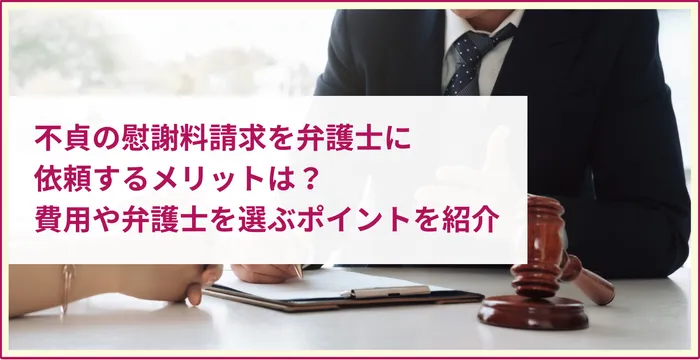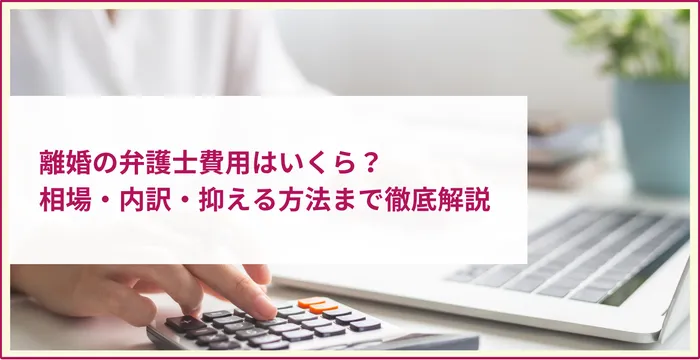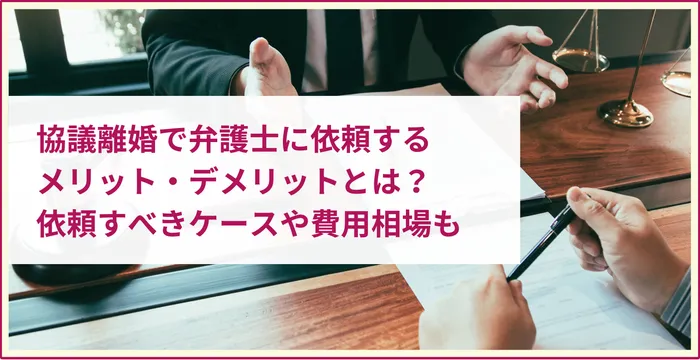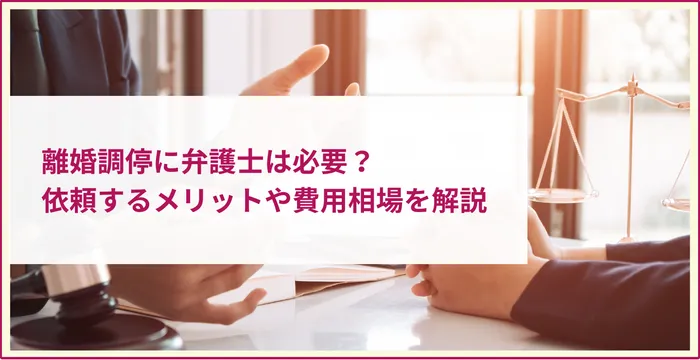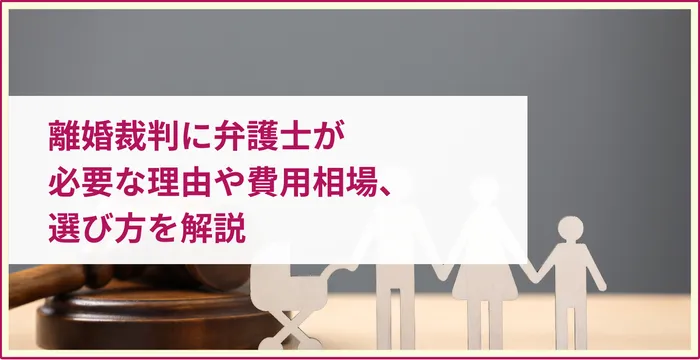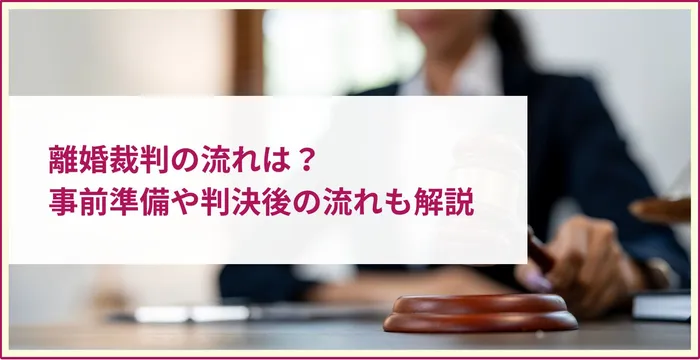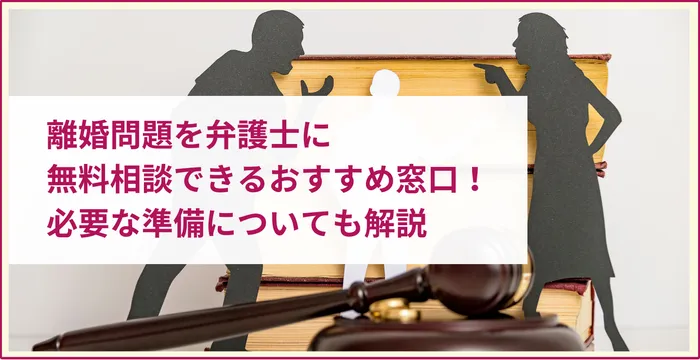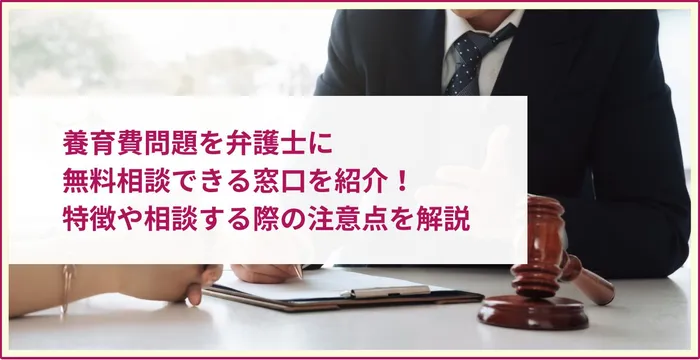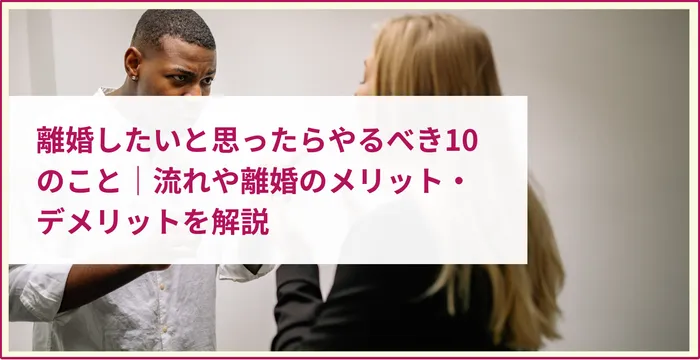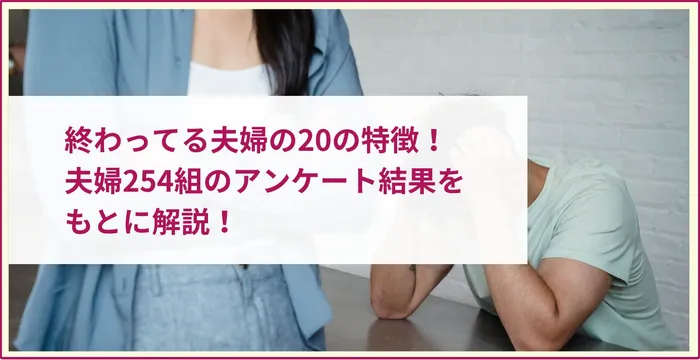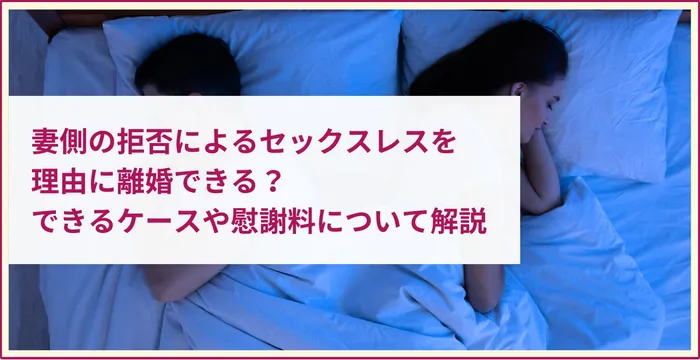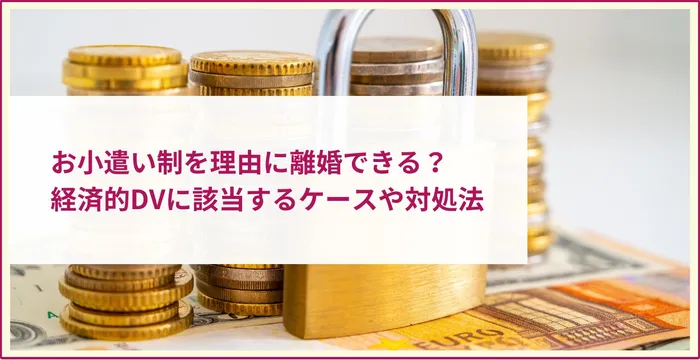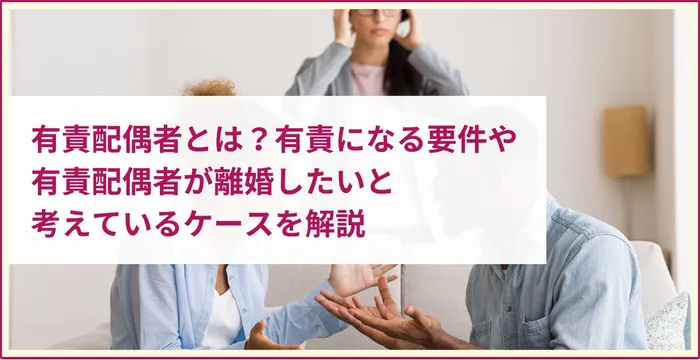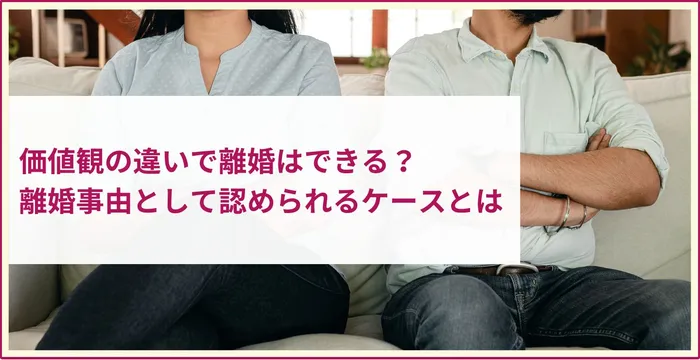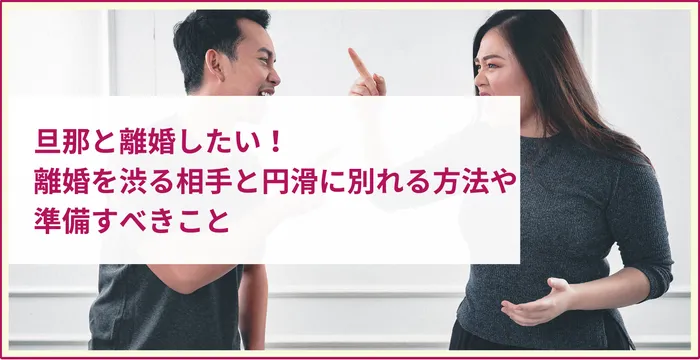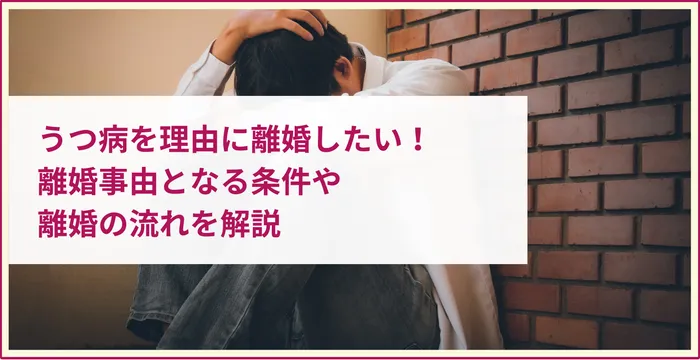離婚問題を弁護士に依頼するタイミング
離婚は感情面だけでなく、法律的にも複雑な問題を伴うため、弁護士に相談すべきタイミングを見極めることが重要です。以下のような状況に当てはまる場合は、できるだけ早めに弁護士に依頼することで、自分にとって不利にならないよう備えることができます。
- 離婚を配偶者に伝える前
- 相手方が弁護士をつけた時
- DVやモラハラを受けており相手に会いたくない時
- 調停や訴訟に発展した時
- 親権・養育費・慰謝料など譲れない要望がある時
- 証拠集めが必要な時
話し合いで解決できそうにないと感じたときや、相手とのやり取りに不安がある場合も、一度専門家に相談してみると安心です。
離婚を配偶者に伝える前
離婚を決意し配偶者に伝える前が、弁護士を立てるベストなタイミングといえます。
その理由として、以下のものが挙げられます。
- 相手に弁護士を立てられる前に主導権を握るため
- 感情的になり、揉めることを防ぐため
- 有利な条件で交渉を進めるため
- 離婚後の生活設計をしっかり立てるため
離婚するとなると、親権や養育費、慰謝料、財産分与、面会交流など、さまざまな条件を決めなければなりません。
これら一つひとつの条件を決めるには、離婚に至った原因や状況を整理し、必要な証拠を集めたうえで、法律に基づいた適正な主張をしなければなりません。
離婚を切り出す前に、法律の専門家である弁護士に依頼することで、何からどのように主張すればよいかアドバイスを受けながら、交渉や手続きを進めることができます。
また、離婚協議で合意した内容をもとに公正証書(離婚公正証書)を作成してもらうこともできるため、離婚後も合意内容が守られる安全性を高めることができます。
費用的に弁護士に依頼することが難しい場合、相談だけでもしてみるとよいでしょう。
相手方が弁護士をつけた時
相手方が弁護士をつけた時も弁護士を立てるべきタイミングといえるでしょう。
当然ですが、相手の弁護士は依頼者の利益のために動くため、あなたにとって不利な条件の主張をされることになります。
一般の方が、法律の専門家である弁護士相手に、交渉したり反論したりすることは容易ではありません。
相手側弁護士の巧みな交渉術によって、相手に有利な状況で話し合いが進む可能性が高くなるでしょう。
この点、相手が弁護士を立てたタイミングで自分も弁護士を立てることで、一方的に不利な状況に追い込まれるリスクを回避し、対等な立場で交渉できます。
親権争いや財産分与など法的にも難しい問題では、弁護士のサポートを受けることで自分の権利を主張しやすくなります。
DVやモラハラを受けており相手に会いたくない時
DVやモラハラを受けており、これ以上相手と会いたくない、当事者だけの交渉は困難と判断したときは、早めに弁護士に依頼することをおすすめします。
こうしたケースでは、被害の再発を防ぐためにも、まずは別居を前提に話し合いを進めることが一般的です。その際、弁護士を立てることで、自分の身を守りながら離婚手続きを進めることができます。
何より大きな利点は、弁護士が相手とのやり取りの「窓口」になってくれる点です。これにより、直接連絡を取る必要がなくなり、相手と顔を合わせたり、メッセージのやり取りをする精神的ストレスから解放されます。弁護士がすべてのやり取りを代理してくれるため、安全かつ冷静に交渉を進めることが可能になります。
また、DVやモラハラのケースでは、相手が離婚協議自体に応じようとしないことも少なくありません。その結果、調停や裁判に発展する可能性もありますが、そうした場合に備えて、弁護士とともに証拠を整理・収集しておくことが極めて重要です。法的な観点から適切な慰謝料の請求にもつながるため、弁護士のサポートは心強い味方となるでしょう。
調停や訴訟に発展する時
離婚には、夫婦間の話し合いで合意する「協議離婚」のほか、家庭裁判所を通じて行う「調停離婚」や「裁判離婚(訴訟)」といった手続きがあります。
話し合いでは解決が難しく、調停や裁判に進む可能性が高くなったと感じたときは、弁護士を立てるタイミングといえるでしょう。
調停や訴訟に進むと、申立書や訴状の作成、調停委員や裁判官とのやり取りが必要になります。また、自分の主張を裏付ける証拠を集めたり、法的に妥当な主張を展開するのは、専門知識がないと難しいものです。
その点、弁護士に依頼すれば、調停に同席してもらえるほか、訴訟では代理人として手続きを任せることができます。法律の専門家として、主張や証拠の整理を的確に行い、納得できる条件での解決を目指すことが可能になります。
また、調停や裁判に進んだ場合、相手も弁護士を立てる可能性は高まります。実際、日本弁護士連合会の統計によると、2023年の離婚調停(夫婦円満調停を含む)では、60.1%の事案で弁護士が関与していました。
相手と対等な立場で交渉を進めるためにも、こちらも弁護士を立てておくことが重要です。加えて、書類の作成や裁判所とのやり取りを任せられることで、時間的・精神的な負担も大きく軽減されます。
日本弁護士連合「夫婦関係調整調停事件における代理人弁護士の関与状況」
親権・養育費・慰謝料など譲れない要望がある時
親権や養育費、慰謝料などで譲れない条件があり、配偶者との合意が難しいときも弁護士に相談すべきタイミングの一つです。
親権や養育費の交渉は、子どもの利益に最大限配慮しつつ、養育者の負担をできるだけ軽減することが大切になります。
もっとも、親権や養育費・慰謝料の適正な金額を、当事者だけで判断することは簡単ではありません。
養育費の相場は、裁判所が公表している「養育費算定表」が目安となりますが、離婚原因や当事者の健康状態、子どもの進学状況などで算定する金額が変わる可能性もあります。
また、養育費の支払いは長期間にわたるため、途中で相手が支払わなくなるケースもあります。
子どもが成長するまで確実に養育費を受け取るためには、公正証書で合意書を作成し、法的な強制力を持たせることが必要です。
適正な養育費や慰謝料の金額を請求し、離婚後のトラブルを防止するためにも、弁護士に相談することをおすすめします。
証拠集めが必要な時
有利な条件で離婚問題を解決するうえで、証拠集めが重要と判断したときは弁護士に依頼すべきでしょう。
特に、配偶者の不倫やDV、モラハラなどが原因で離婚する場合、それらの存在を証明する証拠集めが重要となります。
不倫であれば、写真や動画、音声、領収書、メールやLINEのやりとりなど、DVを受けている場合は、医師診断書や日々の日記なども証拠となり得るでしょう。
また、財産分与にあたって財産の保有状況が分かりにくい場合も、証拠をどれだけ集められるかで財産分与の金額に影響する可能性があります。
この点、弁護士に相談することで、客観的に有効となる証拠やその証明力を高めるための材料、適切な集め方などについて、アドバイスを受けながら進めることができます。
証拠集めが重要と判断した場合、離婚問題に精通した弁護士のサポートのもとすすめることがおすすめです。
離婚問題で弁護士を立てる前にすると良いこと
ここでは、離婚問題で弁護士を立てる前にしておくと良いことを解説します。
事前に準備をしておくことで、弁護士との相談がスムーズに進むだけでなく、自分にとって有利な状況をつくりやすくなります。冷静に状況を整理し、無駄な費用や時間をかけずに手続きを進めるためにも、以下のポイントを意識しておきましょう。
- 離婚理由や希望をまとめておく
- 証拠となりそうなものを集めておく
- 費用を確認しておく
離婚理由や希望をまとめておく
弁護士を立てる前に離婚理由やこれまでの経緯、希望条件をできるだけまとめておきましょう。
裁判所の司法統計によると、離婚調停の申し立て理由として、次のものがあります。
- 性格が合わない
- 精神的な虐待がある(モラハラなど)
- 異性関係(不倫など)
- 浪費する(ギャンブルなど)
- 家族・親族との折り合いが悪い
- 性的不調和
- 同居に応じない
- 暴力を振るう
- 生活費を渡さない
- 家庭を顧みない など
離婚理由として、該当する可能性があるものはすべて整理しておきます。
また、次のように、離婚原因を考慮しながら希望条件をまとめておくとよいでしょう。
- 慰謝料を〇〇万円~請求したい
- 親権を獲得したい
- 養育費を大学卒業まで受け取りたい
- 財産分与で○○円受け取りたい
- 自宅に住み続けたい
- 面会交流は月〇回、1回〇時間までにしたい
- 年金分割の按分割合など
離婚理由や希望条件をしっかりと整理しておくことで、法的な面からみた請求の可否や実現できる見通しについて、正確なアドバイスを受けることができます。
証拠となりそうなものを集めておく
弁護士を立てる前に、証拠となりそうなものを準備しておくことが重要です。
準備すべき証拠は離婚理由や状況によって異なります。
不貞行為の証拠となり得るもの
- 不倫相手をホテルに入るところを撮影した写真や動画
- 相手が不倫を認めた音声の録音
- 不倫相手との食事や利用したホテルの領収書
- 不倫相手と頻繁にやりとりしているメールやLINEの画面 など
裁判上の離婚事由にあたる「不貞行為」といえるためには、単に不倫相手とのデートや食事だけでは足りず、肉体関係の証明が必要です。
DVやモラハラの証拠となる得るもの
- DVを受けているときの録画や録音
- モラハラで暴言を発している、物を壊しているときの録画や録音
- DVやモラハラの場面に立ち会っていた友人や親族の証言
- 暴力や暴言を詳細に記録した日記やメモ
- 医師の診断書 など
直接的な証拠から証拠の証明力を補完するものまで、できるだけ多くの証拠を集めることが重要です。
財産分与の請求に必要な証拠となり得るもの
- 預貯金通帳や取引履歴
- 保険証券の写しや解約返戻金証明書
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産評価納税通知書や査定書
- 給与明細書(財形積立などが記載されているケースがあります)
- 退職金に関する資料
- 車検証、車の査定書 など
夫婦関係が悪く普段コミュニケーションをとっていなければ、どのくらいの財産があるかを把握できていないことも少なくありません。
できるだけ財産状況を把握できるものを準備しておくことが重要です。
こういった証拠をしっかりと集めておくことで、弁護士が離婚手続きを進める方法や請求内容について適正な判断がしやすくなり、スムーズに進められます。
ただし、たとえば、不倫の証拠を入手するために不倫相手の後をつけたり、相手を脅したりしてはいけません。場合によっては、脅迫罪に該当する可能性があります。
あくまで自然に集められる証拠を準備しておきましょう。
費用を確認しておく
弁護士を立てる前に、依頼した場合の費用を確認しておくことが大切です。
たとえば、財産分与や慰謝料請求額が少ない場合、離婚できたとしても、弁護士費用が払えなくなる可能性があります。
離婚問題を弁護士に依頼したときの費用の目安は次のとおりです。
| 弁護士費用 |
相場 |
| 相談料 |
無料~1万円(1時間) |
| 着手金 |
20~40万円 |
| 報酬金 |
・離婚成立:20~30万円
・慰謝料請求:経済的利益の10~20%
・財産分与:経済的利益の10~20%
・親権の獲得:10万円~20万円
・養育費の請求:合意金額の2~5年分の10~20%
|
| 日当 |
3~5万円/1日あたり |
| 実費 |
印紙代や切手代など |
着手金は、弁護士に依頼した際に一括で支払う費用で、解決結果に関係なく、原則として返還されません。
一方、報酬金は、離婚事件を処理した結果、依頼者に利益をもたらした場合に発生する費用です。
依頼者の利益には、慰謝料や財産分与、養育費などの経済的利益と親権、面会交流などの非金銭的利益があり、弁護士に依頼する内容やどこまで請求できたかで報酬金が変わります。
また、次のように離婚手続きによっても弁護士費用は異なり、多くの場合、協議離婚より離婚調停や離婚訴訟のほうが高くなります。
| 離婚手続き |
費用の相場 |
| 協議離婚 |
20万円~60万円 |
| 離婚調停 |
50万円~100万円 |
| 離婚裁判 |
60万円~100万円 |
弁護士費用は、依頼時の状況や希望条件(離婚成立以外の親権など争点が多い)によって異なるため、ある程度の目安を知ったうえで依頼しましょう。
離婚の流れの中で弁護士が行うこと
離婚問題で弁護士に依頼したあと、どのように進むか、その後の流れについて解説します。
協議離婚の場合
協議離婚は、裁判所を介さず、当事者同士や弁護士を入れての話し合いで離婚する手続きです。
協議離婚の流れは次のとおりです。
- 離婚を切り出し、双方が離婚することで合意
- 離婚条件について話し合う
- 合意した内容を離婚協議書にする
- 離婚協議書を公正証書にする
- 離婚届けを提出する
協議離婚において、弁護士には次のような役割が期待できます。
・相手(相手弁護士)との交渉
・法的な観点からの主張・アドバイス
・離婚協議書・公正証書の作成
・財産分与や慰謝料の算定
・離婚後の手続きや生活に関する相談やサポート
離婚問題に強い弁護士に依頼することで、希望する条件で離婚を成立させやすくなり、早期の解決が期待できるでしょう。
また、相手との交渉や離婚協議書・公正証書の作成などの手続きを任せられるため、不安やストレスを軽減でき、離婚後のトラブルを回避しやすくなります。
離婚調停の場合
離婚調停は、裁判所(調停委員会)を介して当事者同士が話し合い、合意による離婚を目指す手続きです。
離婚調停の流れは次のとおりです。
- 申立書を作成し、裁判所へ提出
- 裁判所から呼出状が届く
- 調停期日が開かれ、話し合いを行う
- 1ヶ月に1回の頻度で何度か調停を繰り返す
- 合意内容をもとに調停調書を作成
- 離婚届の提出
離婚調停の調停期日は、1回で終わることもあれば10回以上に及ぶケースもあり、多くの場合、半年から1年程度で終了します。
離婚調停のなかで、弁護士には、次のような役割が期待できます。
・申立書や事情説明書などの書類作成
・調停への同席
・調停委員とのやり取りのサポート
・離婚条件に関するアドバイス
・(調停期日以外で)相手との交渉窓口 など
離婚調停では、申立書を作成し、裁判所へ提出しなければなりません。
養育費や財産分与なども話し合う場合には、申立書以外にもさまざまな書類が必要です。
弁護士に依頼することで、書類作成だけでなく、主張したい内容を陳述書にまとめる際もアドバイスを受けながら進められますサポートを受けられます。
また、調停に出席する前に打ち合わせしたり、話し合いの場に同席してもらえるため、調停委員に対し、離婚の経緯や原因、希望条件について、論理的で冷静な対応がしやすくなるでしょう。
また、相手方が提示する条件に対して、自分が譲歩して受け入れるべきなのか、より有利な条件を出して話合いを続けるべきなのかなどのアドバイスももらえます。
離婚裁判の場合
離婚裁判は、夫婦間における離婚の是非や、離婚の条件について、裁判官が一切の事情を考慮したうえで定める手続きです。
離婚裁判では、調停前置主義が採用されているため、原則として、先に離婚調停の手続きを踏むことが必要です。
調停前置主義とは、裁判や訴訟を提起する前に、調停を経なければならないとする制度。家庭に関する紛争をいきなり訴訟手続きによる公開の法廷で争うべきではなく、当事者間の話し合いで解決を目指すべきとする考え方から採用される制度です。
離婚裁判の流れは、次のとおりです。
- 家庭裁判所へ訴状を提出
- 訴状の送達・第1回期日の指定
- 答弁書の提出
- 第1回口頭弁論・その後複数回の期日
- 当事者への尋問(本人尋問)
- 判決の言い渡し
- 離婚届の提出
裁判所は訴状を受理すると、第1回口頭弁論の期日を指定し、原告と被告に通知します。被告に対しては訴状が送達されます。
被告は、裁判所から送られてきた訴状を確認し、事実の認識の相違や反論があれば答弁書に記載し提出します。
口頭弁論では、自分の主張の正当性を証拠を用いて主張・立証していきます。
証拠が出揃い、争点が整理されると証拠調べが行われ、離婚裁判では、この段階で当事者への尋問(本人尋問)が行われることが一般的です。
本人尋問とは、原告と被告それぞれが、これまでの経緯や経験した事実など、弁護士や裁判官の質問に答える手続きです
当事者双方の主張・立証から裁判官が事実認定できる状態になれば、判決を言い渡します。
離婚請求を認める判決が出て、相手方が控訴しないまま控訴可能期間(2週間)が経過すると、判決は確定して離婚が成立します。
離婚裁判における弁護士の役割は次のようなものです。
・訴状や答弁書など裁判所へ提出する書類の作成
・裁判所とのやり取り
・口頭弁論期日へ代理人として出席
・必要な証拠書類などのアドバイス
・法的観点から離婚条件の設定(慰謝料・財産分与・養育費など) など
裁判手続きでは、協議離婚や調停離婚と異なり、話し合いではなく、法的に正当な主張を展開し、立証することが必要です。
そのため、事前の入念な準備が重要となり、証拠に基づいた適正な主張をするとともに、不利益となり得る供述をしないことも大切です。
希望する離婚条件を実現するためには、弁護士が果たす役割は大きいといえます。
弁護士を早めに立てるメリット
離婚を検討し始めた段階で弁護士に相談することには、さまざまなメリットがあります。
まず、精神的な負担が軽減されるという点が大きいでしょう。離婚問題は感情のもつれや不安がつきものですが、弁護士が間に入ることで冷静に状況を整理し、必要な対応を具体的に示してくれます。早めに弁護士が介入してくれることで、先の見通しが立ちやすくなり、不安を最小限に抑えることができます。
また、離婚においては、親権、養育費、財産分与、慰謝料など多くの争点が発生する可能性があります。早い段階から弁護士の助言を受けておけば、証拠の確保や主張の組み立てといった準備を的確に進めることができ、交渉や調停を有利に進めやすくなります。相手との話し合いがこじれる前に、第三者としての弁護士が関与することで、感情的な衝突を避けられる点も重要です。
さらに、法的な手続きや書類の作成をすべて自分で行うのは負担が大きく、ミスが後々トラブルになることもあります。弁護士を立てることで、こうした手続きを任せることができ、結果としてスムーズに離婚を進めることができます。
離婚は人生における大きな決断です。後悔しないためにも、早い段階で専門家の力を借りるという選択肢を前向きに検討してみる価値は十分にあるでしょう。
弁護士への依頼を迷っているなら、まずは無料相談をおすすめします
正式に弁護士に依頼することを迷っているのであれば、弁護士を立てるべきかどうかを含めて相談しておくとよいでしょう。
事前に相談することで、弁護士を立てるほどではないと気づく場合もあれば、必要となる弁護士費用に対して、どれくらいのメリットがあるかが分かります。
弁護士への相談時に確認できる主な点はつぎのとおりです。
- 離婚手続きの進め方
- 離婚調停や離婚裁判の見通し
- 慰謝料や養育費、婚姻費用の相場
- 財産分与の見通し
- 弁護士費用の見積もり など
事前に相談することで、離婚するうえで合意しなければならないことや離婚協議や調停・裁判にかかる精神的・時間的な負担や手間などがわかります。
離婚問題の解決までにかかる労力と弁護士に依頼するメリットを踏まえて、弁護士を立てるか否かを判断できるでしょう。
なお、弁護士への相談は、30分~1時間程度で、費用は無料~5,000円/30分程度が相場です。
まとめ
離婚に向けて進んでいくことを決めたとき、相手に離婚したい旨を伝える前が弁護士を立てるベストなタイミングといえます。
離婚問題を解決するには、離婚できるかどうか以外にも親権や養育費、慰謝料、財産分与などについて、法的な観点から主張内容や請求額を決めなければなりません。
そのため、できるだけ早い段階で離婚問題に精通した弁護士に相談することで、離婚原因やこれまでの経緯に応じた最適なアドバイスを受けながら進められます。
また、相手が弁護士を立ててきたときや調停や訴訟に発展するとわかった時点では、弁護士を立てる必要性は一層高くなります。
一般の方が、法律や離婚問題に詳しい専門家を相手に離婚手続きを進めることは、不利な形で離婚せざるを得なくなる可能性が高くなるためです。
離婚に至る経緯や状況によって、弁護士を立てるさまざまなタイミングがありますが、早めに弁護士を立てることで、より有利な条件で離婚問題を解決できる可能性は高くなります。