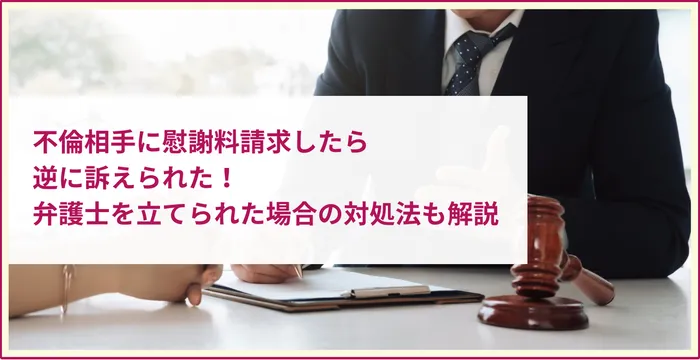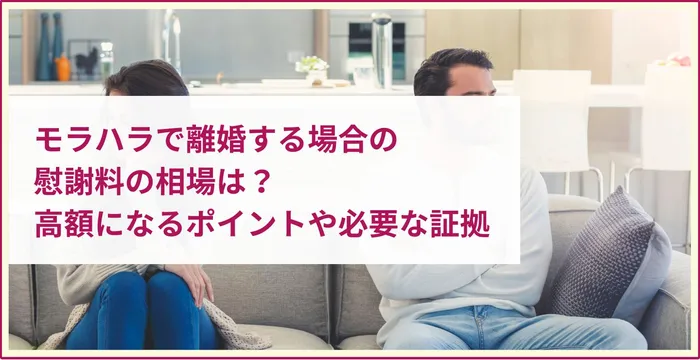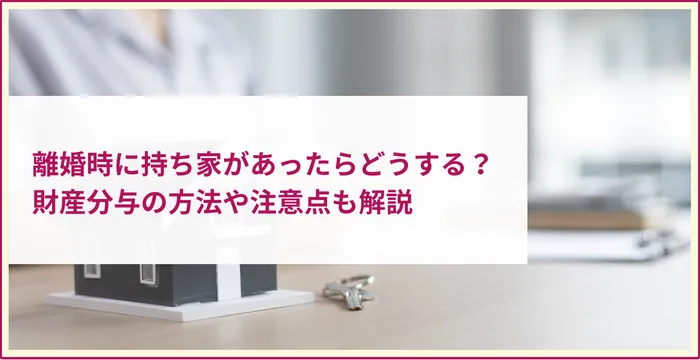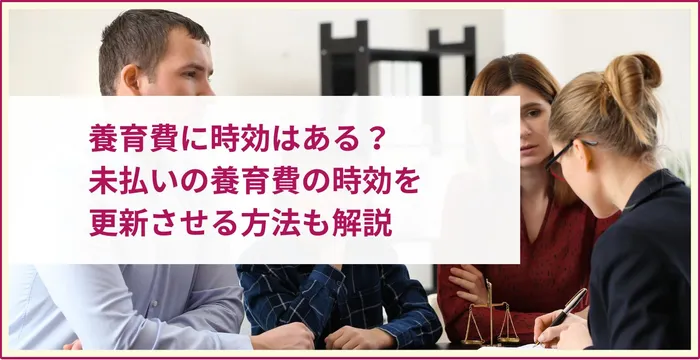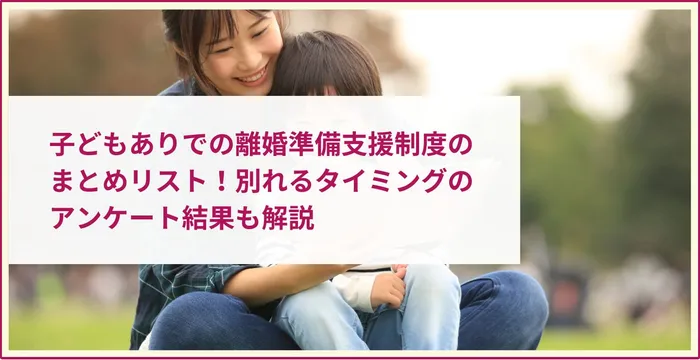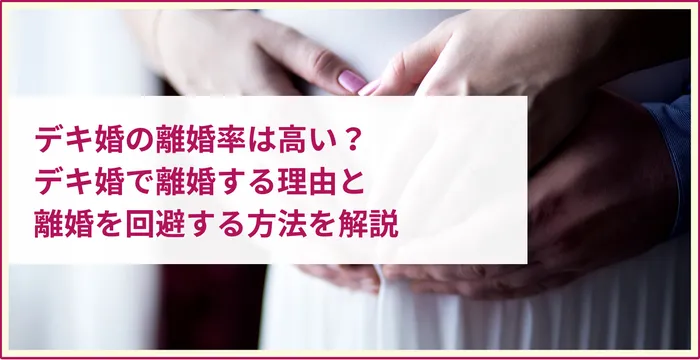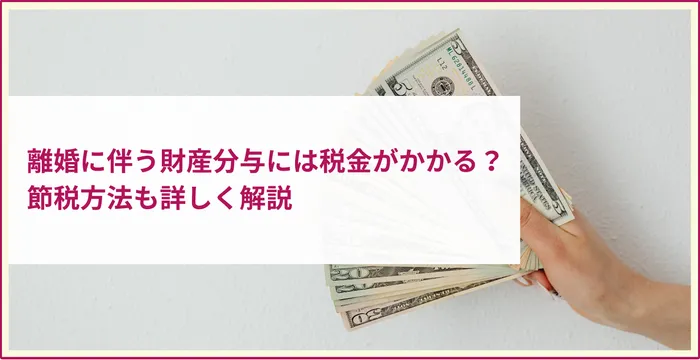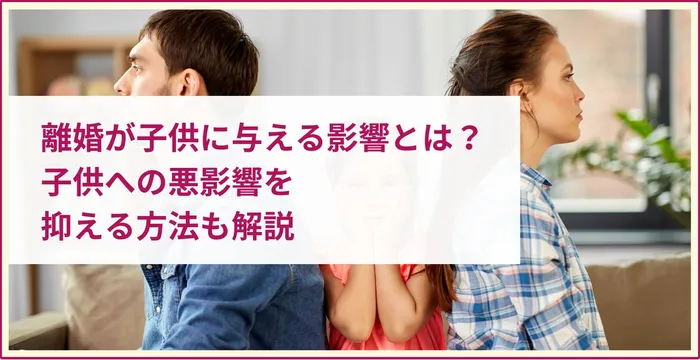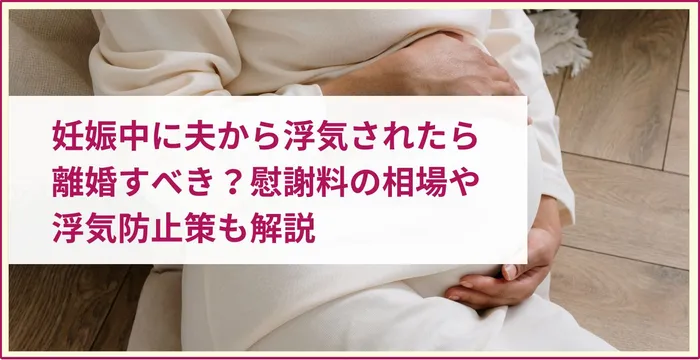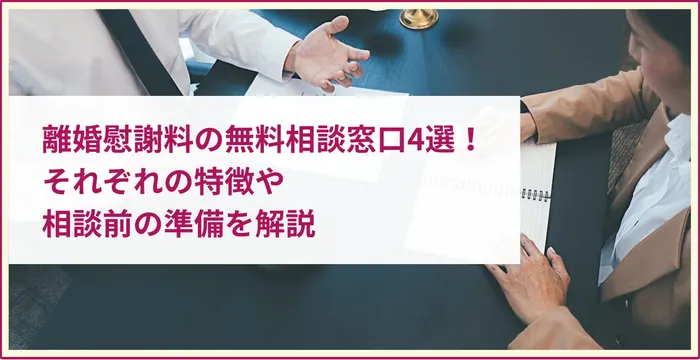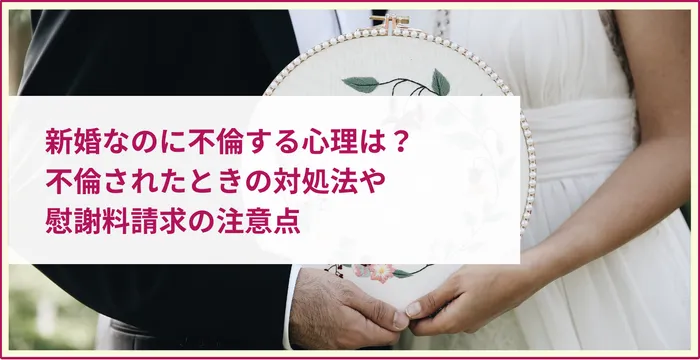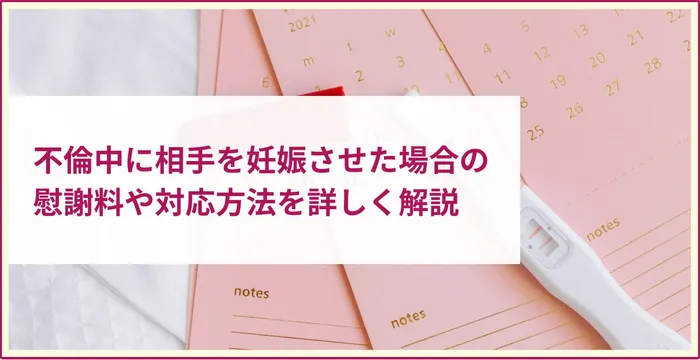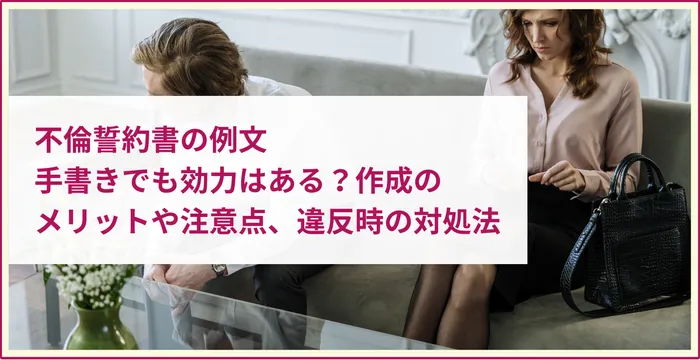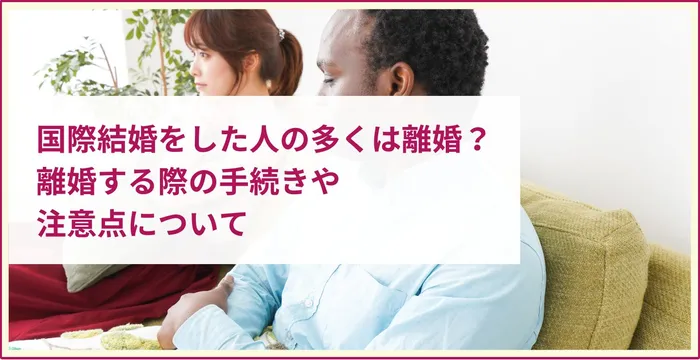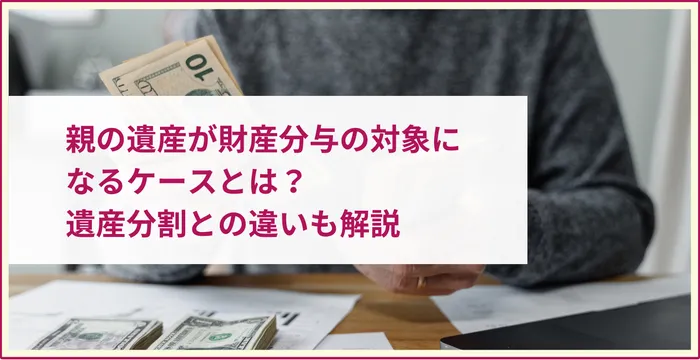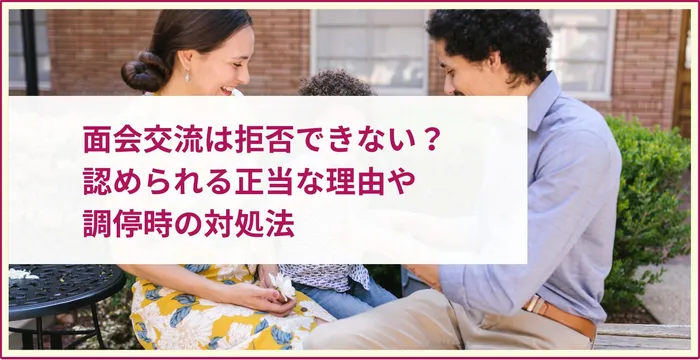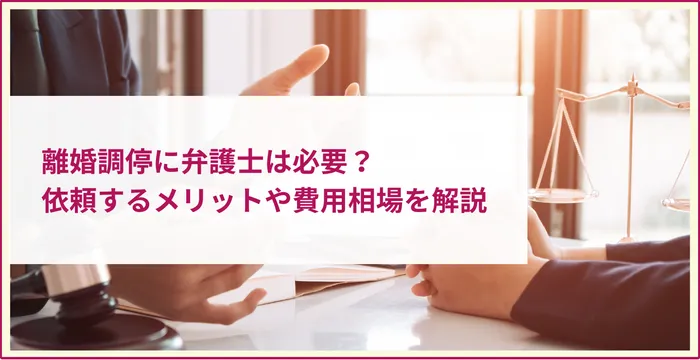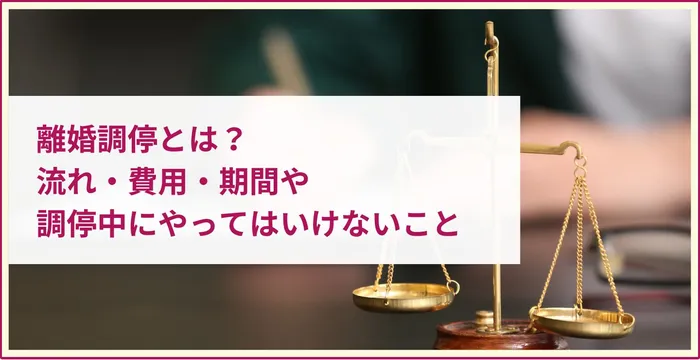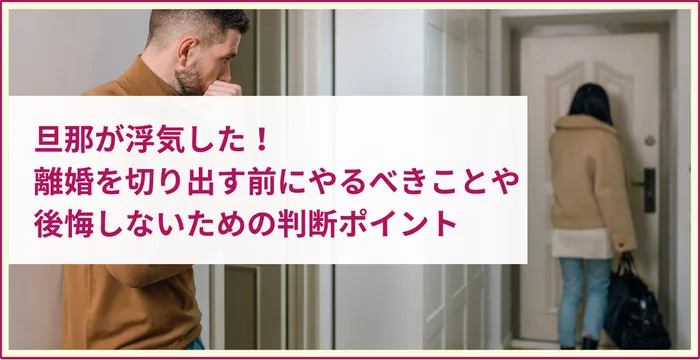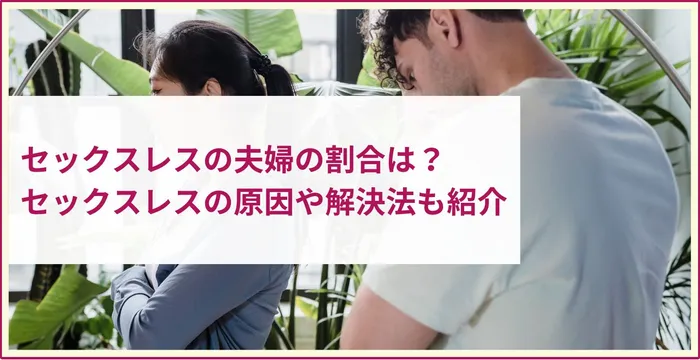配偶者の不倫が発覚して不倫相手に慰謝料請求したら、逆に訴えられてしまうというケースがあります。本記事では不倫相手から逆に訴えられて慰謝料請求が認められるケースや、相手が弁護士を立ててきたときの対処法などを詳しく解説します。
『ツナグ離婚編集部』執筆のコラム一覧
夫婦間のモラハラの慰謝料相場は約50万円〜300万円と、内容や期間、頻度などによって金額が異なります。本記事では、モラハラで離婚する場合の慰謝料相場や金額を左右するポイントなどについて解説します。
離婚時に持ち家がある場合は、売却したり、夫婦で住み続ける人を決めたりします。本記事ではそんな離婚時の持ち家の処置の仕方、持ち家を財産分与するときのポイントなどを解説します。ぜひ参考にしていただき、離婚をスムーズに進めてください。
養育費の時効は5年または10年です。請求権は時効の到来だけでは消滅しませんが、相手が「時効を援用」すると請求できなくなるため要注意です。この記事では、養育費の時効や時効の更新方法について解説します。
子連れ離婚では、親権や養育費の確保、面会交流、財産分与、慰謝料請求、年金分割、婚姻費用の請求、離婚協議書の作成など、さまざまな準備が必要です。また、離婚後も住所や姓の変更に伴う手続きや行政の支援について確認することが大切です。
離婚率の高いイメージのあるデキ婚ですが、離婚率は約40%ともいわれます。この記事では、デキ婚と離婚率の関係や、デキ婚で離婚した理由、結婚を長続きさせる方法を解説します。
財産分与には、基本的に税金が課税されません。ただし、不動産や偽装離婚、受け取る金額が極端に多い場合は税金がかかります。この記事を読むと財産分与に税金がかかるケースや節税方法が分かります。財産分与をする側・される側の注意すべき点も解説します。
両親の離婚は、子供にとって大きな出来事です。生活の変化やひとり親になる不安などで、精神的ダメージを受けます。両親の離婚で子供に悪影響が及ばないように、親がしっかり配慮しましょう。ここでは子供に与える影響と悪影響を抑える方法を解説します。
妊娠中に浮気をされた場合、慰謝料や離婚について慎重に考えなければいけません。本記事では、妊娠中に浮気をされたときの妻が取るべき選択肢をまとめました。ぜひ参考にしていただき、今後夫に対してどのような対応をするべきなのか考えましょう。
本記事では、離婚の慰謝料について無料で相談できる弁護士の窓口のそれぞれの特徴や相談前にやっておくべきこと、さらには離婚の慰謝料問題について相談する弁護士の選び方などについてわかりやすく解説します。
夫婦が仲睦まじい新婚期間であっても、独身気分が抜けなかったり、刺激を求めたりして不倫に走る人はいます。本記事では、新婚で不倫する人の心理や新婚期間の浮気率、不倫された場合の対処法、慰謝料の相場や請求時の注意点を紹介します。
不倫中の相手を妊娠させた場合、配偶者からの慰謝料や離婚請求にどのように対応すればよいか、また、子どもを産み認知することでどのような法律関係が生じるかなどについて解説します。
不倫誓約書は不倫再発の抑止力になり、調停や裁判での証拠書類になることがメリットです。公正証書にすれば、慰謝料の未払い時に強制執行することも可能です。本記事では、誓約書は手書きでもよいのかどうかや注意点、違反時の対処法などについて解説します。
国際結婚をした人の離婚率は約半数と高い割合を占めています。国際結婚の離婚が多い理由は、文化や価値観の違いなどさまざまです。国際結婚をした人の離婚の手続き方法や、国際結婚の離婚率が高い原因について紹介します。
親の遺産は離婚時の財産分与の対象になるのか、具体的な事例を挙げながら解説しています。財産分与でのトラブルを避けたい方は参考にしてください。
面会交流(親子交流)は原則として拒否できません。しかし虐待や連れ去りの恐れや子どもからの拒否といった子どもの福祉を害するとする正当な理由があれば拒否が可能です。面会交流を拒否すると、履行勧告や強制執行といったペナルティが発生します。
離婚調停は自分だけでも対応できますが、有利に進めたいのであれば弁護士への依頼をおすすめします。弁護士に依頼すれば、離婚調停がスムーズに進んで早期解決を図れるだけでなく、調停への同席や書類作成などのサポートを受けられます。
離婚調停とは、家庭裁判所で裁判官や調停委員を交え、離婚の成立や条件について話し合い、合意による解決を目指す手続きです。申立手続きの費用は3,000円程度、弁護士に依頼する場合は50~100万円程度の費用が発生します。
旦那の浮気が発覚し、すぐ問い詰めたくなる気持ちもわかります。ただ、一度冷静になり、いくつかの判断基準に照らし合わせながら離婚するかどうか考えましょう。
本記事ではセックスレス夫婦の割合や、セックスレスになる原因・きっかけ、解決方法を紹介します。日本ではセックスレスの夫婦が多く、不倫や離婚の原因になる可能性もありますが、解決する方法も当然あります。本記事をチェックしてセックスレスについて理解