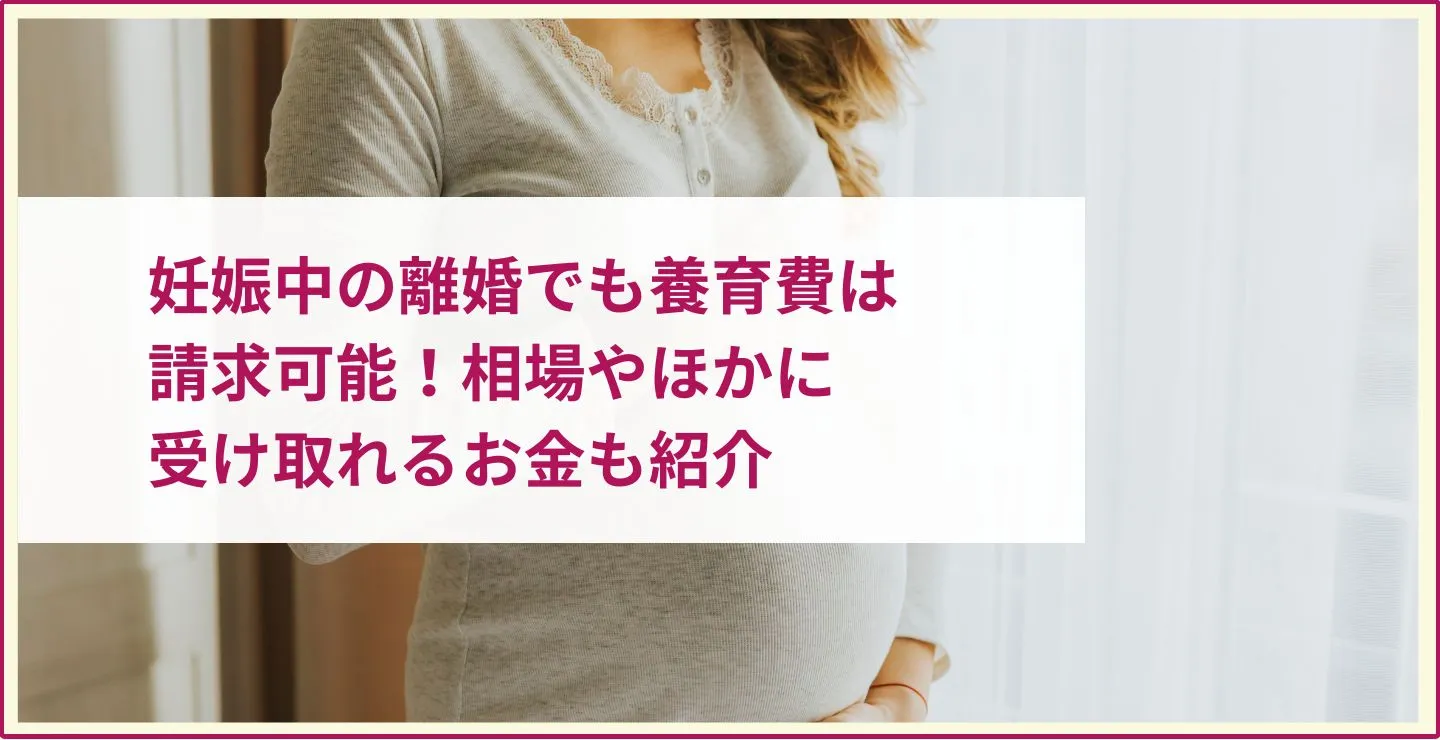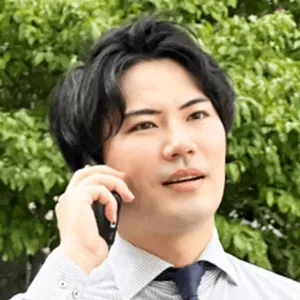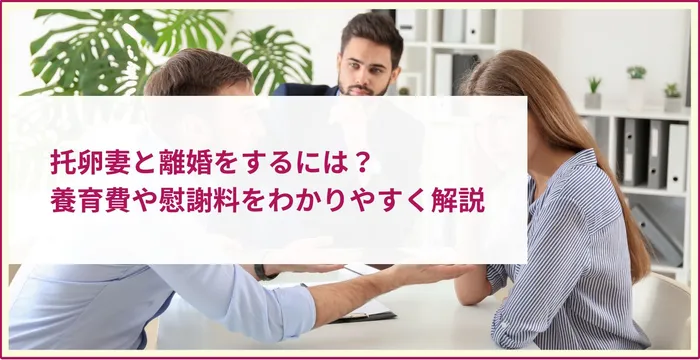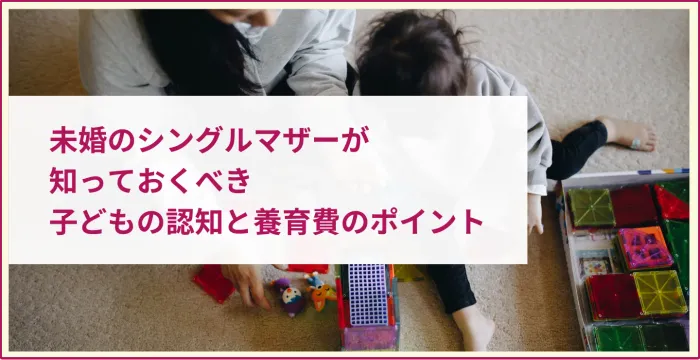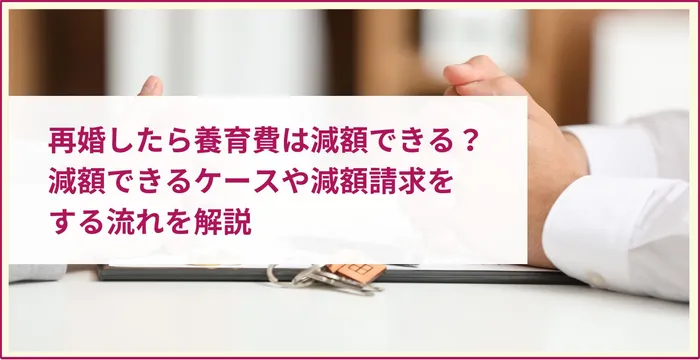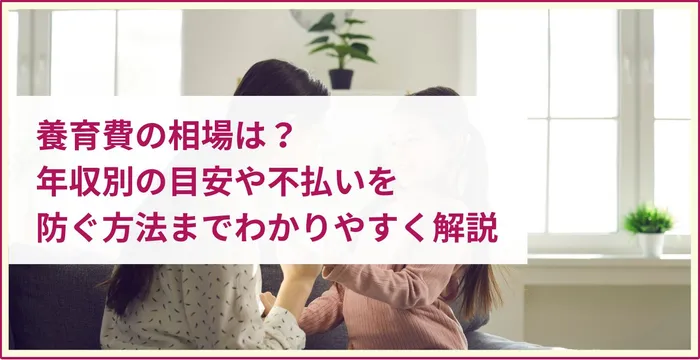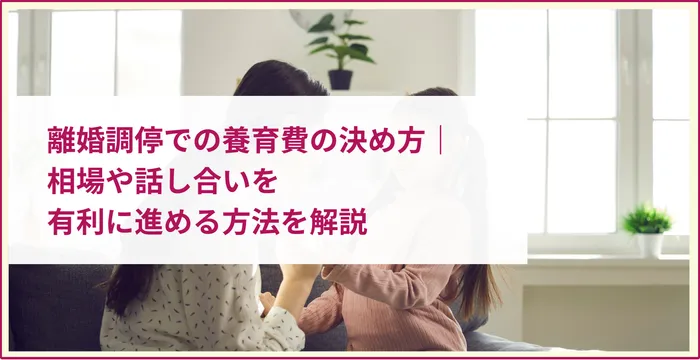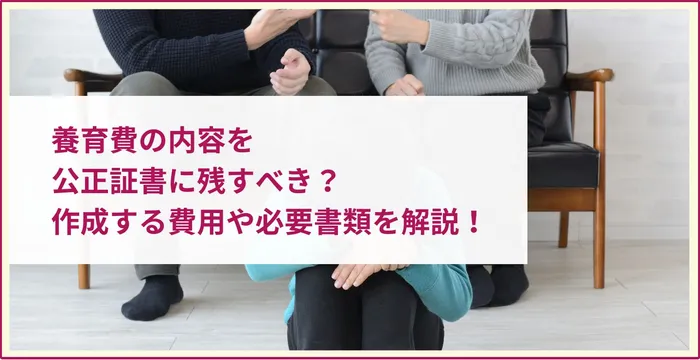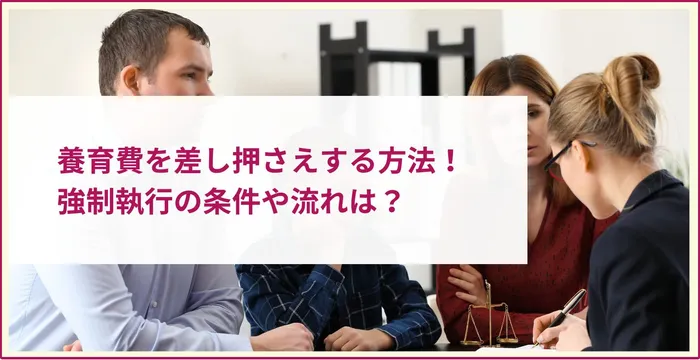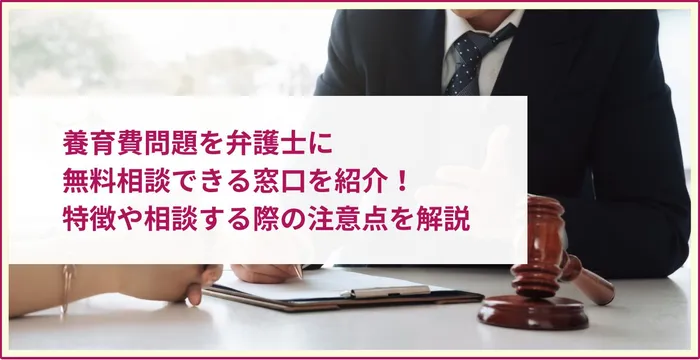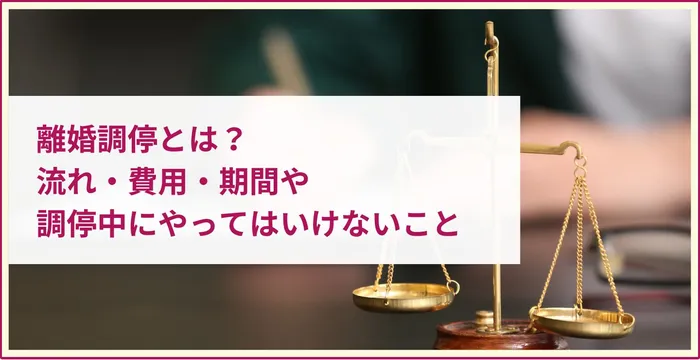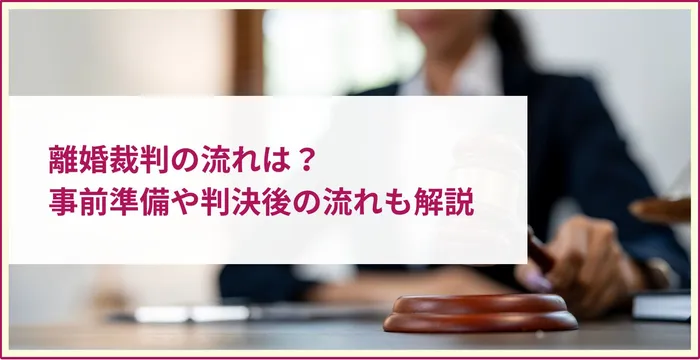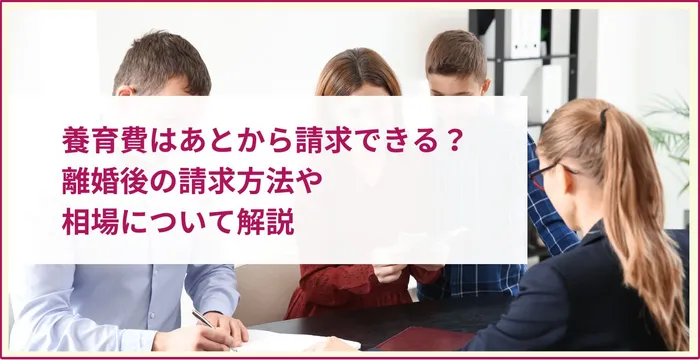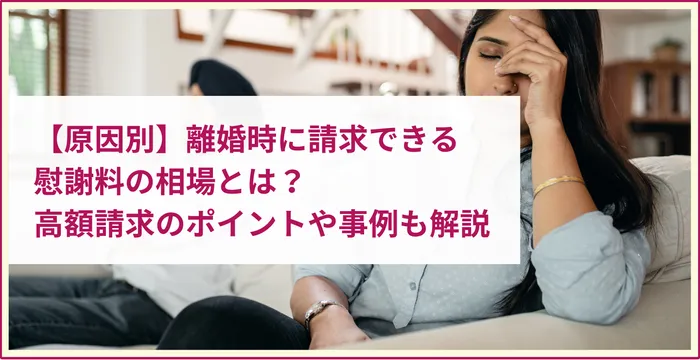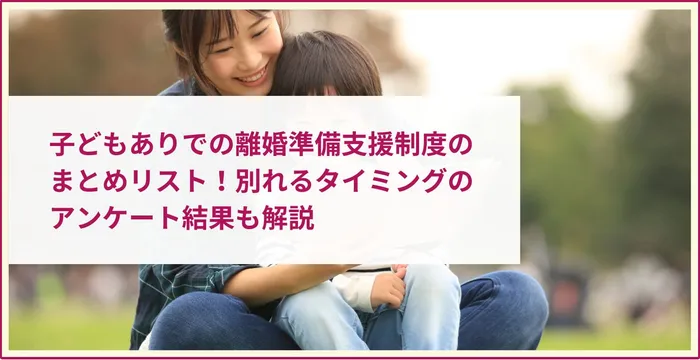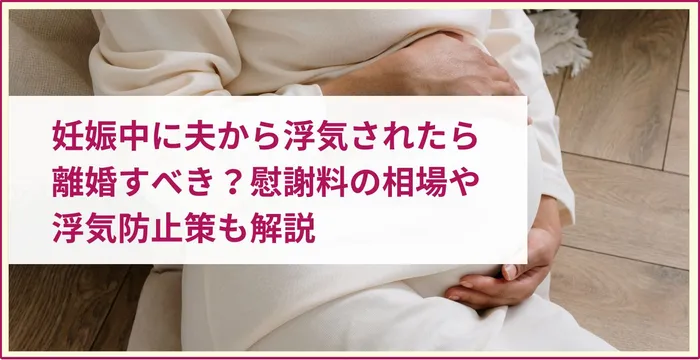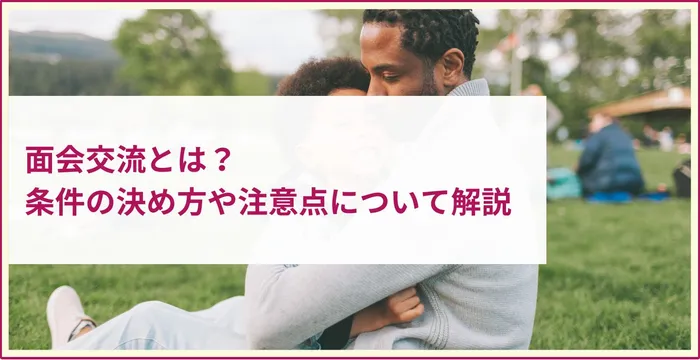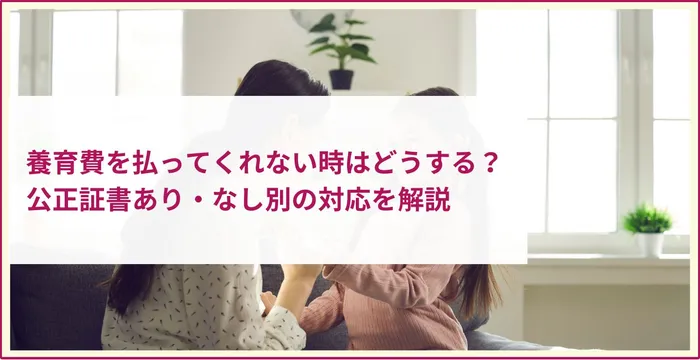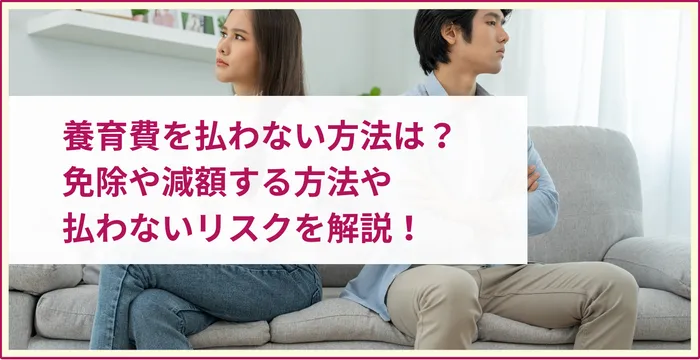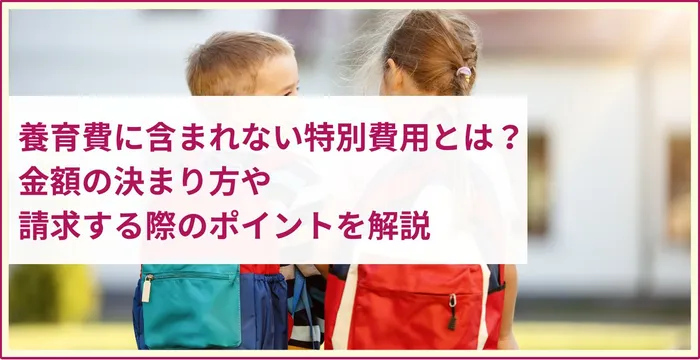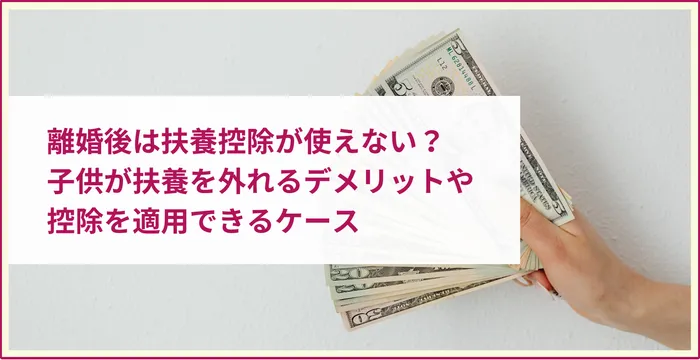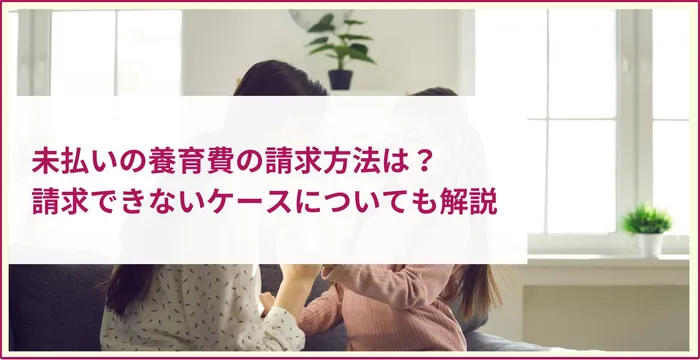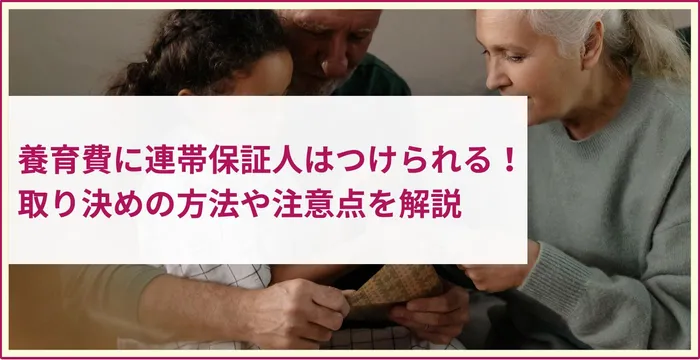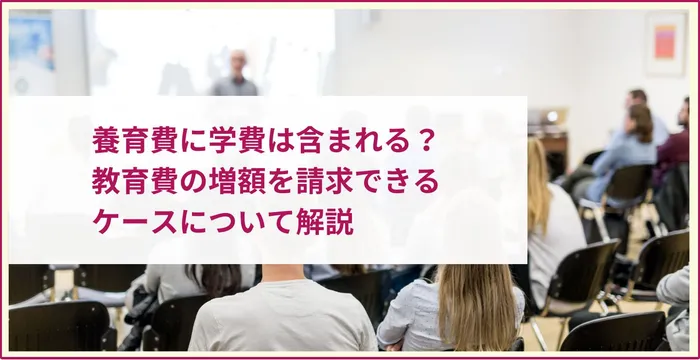妊娠中の離婚でも養育費の請求は可能!
妊娠中に離婚した場合でも、養育費の請求は可能です。ただし、離婚後に子供が生まれるタイミングが重要なポイントとなります。民法第772条2項では、離婚後300日以内に生まれた子供は原則として元夫の子供と推定されます。
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。
2 前項の場合において、婚姻の成立の日から二百日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し、婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
引用元 e-GOV
この場合、元夫には扶養義務が発生し、養育費の請求が可能です。
一方で、離婚後300日を超えて生まれた場合、元夫の子供とは推定されません。そのため、元夫が実際に父親であったとしても、養育費を請求するには「認知」が必要となります。
認知とは、法律上で子供との親子関係を認める手続きのことです。
具体的には以下の方法で認知を行います。
- 任意認知:男性が自らの意思で戸籍上の父となる
- 強制認知:裁判など法的手続きをもって認知させる
元夫の認知を得られれば法律上で親子と認められるため、養育費の請求が可能になります。
妊娠中の離婚で養育費を受け取れない3つのケース
妊娠中の離婚では、以下のようなケースでは養育費を受け取れない可能性があります。
- 離婚後300日以降の出産である
- 出産前に母親が再婚した場合
- 出産後の再婚相手と子どもが養子縁組をした場合
それぞれ詳しく解説します。
離婚後300日以降の出産である
離婚後300日を過ぎて子どもが生まれた場合、その子どもは法律上、元夫の嫡出子とは推定されません。そのため、自動的に父子関係は認められず、元夫に養育費を請求することも困難になります。
このようなケースでは、元夫に「認知」の手続きを行ってもらうことが必要です。認知が成立すれば、法律上の父子関係が確定し、養育費の請求も可能になります。
しかし、元夫が認知を拒否した場合は、家庭裁判所を通じて「親子関係確認の訴え」を提起し、法的に親子関係を確定させる必要があります。その際、裁判所の判断によってはDNA鑑定が求められることもあります。
DNA鑑定の手続きや詳細については、こちらの記事で詳しく解説しています。
子どもを認知してもらって養育費を受け取り、子どもの権利を守る場合は、弁護士などの専門家に相談して適切な準備が必要になります。
出産前に母親が再婚した場合
妊娠中に離婚した後、出産前に母親が再婚した場合、法律上の父親は新しい夫とみなされます。
民法第772条3項では母親が再婚すると、その時点で生まれてくる子供は新しい夫の子供と推定されます。
3 第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
引用元 e-GOV
出産前に再婚すると、生物学的な父親が元夫であったとしても、元夫は法律上の父親ではなくなります。そのため、元夫に対して養育費の請求はできません。その代わりに新しい夫が戸籍上の父親となり、子供に対する扶養義務を負います。
例外的に元夫が子供の生物学的な父親であることを認め、法律的な父子関係を確立したい場合は、新しい夫の同意を得た上で家庭裁判所を通じた手続きが必要です。
ただし、これには多くの手間と時間がかかるため、実際には母親の再婚後、元夫が養育費を支払う義務を負うことはほとんどありません。
母親が再婚する可能性がある場合、事前に養育費や子供の将来についてしっかり話し合うことが重要です。
出産後に再婚相手と子どもが養子縁組をした場合
出産後に母親が再婚して新しい夫と子どもが養子縁組をした場合、元夫からの養育費は減額か免除される可能性があります。
法律上、養子縁組が成立すると新しい夫が子どもの父親となり、子どもの扶養義務を引き受けるためです。
一方で、新しい夫と子どもがともに生活を送る場合でも、養子縁組を行わない場合は再婚相手に扶養義務は発生しません。したがって、元夫側に養育費の支払いが必要になります。
ただし、養育費の金額は基本的に経済状況などを加味して決定されるため、再婚によって妻側の経済状況が大きく好転した場合は養育費の減額が認められるケースもあります。
再婚や養子縁組の養育費は出産のタイミングや経済状況などが複雑に絡むため、正しく理解するためにも弁護士に相談するのがおすすめです。
妊娠中に離婚した場合の養育費の相場と算出方法
妊娠中に離婚した場合でも、子どもの将来や生活費を考慮して養育費を決めることが必要です。
養育費の算定は裁判所が公開している『養育費算定表』を参考にするのが一般的です。『養育費算定表』では双方の収入や子どもの人数に応じた標準的な養育費が示されています。
また、インターネット上には算定表を元に金額を計算できるツールもあるため、自分の状況に応じたおおよその金額を簡単に確認可能です。
具体的な養育費の相場は、令和3年度(2021年)の「全国ひとり親世帯等調査結果」によると以下の結果となっています。
- 母子世帯:50,485円
- 父子世帯:26,992円
ただし、実際に決める金額は夫婦間の話し合いや調停で調整される場合が多く、特別な事情があるケースでは相場から外れることもあります。
まずは算定表やツールを活用し、現実的な金額を把握することが重要です。
養育費を請求する際の注意点
次に養育費を請求する際の注意点を以下の内容で解説します。
- 取り決めた内容は公正証書として残す
- 養育費を受け取るのは出産してからになる
取り決めた内容は公正証書として残す
元夫に養育費の取り決めを確実に守らせるには、書面にまとめ、『公正証書』として残すことが重要です。
公正証書は公証人が公証役場で作成する公式な文書であり、法的拘束力を持ちます。
特に『強制執行認諾文言付の公正証書』として作成すると、万が一養育費が支払われなくなった場合に元夫の財産を差し押さえるなどの強制執行が可能です。
口約束の場合は法的拘束力が弱まるため、あとになって支払いが滞った際に相手の財産などを差し押さえできず、いわゆる泣き寝入り状態になってしまう可能性が高いです。
事実、令和3年度の調査では母子世帯で現在も養育費を受け取っているのは、わずか28.1%に過ぎないという結果が出ています。
口約束や簡易的な書面では支払いが滞るリスクが高いため、公正証書を作成して事前に対策することが大切です。
公正証書の作成には費用がかかりますが、将来的なトラブルを防ぐための重要な投資と捉えましょう。
公正証書の作成方法や費用は下記で詳しく解説しているので参考にしてください。
養育費を受け取るのは出産してからになる
妊娠中に離婚しても、養育費を実際に受け取れるのは出産後になります。
法律上、胎児には独立した法的権利が認められておらず、母親が胎児を代理して養育費を請求することもできません。
妊娠中に離婚した場合は、出産後に養育費の取り決めを正式に進めることが必要です。
なお、出産前の生活費や医療費が心配な場合は離婚時に慰謝料や財産分与としてカバーできる可能性もあるため、事前に元夫と話し合っておくことが重要です。
妊娠中に離婚する際に養育費を取り決める流れ
妊娠中に離婚する際の養育費に関する取り決めは、以下の流れで決定します。
- 養育費について相手と話し合う
- 夫婦双方の話し合い(協議)で離婚がまとまらなければ離婚調停を行う
- 調停で合意に至らない場合は裁判に移行する
ただし、相手が養育費についての話し合いに応じない場合や、離婚原因がDVなどの場合は離婚調停から始めても問題ありません。
養育費について相手と話し合う
妊娠中に離婚する際はまず元夫と連絡を取り、養育費について具体的に話し合うことが重要です。
具体的には以下の内容について詳細に決めていきます。
- 養育費の金額
- 支払い方法(振込や現金手渡しなど)
- 支払い期間(例えば子どもが20歳になるまで)
これらの内容は後々のトラブルを防ぐために書面化し、可能であれば「強制執行認諾文言付きの公正証書」として公証役場で作成するのがおすすめです。
公正証書があれば養育費が未払いになった際、裁判を経ることなく元配偶者の財産を差し押さえるなどの強制執行が可能になります。
すでに別居している、または直接交渉することが難しい場合は弁護士に代理交渉を依頼するのも有効な手段です。
冷静な話し合いを心がけ、子どものために最善の条件を整えましょう。
養育費問題を弁護士に無料で相談できる窓口は、下記で解説しているので参考にしてください。
夫婦双方の話し合い(協議)で離婚がまとまらなければ離婚調停を行う
夫婦間の話し合いで離婚や養育費の取り決めがまとまらない場合や相手と会いたくない、連絡がつかないなどの場合は、家庭裁判所で「夫婦関係調整調停(離婚調停)」の申し立てが可能です。
離婚調停では、裁判官1名と一般的に男女1名ずつの調停委員2名が間に入り、公平な立場で以下の事柄について双方の意見を調整します。
- 離婚自体が認められるか
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 養育費
- 面会交流
- 年金分割
双方が柔軟に意見を交わして合意が成立した場合は、法的拘束力を持った調停調書が作成されます。
なお、離婚調停については下記で詳しく解説しています。
調停で合意に至らない場合は裁判に移行する
調停で合意に至らなかった場合、離婚問題は自動的に裁判に移行します。
裁判では裁判官が法律に基づいて離婚の妥当性や親権、慰謝料や財産などを決定します。
調停とは異なり当事者間の柔軟な話し合いではなく、提出された証拠や主張をもとに法的判断が下されるので確実な解決を目指すことが可能です。
裁判を起こす側は離婚原因や求める条件を記載した訴状を提出し、相手側は答弁書を通じて反論する流れとなります。
一般的な裁判と同様に審議が進むため、時間や費用だけなく精神的な負担も大きくなるものです。
できる限り調停で解決できるよう努力するのが望ましいですが、必要に応じて弁護士のサポートを受けながら進めると良いでしょう。
既に離婚している場合は養育費請求調停で養育費を決める
既に離婚している場合でも「養育費請求調停」を家庭裁判所に申立が可能です。
養育費請求調停は養育費に関する夫婦間の合意が得られない場合に利用され、調停委員が双方の意見を聞きながら公平な解決策を提案する場です。
離婚調停と異なり、主に以下のような養育費の支払いに特化した話し合いが行われます。
- 支払い額
- 支払い期間(例:子どもが20歳になるまで)
- 支払い方法(一括、分割、振込など)
また、一度決まった養育費でも収入の変動や生活状況の変化などの理由で金額や条件を変更したい場合には、「養育費変更調停」の申立も可能です。
調停で合意に至った場合は、離婚調停と同じように法的拘束力がある調停調書が作成されます。
養育費請求審判|養育費について争う裁判のこと
「養育費請求調停」で話がまとまらない場合は、養育費請求審判に自動的に移行します。
養育費請求審判は裁判官が一切の事情を考慮し、審判によって養育費の額を決定する手続きです。
審判では、双方が提出する収入や生活費に関する資料が重要な判断材料となり、裁判官が子どもの利益を最優先に金額を決めます。
審判の決定には法的拘束力があり、養育費の支払いが義務化されます。
審判の結果に不服がある場合は、決定後2週間以内に「即時抗告」を申し立て、再度の審理を求めることが可能です。
ただし、即時抗告が認められるかは状況により異なるため、弁護士の助言を得ながら進めることをおすすめします。
養育費以外で離婚後にもらえる可能性のあるお金
子どもの健全な成長のためには養育費を受け取れることが重要ですが、以下のように養育費以外でも離婚後にお金をもらえるケースがあります。
- 財産分与|婚姻期間中に築いた財産を公平に分ける制度
- 慰謝料|DVや不倫などがあった場合に請求可能
- 出産一時金|健康保険に加入している方が受け取れるお金
- その他シングルマザーが利用できる公的支援
それぞれ詳しく解説します。
財産分与|婚姻期間中に築いた財産を公平に分ける制度
財産分与とは婚姻生活中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時にそれぞれの貢献度に応じて公平に分ける制度です。
民法第768条1項および第771条に基づき、離婚時には相手方に対して財産分与を請求する権利があります。
対象となる財産は以下のとおりです。
離婚を急ぐあまり財産分与について十分に話し合わないと、本来受け取れるはずの財産を失うリスクがあります。
特に婚姻期間中の妻の家事労働など目に見えない貢献も財産分与の対象となるため、慎重に取り決めることが重要です。
財産分与は法律で認められた正当な権利であるため、離婚時には具体的なリストを作成し、夫婦間での協議や調停を通じて明確に分配内容を決定しましょう。
また、不安がある場合は弁護士に相談することで、権利を確実に守ることができます。
慰謝料|DVや不倫などがあった場合に請求可能
離婚の際、夫に慰謝料を請求できる可能性があります。
慰謝料は以下のような夫の行為によって受けた精神的苦痛や生活上の損害に対する賠償として支払われるものです。
- DV(ドメスティックバイオレンス)
- モラハラ
- 不倫
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、家庭を顧みないなど)
慰謝料の金額はケースによって異なり、次のようなことが考慮されたうえで決定します。
- 行為の悪質さ
- 被害の程度
- 婚姻期間
- 夫婦の経済状況
一般的な相場は100万円から300万円程度ですが、不倫相手が特定できる場合にはその相手にも請求できる可能性があります。
また、DVやモラハラに関しては、程度によっては刑事事件などに発展するケースも考えられるでしょう。
慰謝料を請求する際は、診断書やメール、写真などのDVや不倫の証拠をしっかりと用意することが重要です。
これらの行為があった場合には専門家に相談し、法律に基づいた正当な補償を受けるようにしましょう。
離婚時の慰謝料については下記で詳しく解説しています。
出産一時金|健康保険に加入している方が受け取れるお金
出産一時金は健康保険に加入している方が出産時に受け取れる支援金で、子ども1人につき48.8万円または50万円が支給されます。
具体的な金額は健康保険の種類によって異なりますが、会社の健康保険と国民健康保険の両方が対象となります。
離婚前に夫の扶養に入っていた場合は、新たに自分で健康保険に加入する必要があるため注意が必要です。
職場に相談したり市役所などに出向いたりして、健康保険に加入する手続きを行いましょう。
加入手続きを怠ると最悪の場合、出産一時金を受け取る権利がなくなってしまう可能性もあります。
出産一時金は妊娠中に離婚する場合の生活において大きな助けとなるため、健康保険の手続きを忘れずに行い、確実に受け取るようにしましょう。
なお、妊娠4カ月(85日)以上の出産であれば、流産や死産の場合でも支給されます。
その他シングルマザーが利用できる公的支援
上記以外にもシングルマザーが利用できる公的支援として、以下のようなものがあげられます。
| 制度名 |
内容 |
支給額 |
| 児童手当 |
日本に住む中学生以下の子どもを養育している保護者に支給される手当。支給額は年齢によって違いがある。 |
- 3歳未満:1人あたり月額15,000円
- 3歳以上:1人目・2人目は月額10,000円、3人目以降は月額30,000円
|
| 児童扶養手当 |
ひとり親家庭やこれに準ずる家庭を経済的に支援するための制度。子どもが18歳到達後の最初の3月31日まで受け取れる。
所得によって支給額は変動する。 |
- 1人目:最大45,500円
- 2人目以降:1人目に加えて最大10,750円
|
| 公正証書作成費用支援 |
主に養育費の取り決めやその支払い確保を目的として、公正証書を作成する際に発生する費用の一部または全額を自治体が助成する制度。 |
自治体によって異なるが一般的には数千円程度 |
| 母子家庭医療費助成 |
母子家庭や父子家庭を対象に、医療費の自己負担分を軽減するための支援制度。
一般的には医療費の一部または全額が助成される。 |
- 医療機関の自己負担額の全額または一部を助成
- 入院費や外来診療費、処方薬の費用軽減
- 初診料や再診料の助成
|
| 自立支援訓練給付金 |
ひとり親家庭の親が経済的自立を目指すために、職業訓練やスキルアップを受ける際に、その費用の一部を自治体が助成する制度。 |
対象教育訓練を修了した場合に講座費用の60%を支給。 |
また、上記以外にも自治体によって独自に支援を実施しているケースもあります。気になる方はお住まいの自治体ホームページを確認してみましょう。
妊娠中の離婚を希望する場合は弁護士に相談してみましょう
妊娠中に離婚を進めることは、心身ともに大きな負担を伴います。そのため、自ら動くことはあまりおすすめできません。
妊娠中は特に体調や精神面を優先すべき時期ですので、離婚手続きを急ぐ必要がない場合は出産後に動き出しても遅くないでしょう。
どうしても妊娠中に離婚を進めたい場合や養育費の交渉が必要な場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士は法律の専門知識を活かしてあなたの代わりに交渉や手続きを行い、適切な条件で離婚や養育費の取り決めができるようサポートしてくれます。
まずは無料相談を活用し、専門家に状況を伝えてみましょう。
まとめ
今回は妊娠中の離婚における養育費を解説しました。
妊娠中の離婚では、子どもが離婚後300日以内に生まれてきた場合は養育費の受け取りが可能です。
しかし、以下のようなケースでは養育費を受け取れないので確認が大切です。
- 離婚後300日以降の出産である
- 出産前に母親が再婚した場合
- 出産後の再婚相手と子どもが養子縁組をした場合
また、養育費を受け取るためには双方での話し合いが必要になりますが、離婚した場合は相手と険悪なケースも多く話し合いが成立しないことも少なくありません。
場合によっては調停や審判などの法的処置をしなければいけない場合もあり、これらの処置には専門的な知識が必要不可欠です。
弁護士に依頼すればこれらの法的手続きや相手とのやり取りを全て代行してくれます。時間的なコストや精神的な負担を大きく軽減できるので、ぜひ利用してみましょう。
妊娠中の離婚についてよくある質問
妊娠中に離婚すると面会交流はどうなりますか?
面会交流とは離婚や別居によって子どもと一緒に暮らさない親が、子どもと定期的かつ継続的に会ったり交流したりする権利のことです。
妊娠中に離婚しても
元夫が戸籍上の父親である限り、この権利は失われません。元夫が面会交流を求めた場合は子どもの利益に反しない限り、原則として拒否することはできないと覚えておきましょう。
ただし、以下のようなケースでは、例外的に面会交流を制限できる場合もあります。
- 元夫がモラハラやDVを行っていた
- 子どもが面会を強く拒否している
- 子どもを連れ去る危険性がある
上記の事情がある場合には、家庭裁判所に面会交流の制限や禁止を申し立てることができます。
また、頻度や場所など面会交流の条件は、両親の話し合いや調停を通じて取り決めるのが一般的です。子どもの心身の安定を最優先に考え、適切な形で面会交流を行えるよう準備することが大切です。
面会交流は以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。
元夫に生活費の請求は可能ですか?
離婚が成立すると元夫との間で生活費の分担義務はなくなるため、
婚姻費用を請求することはできません。
しかし、特定の条件下では「扶養的財産分与」として離婚後の生活費を受け取れる場合があります。
扶養的財産分与とは離婚後に経済的に弱い立場にある方を支援する目的で、財産分与の一環として生活費を受け取る仕組みです。
例えば、以下のようなケースでは話し合いや調停を通じて扶養的財産分与が認められる可能性があります。
- 夫婦間で収入格差が大きい
- 妊娠などが理由で離婚後に働くのが難しい
ただし、この支援は必ずしも法律上の義務ではないため、元夫との協議が重要です。離婚後の生活費が不安な場合は、まずは弁護士に相談し具体的な手続きや可能性を確認しましょう。
また、扶養的財産分与の申請が難しい場合でも、公的な支援制度を活用する選択肢もあります。
元夫に出産費用を請求できますか?
出産費用を元夫に請求できるかどうかは、請求するタイミングによって異なります。
婚姻期間中であれば夫婦間には扶養義務があるため、妊娠中の通院費や入院費、出産費用などを婚姻費用として請求することが可能です。
一方、離婚が成立してしまうと夫婦間の扶養義務は消滅するため、出産費用を元夫に請求するのは非常に難しくなります。
ただし、元夫が任意で費用を支払う意思を示してくれる可能性もあるため、まずは直接話し合いを試みるのも一つの方法です。
また、出産費用の一部は健康保険の「出産育児一時金」などでカバーされる場合もあるため、公的制度の活用も併せて検討することが大切です。
離婚後300日以内に生まれた子供はどちらの戸籍に入りますか?
離婚後300日以内に生まれた子供は、法律上、元夫の子供と推定されます。
そのため元夫が結婚時の戸籍の筆頭者であれば、子供は自動的に元夫の戸籍に入ります。
上記の状態で離婚した場合は、子どもの姓と親権者である母親の姓が異なる状況が生じる可能性が高いです。
母親と子供の姓を揃えたい場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申立てることが必要です。この申立てが許可されると子供を母親の戸籍に移し、母親の姓を名乗れます。
また、離婚後300日以降に生まれた子供は、元夫の子供とは推定されず母親の戸籍に入ります。
ただし、上記ケースで確実に元夫が父親であり養育費を請求したい場合は、認知を通じて法律上の父子関係を確立することが必要です。